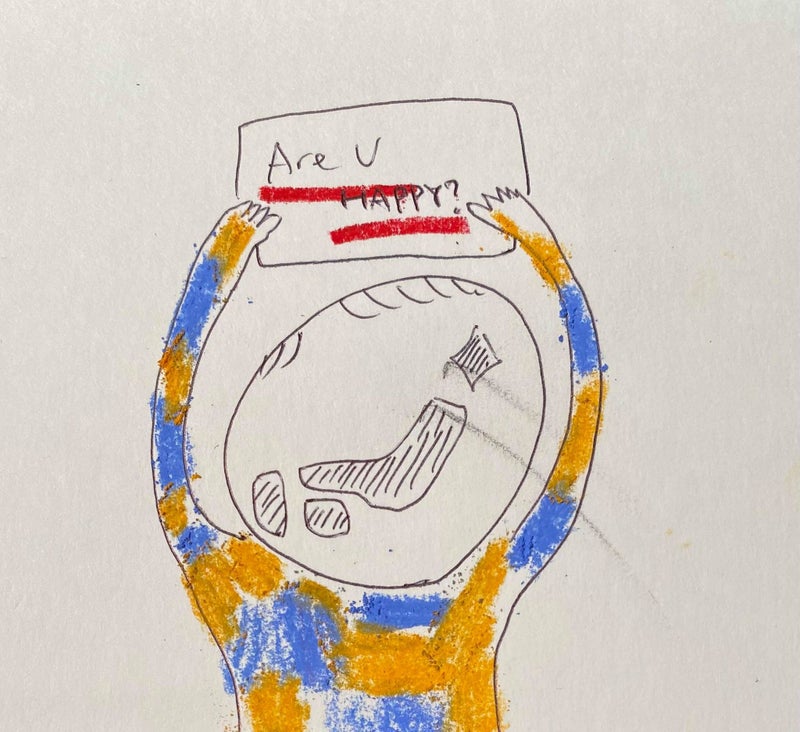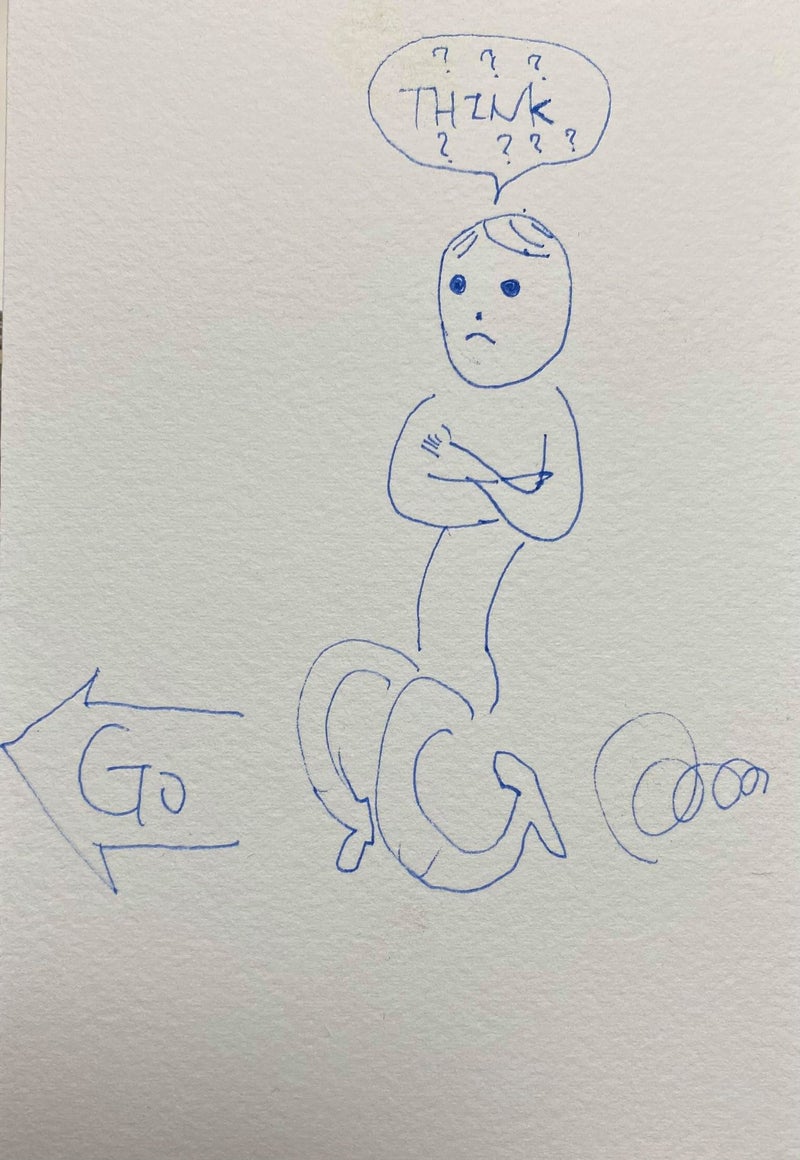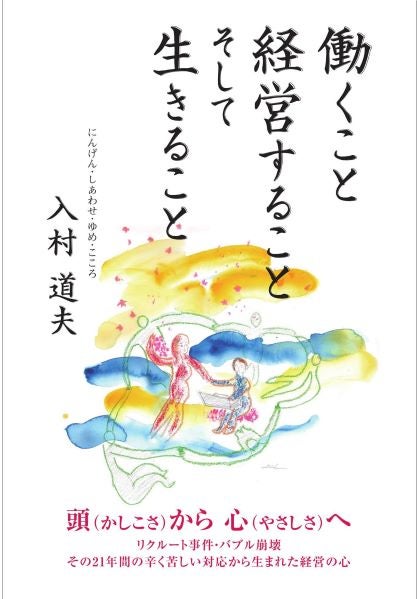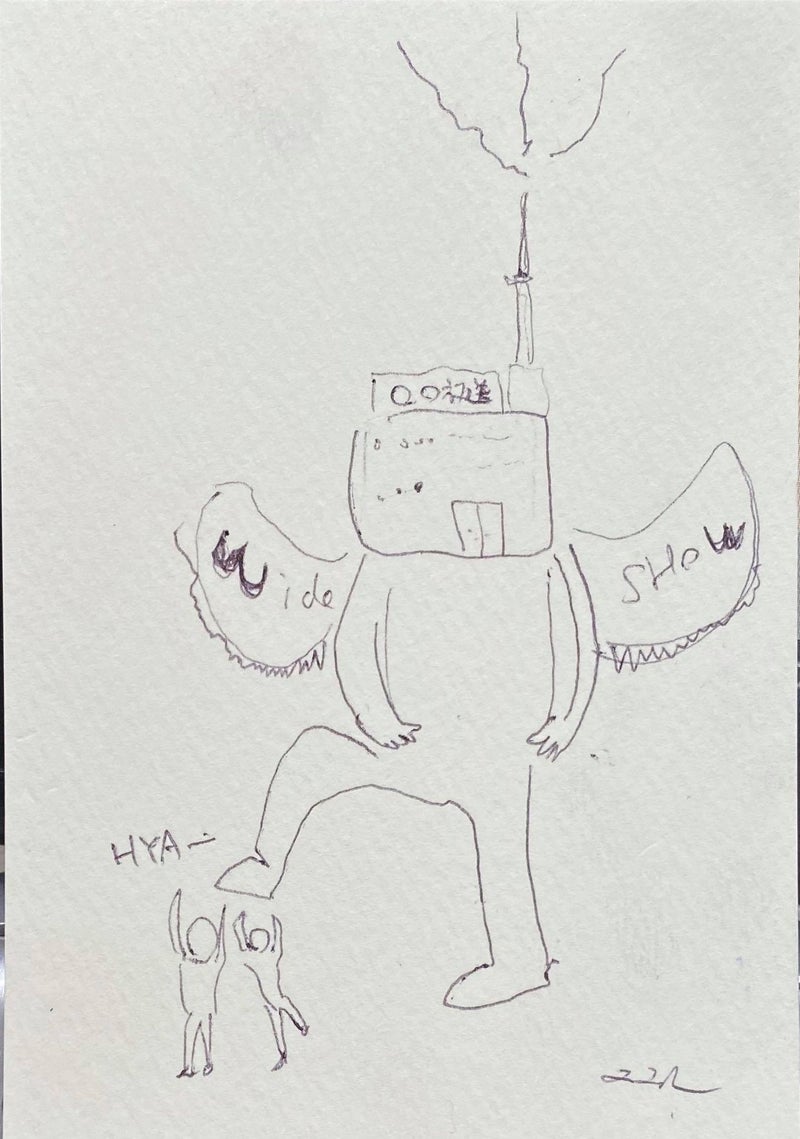<<ブログ 321>>
国会議員の先生方へのお願い
「災害時並み」の表現になった対コロナ医療体制報道から想うこと
今までと同じ「政府の責任」的な動きの繰り返しでなく
今こそ「三位一体」となって日本に「変化」を
そのためにも国会議員の先生は
政党・与野党そして派閥なんて捨てて
選ばれた「国会議員」としての動きを!!
~私の想い~ by 入道
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回も秋葉原を基地として世界への羽ばたきを重ねている
私のちょっとだけ歳の離れた友達
画家の田中拓馬さんがご厚意で素敵な挿絵を画いてくださいました。
拓馬さん、ありがとうございます。お心に感謝です。
田中拓馬さんのサイトも訪ねていただければと思います。
http://tanakatakuma.com/
https://ttakuma.thebace.in/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●8月・・・新型コロナウィルスの各道府県での新規感染者数そして全国での新規感染者数が「過去最高」を更新し続け、8月11日には厚生労働省の助言機関が「これまでに経験したことのない感染拡大で首都圏を中心に「医療提供体制は「災害時」の状況に近い」と訴えたと報道されています。
●盆休みもあり、政府そして各都道府県知事さんからは「人流を押さえる」「お盆の帰省は取りやめて」と国民・道府県民に対して訴えを強くしていますが、報道によれば「人の流れは抑えられていない」「人の滞留状況も減じていない」・・・単純、日本人は「訴えに対してそのとおりの動きをしていない」状況になっています。
●コロナ禍状況・・・20ヵ月の長い時間軸の中で「訴えていることは違うワードを使ってはいるものの中味はほとんど同じ」・・・何度も言われ何回かその訴えのとおりの動きをしてきた、しかも今回は今までとは異なりワクチン接種率が伸びてきているのにも関わらず、変わらない訴え・要望・・・。改善されていない現実!!
●政府そして都道府県知事からの指示された動きをしてきていたのに状況は変わっていない、もっとひどくなってきているじゃないか・・・本当に的確な指示・要望なのだろうか???
みんながこんな想いになってしまっているのでは・・。
★この状況を打破していく、「今これから」を「変えていく」一つの動きとして私がずっと心に想っていることがあります。
★それは一言で言ってしまうと「勇気を持って『三位一体』になっての変化の実現」「変化を実現していくために勇気を持って『三位一体に』」となります。
挿絵は田中拓馬画伯 画
★そのお願いをさせていただく対象、それは「国会議員の先生お一人お一人」になります。
国会議員のみなさま
『勇気を持って三位一体になって
日本を変えてください』
国会議員のみなさま
『日本を変えていくために勇気を持って
三位一体の動きを』
★三位一体(さんみいったい) 三省堂新明解四字熟語辞典
キリスト教で父(神)と子(キリスト)と聖霊は一つの神が三つの姿となって現れたものであるという考え方。
⇩
転じて、三つのものが一つのものの三つの側面とあること、
三つの別々のものが密接に結びつくこと。
また
三者が心を合わせて一つになること。
★では、今回私が想っている「三位一体の動き」の「三位」とは何?なのでしょうか。
★それは
政府(首相をはじめとする内閣)
国会議員(国会)
そして
都道府県知事 です。
挿絵は田中拓馬画伯 画
★この想いは連日、これでもかと感じる位、見せられている聞かされている報道内容に対して私が「とっても不思議に感じている」「なんでなの?」と想っていることから産まれてきたものです。
★連日の新規感染者そして医療体制の危機
更にここのところほぼ連日、「行動・移動自粛」等のお願いをしているのは「政府(総理・担当大臣)」であり「都道府県知事」です。
★しかも「この二つ、残念ですが一体とはなっていません」。
★政府は都道府県に、都道府県は政府に新たな投げかけをしたり・・・言い切ってしまうと責任を相手に求めたりもしている、そんな気もするのです。
★これでは日本人は一つになることはできません。
★ネットで全国知事会にコロナ担当大臣も参加して状況確認と打合せを行っていることも報道されてはいます。
☆長くなりそうなので想いの過程をはここで省きます・・・
☆私の今回の想いは、このような対コロナの動きの報道に「なんで地域住民から選ばれた国会議員」「都道府県代表とも言えるひとり一人の国会議員の先生の動き」が重なって見えてこないのだろう、この単純な疑問から産まれてきています。
☆国会議員の先生は「各地域」「各都道府県」から選出されています。
☆国会議員は「都道府県住民によって選ばれた都道府県の代表者」である、そう想うのです。
☆でも、この対コロナの動きに関しては国会議員の先生方おひとりお一人の動きがみえない、政府と都道府県知事の動きに重なっての国会議員の先生方おひとりお一人の動きがまったく見えてこない、聞こえてこないのです。(聞こえてくるのは衆議院選挙が近いから地元に張り付けの政党からの対選挙指示・・・)
★政府は国会議員に対して「政府の対コロナの考え方、なぜこの施策なのか」を「知事にきちんと説明し」「知事の相談相手になる」ことを要請しているのでしょうか。
★国会議員の先生は地元の知事に適切なアドバイスをしているのでしょうか。都道府県の「施策決定」への相談相手になっているのでしょうか。
★国会議員の先生は「地元に対して知事と一体となっての動き」をされているのでしょうか。
●コロナ対応に対しての「三位一体」。
政府と国会議員(国会)そして都道府県知事の「三者」が
「想いを一つ」にして「一つの動き」を共にしていく・・・
★国会議員の先生おひとりお一人の動きこそがものすごく重要な要因であり、三位一体を実現していくための必要十分条件、私はそう想うのですが残念ながら現状、全くそんな動きをされている、要請されているとは感じることはできません。
反対意見はあったとしても「所属している組織=国会」で
「決議された」こと
それを「実施」「実行」に移す時には「反対した」tは
関係なく、その実現のために自分も動く
それが組織人のとして「あたりまえ」・・・
40年、組織で仕事をしてきた私の「変わらない想い」です。
特に「非常時・災害時並み」と表現されている今は
「国会」という組織に所属している一人として
意識を新たにしていただき
「みんなで即行動」していただきたいと思います。
★今の非常時的状態で日本を、日本人の動きを変えていく、確固たるものにしていくために・・・・
与党であるとか野党であるとか、そして派閥なんて勇気をもって捨て去ってください。
☆日本国民によって、ご自身の地盤である都道府県民によって選ばれた・選んでもらえた国会議員の「あたりまえ」に「勇気を持って」立ち還ってください。お願いいたします。
比例代表の先生も変わりません、同じです。
日本を素敵な楽しい国にしていくための組織が国会
その国会と言う組織に所属している一人の国会議員として
組織人としての「あたりまえ」の
ひとり一人の動きを
コロナ対応においては
政府と都道府県の「間」の
「想いと行動の橋渡し」役としての動きを直ぐに
★都道府県の対コロナ会議にその都道府県選出国会議員が参加して、一緒に議論し施策を決定していくそんな動きを是非に!!!
●本気でそんな動きをお願いいたしたいと思います。
●40年組織で仕事をしてきた私の「日本を一つの『組織』として考えた時の『組織人』としての『あたりまえ』
その一つの想い、そして仮に仮に私が国会と言う組織の長だとしたら、自分だけでできること、自分の所属している党だけでできることなんて限られてくるのできっと党派を飛び越えて国会という組織に属している「仲間」みなさんにきっとお願いしている、と感じていることです。
にんげんはどんな人でも自分一人ではできないことだらけ
でも 自分を助けてくれる
一緒に考え動いてくれる仲間がいてくれれば
できないこともできることになっていく
仲間そして自分を知っている人
そして 信頼で心が繋がっている人が
たくさんいてくれれば嬉しい
だから
仕事をしていくってそして生きていくって
人生はきっとずっとずっと人探しと出逢い探しの旅
そう想うのです
●国会と言う「組織力」を徹底的に追求していただきたい、見せていただきたい、示していただきたい・・そして「政府-国会議員-都道府県知事」の「三位一体」で日本の明日のために「今を変えて」ください。
☆国会という組織に所属されている国会議員の先生おひとり
お一人の「想い」が変わることが「勇気を持って今を変えていく」
その入り口。
私は本気でそう想っています。お願いいたします。
今回も最終行にまでお眼を進めていただきまして
ありがとうございます。
「国会」って「組織」のはず
「日本国の明日のための動きを決めていく最高組織」なのだと
強く思い続けているのですが、現実は
「非常事態」と言われ始めている今でも
国会では追求と応戦だらけ・・・・
国会という「組織」として「一体になっての動き」がまったくない
「期待」を持ってはいけない・・・
残念ですがそう思います
自分(たち)の主張を守るために相手を追求する
そして 抽象論議で応戦していく・・・
そのために私たち国民は国会議員みなさまを選ばせていただき
単純表現してしまいますが「高い報酬」をお支払いしているのではありません
「日本を良くしていく」「今より楽しく素敵な国にしていく」
所属党派は異なっていても
この「想い」では「一つ」のはずです
どうか「国会組織力」を今この「コロナ禍非常時」であるが故に
勇気をもって、今これまでを捨て去って
あたらしい動き方に変えていく勇気を持っていただきたい
正直な私、一日本国民の想いです。
ありがとうございます。
にんげん・しあわせ・ゆめ・こころ 入道(入村道夫)