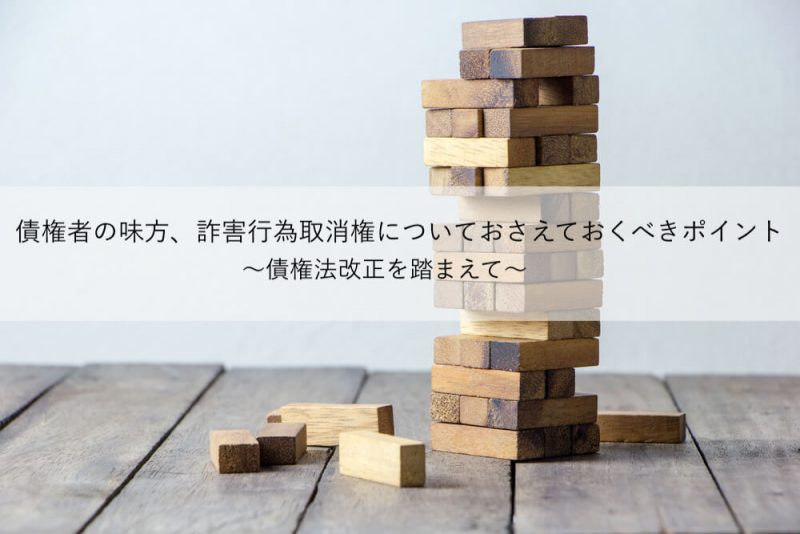↓
債権法改正以前は判例法理により、詐害行為取消しの効果は「債務者に及ばない」とされていました。今回の債権法改正により、債務者も効果の対象に含まれました。
詐害行為取消権(部会資料35の第2)についての意見
高須順一弁護士(法政大学大学院法務研究科教授)
https://www.moj.go.jp/content/000095029.pdf
民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)
民法(債権関係)部会資料 88-1
https://www.moj.go.jp/content/001132328.pdf
↓(引用)
中間試案【第15.8(4)】 では「…受益者又は転得者が債権者に対して金銭その他の動産を引き渡したときは,債権者は,その金銭その他の動産を債務者に対して返還しなければならないものとする。この場合において,債権者は,その返還に係る債務を受働債権とする相殺をすることができないものとする」との規律を設けることが提案され、「…取消債権者による直接の引渡請求を認めない旨の規定を設けるという考え方」も注記されていましたが、
相殺を禁止し、事実上の優先弁済権を否定すると債権者が詐害行為取消権を行使するイニシアティブが失われることや、総債権者に分配するための手続規定が存しないこと等から、要綱仮案では相殺禁止の明文化は見送られました。
その結果、事実上の優先弁済が容認されることとなっています。
↓(引用)
詐害行為取消権は本来、後の強制執行の準備として全ての債権者のために債務者の責任財産を保全するためのものです。
その確定判決の効力は、旧民法では、取消債権者と被告とされた受益者ないし転得者及び全ての債権者の利益のためにその効力が生じるとされ、債務者との間には生じないとされていました。
そのため、取消債権者の詐害行為取消権により損失を被った受益者は、例えば、債務者と受益者間の(詐害)行為は有効であるため、債務者に契約責任を問うことはできず、債務者に対して不当利得返還請求(703条)等をすることにより損失の補填をするしかありませんでした。
詐害行為取消訴訟により債務者の詐害行為が否定されたはずなのに、以前として債務者の詐害行為が有効とされることは法律関係をいたずらに複雑にしますし、皆さんも違和感を感じると思います。
そこで、改正民法ではこの点が修正され、詐害行為取消権の確定判決の効力は、債務者及びその全ての債権者に対して効力が生じるとされています(425条)。
【権利行使の時期的制限】
詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを取消債権者が知ったときから2年が経過するまでに訴えを提起しなければ、行使できなくなります。
また、詐害行為時から10年が経過したときも訴えを提起できなくなります(426条)。
旧民法では、上記期間制限は時効に基づくものとされていましたが、改正民法ではそのような定めはされていません。
というのも、詐害行為取消権は、裁判所に訴訟を提起することでのみ行使が可能な権利であり、訴訟外でも行使可能な実体法上の権利とは異なります。
このような性質から、この期間制限を、消滅時効というよりは除斥期間・出訴期間と捉えた方が適格であるため、改正民法では期間制限を時効に基づくものとはしていません。
そのため、当然のことですが、時効にみられる中断等もこの期間制限にはありません。
また、期間についても、旧民法では「詐害行為時から20年」とされていましたが、20年もの長い年月、詐害行為取消権の行使を債権者に認めることは取引の安全を不当に害するとともに、過度に債権者を保護することにつながるとして、改正民法では前述のように「詐害行為時から10年」とされています。
いざ詐害行為取消権を行使しようといくら証拠を完璧に揃えても、上記期間を徒過していれば意味がなくなってしまいますので、詐害行為取消権行使の際には、その点に十分にお気を付け下さい。