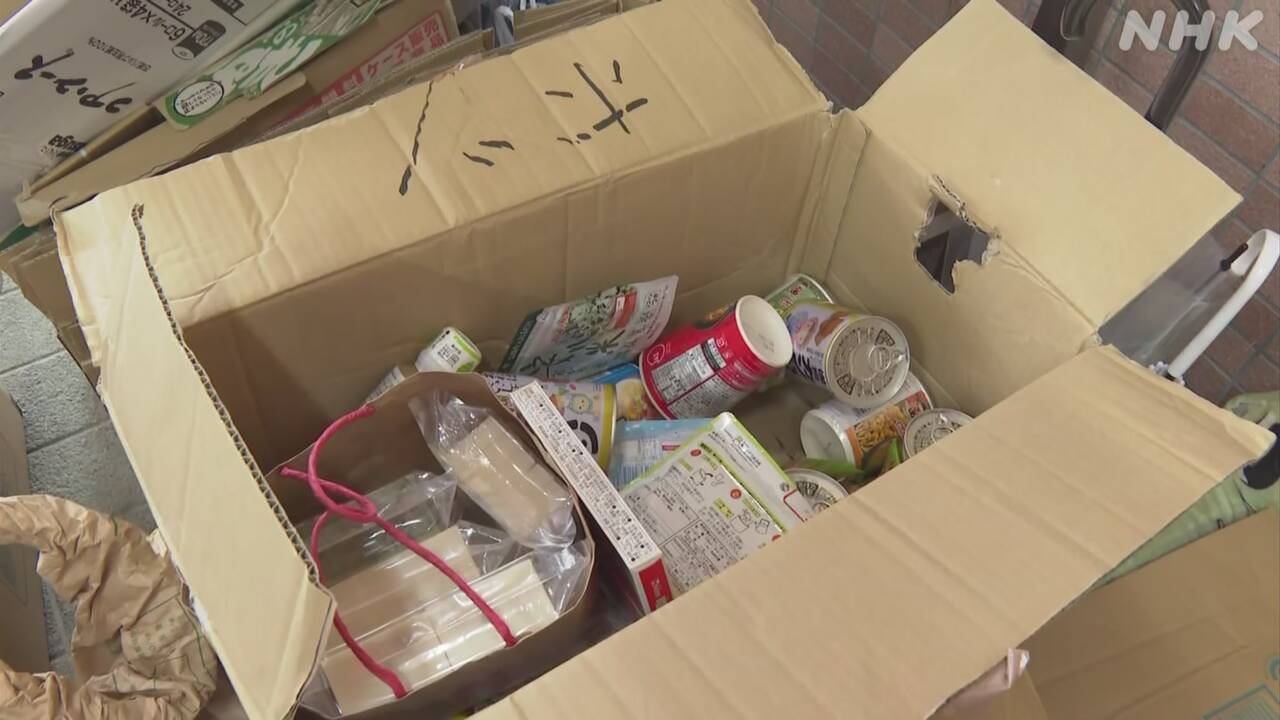どうしたの❓
また何かあったの❓

うーん、レポート通りかぁ・・・。そのレポートって、一体いつのやつ❓ 最近受けたレポート❓

3年前❗❓3年前からずっと同じアプローチ続けてたの❓

いやいや、レポートに書かれている栄養アドバイスは、その時の状態に対して需要が高かった物しかアドバイスされてないよ。実際には体の状態は加齢や生活習慣などで変化するから、定期的に検査を受けてアプローチを見直していく必要があるんだ。

よく勘違いされる事が多いけど、オーソモレキュラー療法の検査は定期的に受けて初めて意味がある物なんだ。
一回受けただけだと、逆にお金の無駄になっちゃうよ。ナンナンのアプローチも、もしかしたら無駄になっているかもね
オーソモレキュラー療法では、血液検査を受けるごとに分子栄養学的解析とアプローチのアドバイスがレポートが送られてきます。
例えば、ケンビックスのオーソモレキュラー療法を受けると、血液検査結果を解析した「メディカルレポート」と、分子栄養学的アドバイスが書かれた「栄養レポート」が送られてきます。
メディカルレポートの例
栄養レポートの例
もし今、このようなレポートを持っている方は、レポートのアドバイス内容を参考に栄養アプローチを行っているかと思います。何をどれくらい摂れば良いかの目安が具体的に書かれているので、分かりやすいですよね。
ただ、このレポートの内容は、一生ずっと参考になるわけではありません。最低でも一年に一度は再検査を行い、定期的に見直していくことが必要です。
なぜなら、レポートの内容は血液検査を受けた時点の「現在の状態」において「需要が高いもの」を優先的にアドバイスされているだけだからです。
例えば、私達の体の中では、常に体内に侵入してきた細菌やウィルスと闘っています。発熱や倦怠感などの自覚症状が無くても、これらと闘っている場合は好中球やリンパ球などの数値に変化が現れます。
仮に、血液検査の結果でこれら数値から感染症などの疑いがあった場合、レポートに書かれる分子栄養学的アプローチは、感染症によって消耗や需要が大きくなる栄養素等を優先してアドバイスが行われます。
また、人によって何らかの自覚症状の強度が高かった場合、その自覚症状の原因と関連のある栄養素や、自覚症状によって消耗や需要が高まる栄養素が優先的にアドバイスされます。
つまり、レポートに書かれている栄養アドバイスは、血液検査を受けたその時の状態に対して消耗や需要が高まっているものが優先的にアドバイスされているだけなので、その栄養アドバイス通りに一生飲み続ければ良いという物では無いんですね。
よく、オーソモレキュラー療法の検査は「足りない栄養素を調べる検査」だから、一回受ければ十分と思ってしまう方が多く見えます。初心者の方に多いのですが、これは大きな間違いです。
私達の体の状態は加齢や生活習慣、環境など様々な要因によって変化しています。その変化に応じて、私達の体に必要な栄養素や、消耗・需要が大きくなる栄養素も変化します。分子栄養学では、このような経時的な変化に対応するために、定期的な血液検査を行ってアプローチを見直していくことが必要です。

それも、初心者によくある間違いだね。
サプリを飲んで血中濃度が上がったとしても、それで栄養が足りたからサプリが要らなくなるっていう訳じゃないよ。
分子栄養学は血中濃度だけで判断するんじゃ無くて、もっと視野を広げて体全体の状態で見ていくものなんだ
血液検査やレポートを参考にしていると、どうしても「この数値がここまで上がったら栄養が足りた」みたいに思ってしまいがちだと思います。
栄養が足りたなら、それ以上栄養を補給する必要は無く、オーソモレキュラー療法の血液検査も要らないと考えてしまいますよね。
しかし、分子栄養学の血液検査やレポートは、血中濃度だけで栄養状態を判断しているわけではありません。血中濃度はあくまで血液中にどれだけ栄養素や代謝関連物質などが溶け込んでいるかを調べているものです。実際には、それらを利用して活動している細胞の状態などでも判断する必要があります。
例えば、前回の記事ではレポートの見方として、血液検査が「高速道路を走るトラックが物をどれだけ運んでいるか」を調べる検査であるのに対し、体組成は「高速道路を降りた後の街がどれだけ発展しているか」を見ているということを解説しました。
例えば、BUNや総タンパク、アルブミン、フェリチンなどの数値は、血管内を通過する血液成分のうち、特定の成分がどれだけ含まれているかを調べています。そして、この血管を高速道路、血液成分を大型トラックに例えると、高速道路でどれだけトラックが荷物を運んでいるかを見ています。
そして、運ばれた荷物(栄養素)は、一つ一つの細胞に届けられ、それらを細胞が利用することで生命活動を行っています。その結果として表れるのが、体組成などです。
この体組成は、いわば高速道路を降りた後の「街」に例えることが出来ます。荷物を積んだトラックは、目的の場所で荷物を降ろし、それを消費することで家が建ったりお店が出来たりと、街が発展していきますよね。
この街が、どのくらい正常に発展しているのかを見ているのが体組成などになります。いくら血液検査結果のデータがよく見えても、この体組成(街)が全然良くなっていなかったり、偏っていたり、問題があったりした場合は、何かしら根本的に原因があると考える必要があります。
これら状態は加齢や生活習慣、環境など様々な要因によって刻一刻と変化するため、その時々に応じて適切なアプローチを行っていく事が必要です。
このあたりを少しわかりやすくするために、体全体を日本列島で例えてみましょう。
体全体を日本列島とした場合、血管を高速道路、高速道路を走る荷物を積んだトラックを血液成分、高速道路を降りた先の道を毛細血管、家や建物などの街並みを細胞と例えることが出来ます。
血液検査は、このうちの「高速道路を走る荷物を積んだトラック」がどれだけ走っているか、どれだけ荷物を積んでいるかを見ています。
例えるなら、よく聞く渋滞情報やトラフィック情報のような感じですね。高速道路が渋滞していないか、ガラガラに空いていないか、事故が起きていないかなどを見ています。イメージとしては、こんな感じです↓
ドライブトラフィックより
これはお昼過ぎの東名高速御殿場IC付近の様子ですが、名古屋方面へはガラガラですね。こんな感じで、荷物を積んだトラックがどれくらい高速道路を走っているのかを可視化するのが、血液検査の役割です。
このトラフィック情報は、皆さんもご存じの通り、時間帯や日によって刻々と変化します。年末年始やゴールデンウィークなど、人が大勢移動するときは混雑しますし、逆に平日の昼間などはスカスカに空いている時もあります。
血液の状態も同じで、私達が食べた食べ物や生活習慣、細菌やウィルス感染など様々な要因によって、刻一刻と変化しています。
この変化しているうちの一瞬を、「採血」という手法で一瞬だけ切り取って見てみるのが血液検査です。ちょうど、高速道路状況をカメラでパシャッと撮影したような感じです。
現代では高速道路情報なども動画や映像などでリアルタイムに確認することが出来ますが、血液の場合はそうはいきません。安全にリアルタイムで血液の状態を確認し続ける方法が現時点では存在しないので、経時的な変化を知るためには定期的に採血を行って推移を確認していく必要があります。たった一枚の写真だけで常に変化する高速道路の状況が分からないのと同じように、血液検査の結果もたった1回では分からないのです。
そして、もしこのトラフィック情報に何らかの異常や問題が見受けられた場合は、きちんと原因を究明して適切に対処していく必要があります。高速道路で言えば、路面状態はどうか、落下物など道路上に問題が無いか、事故などが起こっていないかなどがこれにあたります。
特に、走っているトラックの量が多く見えても、実はいつもスカスカで、この日は事故でちょっと車の流れが詰まっていて沢山走っているように見えた、みたいなこともよくあります。
走っているトラックの量だけで状況を判断するのでは無く、高速道路状況などもっと全体を見て判断する事、経時的に変化を記録して観察していく事が大切です。
では、より分子栄養学を理解するために、もう少し踏み込んだパターンも見てみましょう。先ほど、体全体を日本列島に例えました。私達が住んでいる日本列島では、日々普通に暮らしていても、地震災害や台風、火山の噴火など、様々な自然災害が襲ってきます。
最近では、お正月に起きた能登半島地震が記憶に新しいですよね。他にも、中国による領海侵犯、北朝鮮からの弾道ミサイルなど、様々な脅威に直面しています。
そして、これらと似たようなことは、実は私達の体の中でも日々起こっています。例えば、病気や怪我などですね。これら脅威から身を守ったり、体を修復したりするための材料を補給するのが、分子栄養学です。
具体的には、能登半島地震が起こった際、日本全国から支援物資が届けられました。この支援物資が、分子栄養学で言う栄養素のようなものです。
この栄養素は、「ただ大量に入れれば良い」と考える人が多いですが、それは間違いです。地震などで大きなダメージを受けた街を復興させるためには、その時その時の状況に応じて適切な物資を届けてあげる必要があります。
例えば、能登半島地震が起こった直後では、水と食料よりも「弾性ストッキング」の方が重要性が高いとして優先的に支援が行われました。これは、避難所などでエコノミー症候群を予防するために必要となるものです。
震災が起こると水と食料の方が重要そうに思えますが、実は災害用の備蓄が何日分か用意されているので、そこまで重要では無いんですね。
他にも、全国から良かれと思って送られてきた支援物資の中には、全く使えず処分することになったものも多かったと聞きます。
この中には、賞味期限切れの食料や、千羽鶴、着古した衣類や肌着など、被災地の方の助けにならず、役にもたたなかったものが多くありました。
これらはボランティアの方々の助けや税金を投入して処分され、処分費用や処分に関する労力が大きかったことから、結果的に「二次災害」として迷惑をかける事になってしまいました。
実は、これと同じようなことが私達の体の中や、間違った分子栄養学の実践においても起こっています。
先ほど、地震などで大きなダメージを受けた街を復興させるためには、その時その時の状況に応じて適切な物資を届けてあげる必要があることを解説しました。例えば、震災直後に必要な物資、ある程度インフラが回復してから必要になる物資、その後街を継続的に発展させていくために必要な物資など、同じ街(細胞)でも、時と状況によって必要なものや量は全く異なります。
体の中も同じで、体の中で炎症が起きているときに必要な栄養素や、ある程度炎症が治まってから必要になる栄養素、その後機能が正常に整ってから必要になる栄養素、その後更に機能を向上させたり維持していくために必要な栄養素など、同じ細胞でも時と状況によって必要なものや量は全く異なってきます。
このような変化に応じて柔軟に対応していかなければならない状況下において、
- マグネシウムが体に良さそうだからマグネシウムを摂り続ける
- 鉄が足りていないみたいだから鉄サプリを摂り続ける
といったような、特定の栄養素を大量に長期間摂り続けたらどうなるでしょうか?
先ほどの能登半島地震で言えば、ある程度インフラや避難設備が整っている状態で他の物資が必要にもかかわらず、震災直後に必要性が高かった「弾性ストッキング」をずっと送り続けたらどうなるでしょう?
当然、必要ないものや使えないものを大量に送られてきても困ります。使えないものは、処分するか、処分できないものは溜め込んでいくしかありません。これは体も同じです。
また、賞味期限切れの腐った食料を送りつけられても食べられないのと同じように、腐った栄養素や自然界に存在しない化学構造のものなどを大量に入れられても、体は使うことができません。
これらが体の中に大量に入ってくると、体は膨大なエネルギーを使用して処分する必要が出てきます。
つまり、あなたが良かれと思って大量に飲んでいるその栄養素は、実は体にとって二次被害となる迷惑な行為になっている事もあるんですね。
特に、「サプリメントの質」をよく理解していない方は要注意です。安いからといって、海外サプリメントやドラッグストアで売られているようなサプリメントを大量に飲んでいませんか?
栄養素は単に含まれていれば良いというわけでは無く、新鮮で体が自然に使える化学構造である事と、栄養素がきちんと消化・吸収され、栄養素同士が助け合って働けるように設計されていることが重要です。
体内で使えない分子構造の栄養成分や、鮮度を失って腐った栄養成分を大量に入れてはいけません。
特に無添加のものなどは体に良さそうに見えて逆効果となる恐れが高いので注意が必要です。
このような二次被害を起こさないためにも、今現在自分にはどのような物資(栄養)が必要なのか、送った物資がちゃんと使われているのか?をよく確認する必要があります。
その確認する手段として必要になるのが、定期的な分子栄養学の血液検査です。
分子栄養学は、サプリメントを飲んで血中濃度が上がったらそれでOKといったそんな単純なものではありません。血中濃度以外にも、栄養がきちんと使われているかや捨てられていないか、需要と消耗の度合いはどうかなど様々な面から分析する必要があります。
高速道路を走っているトラックや荷物の量だけで日本の経済状況が分からないのと同じように、適切な分析やアプローチを行うためには、もっと視野を広げて分析することが必要です。
そして、それぞれのステージにおいて、適時アプローチを見直していくことが必要になります。日本経済においても、ずっと同じ経済対策を続けていたらむしろ景気が悪くなってしまうのと同じように、栄養アプローチも見直しが必要です。
例えば、「調子が悪いから調子が良くなってから血液検査を受ける」と考える方がいますが、そうではありません。
悪いときにこそ血液検査を受けることによって、その時に消耗している栄養や需要が高い栄養素の栄養アプローチが分かります。
同じく、「元気になったらもう血液検査を受ける必要は無い」と考える方がいますが、それも違います。
元気になったらなったで、活動量が増えたり消耗する栄養が増えたりして必要な栄養素やアプローチが変わります。また、今度は体を作るための栄養も補給していく必要があります。
このように、体の状態は加齢や生活習慣、環境など様々な要因によって刻一刻と変化するため、その時々に応じて適切なアプローチを行っていく事が必要です。
分子栄養学は、病気が治ったら「はい、さよなら」というものではありません。健康は習慣で作られるため、健康習慣は一生続ける必要があります。
その最適な健康習慣を続けるためにも、分子栄養学の検査は必ず定期的に受けてアプローチを見直して下さい。

そうだよ。需要や消耗の度合いを考慮せずに大量に栄養素を摂り続けると、その栄養素を捨てたり調節するために体は大量のエネルギーを消耗することになるよ。
栄養アプローチは状態に応じて適時見直しが必要だから、必ず定期的に検査を受けるようにしてね。
本格的な分子栄養学を無料で学べる「分子栄養療ナビ」はこちら
オーソモレキュラー療法・無料栄養相談のお申し込みはこちら