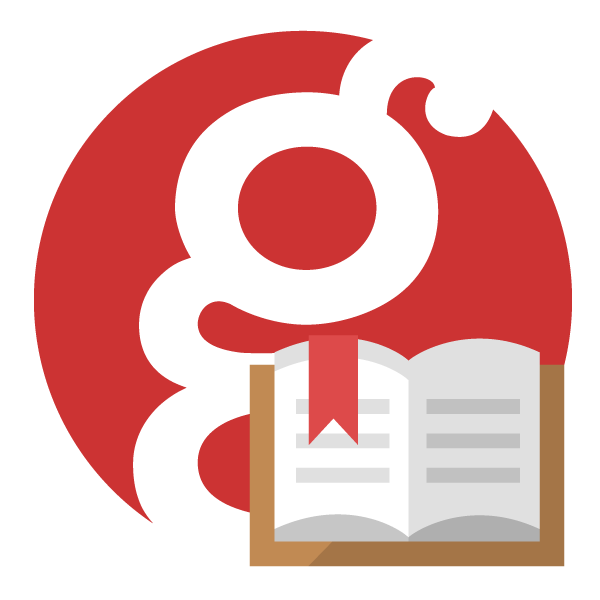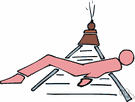ことしの6月上旬、土・日に、アニメ「佐々木とピーちゃん」を一気に見た。類は友を呼ぶというやつなのか。たまたま めぐりあったのが、強引だけど心やさしき星の賢者。人のいい佐々木は、ごたごたに巻き込まれることになるが、特殊な能力が使えるようになったり、人脈が形成されたりする。
とにかく、おもしろい。そして、オープニング主題歌がとてもいい。でも、うた の かし が なにをいっているのか ほとんど わからなかった。一気に見たせいもあるのかもしれない。1週間ごとに間をあけて見ていれば違ったかもしれない。
で、かしを かくにん してみて、うちのめされた。ずっと bird だと おもっていたのに、bond(きずな)だった。先入観もあったのか? だが、それだけではない よう に おもえる。
PV を見たら、I BELIEVE IN OUR BOND.で、メンバーが一斉に両腕を広げて、まるで鳥の翼のようだった。
ピーちゃんが鳥なので、主題歌が FLY なのは、とてもいい。「大切なものをこの肩に」って、作品をふまえてるなあ。
で、「パス」は pass じゃなくて path だったようだ。
わたしの耳は、あてにならないということが 身に しみて よく わかった。目で見て確認することにしよう。百聞は一見に如かず。SEEING IS BELIEVING. なのだ。
で、「佐々木とピーちゃん」を見終わってアメブロにログインしたら記事にコメントをいただいていて、ウェブサイトに行ってみたら、小鳥のイラストが! 色が違うけど、まるでピーちゃんと仲間たち(peeps?!)じゃないか。エヌ先生も、なんだか銀さんにしか見えないし。(そんなことはないだろう。)
とにかく絶妙なタイミングだった。行動するといろいろ手に入るものだ。それは現実世界でも変わらない。エヌ先生は、むかしから いろいろ がんばってきたのだろうな。