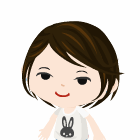海外からの来客が続き、観劇から遠ざかっていて半月ぶり!!の劇場通い。
新国立劇場でデカローグ(十戒をテーマにした10話)連続上演企画の第5弾と6弾を観た。
こちらはそのシリーズの1~4のレビュー ↓
***演劇サイト より *****
デカローグ5 「ある殺人に関する物語」 [演出:小川絵梨子]
タクシー運転手を殺害した青年と、若い弁護士。死刑判決を受けた青年を救えなかった弁護士の悲嘆。
街中でたまたま、傲慢で好色な中年の運転手のタクシーに乗り込んだ20歳の青年ヤツェクは、人気のない野原で運転手の首を絞め命乞いする彼を撲殺する。殺人により法廷で有罪判決を受けたヤツェクの弁護を担当したのは、新米弁護士のピョトルだった......。
キャスト:福崎那由他・渋谷謙人・寺十 吾・亀田佳明・斉藤直樹・内田健介・名越志保・田中 亨
----------
デカローグ6 「ある愛に関する物語」 [演出:上村聡史]
向かいのアパートに住む魅力的な女性の部屋を望遠鏡で覗く青年の何も求めない愛とは?
友人の母親と暮らす19歳の孤児トメクは、地元の郵便局に勤めている。彼は向かいに住む30代の魅力的な女性マグダの生活を日々望遠鏡で覗き見ていた。マグダと鉢合わせしたトメクは、彼女に愛を告白するが、自分に何を求めているのかとマグダに問われてもトメクは答えられない。その後デートをした二人、マグダはトメクを部屋に招き入れるが......。
キャスト:仙名彩世・田中 亨・亀田佳明・寺十 吾・名越志保・斉藤直樹・内田健介
***************
1〜4のレビューでも触れたのだが、何かボタンのかけ間違いがあるような、、人間の根源にあるドラマを描こうとしているのだろうが、それを今の観客に普遍のものがたりとして届けようとしているのにどうにもダイレクトに刺さってこない。
”わたしたちの今の話”からはあまりにも遠く離れたものが舞台上で行われている感覚を持った。
観ながら名作として今でも語り継がれている映画版(ドラマ版)のことを想像したのだが、観ていないのでなんとも断言できないが、おそらく映像版では映像表現と演劇表現の違いから—頭の中の想像、心象風景などを言葉ではなくイメージで映像表現するなど—そのあたりの違和感なく時を超えたものとして、それこそ誰にでも(どの国でもどの時代でも)刺さるものとなっているのではないだろうか。
なんだかむしょうに映像版を観たい気持ちになってきた。
また、ポーランドという国の当時(1990年前後)の社会状況が身にしみている自国、また隣国の人たちにはまさに自分の事としてさらにダイレクトに受けとめられたのだろう、ということも容易に考えられる。(なので、ポーランド情勢をちょこっとかじっていった方が良いかも)
一方、今の初台の劇場でこの人間ドラマを観ていると、、どうしても首を傾げる箇所が出てきてしまうのだ。
例えば、題5話「ある殺人に関する物語」では、
まず主人公の若い男の殺人に至る彼の、そして彼の家族の社会的バックグラウンドと彼らの不満の声がきちんと(言葉の補足でも、なんらかの補足の説明でも)伝わってなければ、弁護士の死刑制度に対する主張も死刑囚の最後の叫びも届かない。
(右から)福崎那由他、寺十 吾
撮影:宮川舞子
なんなら、冒頭の新米弁護士の死刑制度、ポーランドにおける司法制度、また現代の司法制度の限界に関する1分ほどの主張の台詞だけで、この話のすべては語られ尽くされていると言っても良いかもしれない。
最後はとてもショッキングなシーンで幕を閉じるのだが、それを観たあとで拍手をする気持ちに切り替えられる人は多くないはず。もちろん役者にありがとうの拍手をしたいのだが、なんとも複雑な気分になった。
カーテンコールは6話のあとにまとめても全体の流れとしては良かったのかも。
(右から)福崎那由他、渋谷謙人
撮影:宮川舞子
第6話は「愛」と「姦淫」についての話なのだが、、、今の私たちには未成熟なストーカーの話にしか見えない。
90年代にはそのような言葉は一般的ではなかっただろうし、その方法も主人公がとったような望遠鏡での覗き、郵便物の窃盗などが考えられたのかもしれないが(その意味では今の方がさまざまな方法がとられていて、内容も陰湿なのかもしれないが)、それでもやはり立派なストーキングで犯罪でしょう。
— これも映像では幼い「愛」のかたちとして成立していたのかも。でも舞台で今日生身の人間に表現されると??なぜ??となる。
(右から)仙名彩世、田中 亨
撮影:宮川舞子
俳優では繊細な演技でみせた寺十吾、見事な存在感をみせた仙名彩世、両作を通じて重要な役どころを担った名越志保が光っていた。