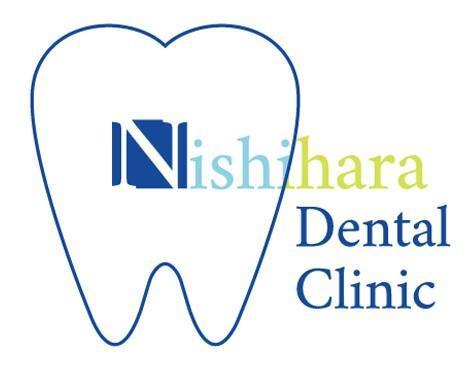さて、ウイルスはどうするだろう···。
から、の続きです。
ウイルスは、ただただ自分で分身を増やすことだけを目的に行動します。
勘弁願いたいですよね。
今日は急なキャンセルで時間が空きましたので、(泣)さて続きを。
ウイルスは、前回書きましたが
DNAを複製し自分の分身をつくる。
その場所が、ヒトであれ、動物であれ細胞本体になります。
その細胞に入り込むというのは、ヒトは、外敵であるもの(ウイルスや細菌等)を自己か非自己かを免疫細胞や白血球などが判断する訳です。
悪いものは排除し、吸収したいものは受け入れる仕組みになっています。
新型コロナウイルスに関しては、
外側のひげのようなSタンパクが細胞表面のACE2受容体とくっつき細胞膜とウイルス表面が融合し、細胞に中に入り込みます。
この融合の際のハサミの役目を口腔細菌が関与しているとも?
○受容体: 細胞表面にある鍵穴のような構造体
故にそのSタンパクがいわゆる細胞に入るためカギ(きっかけ)になります。
今だに、細胞内に入って自分の分身を作るときに、間違って遺伝情報を作ってしまうのです。これが変異と言われるものです。
要するに、自分の分身を作る際のエラーが変異であり、その構造変化が、人体への良い影響(壊れたり)だったり、悪い影響(感染力が強まったり、免疫を回避できるようになったり)に変わる訳です。
ウイルスは、分身しつづけたいために、他の細胞あるいは、他の個体へ移動したいのです。
それが、人の咳や飛沫の中にウイルスが存在すると、移動出来てしまうという事です。
その移動が可能な状況が、発症前3日と言われています。
この発症3日前程度が非常にこのウイルスの厄介な所でそれは、残念ながら変わっていません。
それは、ウイルスの個体の性質という事を理解しなければなりません。
また、その発症後、研究が進み7日〜10日に変わって来ましたが、まだその後でもウイルスが他人へうつるリスクは少ないですが可能性としてはあり得ます。、それは多少の誤差があるという事という認識です。
さて、口腔細菌とウイルスの関係性。
入り込む受容体、ACE2受容体。
これは、体の各部に局在しています。
肺や鼻腔粘膜、あとは、舌粘膜。
粘膜の表面。
口腔ケアで、細菌の数を少なくすると、
それが予防に繋がる訳です。
ある細菌が、そのウイルスに関与しているとの話も出てきているようです。
いずれそれも知れる事でしょう。
細菌は様々な代謝産物があります。
ある種の物質が、免疫のスイッチをいれたり、ウイルスの活性を高めたりする訳です。怖いですね。
【最新の知見を紹介します。】
○歯周炎と新型コロナウイルス感染症重症化と関係している。死亡リスクが、約8倍。
○白血球数とある種のタンパク質はが増えてしまう。 J.Clinical.Periodontal.
○歯周炎は新型コロナウイルス感染症の死亡率を高める。(14.6倍)Lancet 2022
○歯周炎の重症度と新型コロナウイルス感染症罹患は関連性がある。17.7倍
J of clin periodontal.2021
○新型コロナウイルス陽性者で歯周病を有するものの死亡率が高い。 Int Med 2020
新型コロナウイルスにかかると、体力が落ちます。すると歯磨きや口腔ケアが出来なくなります。
元々歯周病がある方は、それが悪化してしまいます。
口腔ケアの困難さから、体調の悪化も引金になってしまう。
歯周病治療は、やはり重要で、初期治療がとても重要であることは言うまでもありません。
これだけ、口腔細菌とウイルスの関係があるという事実を踏まえ、当院は、何も症状がない状態で、口腔細菌を減少させある意味リセットし、健康維持のため定期的な口腔ケアの推進をしています。
新潟市西区小針南台3-6
西原歯科クリニック
ご予約はこちら↓