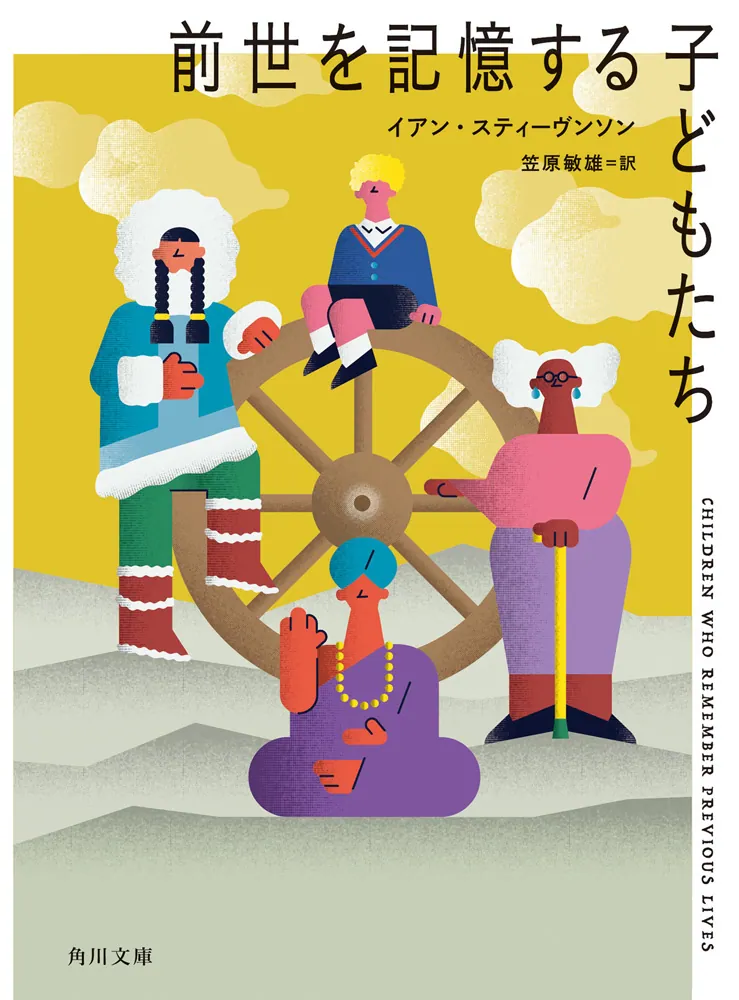たまたま図書館の書架で目にして、題名に興味を惹かれて借りました。
これまでにも少し聞き及んでいた現象ではあったのですが、初めてきちんと本で読み、やはり衝撃的でした。
この本は、世界中で報告されている、前世の記憶がある子どもたちについての研究内容を紹介するものです。
著者のイアン・スティーヴンソン(1918年 - 2007年)はもう亡くなりましたが、米ヴァージニア大学教授。この分野の第一人者で、膨大な著書や論文を発表している研究者とのこと(なお同大学はトーマス・ジェファーソンが創立者という、歴史ある大変な名門です)。
この本は一般読者向けの概説書です。
さて、
ここまでの紹介でもう「その手の話」として拒否感のある人もいるかもしれません。
ただ、私はそうした人にこそ読んでほしいと、真剣に考えています。
この本は、いわゆるスピ系の本ではありません。
根拠なく魂だのエネルギーだの波動などを語る、私の大嫌いな本ではないのです。
国も文化も異なる多数の国々で、前世の記憶がある子どもたちが観察され、しかもそこに一定の類型があることについて、その理由を探求しようとする研究書です。
世の中には、他人の前世がわかる主張する人たちがたくさんいます。
また、前世の記憶があると主張する大人も、たくさんいます。
しかし著書は、そのいずれも研究対象としてほぼ無価値であるとして、取り合いません。
理由は簡単で、信頼性に著しく欠けるからです。
著書が調査の対象を子どもに絞っているのはまさにこのためです。
子どもの場合、過去に生きた人物の情報を入手する経路が大人に比べて非常に限定されているため、記憶のもとになる情報がどこかから伝わったのではないかを検証することが容易です。
この本で紹介される事例は「自分は前世で武士だった」とか、そういうレベルの話ではなく、前世の人物を完全に特定できるものを多く含みます。
そしてその前世の人物は、世間で知られる有名人てはなく、ごく普通の市井の人、「◯県◯市で会社員をしていたが、自動車事故て亡くなった◯◯さん」のような人なのです。
それら子どもは、前世での自分や家族の名前、住んでいた場所、仕事、そして多くの場合、自分が死んだ時の状況について語っています。
前世の記憶を話し出す年齢は2歳から5歳までの間がほとんどで、これは地理や文化にかかわらずほぼ同じだそうです(インドの235例、アメリカの79例て両国の平均は3歳2カ月て全く同じだったとのこと)。
そして、大多数が5歳から8歳までの間にその記憶を喪失してしまいます。
著者によれぱ、この時期は言葉が急速に発達し、視覚的イメージが失われる時期と一致しているため、そのことと関連しているのではと考察しています。
また、前世で横変死した者の割合が極めて高く、自分の死にざまを覚えている子が4分の3近くにのぼるとのこと。
自分を殺害した犯人を街で見つけて殴りかかろうとした子どももいたそうです。
一方で、前世で死亡してから現世で生まれるまでの記憶を話す子どもはほとんどいない。
「雲の上からお母さんを見つけて、優しそうだったからお母さんのところに生まれて来た」のような親が喜ぶエピソードで、厳格な検証に耐えるものはほぼ存在しないということです(ただし、全くないわけではない)。
私がこの本を読んで感じたことは、もっと多くの研究者に、この問題について真剣に取り組んでほしいということです。
なぜなら、例えこうした報告の99.9パーセントが誤りや虚偽だったとしても、その中に1件だけでも厳格な検証に耐えるものがあった場合、私たちの(現状で常識的とみなされている)世界観は、根本的に変更を迫られるからです。
数学の背理法と同じです。
こうした子どもたちの存在が、生まれ変わりや魂の存在を示しているのかは、わかりません。
著者自身も、「生まれ変わりという考え方は最後に受け入れるべき解釈なので、これに変わる説明がすべて棄却できた後に初めて採用すべきである」と述べています。
重要なのは、こうした記憶を語る子どもたちが実際に存在しているという事実です。
ならば、それは何を示唆しているのかを考えるのが科学のはずです。
それをせずに、単に「あり得ない」と思考停止するなら、それは、そうした自らを合理主義者と自認する人々が批判する、世の迷信や妄信にとらわれている人々と全く同じだと思います。
つまり、観測と計算が可能なもへの無批判の信仰です。
でも、人間は自然そのものを観察することはできず、人間が用いうる手段で自然に働きかけ、観測できた結果から自然の姿を推測できるにすぎない、という当たり前の事実を、よく考えるべきだと思います。
考えてみれば、相対論も量子論も、たぶん創始から100年さかのぼった時代であれば「あり得ない」と嘲笑されたのではないでしょうか。
結局私たちが「科学的」だと考えるものは、その時代における科学をあてはめるものでしかありません。
そもそも前世どころか、私たちの科学では、自分自身の意識がなぜ・どのように生じるかさえ、ほとんど全くわかっていないのです。
私はいつか、意識、心、記憶といった問題について、人間が現在とは全く異なる新しい科学を手に入れることを期待しています。