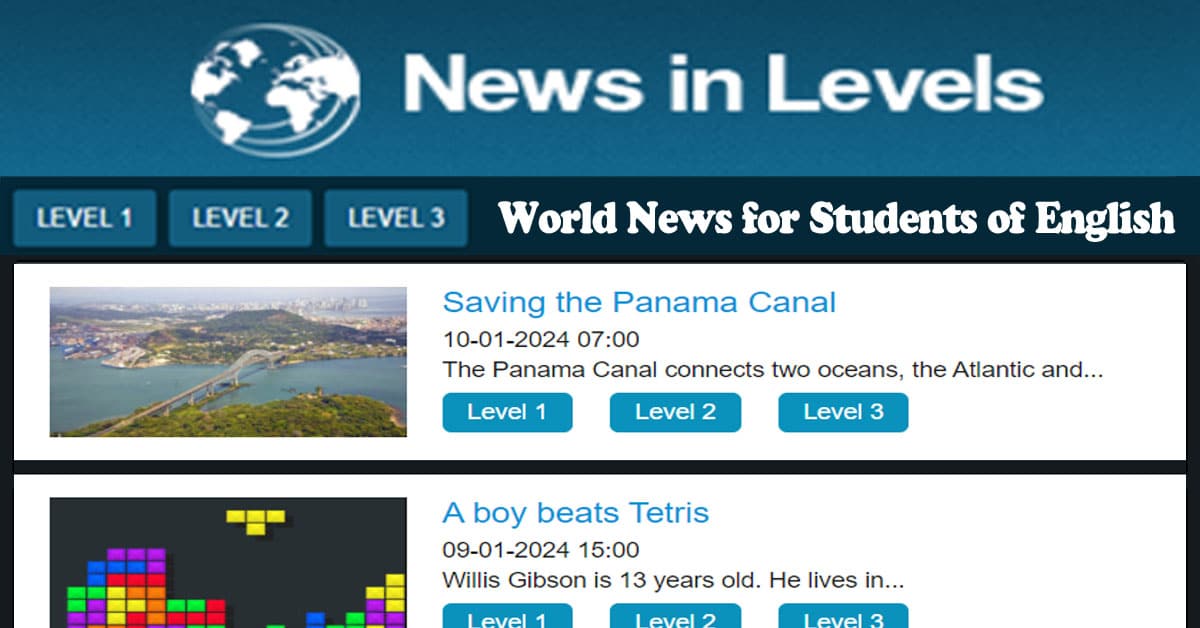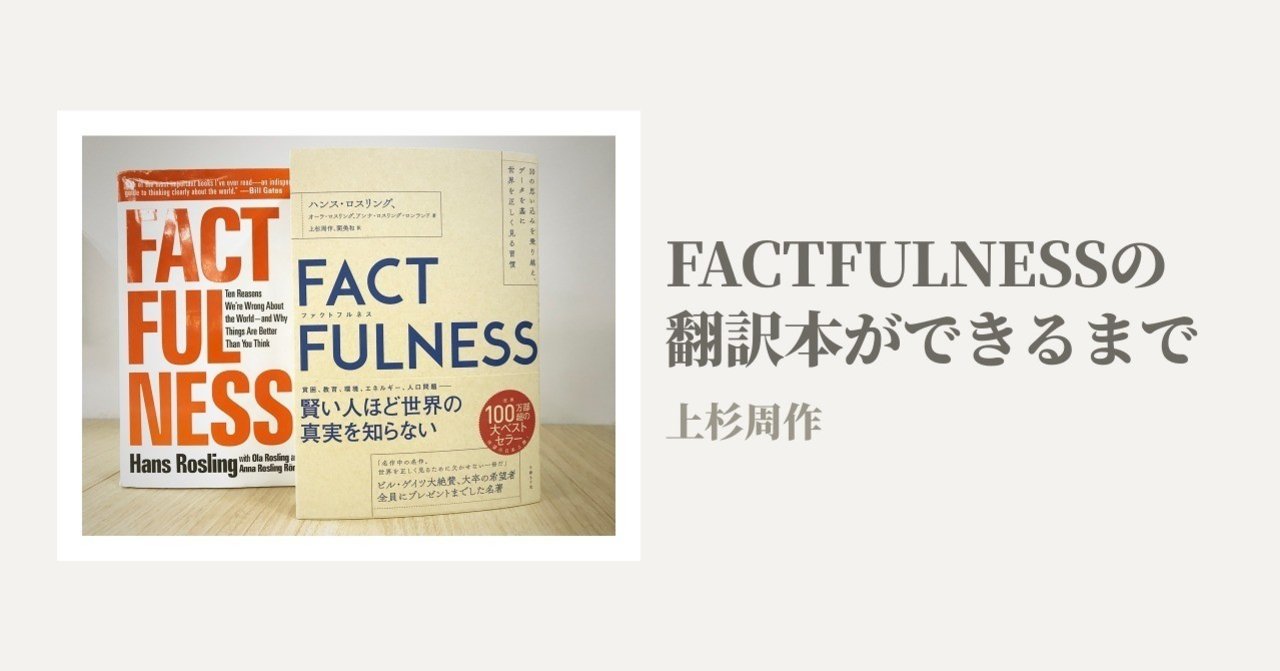題名が長くて書ききれなかったのですが、副題までちゃんと書くと、
『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』。
長いですが、原著のほうも長くて Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think とのこと。
「ファクトフルネス:私たちが世界を誤解する10の理由-なぜ世界はあなたが考えるよりよくなっているのか」とかでしょうか。
ビジネス啓蒙書として売られる本では原題と邦題が全然違うこともありますが、そうでないところには好感を持ちました。
著者はハンス・ロスリング(とその息子夫婦)、訳は上杉周作、関美和の各氏です。著者はスウェーデンの医師、公衆衛生学者。2017年に亡くなりました。本書はその後、2018年に出版されています。
この本は読書会の課題本となったので読みました。
私は知らなかったのですが、世界的なベストセラーとのことで、帯にも「ビル・ゲイツ大絶賛」とうたわれています(ビル・ゲイツが絶賛するとなぜすぐれた本ということになるのかは、よくわからないですが・・・)。
本の詳しい紹介は種々のサイトでもすでにとても多く投稿されているので、内容の紹介は必要な範囲でごく大まかに書くだけにします。
それは、
① 私たち(先進国と言われる国々の人)は、思い込みを生む10のパターンに陥ることで、世界の大半の国々はいまだ飢えや病気に苦しみ、十分な教育も受けられずに貧しい生活に甘んじている、というイメージを抱いている。
② しかしそれが誤りであることはデータから明白で、それら国々の多くはその後発展し、世界の生活レベルは確実に、大幅に向上している。先進国と途上国の分断など存在しないし、世界はどんどんよくなっている
というものです。
①の思い込みを生む人間の「本能」として、「単純化本能」「犯人捜し本能」などの名で10あげられています。
これらが全て本能(先天的なもの)とまでいえるのか少し疑問は感じますが、多くの人にそうした傾向があるのは確かだと思います。
その「本能」の内容はすでに多くの社会学や心理学の文脈のなかで言われてきたものだと思いますが、それを、世界の生活水準に関する指標という、計測可能なデータを使ってあぶりだしたこと、その「本能」を否定した先に「世界はよくなっている」というメッセージを接続させたことが、本書の独自の点と感じました。
著者の主張はデータに基づいていて明快です。
特に異議はありません。
そのうえで、私が考えてしまうのは、著者が人生の集大成としてこの本を出版した、その後の世界です。
著者は世界は分断などしていないと言います(第1章「分断化本能」)。
それは先進国と途上国についての、主として経済的な格差についてでした。
その点は特に異議なしなのですが、でも、その後の世界では、分断はやはり深刻な問題であり続けていると感じます。
そしてそれは、単なる経済問題ではなく、人間や社会に対する態度そのものの分断であるように感じます。
同じ生活水準の国々の間で戦争が起こる現実があります。
また、同じ国の中でさえ、アメリカのように世論が真っ二つになってしまっている国もあります。
事実を見る。
著者が人生をかけて訴え、この本も世界的ベストセラーになったはずなのに、今も事実どころか、全くの嘘デタラメを平然と叫ぶ指導者と、それを喝采する人々が勢力を得ています。
彼らは、著者が戒めた10の「本能」を正すどころか、問題を「単純化」し、「犯人捜し」をし、犯人を排除して社会を「分断化」することを積極的に推し進めます。
この本で「犯人捜し本能」のエピソードとして、梅毒について、国によって呼び名が違っていた事実が紹介されていました。
ロシアではポーランド病、ポーランドではドイツ病、ドイツではフランス病、フランスではイタリア病、イタリアではフランス病と呼ばれたそうです(本書275頁)。
恐ろしい感染症の原因は外国だと、皆が思いたがったということです。
笑い話のようです。
でもまさに、トランプ政権が新型コロナウイルスを「中国ウイルス」、「武漢ウイルス」と呼んでいました。
ウイルスの感染源を外国に押し付けたとしても、パンデミックの現実は何も変わらないのに。
うまくいけば、いずれ、世界中の国々が先進国(著者のいうレベル4)の生活ができるようになるのかもしれませんし、私もそれを望みます。
しかし、生活がその水準に到達した国は、結局、別の分断や行き詰まりに直面するのではないか。
そしてそれは、著者のような人々が尽力してきた、生活水準を引き上げる努力とは全く別の方向の努力が必要で、人間はそれに対する解決法をまだ持っていないのではないか。
私はそういう恐れを感じてしまいます。
ところで、本書は訳者のひとりである上杉さんがnoteに翻訳の経緯を投稿してくださっており、ひとつの翻訳が仕上がるまでの過程を知るという意味でも興味深い内容です。
本書を読まれた方にはお勧めします。