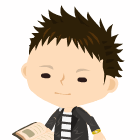たぶん『はてしない物語』と並んで、ミヒャエル・エンデの最も有名な作品のひとつだと思います。
子どもの頃に読んだ人も多いのでは。
私も小学校高学年のころ読んだ記憶です。
今回、読書会の課題図書になったため読んたのですが、気づけば、モモよりも道路掃除夫ベッポや居酒屋ニノの年齢にずっと近い大人になってしまいました。
今読むと、かなりあからさまな現代社会批判が前面に出ていて、「思想やイデオロギーを語るために物語が奉仕してしまっている」と、あまり評価しない意見があるのもわかる気がします。
要するに、ちょっと説教くさい![]()
子どもの頃は、時間泥棒か何を意味するのかはよくわかりませんでした。
灰色の男たちは形のない時間をどうやって盗んでいるんだろう?
盗まれている人は何も得していないのになぜ節約を続けるのだろう?
など気になりつつ、単純にファンタジー小説として読んでいました。
灰色の男たちは極端な効率主義や合理主義を擬人化したものたと思うのですが、これを子どもが理解するのはとても難しいと思います。
実際、私は全く理解できなかったし、教訓として何かを心のなかにとどめておくことはできませんでした。
今回読んで少し不満に感じたのは
社会批判はわかった、では、著者はどうすべきと言うのだろう?ということです。
神様のようなマイスター・ホラの超常の力とモモの活躍で、灰色の男たちは退治されます。
でも、社会で生活する大人や子どもたちは、結局最後まで何もできません。
子どもたちが決行したデモは失敗し、モモの大事な2人の友人も灰色の男たちに取り込まれてしまいます。
現実にはモモはいない世の中で、私たちはどうすべきだとエンデは言いたかったのでしょうか。
このあたりが当時『逃避文学』だと批判された点なのかもしれません。
一方で、大人になってからこそ味わえた楽しさもありました。
時間の花の描写は、子どもの頃は全く印象にものこっていなかったのですが、今読むと大変美しく、モモが泣きたくなった気持ちがわかります。
どの花も同じものはない美しさで、次々に咲いては散っていくそのイメージは、この一瞬一瞬がもう絶対に戻ってこないという痛みを知る大人になって、はじめて味わえたものでした。
児童文学というのは難しいなと思いました。
児童文学は、何か「善いもの」を子どもに手渡すという使命を負っているのだと思います。
しかも、子どもがそれを理解し、または理解できずとも心のなかにとどめておけるように書かないといけない。
それは、たぶんとても難しい。
現実の残酷さをそのまま書いて何も問題がない「大人の」文学とは根本的に違います。
そう考えると、児童文学は作り手にとっては大人の文学よりよほと困難な仕事ではないかと思えてきます。