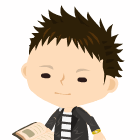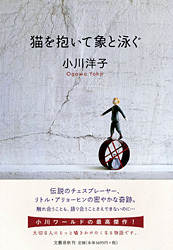先日読んだ『ことり』が素晴らしかったので、続けて読みました。
小川ワールド全開でした。
やはり、ひんやりと静かな、閉じた世界です。
ただ、世界の隅で言葉にならない何かを語っている人を描くという、『ことり』とも近い内容だったはずなのに、私自身は『ことり』の方がずっと好きでした。
というよりも、『猫を抱いて象と泳ぐ』は、読み終わって戸惑いがありました。
それがなぜなのか、というのが、この作品についての私の考察になりました。
この作品では、いかにも著者らしいと感じる、秘密めいた、たくさんの人や物が登場します。
チェス盤の下に潜ったまま指す、成長しない少年。
成長してデパートの屋上から降りられずに一生を終えた象。
地下のプールを改造した秘密のチェスクラブ・・・。
ただ、それらの道具立てが、著者が描きたかったことにどう結びついているのか、読んでいてよくわからなかったのが、戸惑いの理由のようです。
思わせぶりな道具は、ほかにも多く登場します。
夜のプールの溺死体。
脛毛の生えた唇。
250キロの肥満で死亡してクレーンで釣り上げられる男の死体。
壁に挟まれたまま死んだ少女。
奇妙な匂いを放つ布巾を絶対に手放さない祖母。
成長を止めた大人が中に入ってチェスを指す人形。
性加害を目的とした地下の人間チェス・・・。
こうして並べてみると、思わせぶりというよりも、グロテスクというのが近い気がします。
著者の作品には、どこか歪だったり、心身のどこかが欠落した人が多く登場します。
それが独特の魅力なのは間違いないのですが、この作品では、ちょっと生理的に嫌悪を感じてしまいました。
特に人間チェスについては、少女(ミイラ)の反応も含め、こんな小道具の一つのように扱っていいのかと、困惑しました。
これらが作品の感動に結びついていればよいのですが、私にはいまひとつ、それがわかりませんでした。
技術的な問題として、チェスというものの難しさもあったと思います。
私はチェスのことは全く知らないため、チェス自体の美しさ、奥深さは、どうしてもこの作品を読んだだけではわかりません。
これが、『博士の愛した数式』のオイラーの公式のようなものであれば、素人なりにその美しさがわかるのですが・・・。
そこがわからず、周囲の設定や道具ばかりが目についてしまう、というのが、私の一番大きな不満のようです。
ただ、レビュー等ではほとんど例外なく絶賛されているようだし、この作品についての私のアンテナが単に弱かったのかもしれません。
村上春樹もそうですが、リアリズムによらず、決してわかりやすい内容ではないのに、これだけ広く読まれている作家はなかなかいないと感じます。
著者の本作品についてのインタビューがありました。
著者が数学、チェス、小鳥の歌声を素材に選んでいったのは、言葉以外の、世界の秘密につながる美しい方法としてだったのだなと、納得しました。