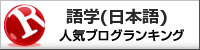朝から一日、三鷹の国際基督教大学へ。
これに行ってきました。

かれこれ5,6年くらい前から毎年参加しています。
毎年の楽しみの一つです。
1年ぶりの「バカ山」。
ICUの在校生、卒業生、関係者なら知っていますが、
校内に本館の前には広いきれいな芝生が広がっています。
この芝生に存在する二つの丘、一つをバカ山、もう一つをアホ山と呼びます。
この名前の由来は、「この丘で寝てばっかりで授業をサボっていると単位を落としてバカかアホになるぞ」ということだとか。
この話は数年前の小出記念研究会で知りました。
天気のいい日には、学生たちはこの芝生でランチを食べたり、
遊んだりしているそうです。土日は家族づれなど一般の方も
ここにランチを食べたり、遊んだりしています。
今年はさすがに暑すぎて誰もいませんでした。
そんなICU名物のバカ山を見ながら、会場へ。
回を重ねるごとに内容も充実、来場者も増え、大盛況です。
この研究会は会費のわりに内容が充実しているので毎回参加しています。
基調講演が内容が毎回素晴らしい内容、
そして、ポスター発表で今の研究のトレンドも探れ、
自分が関心のあるテーマの発表を聞けること、
ブックバザールで運が良ければ、掘り出し物の本に巡り合えること、
終わった後のお茶会は無料参加。いろいろな方とお話ができ、大変魅力的な
研究会です。![]()
とにかくアットホームで素敵な研究会なんです。![]()
この会は日本語教育に多大な貢献をされた小出詞子先生
(国際基督教大学名誉教授・姫路獨協大学名誉教授)の
古稀をお祝いする会(1991年)が発端となり、
1992年に発足した全国規模の研究会で、
日本語教師養成に非常に力を注いでいた小出先生が
お亡くなりになられた後も小出先生の意思を受け継ぎ、
お弟子さん達がこの会を存続しています。
私は5・6年毎年参加していますが、今回は普段の倍の来場者で
予稿集も席も足りないない事態で、基調講演のレジュメも足りず
急遽コピー対応に追われていました。
何と200人を超える来場者とは、関心の高さが伺えます。
事務局も予想以上の反響で、嬉しい悲鳴だったようです。
私は一足遅く、予稿集を手にできず、何もない状態で
講演や発表を拝聴しました。
毎年参加していますが、予稿集や関が足りなかったということは
未だかつてなく、後日、予稿集は配送してくださるとのことでした。
この研究会で毎回一番の楽しみは基調講演です。
今年は大阪大学の青木直子先生。
「教えるのをやめる ―言語学習アドバイジングというもう一つの方法―」
日本語教師ならだれでもしっている「学習者オートノミー」
これは青木先生が研究されている分野で、
日本語教育能力検定試験で出題され、検定対策本の用語集などに
載っています。
「学習者オートノミー(learner autonomy)とは、学習者が自分で自分の学習の理由あるいは目的と内容、方法に関して選択を行い、その選択に基づいた計画を実行し、結果を評価できる能力のことをいう」
日本語教育では1990 年代以降、自律学習という用語とともに使われるようになりました。
詳しくはこちら→ 学習者オートノミー
学習者オートノミーとは、青木先生によれば、
「自分の学習に関する意志決定を自分で行うための能力であって、またその能力を使う権利」
「自分の学習について自分で決めるというのは、学習の目的、目標、内容、順序、リソースとその利用法、ペース、場所、
評価方法を選ぶということ」
詳しくはこちら
↓
学習者オートノミー、自己主導型学習、日本語ポートフォリオ、アドバイジング、セルフ・アクセス
来場者は、この講演を拝聴に殺到したのではないかと思いました。
今、日本語教師の多くは学習者のモチベーションの低さ、
そういう学生への動機づけなどに悩んでいることが多いかと思います。
自立学習のためにはどうすればよいのか、
雲をつかむ思いでこの講演に来たのではないかと思いました。
関心の高さがうかがえました。
しかし200人以上も来場者とは凄いですね!
青木先生の非常に内容の濃い、素晴らしい講演でした。
往々にして、教師は学生に期待しすぎ、あれもこれも教えすぎていたり、
学習者が意図してしない教え方をして押しつけていたりしてしまいがちです。
学習者の学習法も千差万別。
それをこれが「いいからこれをやりなさい」と
教師が一方的に押し付けていないか。
また、学習者がそれを期待しない場合、学習者にしてみるとどうなのか。
それならば「教えることをやめてみる」ことだと。
『教えることで学習は起きるとは限らない』
↓
『「教える」ことで「動機」は生まれない』
↓
『教師は学習をサポートしていく』
↓
「教師は言語学習アドバイザー」
コーチングのプロでもカウンセリングのプロでもなく
言語教師として専門性があり、言語学習の上でのプロである。
↓
「アドバイジングは言語学習のプロセスに関する気付きを促すことにつながる」
学習の成果を自己評価し、自分の学習について振り返りをするのを
助けること
学習者が自分にとって最善の学習方法(と自分には合わない学習方法)を
発見する機会を増やすこと
アドバイジングはコーチングに似ているが質問の仕方が違う。
質問はYESかNOで答えられる質問ではNG。
質問の仕方に工夫する。→考えを深める質問をする
「選択肢を提供する」
「考えに自由を与える」
「押しつけてはいけない」
これは日本語教育以外にも、子育て、夫婦間、部下への質問
の仕方にも大いに応用できつのではないかと思いました。
青木先生の講演はたくさんの気づきを与えてくださいました。
講演を拝聴しながら、普段学生に自分の意見をおしつけていたり、
教えすぎていたと反省の連続…。![]()
![]()
ポスター発表では学習者オートノミーの研究発表をされている方が
多く、大変興味深かったです。
中にはアドラー心理学、アサーションなど心理学の要素を取り入れて
研究されていました。
非常に興味深かったです。
またピアで授業を工夫されている方も多く、
大変勉強になりました。
自分の授業でも大いに役立ててけるものもあり
授業のヒントをたくさんもらいました。![]()
やる気スイッチも入り、これからの授業に
大いに役立てていきたいと思いました。
非常に充実した一日でした![]()