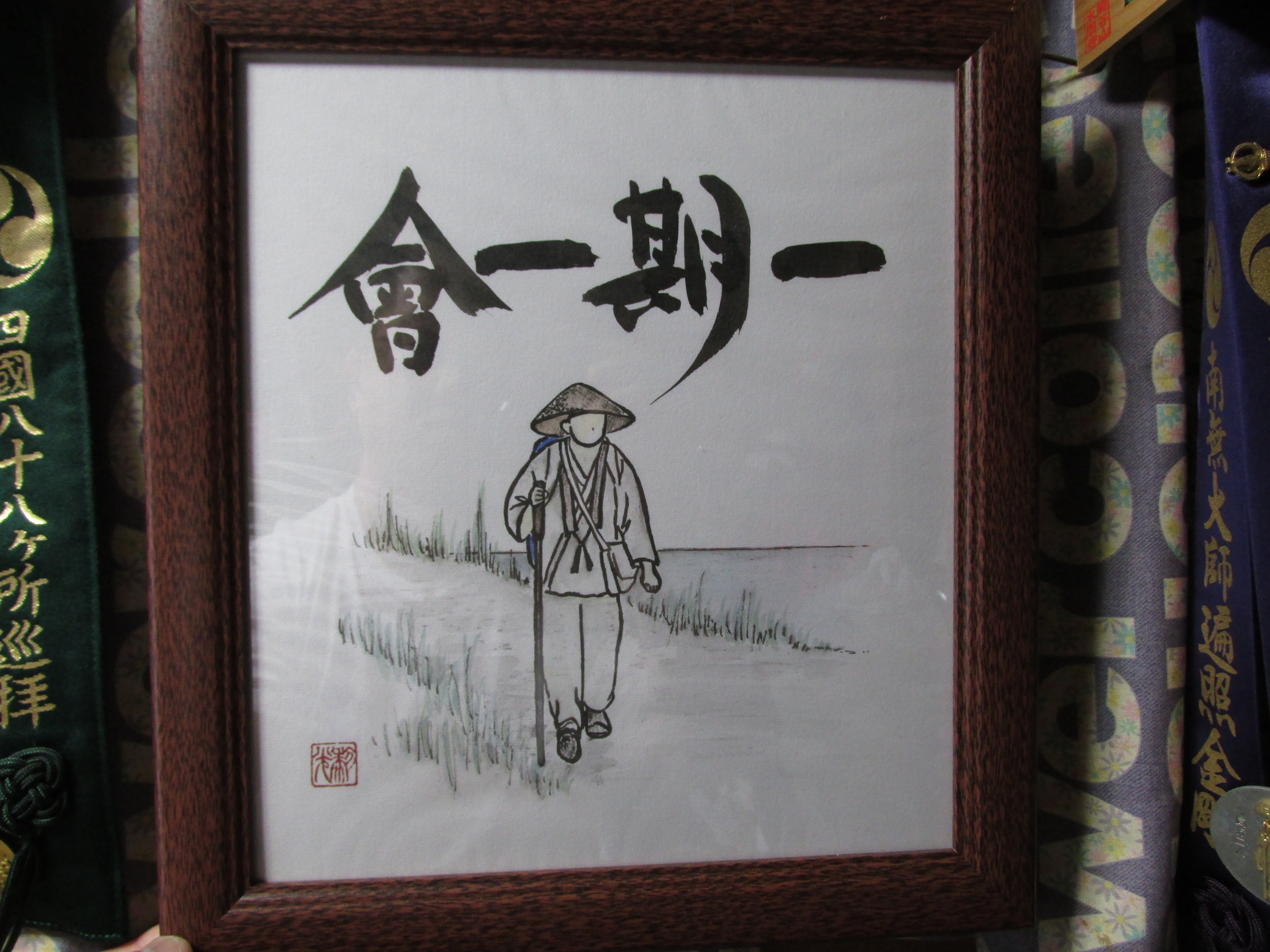↓古いノート記録の書き出し、歩き遍路2度目・区切り打ち
最初の日のリンク。
↓歩き6度目 区切り打ちスタート(現在進行中)
ノートの記録があるので、参考に書いていきます。
ノートは20年も前の僕の言葉です、、、。
注:もちろん写真のデータは古いです。
写真が少ないので、新しい遍路の時の写真も、借りています。
六度目の野根川橋
橋さんとも、話しながら渡る。
また、、会いに行きたい。
続く。からです。
東洋大師・明徳寺を出て、野根の橋を渡りました。
橋を渡った先に、地蔵堂(庚申堂)があります。
野根川橋を渡って、、
こちらですね。
お堂の横に石碑
どう読むんだろう、、、
創建碑だろうか
天満寺住職とあります。
ここの御堂の為に、御尽力された方々だろう。
地図に記載されていたお地蔵様と思われる。
この、お地蔵様、庚申様について、記されています。
「土佐の神仏案内」より
市原麟一郎著
野根地蔵堂八十四ぺージから八十六ページ
お堂中央のお地蔵さんは明治三十八年、野根川橋をかける
とき、橋の下の渕から発見されて、夫婦岩のところに地蔵
堂を建てて安置されました。
後、ここに庚申堂もやってきて合祀され、お遍路さんの仮
宿にもなっていました。ところが夫婦岩は野根八景の一つ
の大岩でしたが昭和四十五年の国道工事で破壊され消えて
しまいました。そこでお地蔵さんと庚申さんは現在地へ移
転、平成八年に新しいお堂に建てかえられました。お地蔵
さんは舟形光背半浮き彫りで高さ七十糎幅三十五糎のもの
ですが右側に「左りへんろうみち」左側に「さきのはまへ
四り、願主木食仏海」と彫り込まれています。
けがや病気にご利益があるといわれ、仏海上人晩年の作
です。「木食」というのは米や麦などの五穀を食べないで
苦行を重ねている修行僧をこう呼ぶそうです。
この仏海上人は元禄十三年(1700)伊予国風早郡猿川村
の生まれで、諸国行脚霊場巡礼を続け、宝暦十年(1760)
入木(室戸市)に「仏海庵を結び難所に苦しむお遍路さんを
助けました。
昭和六年、入木にて入定(生きながらにして墓に入り即身
成仏すること)しました。
現在も入木には仏海庵と彼の墓があり、多くの信奉者によっ
て今も毎年供養祭が行われています。
仏海上人は生涯に三千体の仏像や地蔵を作ったといわれ、
その地蔵は「○○まで何里」と里程が刻まれた「しるべ石」
となっているそうです。
ところでお地蔵さんの右手の庚申さまは「失せもの探し」
の神様という信仰があり、ここには「青面金剛童子」の神札
が祀られていました。
この庚申様がよそと変わっている点は、失せ物に気が付い
たら、二十四時間以内に庚申様にお願かけをすること、願か
けに行く途中は誰とも口をきかないーーそうすれば必ず失せ
物は出てくると言われています。
とのこと。
室戸に向かう難所だった道、、
道じゃなく、海岸線の石の上や、山の道を行ったという、、。
荒くれる、太平洋の海
延々と続くように思える道。
行こう、、最御崎寺へ、、
続く。