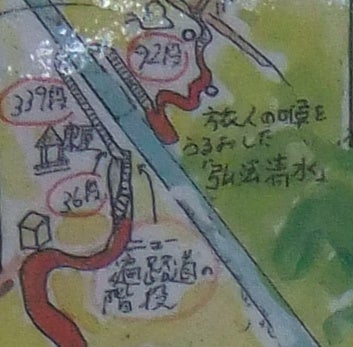さぁ、、荷物を降ろして、参ります。
続く。よりです。
雨で、、、シャッター押しにくい、、、。(;^ω^)
カメラさん、、扱い悪くてスミマセン。
階段をのぼると、、狛犬様
さらに上に稲荷神社
本堂
大師堂、、雨で正面を写すのを忘れました💦
2010年の大師堂
2008年の大師堂
本堂、大師堂に参らせてもらった(*^_^*)
さぁ、、稲荷神社に参ります。
(大師様勧請の稲荷明神像は、本尊 十一面観音菩薩と共に、
今の本堂の方に一緒に祀られていると書かれている。)
赤い鳥居の稲荷様
眷属の狐様も
守っておられます
拝殿
コロナの時期で、鈴は鳴らせません、、
稲荷神社の横の御社
<m(__)m>
まわりの御社
奥に、、水が湧いていました
一番上の、三間の稲荷宮
どこからも見える赤い鳥居(*^_^*)
明治以前まで、、旧本堂の稲荷宮だったんだ。
廃仏毀釈により、今のようになる、、、。
お大師様は、、どう思っているだろう。
稲荷宮前から、三間の町を見る。
納経所に行きました。
いきなり
持鈴を使用しないで参ることに、注意を受けました。
へんろみち保存協力会の冊子を示してくださり、
お遍路の正しい お参りの作法を教えてくださいました。
お参りの際には、持鈴を使用して、鳴らす。
持鈴はお参りに使うものです、、と。
確かに、、お遍路の手順書にも書かれていました。
御住職は、お遍路が持鈴を使用して参っているかを、
納経所の窓から確認しておられるようで、正の字を
つけて数えておられました。
この月は、、月末のこの日まで、現住職の言われる正しい
お参りをした人は、0人だそうです、、、。(/ω\)
この日は月末、、時間も夕刻近く、、
スミマセン、、、。
巡礼の作法も知らずに守らずに、歩いていました、、、。
そこから、、お寺の話を始められ、、
賽銭が、銀行で両替するのに手数料が要って、逆にマイナスで
お金が減るので困るとも言われていました。
お金の面で、苦労している話
確定申告や、何でも領収書が必要な事、納経時間の事など、
大変だと、、長く、お寺の苦労話をしてくださいました。
何か、、いい話でもしないと、、と思い、
以前、逆打ちでこのお寺に来た時、前の塩田光玄住職に、
納経帳を見て、「あなたは逆打ちですね」と
いつもと違う大きな石の印を、出してくださり、
押してくれたのは、ここ龍光寺だけでした、嬉しかったです。
と言ったら、、、、、そんなものは無いと((+_+))
足元の方から出して、押してくださったんです、、。
そんな印はこのお寺に無い!!
この今持ってきた納経帳でなくて、先達になる前の納経帳なんです、、
家に帰ったら、その印の写真を送ります、、
と話すも、、そんなものない。送らなくていいと、、、、。
でも、、、頂いたんです。
いや、無い。
でも、、、、
無い。
もう、、、ふにゃふにゃ。
降参です。
でも!!
僕の前の納経帳には、ここだけ石の大きな印を頂いたんです
(>_<)
お坊様じゃなく、三間の御狐様が押してくださったのかな。。。
確かに、本当に、、納経帳を開かずに出したら、開いて出しなさいと、
叱られたことのある、あの塩田住職が、、6度目に参りに来たその時には、こちらから言わなくても、
開いた納経帳を見て、逆打ちだからと言って、
押してくださったのに、、。
もう今は無いのかな
大きな石の印
嬉しかったです。僕の、、お宝だ(≧▽≦)
、、、、、とにかく、、
いろいろと教えてくださり
お寺の苦労話まで話してくださり、
まずは、作法まで、、教えてくださり、
ありがとうございます。
まだまだ、至らないお遍路でした、、、。
御礼を言って、、納経所を出た。( ;∀;)
今回頂いた納経帳の墨書受印
三間の稻荷山にて
続く。