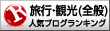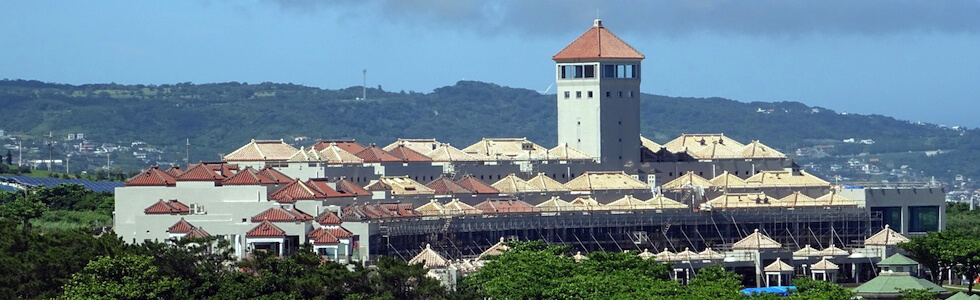1月4日(日)、映画「新解釈・幕末伝」10時20分~12時25分の回を観に、久しぶりのT・ジョイ横浜へ。


坂本龍馬がムロツヨシ、西郷隆盛が佐藤二朗、吉田松陰が高橋克実という時点で、どんなハチャメチャ喜劇になるかと思っていましたが、果たして、桂小五郎(木戸寬治(孝允))役の山田孝之や土方歳三役の松山ケンイチ迄真面目な顔で大ノリノリ、ストーリーテラーの歴史学者小石川二郎役の市村正親の味のある演技、佐藤二朗の意表を衝いた小声で気弱な西郷吉之助(隆盛)、そしておりょう役の広瀬アリスと何よりムロツヨシの振れきった怪演と展開のあまりのバカバカしさに、新年早々腹の皮がよじれる程大笑いしました。

全般ランキング