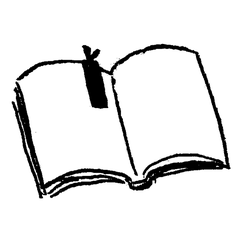久々に医学史小説を読みました。
主人公は緒方洪庵と佐藤泰然。しかし、割合的には洪庵ターンの方が多めになっています。読む前に注意したいのは、あまり物語性がないところ。どちらかというと、小説というよりは伝記に近い感じかな?また、登場人物がかなり多く、(江戸時代なので)その名前もコロコロ変わってしまうため、不勉強な私には窒息してしまいそうな読書時間となってしまいました。
評価:3.5/5
江戸にタイムスリップしたような感覚をプレゼントしてくれる一冊。初めて知る内容ばかりで面白かった。しかし、ひたすら日本の医学史を説明してくれるという構成が、刺激を求める私をダラけさせてしまった。そのため読み終えるまでに五日もかかってしまった。はい、これは自己責任です。
<あらすじ>
江戸時代後期、医者に憧れを抱くひとりの青年が、大坂なにわ橋の上で佇んでいた。青年の名は田上惟章――のちに「緒方洪庵」と名乗る人物である。貧乏藩士の三男坊だった彼は、大坂で師・中天游と出会い、蘭学にのめり込んでいく。同じ頃、江戸で祝言を挙げるひとりの青年が、医者の道へ歩み出そうとしていた。彼の名は田辺昇太郎――のちの「佐藤泰然」である。知り合いの商人から異国の話を聞いた昇太郎は、蘭学がこの先の世に役立つと考え……。真面目な洪庵と、破天荒な泰然。長崎で同じ時期に蘭学を学んだ二人は、互いをライバル視しつつも、その歩みは蘭学を大きく発展させ、それぞれ立ち上げた私塾は「西の適塾、東の順天堂」として、若者にとっての憧れの学び舎となっていく。そして二人は、世間を脅かす「天然痘」の撲滅に挑むのだった――。
「西の洪庵」と「東の泰然」
手短にいうと、本書は東西(西の適塾、東の順天堂)に私塾を創設した二人の蘭方医が天然痘の撲滅に挑む姿を描いています。
<感想>
歴史ドラマを観ていると、「漢方医って大丈夫なん?」と思いがちな私。失礼ながら脈診だけで何がわかるん?とか、漢方薬飲んだだけでは治らなくね?と思ってしまって・・。韓国ドラマなんかだと、心筋梗塞とか脳梗塞、がんの患者まで漢方(あちらでは韓方?)と針治療の合わせ技で治してしまうので、さすがに外科治療しないと無理でしょとツッコミを入れてしまいます。
ただ昔の人にとっては蘭方医の方が怖いよなぁ。天然痘のワクチンしてくださーいと言われても「えっ、何それ。健康な体に傷をつけて痛い目したくないんだけど。てか逆に病気になりそう」という拒否感は半端なかったと思います。何となくコロナワクチンの時を思い出しましたね。
しかし蘭方医が思っていた以上に凄い技術を当時から学んでいたことには驚きました。特に泰然が「手術の同意書」までつくっていたことには脱帽。これには江戸時代のイメージがちょっと変わったなぁ。
そうそう、福沢諭吉が「適塾」出身だとは初めて知りました。「学問のすゝめ」が読みやすいのも洪庵から文法を学んだからなのかーと。そして諭吉はオランダ語が廃れてきていると察知するや否や、即効英語を学びに行っているところも素晴らしいなぁと。
漢文を土台に蘭語を学んで、さらにそれを土台に英語を学ぶ。昔の人は辞書を片手に地道な翻訳作業をしていましたが、日本語に訳すセンスも「適塾」出身者はピカイチだったのだろうなぁと思います。特に橋本佐内なんて今の時代生きていたらギフテッド扱いなんじゃない?と思うくらいの天才っぷりで、こんな人を斬首刑にした井伊直弼にはイラつきました。
ただ、本書では井伊直弼を完全な悪者にはしておらず、きちんとフォローしていたのが印象的でした。確かに歴史において、こういう見方は大事よね、と思います。
比較でいえば、当然主人公の二人も面白い。ひたすら机上で蘭学を学ぶ洪庵に対して、生きた蘭学を推していた泰然。書物から医学を学ぶ洪庵は今でいう研究者向きなのかな?勉強は得意だけれど、診療は苦手で病院が流行らない、洪庵のいうことは患者には難しくてわからない・・とか、典型的なエリート医師ではないですか。
一方、陽キャ泰然は「本から学ぶより実践から学んだ方がはやいぜ」というスタンスで何事も吸収していき、語学も医学も「実際に使えなきゃ意味ないぜ」ということを洪庵に諭していきます。こうして泰然は患者の扱いにも長け、まさに現場で使える医師的な存在になっていきます。
今でいうと、内科の洪庵、外科の泰然みたいな感じなのかな?真面目で優等生な洪庵に、体育会系の泰然みたいな?泰然の方は途中から「早見えの泰然」として、新しいものには積極的に体当たりしていきます。これは蘭学者の多くがそうなのでしょうけれど、みんな医師になりたいから蘭方医の勉強に励むのではなく、世のためになることを学びたいから手始めに医学を・・という感じで、他にも天文学だったり化学だったり、やがて国防のために兵器開発へと向かっていくのが切なかったな。まぁ仕方ないのだけれど。(そもそも蘭学医の師・シーボルトさえ本業は医師ではないし、本当はドイツ人だった)それと同時に、ここからどんどん日本の技術や学問が発展していくのも、優秀な翻訳者がいてくれたからこそなんだよなぁと改めて思いました。ジャンル問わず外国の数多くの書物が日本語で読める、訳せている、これは日本の財産でもあると思っています!!
ちなみに本書のラストについてですが、長々と説明が続いたあとに急に「洪庵死す」という状況になって幕を閉じます。ここいきなりで驚きました(笑)あれ?緒方洪庵って死因不明で亡くなったんじゃなかったけ?私のしょぼい知識と記憶では、やりたくもない奥医師に任命されたストレスで体を悪くして亡くなった気が・・。最後は大量に喀血して亡くなったと何かで見た記憶が。
しかし筆者が用意した結末は「暗殺」となっています。ここだけめちゃくちゃストーリー!へぇ、よくわからないけれどそんなふうにも思える死だったのですね。犯人はここでは言いませんでので、気になる方はぜひ直接読んでみてください。
その際は耐久性のご用意を・・(笑)
以上、『蘭医繚乱 洪庵と泰然』のレビューでした!