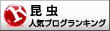親のやる気に反して中学受験を志している我が虫ガール。
彼女にはかなり行きたい志望校がある。
それは
東京農大一中。
いろんな学校が来る説明会に行ったとき、
「生き物好きな子が多いです」
「生物部の人数が一番多いです」
と言われてかなり惹かれたらしい。
そこで、お友達も誘って9月末の東京農大一中学校祭「桜花祭」へ行ってみました。
門の前で待ち合わせて中へ入ると、
まず入り口で配られるパンフレットの表紙からして一味違っていた。
普通は女の子やら男女やら風景だったりするわけですが、
ここは「鯉」だった。
しかも中高生らしくない渋いタッチ。
すげー!
まずは楽しみにしていた二号館の化学部・生物部へ向かう。
2階の化学部で人工イクラ作りなどを満喫してから3階の生物部へ。
かなり広い部屋いっぱいに生き物が展示されていた。
まず入り口に超カッコイイ軍鶏的な鶏がいた。
足に刺されたら大怪我しそうな爪がつき。
娘は当然触りたがるが、係員も軽くOKしてくれる。
どうですかこの爪!!
聞くと野生に近い種類なので退化せずに残っているんだそう。
続いて小鳥、魚の透明標本、ばかでかいカエル(噛むらしい)、
いろんな生き物の骨格標本、コンクールで入賞するような金魚などなどが
かなり広い部屋いっぱいに展示が並べられていた。
こんなに生物部が生存権を認められている学校は初めてだった。
母の先入観では、生物部って大抵マニアックな部で、
数人の生き物オタクが細々とやってる感じだよね?
それから昆虫ゾーン。
ここにはカブトムシやクワガタの標本と並んで
生きたゴキブリがいた。
よりによってなぜこの晴れの舞台にゴキブリを選んだ・・・
と思っていると、おそらくゴキブリを愛して止まないであろう説明員のお兄さんが
「これはヤエヤマ(多分)オオゴキブリと言って、普段は森に住んでいて、
人の家で悪さをしないきれい(?!)なゴキブリです」
と説明。続いて
「触ってみる?」
と近くの男の子に聞く。→断られる
そのお父さんに聞く →断られる
その隣にいた娘に聞く →「ウン」
やっぱりorz
さっき断った近くの父親がビクッと顔を上げ、
信じられないという表情で娘を見たのを私は見逃さなかった。
娘の友達もつられたのか「ウン」
・・・え、さわるの??
逆に私が驚いた。
生き物好きな子でしたが、ゴキブリに触るほどとは思わなかった。
その後、
「お母さんはなんで触らなかったの?かわいいよ!」
と娘に責められた。
いや、・・・特に聞かれなかったし・・・ね・・・。
そしてかわいいという形容詞にはちょっと同意しかねる。
実のところ彼女らに育て上げられた今の私なら
触れないことはなかったかもしれませんが、
いやでも見た目ほとんどゴキブリだよ…?
それから
「農大の生物部の生徒は道に生き物の死体があると喜んで持ち帰って
解剖したり標本にするんです!」
と嬉しそうに語る男子とか、
ヘビを愛して止まない女子とかにいろいろ話を聞き、
金魚すくい(無料)にチャレンジして終了。
農大すげー!
母は感動した。
そして娘は
「うちぜったいここに入る!」
と決意を新たにした。
いやでもその前に偏差値があと10ぐらい必要なんですけれどもね。
しかし大抵の私立校が「東大合格率」か「英語」でしか特色を出せない中、
この路線を貫くのは賞賛に値すると思いました。
こういう学校、他にもあればいいのに。