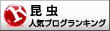我が家の虫姉弟は観音崎自然博物館の
「ジュニア生物調査隊」に入隊しています。
これは博物館のスタッフさんと生き物好きの子供達で
周囲の野や川を探検し、生き物の生息分布を調べたりするもので、
今回はその3回目の活動がありました。
前回娘は学校の自然教室と見事に被って参加できなかったので、
やっと参加できた今回の調査。
今回は、観音崎自然博物館周辺の淡水域の生き物調査だそう。
その中からいくつか捕まえて、秋に標本を作るんだそうです。
はい、ここで虫姉弟、特に姉に一つ試練ができました。
それは・・・「標本」。
標本自体はいいんだけど、作ったこともあるんだけど、
本格的に作るとなると
まだ生きてるうちに殺すわけですよね?
それって・・・我が虫愛に溢れる虫ガールに耐えられるのだろうか?
と母は一抹の不安をおぼえました。
まあ、行ってみるしかないけれども。
そして今回の恒例のキャラ弁?ですが、
息子が観音崎と聞いて海と思い込み、
「アオウミウシ捕る!!」 ※ウミウシといえばこれ!というレベルのメジャーなウミウシ
と言ったので母も何も考えずにウミウシにした。

はい、ウミウシに見えませんね。
色なしでウミウシを作るのは至難の業だと知りました。
白い斑点まで再現しようと少し試みたのですが無駄でした。
そしてさらに無駄だったことに、今回は海じゃなくて川だったという落とし穴。
ウミウシいねーよ!
そんなこんなで観音崎へ行き、博物館前で子供たちを預けて親は一旦退散。
ここにずっといても暇なのでペリー記念館とかに行き、
子供に内緒でちょっといい回らない寿司を食べてきた。てへ。
活動が終わる15:00前に博物館へお迎え。
解散の挨拶の後は親も部屋に入れたのでのぞいてみた。
そこには今度標本にする子供達の収穫物がたくさんあったわけですが、
中でも壮絶だったのが
頭と足だけのカブトムシ。
鳥か何かに食べられていたところを誰かが見つけたらしい。
で、何が壮絶だったかというと
まだ生きててめっちゃ動くとこ。
バランス悪いながらも4本の足で机の上を自在に歩き回る。
衝撃。
ちょっと見た目にアレなので写真は控えます。
他には大量のトンボやら甲虫類。
今回は標本にするためにチョウやトンボは三角紙という保存用の紙、
他の虫は殺虫ビンに入れて持ち帰っていた。
我が家の子供達はどうなったかというと、
娘は三角紙には辛うじてトンボを入れられたけど(その場で死なないので)
殺虫ビンに入れるのは予想通り無理でカラのままだった。
かわりに今まで見た中で一番ぐらいにでかいコクワガタを捕まえていて、
飼って死んだら持ってくるのでもいいという約束をしていた。よかった。
そして息子はずっと気になっていたハンミョウを捕まえて
大騒ぎしていたらしいけど、結局最後は
「殺したくない」
と言ってビンには入れず、さらに持ち帰るか聞かれても
「エサに毎回アリをあげるのが大変だから逃がす」
と逃がしたらしい。
それで、結局ビンに入れることができたのは、ワラジムシとアリジゴクw

ほう!キミもおねえちゃんに似て生き物に優しくなったんだね!と思ったけど、
じゃあ何で魚持って帰って来てるんだよ!!
彼の飼育ケースにはモツゴと呼ばれる魚がどーんと入っていた。
魚は標本にしないので普通に持ち帰って飼うんですが、
いやあのさ、帰り道は電車で2時間かかるから家に着くまでに死んじゃう可能性があるうえに、
今回オマエに持たせた飼育ケースは水漏れするヤツじゃねーかー!!
※息子が乱暴に扱うため、我が家には水漏れしない飼育ケースは2つしかなく、
それぞれアカハライモリとサンショウウオが既に入っている。
そして帰りの電車で息子本人は当然疲れて寝たので、
水漏れする飼育ケースから電車に水がこぼれないようビニールで保護したり、
乗り換えのたびに少しずつ水を足すのも全部親!!
アホめーー!!
次から魚禁止!!
観音崎から出る直前、博物館の学芸員さんが数人残った子供達に
トンボの標本の前処理を教えていた。
前処理とは、キレイに標本にするために内臓を抜いたりする処理のこと。
はい、きました。母が一抹の不安を抱えていたポイント。
娘はどんな反応をするんだろうか。
ショックを受けて「次から行きたくない!!」とか言うんじゃないだろうか。
ドキドキしながら見守る母。
娘は意外にも大丈夫で、
処理されるトンボを黙ってじっと凝視していた。
後で聞いたら、研究をするうえで標本はなくてはいけないこと、
そういう標本を作るには生きているうちから処理しないと長持ちしないことは分かっていて、
でも自分はやっぱり生きているものを殺すのは嫌だから、
今回自分が捕まえたトンボはキレイな標本にはならないかもしれないけど、
死んでから作るのでいい、と言っていた。
本格的な昆虫学者になるにはそれじゃダメなんだろうけど、
学者でなくてもずっと虫や生き物に関っていく人としてはそれでいいんだと思う。
殺したくないのに無理に殺して、生き物に関わること自体が嫌になってしまっては意味ないですからね。
というか、逆にいろんな考え方の人が共存した方がその世界にも深みが出るんだと思う。
生き物っていろんな愛し方があるんだなあ。
と娘を見て学びました。