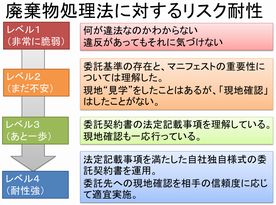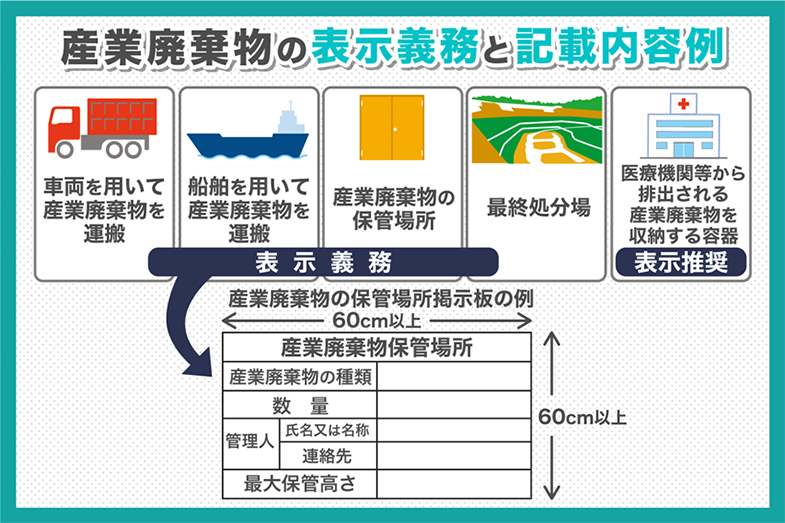吉川英治(歴史上の偉い人なので敬称略)の『随筆 新平家』に「一ノ谷」が登場する。
『随筆 新平家』(昭和33年初版)に収録の昭和26年(1951年)に書いた「新 平家今昔紀行」に「一の谷」の地名が登場する。『週刊朝日』での『新平家物語』の連載が1950年から1957年までらしいので、1950年前のことだろうと思われる。
史跡巡りの二日目の記述に「六月一日、舞子ホテルにて、雨。」とあるので、史跡巡りの一日目は5月31日であったと考えられる。時間をかけて調べると年月を正確に特定できると思うが、ネットで確認できる範囲では、昭和25年前後の5月31日から6月1日の話である。
『随筆 新平家』によると、
有馬では明朝、鵯越えから一ノ谷の史蹟案内をしてくださるために、神戸市史編纂の川辺賢武氏が来合わせる約束になっている。
と、神戸市史編纂の川辺賢武氏が吉川英治の案内をしたという。
史跡巡りの当日 、
神戸の市史編纂にたずさわる川辺賢武氏が早くも来訪される。
「きょうはどういう御予定で」と、川辺氏はさっそく二万五千分ノ一地図を卓いっぱいに拡げた。そして京都から義経軍の潜行したいわゆる、鵯越(ひよどりご)え間道(かんどう)”の[#「間道(かんどう)”の」はママ]径路を、その豊かな郷土史の見地から何くれとなく説明された。
これは後での笑い話だが、川辺氏はもちろんぼくら一行が、有馬を起点とし、丹波境から椅鹿(はしか)、淡河(おうご)、藍那(あいな)などの山岳地を踏破して、義経の進んだ径路どおり鵯越えに出るものと予定していた。そのため、ハイキング支度で来られたそうだし、ぼくも東京を出るときは、そのつもりで、ズックのゴルフ靴など携えては来たのであった。だが今はとてもそれほどな元気もない。「ともかく神戸まで出ようじゃありませんか、その上で」と、ただなんとなく腰を上げた。
と、「丹波境から椅鹿(はしか)、淡河(おうご)、藍那(あいな)などの山岳地を踏破して、義経の進んだ径路どおり鵯越えに出る」予定であったが、吉川英治は体調不良(腹痛)のため予定を変更している。
宿舎にしていた有馬温泉の旅館を出て
有馬道から神戸に入る。山手を東へ、生田区を一巡、生田神社で車を下りる。
吉川英治一行は、生田の森(中央区)のあたりをちょっと見て、
車へもどって、すぐそこから市の北陵にある会下山(えげさん)へ急ぐ。
「会下山に立ってみるのが、いちばん要領を得られるでしょう。生田方面も鵯越えも、そして輪田岬から一ノ谷、須磨辺まで、一望ですから」と、これはもうぼくの意気地のない足つきを見て察しられた川辺氏の懇切なおすすめだった。(二九・七・一一)
と、一行は会下山(兵庫区会下山町)へ向かった。
そして、吉川英治は会下山で川辺氏から鵯越兵庫区説の説明を受ける事になる。
「こう考えるのです。私は」と、川辺氏はそこでいう。
「あの鵯越え口から、その山麓の長田方面にまで守備を布(し)いていた平ノ盛俊、能登守教経(のりつね)などの平家軍は、この会下山の天然な地形を決して利用せずにはいなかったろうということです。なぜならばですね」と、かなたこなたへ、歩を移しつつ、ここの戦略的な重要さをなお力説された。
「第一にここほど視野の利く所はありません。海陸、どこも見通しでしょう。鵯越えの抑えとして、絶好な一高地です。――もっとも、その鵯越えにも、従来、幾つもの異説があって、あれから夢野、刈藻(かるも)川へ南下して来る道と、また、山上の小道を西方へ反(そ)れて、鉄拐(てっかい)ヶ峰を迂回し、遠く一ノ谷の断崖の上に出たという説など区々ですがね。私には、平家が主力をおいたのは、この会下山で、そしてまた、義経が降りて来たのも、この会下山の西の低地、刈藻川すじから遠くないものと考えられるのです」
川辺氏がいうところは、おおむねずっと以前に喜田貞吉博士が歴史地理学会の誌上に書いた所説と近いようであった。
けれどその喜田博士説にしても、川辺氏のように、この会下山を重要視してはいない。一ノ谷逆落しというようないい伝えは、まったく誤りであり、鵯越えとは、そんな断崖絶壁を駆け落したのではなく、現今の夢野の坂道を長田町の方へ攻め下って来たに過ぎない、と断定しているだけである。
「その鵯越えの道とか、一ノ谷合戦の真相はどうかという点などを解く鍵はですね、つまり、会下山ですよ。ここへ来てみなければ分からんですよ。まあ、ゆっくり腰を下ろしてください。多言は要しませんから」
と、川辺氏はかさねていった。ほんとに、こういう時にこそ、史蹟歩きの値うちはあるものだった。ぼくは幾たびもうなずいた。余りに課題は大きすぎるが、湿っぽい梅雨じめりの気流の中で、しきりに渋る腹鳴りを片手で抑えながら、とある石に腰をかけた。
と、腹痛で苦しむ吉川英治に川辺氏は「その鵯越えの道とか、一ノ谷合戦の真相はどうかという点などを解く鍵はですね、解く鍵はですね、つまり、会下山ですよ。」と、鵯越兵庫区説のキーポイントは会下山にあると、強調したという。
吉川英治は「おおむねずっと以前に喜田貞吉博士が歴史地理学会の誌上に書いた所説と近い」「喜田博士説にしても、川辺氏のように、この会下山を重要視してはいない。一ノ谷逆落しというようないい伝えは、まったく誤りであり、鵯越えとは、そんな断崖絶壁を駆け落したのではなく、現今の夢野の坂道を長田町の方へ攻め下って来たに過ぎない、と断定しているだけである。」と述べており、川辺氏が鵯越兵庫区説のキーポイントという「会下山の説明」が喜田貞吉の主張を補強するものであると、とらえたようである。
つぎに、吉川英治は川辺氏から会下山の地名の由来と『太平記』から源平合戦を類推して「会下山」の重要性を知るべきとの説明をうけ、以下のように書いて、
会下山という名は、徳川期以後で、古くは、雲梯(うなで)ヶ岡といったらしい。法隆寺財産目録(天平期)には宇奈五(うなご)ヶ丘とも見えるという。
だから、盛衰記や平家物語には、会下山という称もなく、うなでヶ岡とも書いてない。山手と総称されたり、ひと口に、ここも夢野と呼ばれていたのである。
そのため、ここの地形も無名のままつい見落されて来たわけだろうが、その重要さは、ずっと後の延元元年、足利尊氏が九州に再起して東上のさい、楠正成が湊川を後ろに、この会下山から頓田山に陣したことでも考えられる。そのさい、足利勢の一部は、やはり鵯越えから長田へ出て来て、楠勢を、腹背から攻めたてているのである。
それと、もっと重要なことは、天井(てんじょう)のような山丘地から来るものと知れている敵勢を、わざわざ、谷底のくぼや、視野のきかない麓に屈(かが)み込んで、待つばかはない。当然、それへ対するには、遠望も利(き)き、応変も自由な、そしてまた、どこへでも兵力を急派できる高地に司令部を持たねばならない。
とすると、会下山は絶好な地点である。
と、結論している。
だが、「会下山という名は、徳川期以後で」ということは、「会下山」が、源平合戦と同時代の記録には存在しないということを示しており、根拠のない主張であることを吐露している。
つまり『平家物語』や『玉葉』など同時代の記録に出てくる「山の手」が「鵯越」であるとの証拠はないのである。
近年主張されるようになった(NHKなど)とされる多田行綱が鵯越を攻撃したとする説も、『玉葉』の「山の手」を「鵯越」と読み替えているだけである。
「山の手」が「鵯越」であるとの証拠が示されることはない。
鵯越論争は、地理学(現在の地理を問題とする)と歴史地理学を混同して、現在の地名を連呼すれば過去の地名と現在の地名が一致する呪術的技法を使って、過去の文献などによって証拠づけることなく(つまり証拠となる資料の新発見がないまま)、新説が誕生するという錬金術的秘法が使われている。
鵯越兵庫区説は、現在の「鵯越」の位置が絶対的に正しいものとして主張がはじまるが、その主張が文献などによって証拠づけられることはない。例:「『山の手』は『鵯越』なんです。」を二三回繰り返して、けっきょく「山の手」=「鵯越」を示す文献を最後まで示さない。「多田信綱は関西出身で鵯越辺りの地理に詳しかったんです」とか、一遍上人絵図のどの絵か示すことなく一遍上人絵図に大輪田泊あたりに湖が描かれていると主張しつつ「一の谷という湖があったんです」などという。
『玉葉』『吾妻鏡』に書いてないことを現在の地図や『平家物語』の感想から引っ張ってきて、想像を膨らませて主張する。『平家物語』で「鵯越」の位置がどう書いてあったかすら示さない。酷いのになると、引用元を明示せずに兵庫区の鵯越と大輪田泊の間の「湖」だか「池」を「一の谷」と呼んだという話が出てくる。
もし、「湖」や「池」を「谷」と呼ぶ用例が過去にあったのなら、日本語学的な新発見のような気がする。
歴史学でなく日本語学の学会で発表するべきだろう。
『随筆 新平家』には、ほとんど、想像や憶測だけという酒場談義のような主張もある。
会下山を中心とする平軍と義経軍とが衝突した戦闘地域が分かれば、自然、義経の向かって来た通路も明らかになるわけである。
平軍の教経(のりつね)は敗れて海上へ逃げたが、同陣の盛俊だの通盛(みちもり)などは、名倉池や東尻池の附近でみな戦死している。刈藻川の上流で、まさに会下山と鵯越えの中間といってよい。教経の弟業盛(なりもり)が戦死した所も、会下山から遠くではない。
と、会下山を中心として源平の戦闘があったと断言しているがそのようなことを示す文献はない、根拠のない断言を前提にしているが、教経の弟業盛(なりもり)が戦死した場所がその補強となればまだ良いが、教経の弟業盛(なりもり)が戦死した場所も、伝承であって文献などによって証拠づけられているわけではない。
会下山が見晴らしが良いからといって「平軍と義経軍とが衝突した戦闘地域が分か」るわけではない。
そして、
とにかく、世称、一ノ谷合戦で通って来たため、一ノ谷が義経にも平家方にも、主戦地と思われて来たが、ほんとは、一ノ谷、須磨海岸から、駒ヶ林、生田川、そして山手の刈藻川流域一帯を、当日の戦場と見なすべきである。
だから、以後の誤解を避けるためには、その日の合戦を、次の三区域に分けて考えるのが、いちばんいいかとおもわれる。
(東方)生田川を中心とする源平両陣の衝突。
(北方)鵯越えと会下山との間の長田方面の衝突。
(西)明石方面からの磯づたいに一ノ谷の西木戸を突いた源氏と平家勢との戦い。
「その日、義経がいちばん気を揉んだのは、時間だったと思いますね。戦端をひらく時間の一致じゃなかったですか」「そうです、それですよ」と、ぼくの質問に川辺氏もうなずいた。
「前日から範頼が待機していた生田川口と、義経と別れて播州路から一ノ谷の海辺へ迂回した土肥実平の手勢と、そして鵯越えにかかった彼自身と、そう三方の攻勢が、時間的に不一致だったら、まったく、大失敗に終わりますからね」
「とすれば、鉄拐ヶ峰へ登って、一ノ谷の上へ出るなんて迂遠なことは、不可能でしょうな」
「馬などでそう易々と行ける山道ではありません。いくら捨て身でも」
「それでおよそ義経の径路はつかめた気がしましたよ。しかし、一ノ谷の奥には、安徳天皇の行宮(あんぐう)の址(あと)があったり、逆落しやら何やらの名所旧蹟もあるので、そっちじゃない、こっちだと書いたら恨まれましょうな」
「鵯越えは、これまでにも、議論になっていますからいいでしょうが、たとえば、熊谷直実と敦盛(あつもり)の史話などを抹殺したら、それは大変なことですよ。神戸市の名所旧蹟が幾つ減るかわかりませんからな。はははは」
「いや、史実は史実として追っても、庶民の持つ物語的な夢は尊重しましょうよ。須磨海岸には、須磨寺も風致の一つですし、そこの浪音には、熊谷と敦盛の連想もあった方が自然を見る伴奏にもなりますからな。あなたと違って、ぼくは歴史家ではないのだし」
やがて会下山を降りながらも、ぼくらは尽きない話に興じていた。
と、歴史談義をしたことが書かれている。(東方)(北方)(西)の分類はよくある分類で、喜田貞吉も三つに分類していたように思う。よくある分類法である。
神戸市史編纂の川辺賢武氏の言葉だと思うが、酷いことをいっている。
「鵯越えは、これまでにも、議論になっていますからいいでしょうが、たとえば、熊谷直実と敦盛(あつもり)の史話などを抹殺したら、それは大変なことですよ。神戸市の名所旧蹟が幾つ減るかわかりませんからな。はははは」と。
こういうのは、今で言えば、鵯越兵庫区論の風評被害(鵯越兵庫区論には学術的な根拠がないので風評に当たるだろう)を被る人々のことを笑ったということになるだろう。
史実(学術的な根拠の有無)がどうであれ、『平家物語』の文学性やコンテンツツーリズムとしての『聖地巡礼』には影響がないように配慮すべきである。鵯越兵庫区説の評価を上げるために通説(須磨区一の谷)の価値を下げて(あるいは下がることを想像して)、笑うのはいかがなものだろうか。
「それは大変なことですよ。――中略―― はははは」というのは、
税金を使って、明石市の価値を下げるようなキャッチコピーのポスターをJR明石駅などに掲示して神戸市の価値が上がると思って宣伝するのに似ている気がする。
そんな神戸市職員(神戸市史編纂ということだから関係者?)の気質が、昭和から続いているということの歴史的な証拠といえる、ような気がしないだろうか?
とにかく、鵯越兵庫区説を主張する人々には『平家物語』に対する敬意や神戸市の観光政策に対する配慮がない。
兵庫区の価値を上げるために須磨区の価値を下げ、須磨区の価値を下げたほどに兵庫区の価値が上がらなければ、神戸市全体の観光的価値が下がるという想像力が働かない。
とにかく人の不幸を「はははは」と笑う。
神戸市の価値が下がれば、こんどは近隣の都市のイメージを下げて神戸市のイメージを上げようとする。神戸市周辺の都市のイメージが上がったのではなく、神戸市のイメージだけが下がっていることには全く気付かない。
『平家物語』や文学に対する敬意がないから、『平家物語』に「鵯越」がどう書かれているかを全く無視して、今現在の鵯越の場所と文学作品の『平家物語』に出てくる「鵯越」という単語を単純に比べる。
単純だから誰でもわかりやすく、話も広がりやすいから、繰り返し言えばどんどん広がる。
学術的に根拠づけられているわけではないから、単なる決めつけで『平家物語』が嘘を書いているかのような評価になる。
物語だからフィクションでも良いはずで、文学として楽しめば良いのに、文学として楽しむことを許さない。
『平家物語』に描かれた世界を感じようとして神戸を訪れる人にとっては、興ざめでしかない。
『平家物語』に書かれている物語の真実は文学的な真理として普遍性があると思うが、歴史学的な根拠もないお話で文学的な真理を傷つけるというのは、愚かなことだ。
『平家物語』のイメージが下がれば、松尾芭蕉がコンテンツツーリズムして一の谷の内裏屋敷を想像して涙を流した須磨一の谷を中心にした観光のイメージが木っ端みじんである。風評被害といわずしてなんだろう。
もう風評被害にあう人もいないくらいの廃れぶりだ。
歴史学的な根拠もないお話を、テレビや新聞がありがたい新説のように報道するが、
あれは、「STAP細胞は、あります」という論文の報道よりひどい。
「STAP細胞」の報道は、報道を切っ掛けにある程度科学的に検証された(ただし論文通りの実検結果がえられれば今後も評価が変わる可能性はある)ようだが、鵯越兵庫区説は、なんの検証もしていない。
『平家物語』延慶本を引用しているとする論文を紹介するのなら、せめて『平家物語』延慶本の「鵯越」関連の表記をチェックして長門本など主要な数種類の異本の「鵯越」関連の記述内容と比較してから、報道すべきだろう。
『玉葉』で「山の手」といっているのになぜ「山の手」=「鵯越」になるのか、明らかにしない(錬金術的秘法だから?)というのはいかがなものだろうか。
話がそれたが、
さすが、吉川英治という指摘もある。
義経の鵯越えは、旧暦の二月七日だった。今の三月初めごろと考えていい。
けれど彼が京都を立つ数日前は、都では降雪があった。丹波路は残んの雪があったろう。この辺の山坂はどうだったろうか。
生田川口、明石口、そしてこことの三軍が、同時攻勢に出た時刻は、午前六時ごろであったという。途中はまだ暗かったにちがいない。友軍との諜し合わせは、約束だけで足りたろうか。峰々に人を伏せ、火合図なども用いたのではあるまいか。
一歩誤れば、平軍の中へ、わざわざ、身を捨てに入るようなものである。この坂道を、そぞろ馳せ下る思いはどうだったろう。その朝の彼の眉は。彼の姿は。そして暁の下に、敵を見たせつなは。
暮れかかる梅雨雲の下に、ぼくは果てない空想を追っていた。附近の谷にも峰にも、一羽の鳥影さえ、よぎりもしない。
と。
「友軍との諜し合わせは、約束だけで足りたろうか。峰々に人を伏せ、火合図なども用いたのではあるまいか。」というのは、このブログで義経が烽火などを利用した可能性を指摘したことと一致している。
「一歩誤れば、平軍の中へ、わざわざ、身を捨てに入るようなものである。」というのも、このブログで、兵庫区の鵯越から大輪田泊を攻めるのは奇襲にならないと指摘しているのと一致する。
「附近の谷にも峰にも、一羽の鳥影さえ、よぎりもしない。」というのは、鵯の渡りの位置がはたして兵庫区の鵯越なのかという素朴な疑問が生じる。学者なら、本来は動物地理学を応用して、鵯の渡りの位置を確認しておきたいと思うことだろう。ちなみに5月末から6月初めの一の谷では、曇りでも小雨でもいろんな種類の鳥がひっきりなしに鳴いている。
残念なことに、腹痛のせいか吉川英治は、会下山の景色と鵯越兵庫区説を主張する人の押しの強さにやられてしまったようだ。
会下山を訪れた翌日、吉川英治一行は、一ノ谷へと向かうはずであった。
雨は翌日も降りやまず、ぼくの腹ぐあいも、依然、五月雨紀行にふさわしいままである。晴天なら一ノ谷、須磨寺巡りの予定だったが、その勇気もない。午後、春海氏、健吉さん、Kさん、川辺氏など晴間を見て、須磨寺へ出かける。ぼくは懐炉をヘソに当ててむなしく寝て待つ。
惜しいのは、一ノ谷に来ていながら、一ノ谷を踏まないことだが、須磨寺はまず見ずともよしと思う。そして会下山と鵯越えときのうの展望を瞼に、うつらうつら、半眠りの中に、ひとりで幻想をほしいままにしていた。
「小説は小説としてお書きになることもとよりでしょうが、余りに間違いの多い旧来の一ノ谷合戦だけは、どうか忠実に近い裏づけをもってお書きください。『新・平家物語』にそれを期待しているのは小生のみではありません」
これと同様な意味の読者の声を、ぼくは幾通も手にしていた。神戸市史談会の木村省三氏など、わけて熱心な書を寄せられた一人である。
須磨寺へは行かないでもすむように、小説を書くのになにもいちいち実地を見て歩く必要はないともいえる。けれど、どんな史書を読むにも増して、そこの土壌を踏んでみることの方が、ぼくには創作の力づけになる。また発見があり、自己の構想と落筆に信念を加えることも出来るのだった。
ところが、自分の不摂生のため、せっかく案内の任に当って下すった川辺氏にも、杉本画伯や春海局次長にも、なんとも張合いのないお心を煩わせたし、特に読者諸氏には、二回にわたるこんな五月雨紀行で責めをふさぐなどの無責任をお見せしたが、次回からは、多少この旅行でえたところの収穫を生かして、本題の小説を書きつづける。
しかし、お断りしておくが、おそらくそれはなお史実といえるものではあるまい。といって、ぼくは決して単なる虚構を書こうとするものではない。
厳密にいえば、真実などというものは、朝見たことも、晩には違う話に伝わり易いものである。Aの見方と、Bの観察もまた違う。まして、はるかな歴史のかなたのこととなっては、縹渺(ひょうびょう)として、分からないというのが本当なところである。それを追求して、真を解かずにおかないとするのが、史家の科学であり、それを再現して、真に迫るかの如く語ろうとするのが、文芸の徒の妄執である。史家は、物的証拠をもってし、ぼくらは自分の人間性をとおして過去の人間性との官能につなぎを求め、その言動までを描いてゆく。二者、方法はまったく違うが、時には、文学が史学の透視しえない真をものぞきうることもありえないことではない。
と、なんだかスゴイ良いことをいっているようなのだが、けっきょく吉川英治は一の谷を訪れることなく、東京へ帰ってしまった。
『随筆 新平家』で吉川英治が
「『小説は小説としてお書きになることもとよりでしょうが、余りに間違いの多い旧来の一ノ谷合戦だけは、どうか忠実に近い裏づけをもってお書きください。「新・平家物語」にそれを期待しているのは小生のみではありません』これと同様な意味の読者の声を、ぼくは幾通も手にしていた。神戸市史談会の木村省三氏など、わけて熱心な書を寄せられた一人である。」と書いていることが気になる。※「神戸市史談会」は神戸史談会の誤記か。
「余りに間違いの多い旧来の一ノ谷合戦だけは、どうか忠実に近い裏づけをもってお書きください。」と「神戸市史談会」の投書について書いてあるが、この投書の主張は学術的な根拠のある主張ではないはずである。
吉川英治一行を案内した神戸市史編纂の川辺賢武氏は神戸史学会や神戸史談会で活動(寄稿している)していたようで、神戸市史編集室の勤務経験があり神戸史学会の代表でもあった落合重信氏も鵯越兵庫区説である。
吉川英治が指摘しているように、神戸市史編纂の川辺賢武氏の鵯越兵庫区説は喜田貞吉博士の論に、会下山を加えたものである。
喜田貞吉博士は『神戸市史 別録1』の「古代の兵庫及び附近の沿革」を担当し、被差別部落研究の先駆者として知られている研究者で、神戸市史編集室勤務だった落合重信氏は、神戸市や兵庫県の郷土史の他、部落史、在日朝鮮人史を研究した人物である。
喜田貞吉博士の主張を信じる川辺賢武氏や落合重信氏などの郷土史家の集まり、いわば神戸市史編纂室学派のようなものがあり、その派閥の人々が何かの利害で結びついて、鵯越兵庫区説を唱えているかのようである。
神戸市編『神戸市史 別録1』(大正11年)には、
当時の実録として、先づ第一に推すべき日記玉葉の如きは、記事極めて粗略なるが上に、中には単に風聞によりて記せりと思はるゝの嫌あるものなきにあらず。吾妻鏡亦其の経過を記して詳ならざるのみならず、上文記す如く是れ亦頗る誇張の報告に基づけるの疑あり。然れども今是裸の書をし措きては、他に殆ど據るべきものなきが故に、暫く其の記する所を本として、傍ら諸種の平家物語○源平盛衰記亦平家物語の一本たるに過ぎず を参酌して、之を其の実地に徴し、之を当時の情勢に鑑みて、私かに合理的判断を下すの外にあらざるなり。
と書いてある。
つまり、歴史学的な解釈では、実録は粗略な『玉葉』しかなく『吾妻鏡』も詳細は不明で誇張が多く『平家物語』を「参酌して、之を其の実地に徴し、之を当時の情勢に鑑みて、私かに合理的判断を下す」ほかないということである。
学問的には実録の『玉葉』に書かれている以上のことは、新たな古文書や碑文でも発見されないかぎりは、新事実は何一つわからないということである。このことを知っていて、鵯越兵庫区説を主張するのだから確信犯と言って良いだろう。
鵯越兵庫区説では、錬金術的秘法に使う部分は記録文学であるかのように扱って、それ以外は文学作品の脚色(フィクション)であるといって無価値のように扱う。
『玉葉』や『吾妻鏡』にないことを、何の証拠も示さずに想像力を膨らませて「私かに合理的判断を下す」という錬金術的秘法によって、『平家物語』の記述で補って新たな物語をつくるのであれば、それは『平家物語』の下手な模倣でしかない。
鵯越の位置論争といわれる根拠のない言いがかりの恐ろしいところは、『平家物語』の価値より、『平家物語』の下手な模倣作品の方の価値が高いという主張になっているところである。
『平家物語』に敬意を示すことなく「史話などを抹殺したら、それは大変なことですよ。神戸市の名所旧蹟が幾つ減るかわかりませんからな。はははは」というのは、なんと驕った物言いだろう。足りない部分を補うために使わせていただいておきながら、「はははは」は、ないだろう。
そもそも『平家物語』の登場人物、場面設定、風景描写などなど、あれだけの分量を想像力だけで書けるだろうか、目撃談を集め現地を確認した(遊行僧、高野聖などがあやしい)とか、なんらかの資料(河野氏や屋島から源氏に寝返った田口氏の伝承や家伝があやしい)を使ったと考える方が合理的だろう。
それを、現在の地理のたった一つの地名(地理学?)を物語(文学?)に持ち込んで、歴史的(歴史学?錬金術的秘法?)にこうでなければおかしいといって『平家物語』を笑うなど、まともな学者がすることではない。
あたかも、『平家物語』の文学的価値を貶めることが目的かのようである。
鵯越兵庫区説は、無理筋の主張のような気がしてならない。
鵯越兵庫区説は、『平家物語』より「山、海へ行く」という「株式会社神戸市」の物語と深い関係があるような気がする。
神戸市兵庫区里山町の山野井児童公園には、
源平の合戦で源義経が行った「鵯越の逆落し」の古戦場は、この一帯であると云われている。
神戸市長 宮崎辰雄
という石碑がある。
宮崎辰雄氏は第13代神戸市長(1969年 - 1989年)で、第12代神戸市長(1949年 - 1969年)原口忠次郎氏のあとを継いで「山、海へ行く」という政策を推進した人物である。
どうも、鵯越兵庫区説からは政治の匂いがする。
「山、海へ行く」という「株式会社神戸市」の錬金術のために「鵯越、兵庫区へ行く」というお話が必要だったのではないだろうか。
須磨の山は海へ行って、ポートアイランド、六甲アイランド、神戸空港などになって、須磨の山の跡はニュータウンになった。
「株式会社神戸市」の錬金術の物語が終って、何が残ったのだろうか。