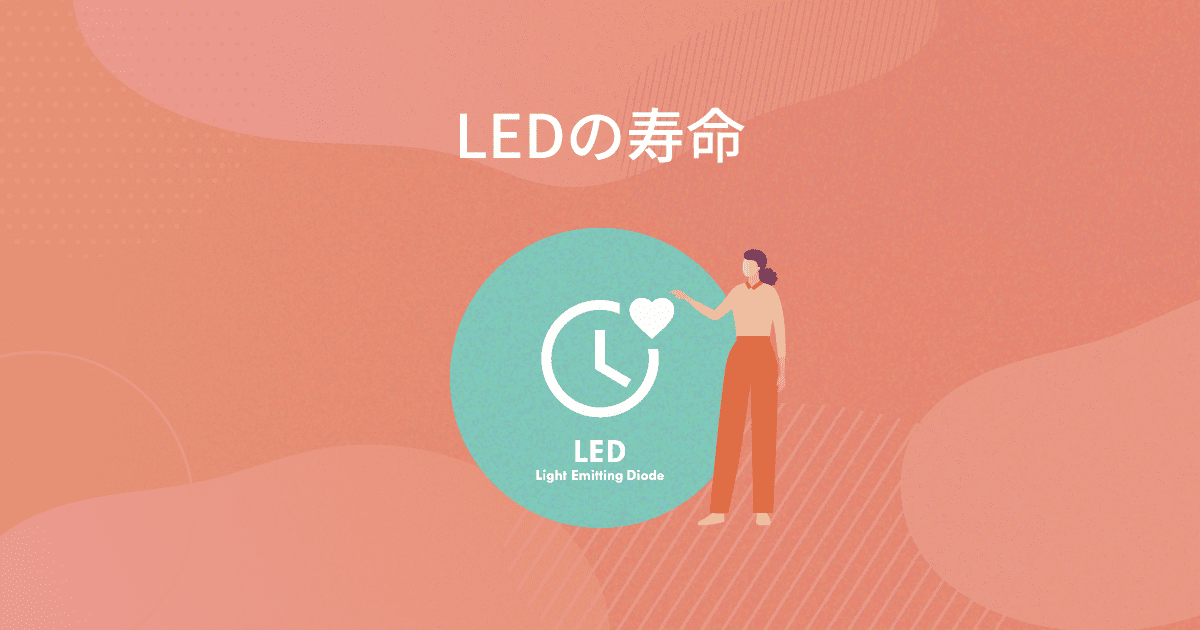188.カラーLEDは経年劣化が目立ちやすい説

カラーLEDが経年劣化で目立ちやすい理由
結論から言うと、カラーLEDは白色LEDに比べて劣化による光量低下や色味の変化が早く、しかも目に見えてわかりやすいため、経年劣化が非常に目立ちやすいです。
1.LED全般の劣化メカニズム
LEDの寿命は「光束維持率」が基準になります。光束維持率とは、初期光束(光の明るさ)を100%としたときに、どれだけの割合を長期間維持できるかを示す値です。LED本体は素子自体が切れるわけではなく、長時間の使用でエンジン部品(チップ)、封止樹脂、封止材の劣化によって徐々に光束が低下し、やがて設計上の維持率(たとえば70%)を下回った時点で「交換時期」とされます。
2.白色LEDとカラーLEDの寿命規格の違い
白色LED
JISなど業界標準では「初期光束の70%まで低下するまで」を寿命とし、一般的に40,000時間前後と規定されることが多い。
カラーLED
色変換用の封止樹脂や蛍光体を含む構造が多いため、「初期光束の50%まで低下するまで」を寿命と定めるケースが一般的。多用途のカラーモジュールは白色に比べて短い光束維持率基準(L50)で設計されることが多く、結果的に数万時間ではなく1万時間台前半で交換時期に達することがあります。
3.カラーLEDが目立ちやすい具体的要因
封止樹脂・蛍光体の劣化
カラーLEDは主に樹脂封止や蛍光体層を色変換に使います。これらの材料は高温や紫外線、湿気に弱く、劣化が進むと透過率が落ちて色むらや黄変を起こしやすいです。
色ずれ・波長変化
劣化が進むと発光スペクトルがシフトし、赤→オレンジ、青→緑っぽく、といった色味の変化が起きます。人間の目は色の微妙なズレに敏感なため、少しのシフトでもすぐに気づかれます。
放熱設計の難しさ
カラーチップは白色LED用よりも小さく、放熱面積が少ないケースが多いです。結果、同じ電流密度でも内部温度が上がりやすく、劣化が加速します。
4.目に見える劣化現象
明るさの低下
色物の場合、光束低下と同時に「色が薄く見える」「ムラが出る」ことが多く、白色のように単に“暗くなる”だけではありません。
色味のばらつき
同じバッチでもLED間で劣化速度が微妙に異なるため、複数並べた際に色温度や色相がずれて目立ちやすくなります。
チップ脱落や点灯不良
封止材の劣化進行により水分侵入やチップと基板の接点不良を起こし、「チラつき」や「点灯しない」といった物理故障に発展するケースも少なくありません。
まとめと対策
カラーLEDは封止材・蛍光体の劣化による色ずれが早く、しかも人の目に敏感に認識されるため、経年劣化が非常に目立ちやすい。
寿命を延ばすには、定格以下の電流で運用する、十分な放熱設計を施す、UVカットコーティングや防湿処理を行うなどが有効。
プロジェクトによってはカラーLEDモジュール自体を定期交換品として扱い、運用コストに組み込む設計が望ましいでしょう。
劣化が目立つぶん、施工前後での品質検査や運用中の定期メンテナンス計画を緻密に立てることで、カラーLEDを安心して長く使うことができます。次は、LEDの新しい放熱技術や色再現性向上の最新動向について掘り下げてみましょうか。
やはり…
最初は美しんだよな…。
(おわり)