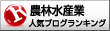漁獲したアワビのうちどのぐらい放流したアワビが入っているか
示す数値を「混獲率」と呼んでいます
漁獲したアワビのうち2割が放流したアワビなら
混獲率20%
これを毎回調べて、どのぐらいアワビ稚貝を放流した効果があるか検証するんです
ざっくり言えば2億円のアワビ水揚げがあって、混獲率が20%なら放流アワビの水揚げは4千万円あるので
3千万円の経費を掛けて稚貝放流しても1千万円の効果があるというようなことですね
震災前から去年まで混獲率はだいたい20%ぐらいでした
震災で種苗生産施設が流失してしまったため、平成23年~26年まで稚貝の放流が途絶え、再開したのは平成27年から
他の地域は混獲率が一旦下がって、その上昇し始めたらしいのに、田老はずっと変わらないのが不思議でした
放流が途絶えたんだから、どこかの時点で混獲率が下がるはずなんですけど・・・・
今年の混獲率はまだ出てませんが、調査した感じからすると、放流貝は去年より大分少ないです
震災前に放流した稚貝が去年まで採れてたのか?
そうだとすれば大分成長が遅いってことになります
エサがないからでしょうか?
でも、従来3~4年で9㎝(漁獲サイズ)になるって言われてましたから、8年とか9年で9㎝ってのはあまりにも遅すぎるし
平成27年に放流した群がそろそろ9㎝になってもいい頃だと思うんですけど・・・・・
水産技術センターでアワビの年齢を調査してくれているので、その結果が出れば、今漁獲してるアワビが何才ぐらいかが解ります
4~5才なら来年以降水揚げ上がってくると思うんですが
8才とか9才だったら、ちょっと深刻な事態です
アワビは外敵に食べられたり、エサがなくて餓死したりで1年に3割ぐらい死ぬといわれてますが
そんなに死なないだろうという説もありまして
仮に1年に2割ぐらいアワビが死ぬとすれば
1,000個のアワビを放流すると
1,000個→800個→640個→512個→409個
4年で漁獲できるとすれば1,000個のうち409個が海に残っているということになります
それが9年だとすれば
→327個→262個→209個→167個→134個
たったの134個・・・・
いよいよ本腰を入れて餌対策を実施せねばなりません