原作越えた。
原作が『八十日間四畳半一周』でアニメが『四畳半紀の終わり』、更には前回エントリが
『オズの異常な愛情』
(本当は語呂も良いし副題「または心配するのをやめて四畳半を愛するようになったか」だったんだけど、お話的&テーマ的に四畳半から脱出する話なのでああなりました。あと正確には『オヅ』だったわ)
なので対抗してやりたくなったのですが、なかなかコレという物がない。
ヴェルヌの作品って結構タイトルシンプルなんだなー。
あ、『気球に乗って四畳半』とかは行けるかもしんない。
飛行船出てきたし。
最終的にアニメ版の感想なので、アニメのタイトルとも前回のタイトルとも関わりのある方向で一つ。
聊かヒネリが無さ過ぎるかも分からんね。
ある程度原作との対比をさせながら語っていきたいと思います。
まず大きな流れで違うのは、原作だとどの人生でも明石さんとくっついておきながら主人公は不満だってこと。正直、これだと全国の純潔なアニメ男子諸君からは
リア充爆発しろ!!!!!
もとい
改心しろ!!! 改心しろ!!!
のシュプレヒコールが上がることだろう。
で、アニメに於いてはどれも結ばれないと言う形になっている。
「いつどうやったら結ばれんの?」という興味を長持ちさせる効能も果たしていたと思う。
また、前回エントリでも少し触れたように原作では「不可能性」という部分が強く出て、自身の人生を受け入れるという意味合いが大きい。
『八十日間四畳半一周』も福猫飯店の人生から分岐していてサークル活動バリエーションの一つに過ぎず、ある程度は小津などの交流があり、その上で不満を残しつつも人生に納得する形で終わる。
しかしアニメではそれをもう一歩進めて、殆ど人間関係そのものが絶えた主人公として描き、その視点から他の人生に於ける「私」の人生や人間関係を俯瞰する形に変わっている。
つまり引き籠もり四畳半地獄の人生は、他の人生の下位互換として描かれているのだ。
もちろん、他の如何なる人生に於いても不満たらたらなのだが、少なくとも他人と交流し、いがみ合い、恨んだり喜んだりという交流をしているのに対して引き籠もり人生ではそれすら殆ど存在していなかったことになっている。
手を伸ばせばどのような形であれ一緒になれた人々すら、見過ごしてしまった。
特に小津の事を考えて涙が畳に落ちるシーン、敢えて顔を見せずに落ちた跡だけで表現するのが上手い。
今まで妖怪だの疫病神だのとして扱ってきた男の重要さ。
「妖怪という人は根性がねじ曲がっているのであろう」という言葉は相島を指すと同時に、今までの人生に於ける「私」の事にも繋がっていて意味深だ。
ただ、重要なのはここで「私」が彼らから離れた(というかそもそも交流を持たなかった)からこそ、その重要性を再確認出来たという点である。
普通に関わりを持っていたら、やはり文句を言うだけの存在であっただろう。
自分事ではなく他人事として人生を俯瞰したから、初めてその素晴らしさが分かるのだ。
これは『素晴らしき哉、人生!』
にも通じるテーマかもしれない。
その小津に危険が迫っているという危機感。
また明石さんに関しても従来とは明確なスタンスの違いを見せている。
それまで「私」は明石さんに対しては、明らかに気があったにも関わらず距離を置いてきた。
あの饒舌な地の文ですら、一言も「好きだ」とか「惚れた」に類することは言っていなかった。
けれど、この私は四畳半世界に迷い込んだせいか、ハッキリとその言葉を口にしてアプローチすると決意する。
するともちぐまが、各四畳半の壁を越えて重なる。
蛾が出現して終われるように外へ出れたのは原作と同様ではあるが、重要なのは「私」の意志が介在しているかどうかだ。原作では占い婆からのキーワード「コロッセオ」に似た状態の歯を見付けて、その後脱出に成功する。けれどアニメでは自身の決断と蛾の出現→脱出が噛み合っている。
これはやはりアニメとして重要な部分だ。
外に出て、並行世界が重なるように町の人の衣服が替わる。
思えば四畳半の背景はほぼモノトーンで構成されていた。
きちんと色が付いているのは恐らくだけどカステラ、モチグマンのマント、香織さんや『海底2万マイル』と言った「外部に繋がっている小道具」だったように記憶している(魚肉ソーセージとか色ついてたか?)
脱出した今、極彩色に広がる光景がまた感慨深い。
更に遠眼鏡で川向こうに小津達を見付ける「私」
その表情の変化が、本当にグッと来る。
この人生では全く手を伸ばして来なかったあの人々が、此処にいる。
小津の名を呼びながら走る「私」
それぞれの世界の「私」の服装に替わりながら走り続ける。
彼らもサークル運動はしていたけれども、肝心なところでいつも間違ったり躊躇ったり失敗してきた。
原因の大部分は私の中にある見栄やプライドからくる躊躇い・勘違いだ。
でも、今は躊躇なんてもう必要がない。
四畳半地獄から帰ってきた「私」には分かっている。
躊躇って手を伸ばさないことの愚かさを。
どの人生でも一緒だった人々のことを。
ヒゲは無くなる、
服も破れる、
衒いも自尊心もカッコつけも、
全部無くなっても走る。
みんなを見付けて走るシーンは、小津を思ってカステラの脇に落ちる涙、壁越しに重なるモチグマンと並んで最終回の見所であり、アニメ作品という枠組みから観ても名シーンの一つとして良いのではないかと思う。
正直、本当に泣きそうになったよ俺は。
「私」は小津に会えて大喜びだが、相手は意味が分からない。
当たり前だ、この世界の小津はゴキブリ発生の謝罪にカステラを運んだだけの仲なのだけだ。
けれども私には関係がない。他の人生で、他の四畳半でずっと一緒だったのだから。
きっと「私」は滑稽だったろう。
全裸で橋の欄干に登り、お世辞にもカッコイイとは言えない女装青年に喜んで抱きついているのだ。
あまつさえ女装青年自身もてんで面識がないときている。
でもやっぱり「私」には関係がない。そんな物を気にしていたらキリがない。
今重要なのは小津を離さないこと。それだけだ。
結局川に落ちるだけにしても。
師匠はキチンと羽貫さんを連れて行って貰う。
男としてのケジメは必要。
自分自身もまた。
モチグマンを渡して猫ラーメンに誘う。
それだけで良かったのに、適当な言い訳をしてずっと約束を果たさなかった。
「私」は彼女のモチグマンを。
彼女は「私」の愛用してきた灰色のボクサーパンツを持っている。
それで充分じゃないか。
原作は、「私」の不可能性をかなり意識して書いてあるであろうことは何度か述べた。
アニメはどうだったか。もちろんそういう部分もキチンと描いた。
けれどそれに収まらず
「手を伸ばさないまま得られない可能性、
手を伸ばせば得られる可能性」
もまた存在するのだ、という所まで書き込んだ。
これは当たり前のテーマだけど、物語にはとても大切なことだ。
もちろん得られる物は僅かかもしれない。
でも、それはこの上なく大切なのだ。
最期に小津の見舞いに行く「私」だが、橋に到達してからのやり取り含めて今までの「私」と小津が完全に逆転している。また小津の表情も、今までのように妖怪じみたそれではなく、変わった顔だが普通の青年のように表現されている。逆にラストシーンで「私なりの愛だ」と語る主人公の表情は今までの小津そのものだ。
原作を読んだ時にも思ったが、ひょっとすると
他の世界の小津もまた四畳半地獄のような場所に迷い込んだのではないか。
だからこそ主人公にあれほど付きまとったのではないか。
思わずそんなことを深読みさせるような終わり方も素晴らしい。
またやや寂しげな曲調で部屋が延々と繰り返されるEDを最終回ではOPとして使い、ループを思わせるような内容を歌詞に盛り込みながらもあっけらかんとして前向きなアジカンのOPをEDに回す……という逆転の構図も「私」と小津の逆転と相まって面白い。
ラストシーンは原作準拠だったものの、一つ一つのサークル人生を緻密に描き、特に「ほんわか」では原作で殆ど語られていなかった部分を思いっ切り描きギャグとして昇華したり、モチグマンと明石さんの因縁も「私」を絡めて描いたり、最期の四畳半地獄も作品のテーマをより突っ込んでアニメ作品らしい盛り上げを作りつつ見事に落ちを付けた。
青春物語としても(私にとっては)原作以上に素晴らしいし、ミステリ的な伏線の貼り方も巧みで、アニメーションとしても動き、構図、演出など様々な部分で独創的にして飽きることがなかった。
これこそ
アニメの醍醐味にして真骨頂!
と、掛け値なしに称賛の声を送りたい。
昨今、一部界隈では「○○は人生」といったフレーズでアニメやゲーム、または小説などを過剰に褒め称えるふりをして小馬鹿にするという日本らしい複雑な文化があることを読者諸君も知っていよう私だって知っていた。
しかし個人的な見解を述べるならば、その大半に於いて揶揄という意味でなく賛同出来るものは少ない。
私にとってそれらは殆ど「取るに足りぬ作品」であって、生暖かい目で見ようとも神の如く崇め奉る気にはなれず、少しばかり語気を強めて批判しようとも悪鬼羅刹の如く蔑如しようという思いも起きない。
だが、ここで宣言しよう。
「四畳半神話体系は人生」だと。
考えてみても頂きたい。「○○は人生」とか「○○は人生讃歌」と言ったところで、誰がその人生に参加出来よう。
自慢ではないが私は幼少時に強盗に襲われ自分以外一家惨殺されたこともなければ深刻な夫婦喧嘩に巻き込まれて脳溢血を起こしたことも交通事故で全身不随になったこともなく、もちろん妹が病死して医者を目指したが受験当日に土砂崩れの合間に乗っていた電車がスッポリ収まって内臓を痛めつつも元気にリーダーシップを発揮しながら一週間を生き延び皆に臓器移植の崇高な精神を起こさしめた事もない。
私以外の人間だって、体験しているのはせいぜいが「妹が死んだ」「医者を目指した」「受験当日に事故にあった」「内臓を痛めたが漸く元気だった」「自らの臓器移植提供に同意した」というこの内のいずれか一つ、もしくは二つくらいであろう。
ひょっとしたらこういう現象が起きなかったのは私の幼いながらも釈迦牟尼仏もかくやと思われるほど神々しい姿が我が家を襲撃せんと舌なめずりをしていた荒くれ者のまなこに天啓の如く突き刺さってパウロもびっくりの回心をもたらし、その満面の笑みから滲み出る癒しの波動が父母の怒り猛った心に触れていい湯加減の快適さを提供せしめたせいかもしれぬ。
また日頃の行いにより神仏の加護を得て電車事故はもちろん交通事故にも巻き込まれず内臓を痛めつつも一週間病院に行かないまま元気に過ごす必要性そのものが無かったせいやもしれぬ。
だが理屈は兎も角自身の現実に起きるは盲腸や骨折ばかりで「我が人生は恐らく劇的ではない」のである。
(正直に言ってしまうと骨折や盲腸すらない)
恐らくは読者諸君も同様であろう。
平凡ではないから劇的なのであって劇的な人生が横溢していたならそれは既に倦怠期夫婦の如きマンネリであり劇とは呼べぬ。
我々の人生は概ね極めて散文的で凡庸で大草原の小さな家である。 それぞれ一時期の面白エピソードを酒宴で肴の足しに食い潰していくのが関の山だ。一方読んで字の如く当然ながら大半の物語が、我々の人生に比べて劇的である。
けれど意志による苦悩の乗り越えでもなく、それ自体を読者視聴者諸氏に問い掛けるでもなく、彼ら自身の特殊な都合と特殊な世界の構造のみでアッという間に解消されてしまう葛藤を、誰の人生に当て嵌めて考えればよいのだ。
「四畳半神話体系もまた劇的ではないか」
と、私に比肩しうる鋭敏な灰色の脳細胞を以て問われる方もいよう。 さもありなん、これもまた平行世界・ループ物として成立しているという意味に於いては特殊な作品である。しかしながらもう一歩、女子トイレの前から踏みだし扉を開けておもむろに便座へ蹲踞する気持ちで考えて頂きたい。
主人公の「私」は内在されている「薔薇色のキャンパスライフ」への可能性を追求し、様々なサークル活動にいそしんでいた。
しかしその過程で必ず悪の権化というよりも悪の煮こごりを煩悩の出汁汁で煮染めたような小津がつきまとい、自らはモチグマンを手慰みに弄ぶばかりで明石さんに渡すでもなく猫ラーメンを食すでもなく恋愛映画を撮るでもない。
無為、圧倒的無為である。
種々の可能性を轢きつぶし平面にしていく有様はあたかもロードローラーの如しであり、これがまだ耕耘機であれば掘り返せるだけ何某かの変化が生じていたであろう。
だが思い返してもみよ。
我々――すなわち私と不本意かもしれないが取り敢えず同列に置かせて頂いている読者諸氏の人生もまた限りなく近いのではないか。
人生が繰り返せば、人生がもう一度あれば。
我々の多くは何処かで(おもに苦悩している時に)そう思う。
思いもしないのは兜甲児くらいのものだ。
けれどたとえ幾十回繰り返し、もう百度あってもその時々の人生において後悔しないなどと言うことがあろうか(いや、ない)
責任者は誰か、それは私である。
運営者は誰か、それも私である。
経営者は誰か、結局は私である。
環境に左右される要素もあろう。
だが基本的に私の人生は私の物であり、またその責任も最終的には私に返ってくるのである。
ならばクレタ迷宮の如き人生の可能性が我々の現前に広がっていたとしても、実際に踏破していくのは困難を極める。
諸君は白皙美貌の黒髪の傾城(乙女でも可)が酔漢に襲われていたら颯爽と助けるだろうか。
他の好漢が憤然として割って入り、その数ヶ月後に好漢と傾城が連れ添っていたなら「あの時憤然と立ち上がっていれば」と思うであろう。けれども実際にはその場面を繰り返したとして躊躇いはしないだろうか。
私は躊躇うつもりなど毫末もないが、「あの人たちはひょっとしたら犬も喰わない痴話喧嘩をしているに過ぎず、中に入った私が逆に空気が読めない男として白眼視されるやもしれぬ」「男が銃刀法違反に触れるような飛び出しナイフなどを所持しており、やおら私の肝臓を抉り抜いて美味しそうに咀嚼するやもしれぬ」といった想定すべき可能性を明晰な頭脳で検討し対策を練っている最中に他の好漢が憤然として正義の鉄槌を下す恐れも大いに考え得る。
また明晰な頭脳で計算し尽くした挙げ句おもむろに立ち上がり、反射的に三十六計を上回る見事な計略を用いて乙女を救い出したとしよう。
そこまではいい、そこまではいいが一時的な感謝の念を利用して男女の縁を結べと言うのは清廉潔白な人生を歩んできた私には耐え難い愚行でありそんな不埒で卑劣な行為は断固反対ではあるが乙女が熱烈な思慕の念を私に向けてくるならばそれを蔑ろにするのはむしろ不誠実と言うべきであるから意気揚々と応えたい。応えたいがどう応えればいいのかは純真高潔な人生を送ってきた私にはフェルマーの最終定理よりも難解な問題であり、よって正解は薮の中である。
たとえその場で応対し始めるうちに己の隠されたジョニーの願望いや原始的本能もとい桃色遊戯の才能が覚醒し、その恐るべき手練手管によって乙女と懇ろになったとしよう。
しかしその後乙女乃至私自身が謎の奇病に伏せって息絶え、或いは道路に飛び出した仔猫乃至幼女を助けようとして死んでしまえば元の木阿弥どころか絶望の奈落へバンジージャンプし、残された方も悲哀の余り七孔噴血して他界するに違いない。
もしそんな状態になるなら凡庸に生きた方がお互いの為であり、見事なWIN―WINの関係として各界からも絶賛されよう。
ひょっとすると完璧で一切不満のない人生も存在するのかもしれない。
ただし無限の可能性からそれを見付け出すのはウナギ掬いの道具でタクラマカンの真砂乃至砂礫の中から一粒の黄金を探るに等しい行為である。
諸君は、いや人はその作業に耐えられるだろうか。
見つけたとして、その不満のない完全な人生は探し続けた労力と釣り合うだけの価値があるのだろうか。
そこで、この「八十日間四畳半一周」である。
これは原作の解説で佐藤哲也氏が指摘しているとおり、「私」の可能性・可変性の象徴であると同時に、いやそれ以上に「私」の不可能性・不可変性の結果である。
樋口師匠の
「可能性という言葉を無限定に使ってはいけない。我々という存在を規定するのは、我々がもつ可能性ではなく、我々がもつ不可能性である」
(角川文庫版『四畳半神話体系』150~151頁)
という言葉はまさにそれを指摘している(と、佐藤哲也氏は仰られている)
そしてこれは、我々自身の人生でもある。
八十日間の四畳半旅行で「私」は悉く他の可能性を羨むが、その可能性を選んだ「私」からすれば羨まれる程の物ではない……ということは我々も共に観てきた通りである。
どうあっても「凡庸で不満が募る人生」であって、そこに大きな差はない。
せいぜいが香織さんの別荘になっているか半七捕物帖があるか、悪友とどれだけ緊密に接触しているかくらいのものだ。
で、あるならば「凡庸で不満が募る人生」をどうアクションして改変していくかではなく「凡庸で不満が募る人生」にどういうリアクションを取るか、という問題足り得る。
我々の過ぎ去りし人生もまた同様である。
変わらないのならば、どう捉え、どうするか。
「八十日間四畳半一周」の「私」は小津と関わる可能性までも閉ざしつつあった。
この小津というソドムとゴモラから男女を取り寄せて息子を作り、それに「深きものども」をあてがって産ませたような男は、実はいずれの「私」の人生に於いても八面六臂の活躍で類い希な才能を発揮し、闊達自在な人生を送っており、性格と容貌以外を羨望の眼差しで焼き尽くしたくなるような人物である。
その小津が如何なる世界でも「私」を友人として認め、運命の黒い糸で結ばれる仲を自認する絆は、(本人が喜ぶかどうかは兎も角)実のところ「私」にとって非常に得がたい物であるのは間違いないであろう。
無限の可能性と不可能性がシュレーディンガーの猫よろしく存在する、この凡庸な人生をどう受け止めるか。
そこで期すと期せずと絡まってくる赤・黒・黄・桃・白といったモチグマン並に多様な運命の糸をどう捉えるか。
そのような意味に於いてまさに「四畳半神話体系は人生」と声高に主張し、この話は「あなたの人生の物語」ではなく「私達の人生の物語」なのだと断言して憚りたくない心持ちであるが、読者諸氏は如何であろうか。
しかし個人的な見解を述べるならば、その大半に於いて揶揄という意味でなく賛同出来るものは少ない。
私にとってそれらは殆ど「取るに足りぬ作品」であって、生暖かい目で見ようとも神の如く崇め奉る気にはなれず、少しばかり語気を強めて批判しようとも悪鬼羅刹の如く蔑如しようという思いも起きない。
だが、ここで宣言しよう。
「四畳半神話体系は人生」だと。
考えてみても頂きたい。「○○は人生」とか「○○は人生讃歌」と言ったところで、誰がその人生に参加出来よう。
自慢ではないが私は幼少時に強盗に襲われ自分以外一家惨殺されたこともなければ深刻な夫婦喧嘩に巻き込まれて脳溢血を起こしたことも交通事故で全身不随になったこともなく、もちろん妹が病死して医者を目指したが受験当日に土砂崩れの合間に乗っていた電車がスッポリ収まって内臓を痛めつつも元気にリーダーシップを発揮しながら一週間を生き延び皆に臓器移植の崇高な精神を起こさしめた事もない。
私以外の人間だって、体験しているのはせいぜいが「妹が死んだ」「医者を目指した」「受験当日に事故にあった」「内臓を痛めたが漸く元気だった」「自らの臓器移植提供に同意した」というこの内のいずれか一つ、もしくは二つくらいであろう。
ひょっとしたらこういう現象が起きなかったのは私の幼いながらも釈迦牟尼仏もかくやと思われるほど神々しい姿が我が家を襲撃せんと舌なめずりをしていた荒くれ者のまなこに天啓の如く突き刺さってパウロもびっくりの回心をもたらし、その満面の笑みから滲み出る癒しの波動が父母の怒り猛った心に触れていい湯加減の快適さを提供せしめたせいかもしれぬ。
また日頃の行いにより神仏の加護を得て電車事故はもちろん交通事故にも巻き込まれず内臓を痛めつつも一週間病院に行かないまま元気に過ごす必要性そのものが無かったせいやもしれぬ。
だが理屈は兎も角自身の現実に起きるは盲腸や骨折ばかりで「我が人生は恐らく劇的ではない」のである。
(正直に言ってしまうと骨折や盲腸すらない)
恐らくは読者諸君も同様であろう。
平凡ではないから劇的なのであって劇的な人生が横溢していたならそれは既に倦怠期夫婦の如きマンネリであり劇とは呼べぬ。
我々の人生は概ね極めて散文的で凡庸で大草原の小さな家である。 それぞれ一時期の面白エピソードを酒宴で肴の足しに食い潰していくのが関の山だ。一方読んで字の如く当然ながら大半の物語が、我々の人生に比べて劇的である。
けれど意志による苦悩の乗り越えでもなく、それ自体を読者視聴者諸氏に問い掛けるでもなく、彼ら自身の特殊な都合と特殊な世界の構造のみでアッという間に解消されてしまう葛藤を、誰の人生に当て嵌めて考えればよいのだ。
「四畳半神話体系もまた劇的ではないか」
と、私に比肩しうる鋭敏な灰色の脳細胞を以て問われる方もいよう。 さもありなん、これもまた平行世界・ループ物として成立しているという意味に於いては特殊な作品である。しかしながらもう一歩、女子トイレの前から踏みだし扉を開けておもむろに便座へ蹲踞する気持ちで考えて頂きたい。
主人公の「私」は内在されている「薔薇色のキャンパスライフ」への可能性を追求し、様々なサークル活動にいそしんでいた。
しかしその過程で必ず悪の権化というよりも悪の煮こごりを煩悩の出汁汁で煮染めたような小津がつきまとい、自らはモチグマンを手慰みに弄ぶばかりで明石さんに渡すでもなく猫ラーメンを食すでもなく恋愛映画を撮るでもない。
無為、圧倒的無為である。
種々の可能性を轢きつぶし平面にしていく有様はあたかもロードローラーの如しであり、これがまだ耕耘機であれば掘り返せるだけ何某かの変化が生じていたであろう。
だが思い返してもみよ。
我々――すなわち私と不本意かもしれないが取り敢えず同列に置かせて頂いている読者諸氏の人生もまた限りなく近いのではないか。
人生が繰り返せば、人生がもう一度あれば。
我々の多くは何処かで(おもに苦悩している時に)そう思う。
思いもしないのは兜甲児くらいのものだ。
けれどたとえ幾十回繰り返し、もう百度あってもその時々の人生において後悔しないなどと言うことがあろうか(いや、ない)
責任者は誰か、それは私である。
運営者は誰か、それも私である。
経営者は誰か、結局は私である。
環境に左右される要素もあろう。
だが基本的に私の人生は私の物であり、またその責任も最終的には私に返ってくるのである。
ならばクレタ迷宮の如き人生の可能性が我々の現前に広がっていたとしても、実際に踏破していくのは困難を極める。
諸君は白皙美貌の黒髪の傾城(乙女でも可)が酔漢に襲われていたら颯爽と助けるだろうか。
他の好漢が憤然として割って入り、その数ヶ月後に好漢と傾城が連れ添っていたなら「あの時憤然と立ち上がっていれば」と思うであろう。けれども実際にはその場面を繰り返したとして躊躇いはしないだろうか。
私は躊躇うつもりなど毫末もないが、「あの人たちはひょっとしたら犬も喰わない痴話喧嘩をしているに過ぎず、中に入った私が逆に空気が読めない男として白眼視されるやもしれぬ」「男が銃刀法違反に触れるような飛び出しナイフなどを所持しており、やおら私の肝臓を抉り抜いて美味しそうに咀嚼するやもしれぬ」といった想定すべき可能性を明晰な頭脳で検討し対策を練っている最中に他の好漢が憤然として正義の鉄槌を下す恐れも大いに考え得る。
また明晰な頭脳で計算し尽くした挙げ句おもむろに立ち上がり、反射的に三十六計を上回る見事な計略を用いて乙女を救い出したとしよう。
そこまではいい、そこまではいいが一時的な感謝の念を利用して男女の縁を結べと言うのは清廉潔白な人生を歩んできた私には耐え難い愚行でありそんな不埒で卑劣な行為は断固反対ではあるが乙女が熱烈な思慕の念を私に向けてくるならばそれを蔑ろにするのはむしろ不誠実と言うべきであるから意気揚々と応えたい。応えたいがどう応えればいいのかは純真高潔な人生を送ってきた私にはフェルマーの最終定理よりも難解な問題であり、よって正解は薮の中である。
たとえその場で応対し始めるうちに己の隠されたジョニーの願望いや原始的本能もとい桃色遊戯の才能が覚醒し、その恐るべき手練手管によって乙女と懇ろになったとしよう。
しかしその後乙女乃至私自身が謎の奇病に伏せって息絶え、或いは道路に飛び出した仔猫乃至幼女を助けようとして死んでしまえば元の木阿弥どころか絶望の奈落へバンジージャンプし、残された方も悲哀の余り七孔噴血して他界するに違いない。
もしそんな状態になるなら凡庸に生きた方がお互いの為であり、見事なWIN―WINの関係として各界からも絶賛されよう。
ひょっとすると完璧で一切不満のない人生も存在するのかもしれない。
ただし無限の可能性からそれを見付け出すのはウナギ掬いの道具でタクラマカンの真砂乃至砂礫の中から一粒の黄金を探るに等しい行為である。
諸君は、いや人はその作業に耐えられるだろうか。
見つけたとして、その不満のない完全な人生は探し続けた労力と釣り合うだけの価値があるのだろうか。
そこで、この「八十日間四畳半一周」である。
これは原作の解説で佐藤哲也氏が指摘しているとおり、「私」の可能性・可変性の象徴であると同時に、いやそれ以上に「私」の不可能性・不可変性の結果である。
樋口師匠の
「可能性という言葉を無限定に使ってはいけない。我々という存在を規定するのは、我々がもつ可能性ではなく、我々がもつ不可能性である」
(角川文庫版『四畳半神話体系』150~151頁)
という言葉はまさにそれを指摘している(と、佐藤哲也氏は仰られている)
そしてこれは、我々自身の人生でもある。
八十日間の四畳半旅行で「私」は悉く他の可能性を羨むが、その可能性を選んだ「私」からすれば羨まれる程の物ではない……ということは我々も共に観てきた通りである。
どうあっても「凡庸で不満が募る人生」であって、そこに大きな差はない。
せいぜいが香織さんの別荘になっているか半七捕物帖があるか、悪友とどれだけ緊密に接触しているかくらいのものだ。
で、あるならば「凡庸で不満が募る人生」をどうアクションして改変していくかではなく「凡庸で不満が募る人生」にどういうリアクションを取るか、という問題足り得る。
我々の過ぎ去りし人生もまた同様である。
変わらないのならば、どう捉え、どうするか。
「八十日間四畳半一周」の「私」は小津と関わる可能性までも閉ざしつつあった。
この小津というソドムとゴモラから男女を取り寄せて息子を作り、それに「深きものども」をあてがって産ませたような男は、実はいずれの「私」の人生に於いても八面六臂の活躍で類い希な才能を発揮し、闊達自在な人生を送っており、性格と容貌以外を羨望の眼差しで焼き尽くしたくなるような人物である。
その小津が如何なる世界でも「私」を友人として認め、運命の黒い糸で結ばれる仲を自認する絆は、(本人が喜ぶかどうかは兎も角)実のところ「私」にとって非常に得がたい物であるのは間違いないであろう。
無限の可能性と不可能性がシュレーディンガーの猫よろしく存在する、この凡庸な人生をどう受け止めるか。
そこで期すと期せずと絡まってくる赤・黒・黄・桃・白といったモチグマン並に多様な運命の糸をどう捉えるか。
そのような意味に於いてまさに「四畳半神話体系は人生」と声高に主張し、この話は「あなたの人生の物語」ではなく「私達の人生の物語」なのだと断言して憚りたくない心持ちであるが、読者諸氏は如何であろうか。
みんな自分が大好き?
先日は一日三本の映画をこなして参りましたw
そこまで詰めなくても良かった気もするけど、まぁいいよ。
第1弾は『告白』、巷でも噂になっていると思われる問題作ですね。
実際かなり突っ込んだ内容で、「衝撃的だった」とか「考えさせられた」というような感想も多かったみたい。
ご多分に漏れず俺も色々考えてしまった。
観に行った作品『告白』『アイアンマン2』『ヒーローショー』の中では『ヒーローショー』の評価が一番高いんだが、反芻度という意味に於いては間違いなく『告白』だ。
ミステリとしても良く出来ていて誰かが黒澤明の『羅生門』に喩えていた。
それは構成という意味では言い得て妙な表現だ。
娘を生徒二人に殺された教師が、その復讐をするという話。
ただ、その文脈で色々と想像の余地がある。
世間的には遺族の気持ちとか復讐の是非とか少年犯罪とか、そんな部分が「考えさせられる」んだろうという気がする。そういう意味合いで言えば、自分はちょっとずれている気がしないではない。
個人的に少年犯罪や死刑制度などについて社会的に少々複雑な立場を取っている。
死刑は基本肯定していない、裁判で弁護士が変な弁論を行っても別に構わないという所謂左派的な立場があるのと同時に、システムとしての死刑が確定してしまったならそれは執行されて叱るべきだし弁護が採用されずに心証を悪くして判決が重くなってもそれは当然。
更に少なくとも復讐という行為自体はやりたきゃやればいいだろうって部分もある。
命の軽重にしても、価値判断とは主観だ。だから軽い命もあれば重い命もあるし、どれが重くてどれが軽いかは人によりけりで同じ対象を示してすら違うだろう。
そんな人間であるにも関わらず、この映画を見ている時の気持ち悪さというか、違和感はどうだろう。
物凄く居心地が悪い、松たか子の演技は確かに凄いしそれでやってる内容がかなり立ち入った話だからと言うのもある。でも、その程度じゃこんなに気持ち悪いとかイラつく感覚にはならない。何が気に入らないのか。
それは中盤で分かった。
そうか、こいつら自分が大好きなんだ。
自分が好きで好きで特別になりたい。守りたい。他人より上に行きたい。
悪いのは自分のせいじゃない、お前らだ、お前らが悪いんだ。
この作品はそういう主張で溢れている。
それで他人を殺してみたり制裁してみたり見下してみたり分かった振りをしてるんだ。
もちろんそういう気持ちは誰にでもある、でも必ずしも人を殺したりだとか制裁をするわけではない。
また少年A・Bや生徒側ヒロイン格の美月、クラスの人間、またモンスターペアレントであるBの母親は、そういう自意識過剰さがかなり自覚的に書かれている。
でも、それだけだろうか?
僕は冒頭から、すなわち松たか子演じる森口が語り始めるそのシーンからすでに気持ち悪さを感じていた。
彼女は被害者という立場にあるぞ?
実際相手が悪いんだから他罰的とは言えないんじゃないか?
しかしそういう思いも終盤にいたって確信に近いものへと変わってしまう。
この書き方もかなり突っ込んだ内容だけれども思い切って書いてしまおうか。
お前は(被害者だからとは言え)そんなに偉いのか?
誤解の無いように言うと、法的な意味合いでの被害者(家族)はもっと守られるべきだろうと思う。
例えば事件の情報開示だとか精神的なケアだとか援助だとか、そういうことだ。
また犯人を非難し責め立て、そしてさっきも言ったように時には何らかの手立てを行うことは心情的にやむを得ない場合もあるかと思う。
光市母子殺人事件に於いて、弁護士の主張は法廷で為されたことだから法廷によって決着を付けられるべきだが、犯人が死刑を回避した場合、本村さんが手を下しても僕は手放しの称賛もしないし完全な意味での否定もしない。
ただ称賛の声を皮肉ったり「犯罪だ」(これは価値判断ではなく事実)とは指摘するかもしれないけれども。
それでも語弊があるかもしれないから、もっと作品に寄って言い換えよう。
森口ってそんなに偉いのか?
これは彼女の行為の是非に直結する訳じゃない。
いや、正確には行為も含まれるのだが、それ以上に彼女の動機というか態度についての話だ。
なんであんなに偉そうなんだろう?
先生だから? 被害者だから? 復讐者だから?
言葉の一々に挑発的な言辞が含まれる。
A・Bに対しての言葉ならまだ分かる。
でも他の人間に対する姿勢や、他の生徒にもそうなのだ。
元々こういう人間だったのか? それとも子供を失ったのが切っ掛けだったのか?
これは非常に微妙な問題だと思う。
そして小さいようで作品の根幹を読み替えられる部分だ。
中島哲也監督は、原作について
「登場人物が嘘を吐いていると考えると収拾がつかなくなった。最終的に僕の中でも結論が出ていない」
というようなことを口にしている。
僕も映画の後に原作を読んだ。
こちらは似ているが小さい部分の積み重ねで、かなり違う作品として成立している。
一番決定的なのはラストシーンだ。
原作では森口はAの母親の所へ爆弾を持っていき、本人の手で爆殺させた後に「これがあなたの更正の第一歩だと思いませんか?」と言って終わる。
ところが映画だと森口は、更正云々に続けてAの「なーんてね」という台詞を真似る。
この「なーんてね」は何に掛かるのか?
母親が爆死したという事に対してだろうか?
更正云々に対してだろうか?
分からないようにしている部分もあるから断定は出来ないが、僕は後者だと思う。
母親を擬似的に殺した場合、確かに一時的にはAを公開させることが出来るだろう。
しかしそれは嘘だとなれば本物の傷として、本物の苦しみとしては残らない。
またこれはAの目的たる「騒動によって母親と繋がる」事を敢えて手助けしてやる行為にもなりうるし、実際この後に母親が生きていれば親子の絆を取り戻しもするだろう。
「貴方の望む猟奇犯罪にはしない」として娘の死を隠蔽した森口が、わざわざAの自己実現を手伝ったりするだろうか?
そして原作では「なーんてね」は入っていない。
爆破は事実として明かされたままだ。
だからここは中島監督の原作に対する「邪推」だろう。
「更正の第一歩なんて言ってるけど、お前も人殺しの手助けしてるし、関係ない人間まで巻き込んで煽ってるだろ? それにガキ一人を更正する為に何人も死ぬとか、どんだけ大切なのそのガキは 結局お前が復讐したいだけなんじゃないの? ホントに更正なんて綺麗事考えてんの?」
という邪推。
これは確かにそう見える。
その観点を入れたことで作品がグッと深まった感じがする。
ただ複合的な観点を入れたせいか、もしくはこれもまた意識しての「邪推」なのか、僕にはもう一つの像が見えてしまった。
本当に復讐だけをしたいのか?
何故こういう事を思ったか。
それは前述した「他者に対する挑発的な言辞」がある。
これは映画版でかなり強化されている部分で、そしてA・Bやその母親のみならず、無関係な人間に対しても同じように語られる。
少年A・B含め作中の登場人物の殆どが
「俺は凄いんだ、だからお前らはみんなバカなんだ」
「俺は悪くない、お前らが悪いんだ」
というないようの主張をする。
貶めることで、自らを高みにあげる。
他人を蹴落として自らを高めようとする自己実現の姿だ。
ただ、殆どの登場人物に於いてはその過剰な自意識が分かり易く書かれているにも関わらず、一人だけそれを認識しづらい人間が居る。
森口だ。
実のところ、彼女の言動に見え隠れする自意識は他の登場人物とよく似ている。
一生徒のメールの内容を嘲弄しながら暴き、後任の教師を操り、いじめをけしかけ、せせら笑う。
にも関わらず、その厭らしさが比較的目立たないのは彼女が教師であり、また被害者だからである。
Aに対しては何度も彼の低劣さに対して言及し、その愚かさを滔々と語り出す。
終盤の表情、言い回し、(作品としてではなく彼女が用意した)演出を見よ。
そこで思うのだ。
お前、もう復讐がどうとかじゃなくて、単に相手より上の自分を見せつけたいだけなんじゃね?
A・Bが自分の価値を高める為の自己実現から殺人を犯したのと全く同様に見える。
相手の計画を暴き、先回りし、より関係のない不特定多数の人間を巻き込む(殺す)やり方を、自らの手を汚さずに行い(これは詭弁だが)勝ち誇る。
それはもう復讐だとかなんとかじゃなくて、相手より上を行って罠に嵌めて快哉を叫んでいるガキと同じだ。
しかも自分は大人、相手は正真正銘のガキ。
もちろん
「それは演技でAに最大級の恥辱をあじあわせ、
後悔させる事が復讐なのだから、敢えて同レベルに下ったのだ」
という見方も出来る。
特に原作に存在しないファミレス前後のシーンで彼女の像は揺らぐだろう。
ただしその時点で無関係な他者を見下し、イジメをし向け、教師を操るようなやり口、つまり「自らは何もせず他人に頼り、他人を利用している」と得意気に語る姿(これはA・Bの行動傾向に近いことにも留意)から、彼女がどういう価値観を持っているかが垣間見える気がする。
もう一つは、例え挑発的態度が他者に見せる為、演技で始めた行為だとしても彼女にそういう部分がなければその発想に辿り着くだろうか。
また本当にそういう気持ちがないままに演技でしかなかったと言えるだろうか?
僕は怪しいと思う。
彼女が他人に見せる態度には、物凄く余裕があるのだ。
怒りとか憎しみみたいな印象を、基本的に受けない。
不条理の帳尻合わせという感じでもない。それならもっとドライになる。
ファミレス後のシーンは、確かにどういう意図なのかやや迷う。
復讐が不完全だった事自体に泣いたのか、完全な復讐をしなければならないと苦悩したのか。
いくらか想定出来るだろうが、少なくとも娘を思っている部分があるのは間違いない。
ただ叫んだ後に「くだらない」と吐き捨てているのもまた事実であり、それは娘のことではないだろうとは思う。
しかし彼女が娘のことを大事に思って、本人としてはその復讐という意識であっても、僕は(自らは手を汚さず)相手を出し抜いて嵌めてやったという裏の意識というか、本人の歪んだ喜び(復讐を果たした喜びではなく、相手が自分の思い通りになったという喜び)が透けて見える気がするのだ。
そこには爆弾で死んだであろう他の人の事とか、美月の事とか(原作ではイジメにあわせたことを一言だけ謝ってる)寺田の事とかは無い……いや、無い訳じゃないな。
A・Bをバカにする小道具として存在しているのだ。
だから、森口も自分が大好きで(復讐を切っ掛けに)ガキ程度に勝ち誇って自己実現を果たした、かなり痛い大人コドモに思えてしまう。単なる被害者ではなく、被害者という立場的な正当性を拠り所として(本来的な大人の教師という強さに加えて)相手よりも上の立場を築いたモノが加害者というオモチャを弄くり回して小馬鹿にする……そんな大人コドモに。
超前田さんが「偽善を全てはぎ取って……」とか言ってたけど、一つだけ有る。
復讐って概念自体が、正当化に過ぎないんだよ。
先日は一日三本の映画をこなして参りましたw
そこまで詰めなくても良かった気もするけど、まぁいいよ。
第1弾は『告白』、巷でも噂になっていると思われる問題作ですね。
実際かなり突っ込んだ内容で、「衝撃的だった」とか「考えさせられた」というような感想も多かったみたい。
ご多分に漏れず俺も色々考えてしまった。
観に行った作品『告白』『アイアンマン2』『ヒーローショー』の中では『ヒーローショー』の評価が一番高いんだが、反芻度という意味に於いては間違いなく『告白』だ。
ミステリとしても良く出来ていて誰かが黒澤明の『羅生門』に喩えていた。
それは構成という意味では言い得て妙な表現だ。
娘を生徒二人に殺された教師が、その復讐をするという話。
ただ、その文脈で色々と想像の余地がある。
世間的には遺族の気持ちとか復讐の是非とか少年犯罪とか、そんな部分が「考えさせられる」んだろうという気がする。そういう意味合いで言えば、自分はちょっとずれている気がしないではない。
個人的に少年犯罪や死刑制度などについて社会的に少々複雑な立場を取っている。
死刑は基本肯定していない、裁判で弁護士が変な弁論を行っても別に構わないという所謂左派的な立場があるのと同時に、システムとしての死刑が確定してしまったならそれは執行されて叱るべきだし弁護が採用されずに心証を悪くして判決が重くなってもそれは当然。
更に少なくとも復讐という行為自体はやりたきゃやればいいだろうって部分もある。
命の軽重にしても、価値判断とは主観だ。だから軽い命もあれば重い命もあるし、どれが重くてどれが軽いかは人によりけりで同じ対象を示してすら違うだろう。
そんな人間であるにも関わらず、この映画を見ている時の気持ち悪さというか、違和感はどうだろう。
物凄く居心地が悪い、松たか子の演技は確かに凄いしそれでやってる内容がかなり立ち入った話だからと言うのもある。でも、その程度じゃこんなに気持ち悪いとかイラつく感覚にはならない。何が気に入らないのか。
それは中盤で分かった。
そうか、こいつら自分が大好きなんだ。
自分が好きで好きで特別になりたい。守りたい。他人より上に行きたい。
悪いのは自分のせいじゃない、お前らだ、お前らが悪いんだ。
この作品はそういう主張で溢れている。
それで他人を殺してみたり制裁してみたり見下してみたり分かった振りをしてるんだ。
もちろんそういう気持ちは誰にでもある、でも必ずしも人を殺したりだとか制裁をするわけではない。
また少年A・Bや生徒側ヒロイン格の美月、クラスの人間、またモンスターペアレントであるBの母親は、そういう自意識過剰さがかなり自覚的に書かれている。
でも、それだけだろうか?
僕は冒頭から、すなわち松たか子演じる森口が語り始めるそのシーンからすでに気持ち悪さを感じていた。
彼女は被害者という立場にあるぞ?
実際相手が悪いんだから他罰的とは言えないんじゃないか?
しかしそういう思いも終盤にいたって確信に近いものへと変わってしまう。
この書き方もかなり突っ込んだ内容だけれども思い切って書いてしまおうか。
お前は(被害者だからとは言え)そんなに偉いのか?
誤解の無いように言うと、法的な意味合いでの被害者(家族)はもっと守られるべきだろうと思う。
例えば事件の情報開示だとか精神的なケアだとか援助だとか、そういうことだ。
また犯人を非難し責め立て、そしてさっきも言ったように時には何らかの手立てを行うことは心情的にやむを得ない場合もあるかと思う。
光市母子殺人事件に於いて、弁護士の主張は法廷で為されたことだから法廷によって決着を付けられるべきだが、犯人が死刑を回避した場合、本村さんが手を下しても僕は手放しの称賛もしないし完全な意味での否定もしない。
ただ称賛の声を皮肉ったり「犯罪だ」(これは価値判断ではなく事実)とは指摘するかもしれないけれども。
それでも語弊があるかもしれないから、もっと作品に寄って言い換えよう。
森口ってそんなに偉いのか?
これは彼女の行為の是非に直結する訳じゃない。
いや、正確には行為も含まれるのだが、それ以上に彼女の動機というか態度についての話だ。
なんであんなに偉そうなんだろう?
先生だから? 被害者だから? 復讐者だから?
言葉の一々に挑発的な言辞が含まれる。
A・Bに対しての言葉ならまだ分かる。
でも他の人間に対する姿勢や、他の生徒にもそうなのだ。
元々こういう人間だったのか? それとも子供を失ったのが切っ掛けだったのか?
これは非常に微妙な問題だと思う。
そして小さいようで作品の根幹を読み替えられる部分だ。
中島哲也監督は、原作について
「登場人物が嘘を吐いていると考えると収拾がつかなくなった。最終的に僕の中でも結論が出ていない」
というようなことを口にしている。
僕も映画の後に原作を読んだ。
こちらは似ているが小さい部分の積み重ねで、かなり違う作品として成立している。
一番決定的なのはラストシーンだ。
原作では森口はAの母親の所へ爆弾を持っていき、本人の手で爆殺させた後に「これがあなたの更正の第一歩だと思いませんか?」と言って終わる。
ところが映画だと森口は、更正云々に続けてAの「なーんてね」という台詞を真似る。
この「なーんてね」は何に掛かるのか?
母親が爆死したという事に対してだろうか?
更正云々に対してだろうか?
分からないようにしている部分もあるから断定は出来ないが、僕は後者だと思う。
母親を擬似的に殺した場合、確かに一時的にはAを公開させることが出来るだろう。
しかしそれは嘘だとなれば本物の傷として、本物の苦しみとしては残らない。
またこれはAの目的たる「騒動によって母親と繋がる」事を敢えて手助けしてやる行為にもなりうるし、実際この後に母親が生きていれば親子の絆を取り戻しもするだろう。
「貴方の望む猟奇犯罪にはしない」として娘の死を隠蔽した森口が、わざわざAの自己実現を手伝ったりするだろうか?
そして原作では「なーんてね」は入っていない。
爆破は事実として明かされたままだ。
だからここは中島監督の原作に対する「邪推」だろう。
「更正の第一歩なんて言ってるけど、お前も人殺しの手助けしてるし、関係ない人間まで巻き込んで煽ってるだろ? それにガキ一人を更正する為に何人も死ぬとか、どんだけ大切なのそのガキは 結局お前が復讐したいだけなんじゃないの? ホントに更正なんて綺麗事考えてんの?」
という邪推。
これは確かにそう見える。
その観点を入れたことで作品がグッと深まった感じがする。
ただ複合的な観点を入れたせいか、もしくはこれもまた意識しての「邪推」なのか、僕にはもう一つの像が見えてしまった。
本当に復讐だけをしたいのか?
何故こういう事を思ったか。
それは前述した「他者に対する挑発的な言辞」がある。
これは映画版でかなり強化されている部分で、そしてA・Bやその母親のみならず、無関係な人間に対しても同じように語られる。
少年A・B含め作中の登場人物の殆どが
「俺は凄いんだ、だからお前らはみんなバカなんだ」
「俺は悪くない、お前らが悪いんだ」
というないようの主張をする。
貶めることで、自らを高みにあげる。
他人を蹴落として自らを高めようとする自己実現の姿だ。
ただ、殆どの登場人物に於いてはその過剰な自意識が分かり易く書かれているにも関わらず、一人だけそれを認識しづらい人間が居る。
森口だ。
実のところ、彼女の言動に見え隠れする自意識は他の登場人物とよく似ている。
一生徒のメールの内容を嘲弄しながら暴き、後任の教師を操り、いじめをけしかけ、せせら笑う。
にも関わらず、その厭らしさが比較的目立たないのは彼女が教師であり、また被害者だからである。
Aに対しては何度も彼の低劣さに対して言及し、その愚かさを滔々と語り出す。
終盤の表情、言い回し、(作品としてではなく彼女が用意した)演出を見よ。
そこで思うのだ。
お前、もう復讐がどうとかじゃなくて、単に相手より上の自分を見せつけたいだけなんじゃね?
A・Bが自分の価値を高める為の自己実現から殺人を犯したのと全く同様に見える。
相手の計画を暴き、先回りし、より関係のない不特定多数の人間を巻き込む(殺す)やり方を、自らの手を汚さずに行い(これは詭弁だが)勝ち誇る。
それはもう復讐だとかなんとかじゃなくて、相手より上を行って罠に嵌めて快哉を叫んでいるガキと同じだ。
しかも自分は大人、相手は正真正銘のガキ。
もちろん
「それは演技でAに最大級の恥辱をあじあわせ、
後悔させる事が復讐なのだから、敢えて同レベルに下ったのだ」
という見方も出来る。
特に原作に存在しないファミレス前後のシーンで彼女の像は揺らぐだろう。
ただしその時点で無関係な他者を見下し、イジメをし向け、教師を操るようなやり口、つまり「自らは何もせず他人に頼り、他人を利用している」と得意気に語る姿(これはA・Bの行動傾向に近いことにも留意)から、彼女がどういう価値観を持っているかが垣間見える気がする。
もう一つは、例え挑発的態度が他者に見せる為、演技で始めた行為だとしても彼女にそういう部分がなければその発想に辿り着くだろうか。
また本当にそういう気持ちがないままに演技でしかなかったと言えるだろうか?
僕は怪しいと思う。
彼女が他人に見せる態度には、物凄く余裕があるのだ。
怒りとか憎しみみたいな印象を、基本的に受けない。
不条理の帳尻合わせという感じでもない。それならもっとドライになる。
ファミレス後のシーンは、確かにどういう意図なのかやや迷う。
復讐が不完全だった事自体に泣いたのか、完全な復讐をしなければならないと苦悩したのか。
いくらか想定出来るだろうが、少なくとも娘を思っている部分があるのは間違いない。
ただ叫んだ後に「くだらない」と吐き捨てているのもまた事実であり、それは娘のことではないだろうとは思う。
しかし彼女が娘のことを大事に思って、本人としてはその復讐という意識であっても、僕は(自らは手を汚さず)相手を出し抜いて嵌めてやったという裏の意識というか、本人の歪んだ喜び(復讐を果たした喜びではなく、相手が自分の思い通りになったという喜び)が透けて見える気がするのだ。
そこには爆弾で死んだであろう他の人の事とか、美月の事とか(原作ではイジメにあわせたことを一言だけ謝ってる)寺田の事とかは無い……いや、無い訳じゃないな。
A・Bをバカにする小道具として存在しているのだ。
だから、森口も自分が大好きで(復讐を切っ掛けに)ガキ程度に勝ち誇って自己実現を果たした、かなり痛い大人コドモに思えてしまう。単なる被害者ではなく、被害者という立場的な正当性を拠り所として(本来的な大人の教師という強さに加えて)相手よりも上の立場を築いたモノが加害者というオモチャを弄くり回して小馬鹿にする……そんな大人コドモに。
超前田さんが「偽善を全てはぎ取って……」とか言ってたけど、一つだけ有る。
復讐って概念自体が、正当化に過ぎないんだよ。
乱歩もビックリのエログロナンセンス犯罪實話!!!!!
犯罪モノが好きで、本屋行って気になってしまうとついつい買っちゃう。
そうなると必然並びが
とかになってしまって店員の目が気になったりする訳です(この三冊は実際同時チョイスでした)
あぁ俺犯罪者になったら絶対やり玉に挙げられるな……とか。
GTAもやってるしね!
で、買ったら読んでるハズなんだけど、最近は積ん読も多くて読書メーターを付けることすら煩わしい不精者としてはどれがどれだか把握していない。
そんななか「前読んだよな~」と思いながらも拾い上げたのが、この
『帝都東京 殺しの万華鏡』
如何にもなタイトル。
新潮関連では他にも『新潮45』に載った面白い犯罪實話ものがあってなかなか信用が置けるのです。
昭和初期の犯罪を(元)刑事自身が思い出しながら書くという形式で、実際当時の雑誌に載ったモノを拾い上げている模様。
そしてその個別事件ラインナップ
情痴の片腕事件
湯上がりの死美人
屋根裏の殺人鬼
女装の殺人魔
母殺し涙の裁判
津田沼の生首事件
旋風殺人事件
樽漬の生美人
どうです、タイトルだけでwktkしてくるでしょう。
湯上がりの死美人
樽漬の生美人
対句みたいになっているのが心憎い。
ていうか樽漬で生美人て何よ!? って感じです。
旋風殺人事件なんて本陣殺人事件よりもカッコイイ題名じゃない!
厨二っぽいけど。
まぁそんな訳で、どれもタイトルに違わず面白いんだけれども取り敢えずはですね、
乱歩を彷彿とさせる
屋根裏の殺人鬼
を紹介してみたいと思います。
犯行現場はイキナリ衝撃的で伏せ字化しています。
ただ妊婦だったことから恐らくは名古屋のアレ (グロ注意)とか最終話が放送禁止になったアレ みたいな状況だったんじゃないかと思われます。
この殺された女はすぎという有名な美人で、芸妓や料亭に於いて浮き名を流し、現在も囲われて不倫の身だった。ただ現在の愛人である竹本は、自身が刑務所入りしてしまっていたそうで、こうなってくると他の情愛絡みかという事で聞き込みが始まる。
そこで樋口という男が浮上、どうやらすぎと心中しようとした過去もあるらしく、更に殺される直前に痴話喧嘩をしていたという。
そこで樋口の愛人もろともしょっぴいて(まぁ戦前ですから)尋問したところ、どうやら小遣いをせびりに来た程度で犯人とは違うらしいと分かった。
しかし樋口が釈放される時、思い出したように言う事は……
「ひょっと今思い出したのですが、私がすぎの宅で小遣銭をもらって帰ろうとしたとき、あの家の天井の隅から妙な男が顔を出していたような気がしますが……。気の迷いかもしれませんが、たしか、あの隅っこの額の蔭から誰かが覗いていたようですよ」
(帝都東京 殺しの万華鏡 81頁)
な に そ れ こ わ い
もちろん刑事さんは
「そんな馬鹿なことがあるか」
(同)
と笑い飛ばしてしまったそうですが、これはむしろ普通のリアクション。
しかしながら更に奇妙な証言が
それはおすぎのお通夜の晩、親戚も身身寄りもないので、近所の人たちが寄り集まって、心ばかりのお通夜をしていると、真夜中ごろ、すぎの棺を置いてある真上の天井裏から突然、
「おすぎ許してくれ! 俺はお前が………心から好きだったんだ! 殺す気なんかなかったんだ……ああ苦しい! 俺の首を絞めてどうするんだ。ああ! 行こう。どうせ地獄へ墜ちるんだ。一緒に行こう、おすぎ……」
と、まるで地獄で悶え苦しむような薄気味の悪い声が、杜絶えがちに洩れてきたので、お通夜の人たちは、ゾッと冷水を浴びたように寒気を覚えながら、天井を見詰めたが、それきり何の異変とてなく、皆は気味が悪くて黙っていたとのことであった。
(同 82~83頁)
気味が悪いってレベルじゃねーぞ!!!!!
絶対怪談話だよそれ!!!
俺が近所の人だったら適当に理由付けて退散するね。
偉いわー、気合入ってるわー、恐るべし昭和初期のご近所付き合い。
流石に刑事さんも不審がって屋根裏に上がると、そこには布団や食器類が。
どうやらこの家の屋根裏には、マジで人が住んでいた模様。
で、調べを勧めるとすぎが甥と称していた梶川久太郎なる男じゃないかと判明したが、その後の捜査は遅々として進まない。
そんな中、連行したかっぱらいの少女がモルヒネ中毒で、中国人窃盗団と関係があったらしく、窃盗団をしょっぴきに阿片窟(!)へと赴いた。
そこへ居たのが久太郎とすぎという名の入れ墨を施した謎の美女(!)
「何か変わったことがあるの……」
「いや、俺の知った男と女に同じ名前の人間があるんだ」
「そうなの? 久太郎という人が妾のいい人なのよ。が、わたしはすぎというんじゃあないの……本当はみさという名前なんだが、あの人がすぎという名にしろというので、名前を変えちゃったの」
(同 88~89頁)
みささん……あんた完全に騙されてますよ。
ともあれ、そいつはきっと探している久太郎だという事でみさに詰問しようとしたところ、カーテンの蔭から脱兎の如く駆け出す人影が!
「うぬ、久太郎待て――」
(同 90頁)
と、時代劇調の台詞を吐く刑事!
『チェイサー』ばりの疾走劇は海によって遮られる。
久太郎は小舟に乗って逃げ出した、同じく船を漕ぐ刑事だが、久太郎は船頭を生業としていて、到底追いつけない。
これまでか……と諦めた時
「危ないぞ! 早く帰らなけりあ(原文ママ)、暴風雨が来るかも知れんぞ!」
(同 92頁)
とやって来たのがモーターボートに乗った水上署の顔馴染み、伊波巡査!
しめたとばかりに追い掛けるが、案の定の大時化で、岸に退避せざるを得ない。
しかしふと思う。
(ひょっとすると久太郎の奴も、ここに非難して来るのではないだろうか……)
(同 93頁)
予想は見事的中で、久太郎が上陸しようとしたところに捕縄を投げ、ドスを持った久太郎とのとっくみあい。
久太郎自力で捕縄を振り切り逃げ出すも、飛び込んだ海が大時化では流石に溺れてあえなく逮捕とあいなった。
逮捕した久太郎を尋問すると、すぎ殺しを自白した。
どうやら二人は幼馴染みで、永遠の愛を誓い合った仲だという。
しかしすぎの家は落ちぶれて、芸妓として売られてしまう羽目になる。
毎夜男を相手にしながらも、想うは久太郎のことばかり。
いつしか久太郎を天井裏に隠して、逢瀬を楽しむようになったという
(恐らく芸妓を抜けた後の事だろうと思われる)
樋口との心中騒ぎも、狂言だったらしい。
久太郎は、屋根裏に居ながらもすぎと愛人の様子を見ていた。
当初は身を切られる思いだったが、その内、愛人が身上食いつぶす程すぎに入れ込むので愉快になって、気にしなくなったそうな。
まぁ……なんか目覚めちゃったのかという感じがしないでもない。
しかし、すぎの最後の愛人竹本が彼女を囲って子供を孕ませた事で久太郎の心に疑念が生じ、更にかつての心中相手樋口が訪ねて来たことでそれが加速、すぎを問いつめた挙げ句口論となって殺害(絞殺)してしまったという。
その後に彼女の白い肌が気になって斬り下げたところ、件の状況になった……という話だが、それはまぁ色々と考えようもあるだろう。
ともあれ、徹頭徹尾怒濤の展開に加えて被害者と加害者の悲しい関係、そして信じられなくなったことによっての陰惨な破局。
犯罪實話だからこういう事を言うのは不謹慎かも分からんが、話としても「お前絶対脚色してるだろ」と思っちゃうほど面白かった。
他の話もメチャメチャ凄いのばっかり。
一つ一つ紹介していきたいが、長くなりすぎてしまうので当座はコレくらいにしておこう。
別にウチのでアフィらなくても良いから、興味が有れば是非とも買って頂きたい一冊。
- 帝都東京 殺しの万華鏡―昭和モダンノンフィクション 事件編 (新潮文庫)/著者不明
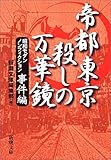
- ¥500
- Amazon.co.jp
犯罪モノが好きで、本屋行って気になってしまうとついつい買っちゃう。
そうなると必然並びが
- でっちあげ―福岡「殺人教師」事件の真相 (新潮文庫)/福田 ますみ

- ¥540
- Amazon.co.jp
- 隣の家の少女 (扶桑社ミステリー)/ジャック ケッチャム

- ¥720
- Amazon.co.jp
- 少年リンチ殺人―ムカついたから、やっただけ―《増補改訂版》 (新潮文庫)/日垣 隆

- ¥540
- Amazon.co.jp
とかになってしまって店員の目が気になったりする訳です(この三冊は実際同時チョイスでした)
あぁ俺犯罪者になったら絶対やり玉に挙げられるな……とか。
GTAもやってるしね!
で、買ったら読んでるハズなんだけど、最近は積ん読も多くて読書メーターを付けることすら煩わしい不精者としてはどれがどれだか把握していない。
そんななか「前読んだよな~」と思いながらも拾い上げたのが、この
『帝都東京 殺しの万華鏡』
如何にもなタイトル。
新潮関連では他にも『新潮45』に載った面白い犯罪實話ものがあってなかなか信用が置けるのです。
昭和初期の犯罪を(元)刑事自身が思い出しながら書くという形式で、実際当時の雑誌に載ったモノを拾い上げている模様。
そしてその個別事件ラインナップ
情痴の片腕事件
湯上がりの死美人
屋根裏の殺人鬼
女装の殺人魔
母殺し涙の裁判
津田沼の生首事件
旋風殺人事件
樽漬の生美人
どうです、タイトルだけでwktkしてくるでしょう。
湯上がりの死美人
樽漬の生美人
対句みたいになっているのが心憎い。
ていうか樽漬で生美人て何よ!? って感じです。
旋風殺人事件なんて本陣殺人事件よりもカッコイイ題名じゃない!
厨二っぽいけど。
まぁそんな訳で、どれもタイトルに違わず面白いんだけれども取り敢えずはですね、
乱歩を彷彿とさせる
屋根裏の殺人鬼
を紹介してみたいと思います。
犯行現場はイキナリ衝撃的で伏せ字化しています。
ただ妊婦だったことから恐らくは名古屋のアレ (グロ注意)とか最終話が放送禁止になったアレ みたいな状況だったんじゃないかと思われます。
この殺された女はすぎという有名な美人で、芸妓や料亭に於いて浮き名を流し、現在も囲われて不倫の身だった。ただ現在の愛人である竹本は、自身が刑務所入りしてしまっていたそうで、こうなってくると他の情愛絡みかという事で聞き込みが始まる。
そこで樋口という男が浮上、どうやらすぎと心中しようとした過去もあるらしく、更に殺される直前に痴話喧嘩をしていたという。
そこで樋口の愛人もろともしょっぴいて(まぁ戦前ですから)尋問したところ、どうやら小遣いをせびりに来た程度で犯人とは違うらしいと分かった。
しかし樋口が釈放される時、思い出したように言う事は……
「ひょっと今思い出したのですが、私がすぎの宅で小遣銭をもらって帰ろうとしたとき、あの家の天井の隅から妙な男が顔を出していたような気がしますが……。気の迷いかもしれませんが、たしか、あの隅っこの額の蔭から誰かが覗いていたようですよ」
(帝都東京 殺しの万華鏡 81頁)
な に そ れ こ わ い
もちろん刑事さんは
「そんな馬鹿なことがあるか」
(同)
と笑い飛ばしてしまったそうですが、これはむしろ普通のリアクション。
しかしながら更に奇妙な証言が
それはおすぎのお通夜の晩、親戚も身身寄りもないので、近所の人たちが寄り集まって、心ばかりのお通夜をしていると、真夜中ごろ、すぎの棺を置いてある真上の天井裏から突然、
「おすぎ許してくれ! 俺はお前が………心から好きだったんだ! 殺す気なんかなかったんだ……ああ苦しい! 俺の首を絞めてどうするんだ。ああ! 行こう。どうせ地獄へ墜ちるんだ。一緒に行こう、おすぎ……」
と、まるで地獄で悶え苦しむような薄気味の悪い声が、杜絶えがちに洩れてきたので、お通夜の人たちは、ゾッと冷水を浴びたように寒気を覚えながら、天井を見詰めたが、それきり何の異変とてなく、皆は気味が悪くて黙っていたとのことであった。
(同 82~83頁)
気味が悪いってレベルじゃねーぞ!!!!!
絶対怪談話だよそれ!!!
俺が近所の人だったら適当に理由付けて退散するね。
偉いわー、気合入ってるわー、恐るべし昭和初期のご近所付き合い。
流石に刑事さんも不審がって屋根裏に上がると、そこには布団や食器類が。
どうやらこの家の屋根裏には、マジで人が住んでいた模様。
で、調べを勧めるとすぎが甥と称していた梶川久太郎なる男じゃないかと判明したが、その後の捜査は遅々として進まない。
そんな中、連行したかっぱらいの少女がモルヒネ中毒で、中国人窃盗団と関係があったらしく、窃盗団をしょっぴきに阿片窟(!)へと赴いた。
そこへ居たのが久太郎とすぎという名の入れ墨を施した謎の美女(!)
「何か変わったことがあるの……」
「いや、俺の知った男と女に同じ名前の人間があるんだ」
「そうなの? 久太郎という人が妾のいい人なのよ。が、わたしはすぎというんじゃあないの……本当はみさという名前なんだが、あの人がすぎという名にしろというので、名前を変えちゃったの」
(同 88~89頁)
みささん……あんた完全に騙されてますよ。
ともあれ、そいつはきっと探している久太郎だという事でみさに詰問しようとしたところ、カーテンの蔭から脱兎の如く駆け出す人影が!
「うぬ、久太郎待て――」
(同 90頁)
と、時代劇調の台詞を吐く刑事!
『チェイサー』ばりの疾走劇は海によって遮られる。
久太郎は小舟に乗って逃げ出した、同じく船を漕ぐ刑事だが、久太郎は船頭を生業としていて、到底追いつけない。
これまでか……と諦めた時
「危ないぞ! 早く帰らなけりあ(原文ママ)、暴風雨が来るかも知れんぞ!」
(同 92頁)
とやって来たのがモーターボートに乗った水上署の顔馴染み、伊波巡査!
しめたとばかりに追い掛けるが、案の定の大時化で、岸に退避せざるを得ない。
しかしふと思う。
(ひょっとすると久太郎の奴も、ここに非難して来るのではないだろうか……)
(同 93頁)
予想は見事的中で、久太郎が上陸しようとしたところに捕縄を投げ、ドスを持った久太郎とのとっくみあい。
久太郎自力で捕縄を振り切り逃げ出すも、飛び込んだ海が大時化では流石に溺れてあえなく逮捕とあいなった。
逮捕した久太郎を尋問すると、すぎ殺しを自白した。
どうやら二人は幼馴染みで、永遠の愛を誓い合った仲だという。
しかしすぎの家は落ちぶれて、芸妓として売られてしまう羽目になる。
毎夜男を相手にしながらも、想うは久太郎のことばかり。
いつしか久太郎を天井裏に隠して、逢瀬を楽しむようになったという
(恐らく芸妓を抜けた後の事だろうと思われる)
樋口との心中騒ぎも、狂言だったらしい。
久太郎は、屋根裏に居ながらもすぎと愛人の様子を見ていた。
当初は身を切られる思いだったが、その内、愛人が身上食いつぶす程すぎに入れ込むので愉快になって、気にしなくなったそうな。
まぁ……なんか目覚めちゃったのかという感じがしないでもない。
しかし、すぎの最後の愛人竹本が彼女を囲って子供を孕ませた事で久太郎の心に疑念が生じ、更にかつての心中相手樋口が訪ねて来たことでそれが加速、すぎを問いつめた挙げ句口論となって殺害(絞殺)してしまったという。
その後に彼女の白い肌が気になって斬り下げたところ、件の状況になった……という話だが、それはまぁ色々と考えようもあるだろう。
ともあれ、徹頭徹尾怒濤の展開に加えて被害者と加害者の悲しい関係、そして信じられなくなったことによっての陰惨な破局。
犯罪實話だからこういう事を言うのは不謹慎かも分からんが、話としても「お前絶対脚色してるだろ」と思っちゃうほど面白かった。
他の話もメチャメチャ凄いのばっかり。
一つ一つ紹介していきたいが、長くなりすぎてしまうので当座はコレくらいにしておこう。
別にウチのでアフィらなくても良いから、興味が有れば是非とも買って頂きたい一冊。
全部むきだし
去年の邦画の中でやたら評価が高かった本作。
3時間40分(『涼宮ハルヒの消失』より1時間長い!)という長さを苦にしないぐらいの作品でした。
冒頭に出てくるテロップは「この作品は実話を元にしています」。
けどこんなん、映画観てる人間にとっては、これは話にハクを付ける常套句みたいなもの。
しかしてそのストーリーは……
父親に懺悔を強制された結果、盗撮魔になった少年が、
愛する義理の妹を取り戻す為に新興宗教団体に戦いを挑む!
というもの。
ね~よ!!!!!
……だが恐ろしいことに園子温監督の知人である盗撮界のカリスマが、妹を新興宗教から救い出したことがアイデアの切っ掛けになっているそうな。
なんつーか、この設定な時点で大半のフィクションは膝を屈する気がするわ。
もちろん、色んな部分は映画的な改変というか、面白さが増すような形になっている。
まず冒頭1時間が主人公ユウが盗撮魔へ変貌するまでの仮定を描いていて、これがまた笑える。
母親が急逝、父親は神父になるも女が出来て、すぐ逃げられて家庭不和。
父親は自身の負い目から息子にも懺悔を強要する……と書くと非常に陰惨な話なのだけれども、これを大まじめにやっているから物凄く面白い。
特にユウが盗撮を懺悔して父親に殴られた時の凄く嬉しそうな表情といったらない。
もちろん、ただのマゾではなく、ネグレクトに近い状態になっていた父親が暴力という形でも自分に関心を持ってくれることが嬉しかったからだろう。
そしてコイケとヨーコとの出会いから物語は本当に始まる。
本作はタランティーノ映画みたいに章立てられていたりする。
ユウが一章でコイケは二章、メインヒロインのヨーコは三章で語られる。
非常にコメディタッチの一章とは打って変わって、二章は笑いを取り入れつつもグロテスクさを強調した造りになっている。キリスト者の父親から体つきだけで淫乱呼ばわりされ折檻を受けるコイケは、ユウの鏡だ。
しかし彼女の場合は、結果としてそれを超克出来てしまう。
ただ、恐らくは心と引き替えに。
(ここは実は超克出来ていない……とか解釈の分かれるところかも。コイケ関連は一番考察が難しい)
ヨーコも父親からのセクハラに近い行いに耐えてきた為、男嫌いになって男性に暴力を振るうようになる。
まぁなんか今期アニメでそういう話があったような気もするのだけれど、それは置いておくとして要するにこの三人は父親との歪んだ関係性の中で犯罪めいた志向を持つようになってしまった三面鏡みたいなものになっている。
で、ヨーコの元にきたのがカオリさん、ユウの親父のところから逃げ出してきたあの女。
ところがヨーコとウマが合い、彼女を連れたまま親父のところへ出戻りしようとする。
その矢先ユウが女装した「姉御サソリ」にヨーコが惚れてしまい、ユウもヨーコに「聖母マリア」を見出す。
この交錯した関係は、更にカオリと親父がよりを戻し、ヨーコがユウの学校に転校してくることで複雑になる。
ユウはヨーコが好き。
ヨーコはサソリ(ユウ)が好きだけど男が嫌いなのでユウは大嫌い。
カオリさんがヨーコを連れてオヤジの元へ来たので、ユウとヨーコは義理の兄妹になる。
ヨーコは嫌がるが、サソリ(ユウ)に電話を掛けて助言をもらい、ユウと仲良くなろうと努力する。
こんな感じ。
絶対コレどっかのアニメで観た事あるな。
こんなごっちゃごちゃになってはいなかったと思うが。
しかし、この微妙な関係はコイケがサソリを騙ってヨーコを陥落させることで崩壊する。
更にユウの盗撮癖も暴露し、彼の居場所は盗撮仲間の所にしかなくなる。
コイケに言われるままAV業界(男優ではなく盗撮カメラマン)で仕事をしつつもユウはヨーコを取り戻そうとする。
……ってホント分かり難い話だなwwww
いや、この分かりにくさが面白い部分ではあるのだけれども。
ともあれ、本作のポイントは何と言っても「愛」だ。
主役三人は父親の歪んだ愛情によって人生を狂わされ、カオリはユウの親父を押し倒したり車をぶち当てたりしながら愛を叫ぶ。
コイケはユウに自身を重ね合わせて偏執的で歪んだ愛情を抱く。
そしてユウは母に誓った聖母マリアをヨーコに見出して救おうとする。
「愛のむきだし」という言葉が明確に使われるのはカオリに関してだが、コイケもユウも、そして最後にはヨーコも愛をむきだしにして相手にぶち当たる。
「愛」とは色々な場面でよく使われる言葉だが、どのようなものか自覚的な人はあまり多くないと思う。
それは社会性に覆われて常識という殻に押し込められているからではないか。
ところがこの映画では「むきだし」なのだ。
だからこそ狂的であり破壊的であり、時には社会の倫理や人間そのものすら薙ぎ倒してしまうほどの強力なものになりうる。
そして同時に、破滅からの救済にもなれる。
たといわたしが、人々の言葉や御使(みつかい)たちの言葉を語っても、もし愛がなければ、わたしは、やかましい鐘や騒がしい鐃鉢 (にょうはち)と同じである。
たといまた、わたしに預言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また、山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ、わたしは無に等しい。
たといまた、わたしが自分の全財産を人に施しても、また、自分のからだを焼かれるために渡しても、もし愛がなければ、 いっさいは無益である。
愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇らない。
不作法をしない。自分の利益を求めない、いらだたない、恨みをいだかない。
不義を喜ばないで真理を喜ぶ。
そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。
愛はいつまでも絶えることがない。 しかし、預言はすたれ、異言はやみ、知識はすたれるであろう。
なぜなら、わたしたちの知るところは一部分であり、預言するところも一部分にすぎない。
全きものが来る時には、部分的なものはすたれる。
わたしたちが幼な子であった時には、幼な子らしく語り、幼な子らしく感じ、また、幼な子らしく考えていた。しかし、おとなとなった今は、幼な子らしいことを捨ててしまった。
わたしたちは、今は、鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には、顔と顔とを合わせて、見るであろ う。わたしの知るところは、今は一部分にすぎない。しかしその時には、わたしが完全に知られているように、完全に知るであろう
このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。
出典はこちら 。
訳は違っているだろうから、言葉遣いは異なる可能性アリ。
これは劇中でユウにヨーコが語る「コリント人への第一の手紙」である。
この時点で、ヨーコは完全に新興宗教に捕らわれており、無理矢理ユウが連れ出して洗脳を解こうとしてもまるで聞かない。あの新興宗教じゃなければ仏教でもキリスト教でも良い、と語るユウに「あんたは何も(聖書も)知らない」として引用する聖書の一節だ。
確かにここで語るユウの宗教観は、やや偏っているようにも見えなくもない(もちろん入会の経緯がコイケの仕業と知っている部分はあるにせよ)
だからヨーコの指摘は必ずしも大きく間違っている訳ではないのだが、同時に此処を引用してしまった事自体を彼女は省みては居ない。
ユウのヨーコに対する行為、それはこの引用の文言そのものであるということを。
彼はヨーコの為に忍び、信じ、望み、耐えた。
そしてこの時のヨーコに信仰はあっても愛が無いということを。
(サソリの事は好きだが、サソリ=コイケだと思っていて本当の相手を知らない)
いつまでも存続するものは、信仰と 希望と愛と、この三つである。
このうちで最も大いなるものは、愛である
まさに此くの如く、信仰を超える物は愛なのだ。
少なくとも、この映画の中に於いては。
寛容という部分については監督自身が「寛容と言っているのに不寛容になってしまう部分が面白い」というような事を語っているので愛情論として別のエントリで語るとして、映画の中で重要なのはユウの行動動機は愛に他ならなかったということだ。
そして一見ユウを苦しめるだけの存在であったかのように見えるコイケも実に奇妙だ。
ユウの全てを奪い、彼自身を誘惑し、彼の心を壊して、自害。
正直エンターテイメントとしてはユウに罰される感じでも良かったのではないかと思うのだが、やはりこの辺りは色々と何かありそうだぞ……という気はする。
確証はないが。
幾つか考えられる仮説として、やはりコイケはユウに強い思い入れ(恐らくはこれも愛と言うべきだろう)を抱き、自身と同じようになって欲しかった……と考えるのが一番スタンダードかなぁと。
そして壊れてしまった姿を見るに嬉しさと同時に悲しさが去来した、という感じだろうか。
またどういう状態であってもユウの愛が常にヨーコへ向かっているというのもあったやもしれん。
この辺りは幾らでも考察出来そうだが、上記二つが一番妥当かなぁと。
そして心を壊したユウにみせるヨーコの「むきだし」
非常にバカバカしくも見えるが、あの愛に対するこの行動だからこそ感動的に映る。
だからやっぱり、この映画は愛の映画だ。
どっかの感想で
「愛なんて最後にちょっぴり出てるだけでみんな騙されてる」
という意見があったが、そりゃ
登場人物のメチャクチャで破壊的な行為の数々が何に由来しているか気付いてないだけか、
もしくは「愛」というのを普通の恋愛映画のそれと同一視しているか
ってだけじゃねーの?
「愛」の衣は厚いものだ、それ自体を自覚していないと取り払うどころか気付くことすら難しいかもしれない。
キリスト教の愛というのも、必ずしもむきだしとは限らないと思うが、この映画の「愛」に一脈通じるモノはある。
だからヨーコはキリストに傾倒したし、ユウも自らのマリアに生涯を捧げた。
「愛」はヤバイ、マジヤバイ。
だから僕らは「愛」に常識とか社会性とかで衣を作り、その姿を隠す。
衣を剥ぐと、人は愛のままに時には社会を脅かし、時には人を救ってしまう。
でもきっと、それが「むきだし」ってことなんだろう。
- 愛のむきだし [DVD]/西島隆弘,満島ひかり,安藤サクラ

- ¥5,460
- Amazon.co.jp
去年の邦画の中でやたら評価が高かった本作。
3時間40分(『涼宮ハルヒの消失』より1時間長い!)という長さを苦にしないぐらいの作品でした。
冒頭に出てくるテロップは「この作品は実話を元にしています」。
けどこんなん、映画観てる人間にとっては、これは話にハクを付ける常套句みたいなもの。
しかしてそのストーリーは……
父親に懺悔を強制された結果、盗撮魔になった少年が、
愛する義理の妹を取り戻す為に新興宗教団体に戦いを挑む!
というもの。
ね~よ!!!!!
……だが恐ろしいことに園子温監督の知人である盗撮界のカリスマが、妹を新興宗教から救い出したことがアイデアの切っ掛けになっているそうな。
なんつーか、この設定な時点で大半のフィクションは膝を屈する気がするわ。
もちろん、色んな部分は映画的な改変というか、面白さが増すような形になっている。
まず冒頭1時間が主人公ユウが盗撮魔へ変貌するまでの仮定を描いていて、これがまた笑える。
母親が急逝、父親は神父になるも女が出来て、すぐ逃げられて家庭不和。
父親は自身の負い目から息子にも懺悔を強要する……と書くと非常に陰惨な話なのだけれども、これを大まじめにやっているから物凄く面白い。
特にユウが盗撮を懺悔して父親に殴られた時の凄く嬉しそうな表情といったらない。
もちろん、ただのマゾではなく、ネグレクトに近い状態になっていた父親が暴力という形でも自分に関心を持ってくれることが嬉しかったからだろう。
そしてコイケとヨーコとの出会いから物語は本当に始まる。
本作はタランティーノ映画みたいに章立てられていたりする。
ユウが一章でコイケは二章、メインヒロインのヨーコは三章で語られる。
非常にコメディタッチの一章とは打って変わって、二章は笑いを取り入れつつもグロテスクさを強調した造りになっている。キリスト者の父親から体つきだけで淫乱呼ばわりされ折檻を受けるコイケは、ユウの鏡だ。
しかし彼女の場合は、結果としてそれを超克出来てしまう。
ただ、恐らくは心と引き替えに。
(ここは実は超克出来ていない……とか解釈の分かれるところかも。コイケ関連は一番考察が難しい)
ヨーコも父親からのセクハラに近い行いに耐えてきた為、男嫌いになって男性に暴力を振るうようになる。
まぁなんか今期アニメでそういう話があったような気もするのだけれど、それは置いておくとして要するにこの三人は父親との歪んだ関係性の中で犯罪めいた志向を持つようになってしまった三面鏡みたいなものになっている。
で、ヨーコの元にきたのがカオリさん、ユウの親父のところから逃げ出してきたあの女。
ところがヨーコとウマが合い、彼女を連れたまま親父のところへ出戻りしようとする。
その矢先ユウが女装した「姉御サソリ」にヨーコが惚れてしまい、ユウもヨーコに「聖母マリア」を見出す。
この交錯した関係は、更にカオリと親父がよりを戻し、ヨーコがユウの学校に転校してくることで複雑になる。
ユウはヨーコが好き。
ヨーコはサソリ(ユウ)が好きだけど男が嫌いなのでユウは大嫌い。
カオリさんがヨーコを連れてオヤジの元へ来たので、ユウとヨーコは義理の兄妹になる。
ヨーコは嫌がるが、サソリ(ユウ)に電話を掛けて助言をもらい、ユウと仲良くなろうと努力する。
こんな感じ。
絶対コレどっかのアニメで観た事あるな。
こんなごっちゃごちゃになってはいなかったと思うが。
しかし、この微妙な関係はコイケがサソリを騙ってヨーコを陥落させることで崩壊する。
更にユウの盗撮癖も暴露し、彼の居場所は盗撮仲間の所にしかなくなる。
コイケに言われるままAV業界(男優ではなく盗撮カメラマン)で仕事をしつつもユウはヨーコを取り戻そうとする。
……ってホント分かり難い話だなwwww
いや、この分かりにくさが面白い部分ではあるのだけれども。
ともあれ、本作のポイントは何と言っても「愛」だ。
主役三人は父親の歪んだ愛情によって人生を狂わされ、カオリはユウの親父を押し倒したり車をぶち当てたりしながら愛を叫ぶ。
コイケはユウに自身を重ね合わせて偏執的で歪んだ愛情を抱く。
そしてユウは母に誓った聖母マリアをヨーコに見出して救おうとする。
「愛のむきだし」という言葉が明確に使われるのはカオリに関してだが、コイケもユウも、そして最後にはヨーコも愛をむきだしにして相手にぶち当たる。
「愛」とは色々な場面でよく使われる言葉だが、どのようなものか自覚的な人はあまり多くないと思う。
それは社会性に覆われて常識という殻に押し込められているからではないか。
ところがこの映画では「むきだし」なのだ。
だからこそ狂的であり破壊的であり、時には社会の倫理や人間そのものすら薙ぎ倒してしまうほどの強力なものになりうる。
そして同時に、破滅からの救済にもなれる。
たといわたしが、人々の言葉や御使(みつかい)たちの言葉を語っても、もし愛がなければ、わたしは、やかましい鐘や騒がしい鐃鉢 (にょうはち)と同じである。
たといまた、わたしに預言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また、山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ、わたしは無に等しい。
たといまた、わたしが自分の全財産を人に施しても、また、自分のからだを焼かれるために渡しても、もし愛がなければ、 いっさいは無益である。
愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇らない。
不作法をしない。自分の利益を求めない、いらだたない、恨みをいだかない。
不義を喜ばないで真理を喜ぶ。
そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。
愛はいつまでも絶えることがない。 しかし、預言はすたれ、異言はやみ、知識はすたれるであろう。
なぜなら、わたしたちの知るところは一部分であり、預言するところも一部分にすぎない。
全きものが来る時には、部分的なものはすたれる。
わたしたちが幼な子であった時には、幼な子らしく語り、幼な子らしく感じ、また、幼な子らしく考えていた。しかし、おとなとなった今は、幼な子らしいことを捨ててしまった。
わたしたちは、今は、鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には、顔と顔とを合わせて、見るであろ う。わたしの知るところは、今は一部分にすぎない。しかしその時には、わたしが完全に知られているように、完全に知るであろう
このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。
出典はこちら 。
訳は違っているだろうから、言葉遣いは異なる可能性アリ。
これは劇中でユウにヨーコが語る「コリント人への第一の手紙」である。
この時点で、ヨーコは完全に新興宗教に捕らわれており、無理矢理ユウが連れ出して洗脳を解こうとしてもまるで聞かない。あの新興宗教じゃなければ仏教でもキリスト教でも良い、と語るユウに「あんたは何も(聖書も)知らない」として引用する聖書の一節だ。
確かにここで語るユウの宗教観は、やや偏っているようにも見えなくもない(もちろん入会の経緯がコイケの仕業と知っている部分はあるにせよ)
だからヨーコの指摘は必ずしも大きく間違っている訳ではないのだが、同時に此処を引用してしまった事自体を彼女は省みては居ない。
ユウのヨーコに対する行為、それはこの引用の文言そのものであるということを。
彼はヨーコの為に忍び、信じ、望み、耐えた。
そしてこの時のヨーコに信仰はあっても愛が無いということを。
(サソリの事は好きだが、サソリ=コイケだと思っていて本当の相手を知らない)
いつまでも存続するものは、信仰と 希望と愛と、この三つである。
このうちで最も大いなるものは、愛である
まさに此くの如く、信仰を超える物は愛なのだ。
少なくとも、この映画の中に於いては。
寛容という部分については監督自身が「寛容と言っているのに不寛容になってしまう部分が面白い」というような事を語っているので愛情論として別のエントリで語るとして、映画の中で重要なのはユウの行動動機は愛に他ならなかったということだ。
そして一見ユウを苦しめるだけの存在であったかのように見えるコイケも実に奇妙だ。
ユウの全てを奪い、彼自身を誘惑し、彼の心を壊して、自害。
正直エンターテイメントとしてはユウに罰される感じでも良かったのではないかと思うのだが、やはりこの辺りは色々と何かありそうだぞ……という気はする。
確証はないが。
幾つか考えられる仮説として、やはりコイケはユウに強い思い入れ(恐らくはこれも愛と言うべきだろう)を抱き、自身と同じようになって欲しかった……と考えるのが一番スタンダードかなぁと。
そして壊れてしまった姿を見るに嬉しさと同時に悲しさが去来した、という感じだろうか。
またどういう状態であってもユウの愛が常にヨーコへ向かっているというのもあったやもしれん。
この辺りは幾らでも考察出来そうだが、上記二つが一番妥当かなぁと。
そして心を壊したユウにみせるヨーコの「むきだし」
非常にバカバカしくも見えるが、あの愛に対するこの行動だからこそ感動的に映る。
だからやっぱり、この映画は愛の映画だ。
どっかの感想で
「愛なんて最後にちょっぴり出てるだけでみんな騙されてる」
という意見があったが、そりゃ
登場人物のメチャクチャで破壊的な行為の数々が何に由来しているか気付いてないだけか、
もしくは「愛」というのを普通の恋愛映画のそれと同一視しているか
ってだけじゃねーの?
「愛」の衣は厚いものだ、それ自体を自覚していないと取り払うどころか気付くことすら難しいかもしれない。
キリスト教の愛というのも、必ずしもむきだしとは限らないと思うが、この映画の「愛」に一脈通じるモノはある。
だからヨーコはキリストに傾倒したし、ユウも自らのマリアに生涯を捧げた。
「愛」はヤバイ、マジヤバイ。
だから僕らは「愛」に常識とか社会性とかで衣を作り、その姿を隠す。
衣を剥ぐと、人は愛のままに時には社会を脅かし、時には人を救ってしまう。
でもきっと、それが「むきだし」ってことなんだろう。