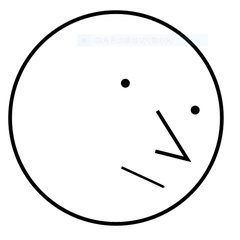『小隊』では、ごく普通の青年が、初めての戦闘を経験し、一端(いっぱし)の職業軍人になる姿を描いている。
この小説を読み始めて、そして半ばまで読み進めて、思った。わからない、のである。最後まで何とか読み終わった。それでも、何が書いてあったのかわからない。
細かい描写が、たくさん並んでいた。で、それが何か、である。
安達3尉は陸上自衛隊の小隊長をしている。北海道に侵攻してくるロシア軍を迎え撃つ、という話である。
まず描かれるものは避難誘導の現場である。一般人のいるところでは、心おきなく戦えない。予想される戦場から人払いをしておく。自衛隊員が人払いに奔走する。凡そピンとこないが、誰かがやらなければならない仕事ではある。
敵の来襲が明日あるかもしれない、とのことで、急遽作戦会議となる。ロシアの戦車隊を迎え撃つための装備はあきらかに不足しているが、ただひたすら、あらゆる確認と手続きが進められる。あたかも、明日の地域の運動会の、機材の、メンバーの、手順のチェックであるかのように細かい。
小隊の陣地でも命令下達、点検、報告と、やることはとめどがない。ここまでと思うような細かな記述が続く。
戦闘が始まる。そして一人の敵を射殺する。
戦闘の描写は凄惨である。部下が殺傷された場面など、思わず目を背けたくなるような描写も多い。
結局、自衛隊はロシア軍の侵攻を止められず、散り散りに退却する。
軍人というものが、職業の選択肢として、ごく普通に存在する。何か信じられない思いがする。若かりし頃に受けた平和教育とやらの影響だろうか。だが、今は、多くの人にとって、そんな意見など眼中に無いだろう。軍人も職業であると認めると、この小説が、安達3尉の成長を描いたものとして納得できるようになった。
安達3尉の戦闘前の姿はいささかこころもとない状態だった。定年も近い小熊曹長が、実際には小隊を取り仕切っている。
<
…とりあえず今もこうしてぎりぎりのところで使い物になっている自分がいるのは小熊のおかげだ、と安達は思っている。
小隊長として不適切な行動があれば、「小隊長ちょっといいですか」、と補給庫とか更衣室とか二人きりの空間に呼び出され焼きを入れられ、あるいは居酒屋で他の隊員がわいわいと騒いでいる中、二人だけはそこからわずかに距離を置いて組織のイロハをこっそりと教えてくれる。…
>(23頁)
戦闘の最中、安達3尉は部下に問いかけつつ思う。
<自分を支えるのは不撓不屈(ふとうふくつ)の精神でも高邁(こうまい)な使命感でも崇高な愛国心でもなく、ただ一個の義務だけだった。3等陸尉という階級に付随する、無数の手続きが、総じて一つの義務となり、自分を支えている。安達は、もう勘弁してくれ、と強く思っていたが、身体は常に義務に忠実で、今も指揮下部隊を掌握し、適時適切な状況把握に努めようとしている。
>(87-88頁)
自分でも一人の敵を射殺する等の最初の戦闘が収まった後、安達小隊長は、自陣地に各分隊長を集める。
<
… 交通壕に降り立つ。視線が注がれる。
「楽にしてくれ」
安達は、言ってから妙な気分になった。古参の陸曹を前に、物おじしなくなっている自分を不意に見つけたのだ。…
>(105頁)
ごく普通の人が、仕事を覚え、職業人として自信を持ち、それぞれの場面で適切に振舞えるようになった。そういうことである。
これらの場面の意味が理解できると、その前後の克明な描写が戦争を描いたものとして、すなおに理解できた。
戦争とは、戦闘とはこのようなものかと思う。事前の徹底した準備こそが要であり、自衛隊の敗退は、隊員たちが作戦会議の場で彼我の戦力比較をした時予想されていた。それでも、多くの隊員たちは、できる限りのことをした。
※短編集『小隊』は、『小隊』、『戦場のレビヤタン』、『市街戦』の3編を収録。