民間調査会社によると、2014年の企業倒産件数が1万件を割り込んだようです。この報道だけを見れば、景気が回復してきたと思う方もいるかもしれません。しかし皆さんの実感はどうでしょうか?街を見渡せば、商店街は1階のテナントも空いているところが目立つし、馴染みの飲食店も閉店の予定で寂しいと感じている方が多いと思います。
実は、倒産件数と廃業件数の合計は、1年間で4万件もあり、そのうち廃業件数は3万件で、倒産件数1万件の3倍もあります。この状況では、倒産件数が減っていると喜ぶことはできません。
では、どうして倒産件数が減っているにもかかわらず、廃業件数は増え続けているのか、企業経営者の視点で考えてみたいと思います。
まず、倒産件数が減っている背景を考えてみると、リーマンショックの後、モラトリアム法ができたことがあります。正確には「中小企業金融円滑化法」と言います。これがどういうものか簡単に説明すると、「銀行から借りているお金を一時的に返さなくてもよい」という法律です。リーマンショックという著しい経済の低下、自分の失敗でなく外的要因による業績の悪化、という背景を考えれば、企業を救うという点でこの法律は、機能していたと思います。実際、返済猶予で命拾いしたという企業は少なくないと思います。もとはと言えば、銀行だって一時的な公的資金投入で業績を回復した経緯があります。しかし、こんなことが未来永劫ずっと許されるわけがありません。返済猶予してもらっている企業が返済を再開することは、簡単なことではありません。そこで銀行は、任意ではありますが返済猶予や返済条件の変更を認めています。これらの理由から、本来倒産する企業が倒産しないでいる状態が生まれ、倒産件数が減っています。
一方、廃業が増えている背景を考えてみると、最も多い廃業理由は後継者不足です。経営者の高齢化に伴い、後継者を探してみたけれど、適当な人材が見当たらない。後継者であるはずの身内は、早々と大企業に勤めてサラリーマンをしている。そんな息子たちや次世代に迷惑だけはかけたくない。そんな思いから、これ以上借金が増えないように、廃業という苦渋の決断をする経営者が後を絶たないということです。
日本の企業数は、99%が中小企業です。従業者数で見ると、70%の人たちが中小企業に勤めています。2000年以降、銀行の合併、大企業の合併や買収、市町村の合併、学校の合併など、あらゆる業界で管理コストの効率化を図る行動が見られています。これは、何もしないで企業や行政がずっと維持できればいいけれど、何とかしないと将来大変なことになってしまうという判断から、管理コストの効率化が進んでいます。そのような現状から中小企業の状況を見ると、99%が中小企業という状態は、何か問題があるのかもしれません。日本人の性質から、慣れ親しんだものを変えるということは、とても大変で寂しいことかもしれません。しかし日本に現存する企業数の30%しか法人税を払っていない現状を見れば、この状態は異常です。
私が言いたいのは、中小企業が多すぎると言いたいのではないのです。誤解しないでください。最も言いたいことは、日本の企業で利益を出すことは、とても難しいということです。ある政治家が、「企業が利益を出さないのは経営者の能力の問題だ」と発言して、大騒ぎになりましたね。企業が利益を出せないのは、挑戦する者が正しい方法で結果を出したとしても、報われる可能性は低いということです。これは、今までの社会を創り上げた政治に問題があるということです。その証拠に、利口な経営者は、どの国が、どの都市がビジネスをしやすいかを考えて、企業の拠点を探しています。世界銀行の資料によると、起業のしやすさを総合的に評価した起業環境の順位は、シンガポールが3位、香港が5位、アメリカが20位、日本はなんと120位となっています。この結果からも、企業が利益を出せない理由は、経営者の能力と関係ないことがわかります。日本の企業を取り巻く環境は、法人税や基礎的負担費が重いだけでなく、そもそも起業や開業しようとしても、スタートから高いハードルが用意され、難しいということです。
これからの日本は、このままの状態が続けば、雇用に貢献している企業が無くなってしまいます。挑戦者には平等に機会を与え、正しい方法で結果を出せば報われる社会ができることを希望しています。そのような社会環境が整うように、私も努力したいと思います。
円安が長期化していることによって、パナソニック、キャノン、ホンダなどの日本企業が生産の国内回帰をしています。超円高のもとで海外に移転していった生産工場が日本国内に戻ってくることは、基本的に良いことです。たくさんの雇用が失われ、地域経済が疲弊し、中小企業が苦しんでいることは、徐々に改善されると予測されます。
しかし、本当にそうでしょうか?今の日本企業の動きを見ていると、国内工場は稼働率を上げることや残業だけで対応しています。正社員の雇用を増やしたり、過去に閉鎖した工場を復活させたり、工場新設に積極的な企業は、多くありません。このような対応では、為替が円高になった瞬間に製造業の状況は、空洞化に戻ります。
また価格については、日本へ戻ってきた製品の価格は、中国で生産していた時と同じことが多いです。これでは、日本と海外の人件費の差が縮まってきたとはいえ、中国価格で日本企業が利益を生み出すことは、とても難しいです。仮に中国価格が長期化すると、企業が破綻する可能性もでてきます。
企業行動の視点で見ると、トヨタなどが改善活動でよいパフォーマンスをしたとしても、業績を上げることはありませんでした。しかし、為替が円高から円安に反転したことによって、今までよくらなかった業績は、一気に上昇してきました。そのような背景からわかることは、トヨタでさえ業績回復するためには、日本経済の安定や成長が不可欠で、いくら企業努力したとしても、自助努力では限界があるということです。もちろん、そんなことに左右されない企業体質にすることが、経営者の仕事だという議論もあります。しかし明らかなのは、税金にも保険料にも頼らない、補助金頼みでもない、本当の民間企業の業績は、日本経済に左右されるということです。金融政策や経済政策や産業政策は中小企業の業績へも大きく寄与しているのです。
一方、本格的に製造業復活と言われているのが、アメリカです。ではどういう点が日本と違うか比較してみると、アメリカは投資したくなるような環境が整備されているのに対し、日本は投資したくなるような環境は整備されていないことがあります。アジアの人件が高騰していく中で、最終的に重要になってくるのは、法人税率です。企業が利益を出したとしても、法人税率によって残るお金が違ってくるのであれば、低税率の国を拠点にするのは当然のことです。税引後、多くのお金が残ることによって、設備投資に廻ったり、従業員の給料を上げてみたりと、積極的なことが可能になるのです。政府が「企業は給料を上げてください、設備投資を増やしてください」などと号令をかけているようですが、そんな号令だけでは限界もあるし、長続きしません。
多くの企業経営者は設備投資をしたり、給料を上げたりしたいと考えています。それらをしたくないと思っている経営者はいません。政府は財政健全化の目標を達成しようとするあまり、バラマキによる見せかけの成長をさせようとしています。税金や保険料で一時的に潤っている業界は、こんなことが長続きしないことくらい一番良く知っているはずです。そんな歪んだ方法ではなく、誰もが積極的に設備投資や給料アップをしたくなる環境を整えるべきなのです。
世界の優秀な企業経営者から、「日本でビジネスをするのが最適だ、だから日本でビジネスしよう」と言われるような環境にしてほしいです。今、日本政府は世界の企業経営者から注目されていることを、もっともっと認識すべきです。次の選挙のことばかり考えるのではなく、次の世代を考えて行動していれば、それは簡単なことです。将来、世界中の人たちから、選ばれる日本になる環境作りが期待されています。

しかし、本当にそうでしょうか?今の日本企業の動きを見ていると、国内工場は稼働率を上げることや残業だけで対応しています。正社員の雇用を増やしたり、過去に閉鎖した工場を復活させたり、工場新設に積極的な企業は、多くありません。このような対応では、為替が円高になった瞬間に製造業の状況は、空洞化に戻ります。
また価格については、日本へ戻ってきた製品の価格は、中国で生産していた時と同じことが多いです。これでは、日本と海外の人件費の差が縮まってきたとはいえ、中国価格で日本企業が利益を生み出すことは、とても難しいです。仮に中国価格が長期化すると、企業が破綻する可能性もでてきます。
企業行動の視点で見ると、トヨタなどが改善活動でよいパフォーマンスをしたとしても、業績を上げることはありませんでした。しかし、為替が円高から円安に反転したことによって、今までよくらなかった業績は、一気に上昇してきました。そのような背景からわかることは、トヨタでさえ業績回復するためには、日本経済の安定や成長が不可欠で、いくら企業努力したとしても、自助努力では限界があるということです。もちろん、そんなことに左右されない企業体質にすることが、経営者の仕事だという議論もあります。しかし明らかなのは、税金にも保険料にも頼らない、補助金頼みでもない、本当の民間企業の業績は、日本経済に左右されるということです。金融政策や経済政策や産業政策は中小企業の業績へも大きく寄与しているのです。
一方、本格的に製造業復活と言われているのが、アメリカです。ではどういう点が日本と違うか比較してみると、アメリカは投資したくなるような環境が整備されているのに対し、日本は投資したくなるような環境は整備されていないことがあります。アジアの人件が高騰していく中で、最終的に重要になってくるのは、法人税率です。企業が利益を出したとしても、法人税率によって残るお金が違ってくるのであれば、低税率の国を拠点にするのは当然のことです。税引後、多くのお金が残ることによって、設備投資に廻ったり、従業員の給料を上げてみたりと、積極的なことが可能になるのです。政府が「企業は給料を上げてください、設備投資を増やしてください」などと号令をかけているようですが、そんな号令だけでは限界もあるし、長続きしません。
多くの企業経営者は設備投資をしたり、給料を上げたりしたいと考えています。それらをしたくないと思っている経営者はいません。政府は財政健全化の目標を達成しようとするあまり、バラマキによる見せかけの成長をさせようとしています。税金や保険料で一時的に潤っている業界は、こんなことが長続きしないことくらい一番良く知っているはずです。そんな歪んだ方法ではなく、誰もが積極的に設備投資や給料アップをしたくなる環境を整えるべきなのです。
世界の優秀な企業経営者から、「日本でビジネスをするのが最適だ、だから日本でビジネスしよう」と言われるような環境にしてほしいです。今、日本政府は世界の企業経営者から注目されていることを、もっともっと認識すべきです。次の選挙のことばかり考えるのではなく、次の世代を考えて行動していれば、それは簡単なことです。将来、世界中の人たちから、選ばれる日本になる環境作りが期待されています。

昨日、映画「うみやまあひだ」の試写会が行われました。この「うみやまあひだ」は、一昨年、伊勢神宮で行われた式年遷宮を題材にしたドキュメンタリー映画です。日本の自然と日本人の奥深さが美しく表現され、あまりにも素晴しく、すごく感動しました。式年遷宮とは、約1300年間続けられている、20年に一度の神事のこと。「なぜ日本人は儀式を絶やさず、祈りを続けてきたのか」。その答えは押し付けられるものではなく、それぞれの国の人がそれぞれ答えを出すもの。決して押し付けるものではないのです。だからこそ伊勢神宮は、世界中の宗教のトップが訪れる神聖な場所なのです。話を戻しますが、私なりに探した答えは、「本物は生き残る」ということです。これは企業でも人でも全てに例えることができると思います。偽物は生き残ることはできません。そのことを伊勢神宮は証明してくれています。老舗企業でも、創業100年くらいがいいところ。それに対し、伊勢神宮は1300年。その歴史と精神には感動します。最後になりますが、「うみやまあひだ」は日本初の4K映画です。高解像度で観る4K映画は、日本の美しい自然と伝統美を最高に表現します。1月31日から全国劇場公開スタートします。どこで上映するかは、前売りチケットの売れ行き次第だそうです。では、お楽しみに!
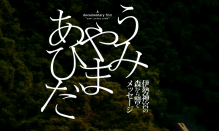
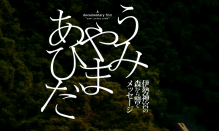
どこかで読んだ記事によると、薬を大量にもらう「モンスター患者」がいるそうです。その方は後期高齢者で、治療費と薬代は1割自己負担。大量の湿布を処方されているので、心配した看護師さんが聞いてみると、「これは家族全員の分」と言ったそうです。その方は春先になると、花粉症の薬や目薬も大量に処方してもらうらしい。高齢者は若者より投票率が高く、人口の構成比率も高い。そのような背景があるので、どの政権も大胆な社会保障費抑制には踏み込めていません。シルバー民主主義に迎合しすぎれば、社会保障制度の崩壊だけでなく、日本の民主主義は破綻します。海外からの視点でみれば、日本の国民皆保険制度は素晴しいです。しかし運営の仕方を間違えれば、これは本末転倒です。

中小企業に限らず日本の企業人が生き残るための選択肢は、3つあります。
①海外へ出て行く。
②外国人労働者を受け入れる。
③日本国内で日本人だけでやるなら、イヤな仕事、大変な仕事は日本人の間でシェアする。
これらの選択肢から言えることは、労働力人口減少の問題は避けて通れないということです。人口予測は確かな予測です。一方、株価や為替や景気などの予測は、難しく不確実な予測です。人口予測を念頭に入れ、企業経営を計画することは、大切なことです。この問題は1人の経営者が抱え込む問題ではありません。しかし未来の企業のあり方をイメージすることは、必要です。どれを選択し、どのように覚悟と責任を果たしていくか、これは難しいことです。人口予測は、未来の社会を映し出す根拠のあるものです。難しい課題ですが、少しずつ前進していきましょう。

①海外へ出て行く。
②外国人労働者を受け入れる。
③日本国内で日本人だけでやるなら、イヤな仕事、大変な仕事は日本人の間でシェアする。
これらの選択肢から言えることは、労働力人口減少の問題は避けて通れないということです。人口予測は確かな予測です。一方、株価や為替や景気などの予測は、難しく不確実な予測です。人口予測を念頭に入れ、企業経営を計画することは、大切なことです。この問題は1人の経営者が抱え込む問題ではありません。しかし未来の企業のあり方をイメージすることは、必要です。どれを選択し、どのように覚悟と責任を果たしていくか、これは難しいことです。人口予測は、未来の社会を映し出す根拠のあるものです。難しい課題ですが、少しずつ前進していきましょう。

