*11月5日エントリー の続きです。
R大学文学部史学科の院生・あんみつ君![]() と、近現代史のしらたま教授
と、近現代史のしらたま教授![]() の歴史トーク、今回のテーマは幕末の庄内藩。
の歴史トーク、今回のテーマは幕末の庄内藩。
本日は、江戸開城 のおはなしです。

![]()
![]()
![]()
あんみつ![]() 「しらたま先生、慶応四年(1868)正月早々に鳥羽伏見の戦いが起き、前将軍・徳川慶喜は江戸に逃走しました。これをもって徳川幕府消滅の時と言えそうです。負けと言っても緒戦、全力の薩摩長州に対し、幕府は膨大な兵力を持ってたんですからじゅうぶん建て直せたはずなんですけど」
「しらたま先生、慶応四年(1868)正月早々に鳥羽伏見の戦いが起き、前将軍・徳川慶喜は江戸に逃走しました。これをもって徳川幕府消滅の時と言えそうです。負けと言っても緒戦、全力の薩摩長州に対し、幕府は膨大な兵力を持ってたんですからじゅうぶん建て直せたはずなんですけど」
しらたま![]() 「第二次長州征伐にしても、大村益次郎や高杉晋作率いる奇兵隊の活躍で幕軍が敗れたというが、その気になれば数にモノを言わせることは出来た。かつての島原の乱(1638)にしたって、緒戦は大名の不調和で負けてるし。しかし総大将である慶喜が幕軍を見捨てて去ったことは決定的だった」
「第二次長州征伐にしても、大村益次郎や高杉晋作率いる奇兵隊の活躍で幕軍が敗れたというが、その気になれば数にモノを言わせることは出来た。かつての島原の乱(1638)にしたって、緒戦は大名の不調和で負けてるし。しかし総大将である慶喜が幕軍を見捨てて去ったことは決定的だった」
あんみつ![]() 「鳥羽伏見では現役老中・稲葉美濃守正邦の淀藩と、藤堂和泉守高猷(たかゆき)の津藩が寝返ったことでの敗戦でした。薩摩長州は官軍を称し、勢いに乗って東征を実行します。総督は有栖川宮熾仁(たるひと)親王、大参謀は西郷吉之助。これに対し諸藩はオセロゲームのように雪崩を打って帰順していきました」
「鳥羽伏見では現役老中・稲葉美濃守正邦の淀藩と、藤堂和泉守高猷(たかゆき)の津藩が寝返ったことでの敗戦でした。薩摩長州は官軍を称し、勢いに乗って東征を実行します。総督は有栖川宮熾仁(たるひと)親王、大参謀は西郷吉之助。これに対し諸藩はオセロゲームのように雪崩を打って帰順していきました」
しらたま![]() 「一月末、京都所司代・松平定敬(さだあき,会津藩主松平容保の実弟)の桑名藩が降伏した。定敬は慶喜の供で江戸にあったから、国元が藩主に無断で降伏したわけだ。二月に入り西郷は東海道に進発。親藩の高須藩松平家(容保・定敬の実家)、譜代の筆頭、彦根藩井伊家もそれに従う」
「一月末、京都所司代・松平定敬(さだあき,会津藩主松平容保の実弟)の桑名藩が降伏した。定敬は慶喜の供で江戸にあったから、国元が藩主に無断で降伏したわけだ。二月に入り西郷は東海道に進発。親藩の高須藩松平家(容保・定敬の実家)、譜代の筆頭、彦根藩井伊家もそれに従う」
あんみつ![]() 「御三家である紀州・尾張もあっさり恭順しましたからねぇ。紀伊大納言茂承(もちつぐ)は藩兵と軍資金15万両を提供。尾張大納言慶勝は抗戦を主張する家老・渡辺新左衛門らを大量処刑してまで官軍に追従しました(青松葉事件)」
「御三家である紀州・尾張もあっさり恭順しましたからねぇ。紀伊大納言茂承(もちつぐ)は藩兵と軍資金15万両を提供。尾張大納言慶勝は抗戦を主張する家老・渡辺新左衛門らを大量処刑してまで官軍に追従しました(青松葉事件)」
しらたま![]() 「父祖家康が、東海道の守りとして築いた壮麗な名古屋城は、何の役にも立たなかったわけだ。長州征伐の時点では幕府方の総督を務めていた尾張候の風見鶏ぶりは、現在の愛知県民に向けられるなんとなしな嘲笑の原因じゃないかなぁ」
「父祖家康が、東海道の守りとして築いた壮麗な名古屋城は、何の役にも立たなかったわけだ。長州征伐の時点では幕府方の総督を務めていた尾張候の風見鶏ぶりは、現在の愛知県民に向けられるなんとなしな嘲笑の原因じゃないかなぁ」
あんみつ![]() 「名古屋ダサいのイメージは、タモリさんのせいじゃないんですか(笑)。ともかくおかげで悠々と東海道を進軍する西郷は三月初めにはもう駿府に着到しました。朝敵徳川慶喜は処刑と公言していたので、恭順を決めていた慶喜の心は揺れ、幕臣は抗戦を主張します。江戸警備の庄内藩は任を解かれ国元に撤収。この瀬戸際で登場したのが山岡鉄太郎と高橋泥舟ですね」
「名古屋ダサいのイメージは、タモリさんのせいじゃないんですか(笑)。ともかくおかげで悠々と東海道を進軍する西郷は三月初めにはもう駿府に着到しました。朝敵徳川慶喜は処刑と公言していたので、恭順を決めていた慶喜の心は揺れ、幕臣は抗戦を主張します。江戸警備の庄内藩は任を解かれ国元に撤収。この瀬戸際で登場したのが山岡鉄太郎と高橋泥舟ですね」
しらたま![]() 「上野寛永寺にいた慶喜は、大総督府に助命と徳川存続を嘆願すべく、高橋を使者に決めたのだが、ボディガードである高橋が離れるのは心細い。そこで高橋の推薦で山岡を召した。山岡はすぐ赤坂の勝 安房守(海舟)を訪ね、西郷への手紙を書いてもらった。『無偏無党、王道堂々たり矣 今官軍、鄙府に逼るといえども君臣謹んで恭順の道を守るは我が徳川氏の士民~』 の文言で知られる」
「上野寛永寺にいた慶喜は、大総督府に助命と徳川存続を嘆願すべく、高橋を使者に決めたのだが、ボディガードである高橋が離れるのは心細い。そこで高橋の推薦で山岡を召した。山岡はすぐ赤坂の勝 安房守(海舟)を訪ね、西郷への手紙を書いてもらった。『無偏無党、王道堂々たり矣 今官軍、鄙府に逼るといえども君臣謹んで恭順の道を守るは我が徳川氏の士民~』 の文言で知られる」
あんみつ![]() 「山岡は庄内藩の薩摩藩邸焼き討ちの際に捕虜となった益満休之助を証人に伴い、急いで駿府に向かいます。川崎や神奈川宿では哨戒線が敷かれていたので、危険と隣り合わせだったようですね。先遣隊の隊長だった中村半次郎(桐野利秋)には怪しまれて斬られそうになったとか」
「山岡は庄内藩の薩摩藩邸焼き討ちの際に捕虜となった益満休之助を証人に伴い、急いで駿府に向かいます。川崎や神奈川宿では哨戒線が敷かれていたので、危険と隣り合わせだったようですね。先遣隊の隊長だった中村半次郎(桐野利秋)には怪しまれて斬られそうになったとか」
しらたま![]() 「小田原では甲州勝沼に出陣する官軍と行き会った。新撰組の近藤 勇、土方歳三が <甲陽鎮撫隊> を称する200人ほどで甲府城接収に向かったからだ。実は江戸に新撰組がいると和平交渉の邪魔になるからと、勝安房が体よく追い出したんだ。勝沼戦争は三月六日、土佐の板垣退助率いる迅衝隊400人と交戦、一日で敗退する」
「小田原では甲州勝沼に出陣する官軍と行き会った。新撰組の近藤 勇、土方歳三が <甲陽鎮撫隊> を称する200人ほどで甲府城接収に向かったからだ。実は江戸に新撰組がいると和平交渉の邪魔になるからと、勝安房が体よく追い出したんだ。勝沼戦争は三月六日、土佐の板垣退助率いる迅衝隊400人と交戦、一日で敗退する」
あんみつ![]() 「三月八日、山岡は駿府で西郷と対面。西郷も英公使パークスから侵攻をたしなめられていたこともあり、江戸開城と武装解除を条件に、慶喜助命と恭順受け入れに合意しました。山岡は急いで江戸に戻り、勝や慶喜本人に報告。十日には江戸市中に高札が立ち、戦火回避に市民は胸をなでおろします」
「三月八日、山岡は駿府で西郷と対面。西郷も英公使パークスから侵攻をたしなめられていたこともあり、江戸開城と武装解除を条件に、慶喜助命と恭順受け入れに合意しました。山岡は急いで江戸に戻り、勝や慶喜本人に報告。十日には江戸市中に高札が立ち、戦火回避に市民は胸をなでおろします」
しらたま![]() 「だが官軍はすでに品川まで迫っており、将士は殺気凛々。幕臣たちも降伏に納得せず、勝や山岡斬るべしと息巻く物騒さだ。もし不測の事態で戦争になったら江戸を焦土にするよう、勝が侠客・新門辰五郎に頼んだというのはこのときだ」
「だが官軍はすでに品川まで迫っており、将士は殺気凛々。幕臣たちも降伏に納得せず、勝や山岡斬るべしと息巻く物騒さだ。もし不測の事態で戦争になったら江戸を焦土にするよう、勝が侠客・新門辰五郎に頼んだというのはこのときだ」
あんみつ![]() 「三月十三日、十四日の両日、高輪と田町の薩摩屋敷で西郷と勝が会見。無血開城が実現となります。勝が回顧録で西郷とは肝胆相照らし、談判は阿吽の呼吸で終わったなんて言うから、英雄同士の名場面的に思われてますけど、中身としてはけっこう切迫したやりとりしてますよね。でなければ二日かかるわけがない。実務担当の海江田武次(有村俊斎)とは詳細な善後策を練っています」
「三月十三日、十四日の両日、高輪と田町の薩摩屋敷で西郷と勝が会見。無血開城が実現となります。勝が回顧録で西郷とは肝胆相照らし、談判は阿吽の呼吸で終わったなんて言うから、英雄同士の名場面的に思われてますけど、中身としてはけっこう切迫したやりとりしてますよね。でなければ二日かかるわけがない。実務担当の海江田武次(有村俊斎)とは詳細な善後策を練っています」
しらたま![]() 「それというのも薩摩以外の官軍に江戸総攻撃する気まんまんのうえ、幕臣の主戦論をどう鎮めるか、江戸城引き渡しの実行法、退去した幕臣の処遇など取り決め事項は山ほどあるからだ。官幕双方、不満だらけの状況だったと言える。肝心の慶喜ですら江戸城には留まるつもりで、勝の合意内容に怒ったというんだから、勝の苦労は想像を絶するものがあったろう」
「それというのも薩摩以外の官軍に江戸総攻撃する気まんまんのうえ、幕臣の主戦論をどう鎮めるか、江戸城引き渡しの実行法、退去した幕臣の処遇など取り決め事項は山ほどあるからだ。官幕双方、不満だらけの状況だったと言える。肝心の慶喜ですら江戸城には留まるつもりで、勝の合意内容に怒ったというんだから、勝の苦労は想像を絶するものがあったろう」
あんみつ![]() 「開城は四月十一日、慶喜は上野から水戸に退隠。山岡や高橋ら1700人ほどがお供しました。江戸城は尾張藩が受け取る体裁で徳川の面目を保ったのは、西郷と勝のアイディアですね。榎本武揚率いる幕府艦隊8隻が積めるだけの武器弾薬を運んで品川沖から脱走したのはこの晩でした」
「開城は四月十一日、慶喜は上野から水戸に退隠。山岡や高橋ら1700人ほどがお供しました。江戸城は尾張藩が受け取る体裁で徳川の面目を保ったのは、西郷と勝のアイディアですね。榎本武揚率いる幕府艦隊8隻が積めるだけの武器弾薬を運んで品川沖から脱走したのはこの晩でした」
しらたま![]() 「さらに江戸に残った一橋家臣が慶喜の冤罪を訴えると称して徒党を組むと、主戦派の幕臣や無頼漢が続々集まって約2000人、<彰義隊> を称して暴発の気配を見せた。海江田や勝はなんとか穏便に済まそうと奔走するが、薩摩以外の官軍、長州・大村益次郎、土佐・板垣退助、佐賀・江藤新平らの反発も抑えられず、上野戦争に至る。こうして結局は戊辰戦争という武力革命が不可避になったんだ」
「さらに江戸に残った一橋家臣が慶喜の冤罪を訴えると称して徒党を組むと、主戦派の幕臣や無頼漢が続々集まって約2000人、<彰義隊> を称して暴発の気配を見せた。海江田や勝はなんとか穏便に済まそうと奔走するが、薩摩以外の官軍、長州・大村益次郎、土佐・板垣退助、佐賀・江藤新平らの反発も抑えられず、上野戦争に至る。こうして結局は戊辰戦争という武力革命が不可避になったんだ」
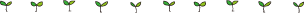
今回はここまでです。
鳥羽伏見の緒戦からわずか3ヶ月、徳川幕府の拠点江戸城は官軍の手に引き渡され、徳川慶喜は恭順蟄居を受け入れました。
しかし、不抗戦に納得しない幕臣はおのおの独自の行動を模索していきます。
次回、奥羽越列藩同盟 のおはなし。
それではごきげんよう![]()
![]() 。
。