*6月5日エントリー の続きです。
R大学文学部史学科のぜんざい教授![]() と、継子の院生・あんみつ君
と、継子の院生・あんみつ君![]() の歴史トーク、今回のテーマは戦国時代の中国地方。
の歴史トーク、今回のテーマは戦国時代の中国地方。
本日は、飢餓地獄 のおはなしです。
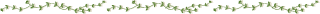
🍨 🥮 🍹
あんみつ![]() 「先生、播磨での戦況有利で、東上しての決戦まで乗り出そうとした毛利輝元ですが、内外の情勢が激変しました。天正六年(1578)三月に、頼りの上杉謙信が亡くなり織田包囲網が崩れます。北陸から織田勢を破り越前まで進軍していたのに、謙信没後は後継者争いで上杉家は弱体化しますから」
「先生、播磨での戦況有利で、東上しての決戦まで乗り出そうとした毛利輝元ですが、内外の情勢が激変しました。天正六年(1578)三月に、頼りの上杉謙信が亡くなり織田包囲網が崩れます。北陸から織田勢を破り越前まで進軍していたのに、謙信没後は後継者争いで上杉家は弱体化しますから」
ぜんざい![]() 「毛利内部でも、周防山口を任せていた市川経好の子・元教が背く事態が起きた。どうやら織田毛利が播磨で対戦してる隙に、豊後の大友宗麟が策動したようだ。元教の母は、かつて経好不在時の大内輝弘の侵攻に、自ら鎧を着て城兵を督戦したほどの女傑なのに、その子が裏切るとは不可解な話だ。経好はわが子をすぐ討ち果たし、毛利家への忠心をみせている」
「毛利内部でも、周防山口を任せていた市川経好の子・元教が背く事態が起きた。どうやら織田毛利が播磨で対戦してる隙に、豊後の大友宗麟が策動したようだ。元教の母は、かつて経好不在時の大内輝弘の侵攻に、自ら鎧を着て城兵を督戦したほどの女傑なのに、その子が裏切るとは不可解な話だ。経好はわが子をすぐ討ち果たし、毛利家への忠心をみせている」
あんみつ![]() 「天正六年(1578)十一月、毛利はふたたび大阪本願寺に兵糧米を搬入すべく、摂津木津川口に村上水軍を派遣しました。前回の敗戦を受け、信長は志摩の海賊・九鬼嘉隆水軍に大きな安宅船を作らせ、大砲を備えた艦隊で迎え撃ちます。かつては船体を鉄板で装甲した <鉄甲船> を開発したなどと言われましたが、それはフィクションだったようですね。信長=戦術革命幻想という」
「天正六年(1578)十一月、毛利はふたたび大阪本願寺に兵糧米を搬入すべく、摂津木津川口に村上水軍を派遣しました。前回の敗戦を受け、信長は志摩の海賊・九鬼嘉隆水軍に大きな安宅船を作らせ、大砲を備えた艦隊で迎え撃ちます。かつては船体を鉄板で装甲した <鉄甲船> を開発したなどと言われましたが、それはフィクションだったようですね。信長=戦術革命幻想という」
ぜんざい![]() 「うん、村上水軍が大砲で被害を受けたのは事実だけど、目的の本願寺への兵糧搬入は果たした。とはいえこれ以降、大阪湾の制海権を織田が握ることになり本願寺は孤立してしまう。摂津では離反した荒木村重の与党、高槻城主・高山右近、茨木城主・中川清秀を降伏させ、織田が一気に巻き返しに出た」
「うん、村上水軍が大砲で被害を受けたのは事実だけど、目的の本願寺への兵糧搬入は果たした。とはいえこれ以降、大阪湾の制海権を織田が握ることになり本願寺は孤立してしまう。摂津では離反した荒木村重の与党、高槻城主・高山右近、茨木城主・中川清秀を降伏させ、織田が一気に巻き返しに出た」
あんみつ![]() 「天正七年(1579)に入ると、毛利の北九州唯一の拠点、豊前松山城主・杉七郎重良が独立します。杉はかつて大内氏の家臣で、毛利に随身していました。十一月に大友宗麟が島津に大敗したことで勢威が落ち、火事場ドロを狙ったものです。これもまた鎮圧されますが、相次ぐ領内豪族の動揺にイラついた小早川隆景が、若い当主の毛利輝元を厳しく叱咤したと言います。求心力不足ではないですか、と...輝元にしたら心外でしょうけど」
「天正七年(1579)に入ると、毛利の北九州唯一の拠点、豊前松山城主・杉七郎重良が独立します。杉はかつて大内氏の家臣で、毛利に随身していました。十一月に大友宗麟が島津に大敗したことで勢威が落ち、火事場ドロを狙ったものです。これもまた鎮圧されますが、相次ぐ領内豪族の動揺にイラついた小早川隆景が、若い当主の毛利輝元を厳しく叱咤したと言います。求心力不足ではないですか、と...輝元にしたら心外でしょうけど」
ぜんざい![]() 「信長が包囲網と荒木村重や別所長治の離反で窮地に陥ったように、毛利もまた背後の大友や家臣の謀反で動きを封じられた。戦国大名の領国統治の脆さと、国人豪族の倫理観がわかるだろう。彼らはけっして義理や忠誠心で随身してるわけじゃなく、自家生き残りが第一だ。それも出来るだけ良い条件で」
「信長が包囲網と荒木村重や別所長治の離反で窮地に陥ったように、毛利もまた背後の大友や家臣の謀反で動きを封じられた。戦国大名の領国統治の脆さと、国人豪族の倫理観がわかるだろう。彼らはけっして義理や忠誠心で随身してるわけじゃなく、自家生き残りが第一だ。それも出来るだけ良い条件で」
あんみつ![]() 「その倫理観の欠如と現金さをもっとも体現してるのが宇喜多直家ですね。毛利の先鋒として播磨で戦いながら、形勢は織田にあり、と羽柴秀吉を通じて内応を申し出ました。信長は宇喜多の二枚舌などお見通しですから当初認めませんでしたが、備中・美作でせっせと毛利方を攪乱し、信長のご機嫌を取って秀吉にとりなしてもらうという。伯耆でも、羽衣石(うえいし)城主・南条元続が織田に寝返ります」
「その倫理観の欠如と現金さをもっとも体現してるのが宇喜多直家ですね。毛利の先鋒として播磨で戦いながら、形勢は織田にあり、と羽柴秀吉を通じて内応を申し出ました。信長は宇喜多の二枚舌などお見通しですから当初認めませんでしたが、備中・美作でせっせと毛利方を攪乱し、信長のご機嫌を取って秀吉にとりなしてもらうという。伯耆でも、羽衣石(うえいし)城主・南条元続が織田に寝返ります」
ぜんざい![]() 「毛利輝元が進軍できないうち、丹波八上城主・波多野秀治・秀尚兄弟が明智光秀に降伏し、安土に送られ処刑された。ちなみにこのとき、光秀は母親を人質に出してないよ。一年以上に及ぶ包囲戦の末だ。摂津でも荒木村重が有岡城(伊丹市)を単身脱出、尼崎城に移り毛利の援軍を待つ」
「毛利輝元が進軍できないうち、丹波八上城主・波多野秀治・秀尚兄弟が明智光秀に降伏し、安土に送られ処刑された。ちなみにこのとき、光秀は母親を人質に出してないよ。一年以上に及ぶ包囲戦の末だ。摂津でも荒木村重が有岡城(伊丹市)を単身脱出、尼崎城に移り毛利の援軍を待つ」
あんみつ![]() 「十一月に有岡城は陥落し、城兵も女性・子どもの非戦闘員も信長の命令で殺戮されました。荒木を説得しようと単身有岡城を訪れた黒田官兵衛が捕虜となり、1年半もの幽閉から救助されたのはこのときですね。信長は官兵衛も裏切ったと思い込み、人質の嫡子・松寿丸を斬るよう秀吉に命じたのを、竹中半兵衛がこっそりかくまってくれていました」
「十一月に有岡城は陥落し、城兵も女性・子どもの非戦闘員も信長の命令で殺戮されました。荒木を説得しようと単身有岡城を訪れた黒田官兵衛が捕虜となり、1年半もの幽閉から救助されたのはこのときですね。信長は官兵衛も裏切ったと思い込み、人質の嫡子・松寿丸を斬るよう秀吉に命じたのを、竹中半兵衛がこっそりかくまってくれていました」
ぜんざい![]() 「もし半兵衛の機転がなかったら、江戸時代福岡52万石の藩祖・黒田長政はいなかったわけだから、人間つくづく運の巡りあわせだよ。荒木村重は翌天正八年(1580)七月まで花隈城で抗戦したが、織田の重鎮・池田恒興軍に囲まれると、毛利水軍に救助されて安芸尾道に亡命した」
「もし半兵衛の機転がなかったら、江戸時代福岡52万石の藩祖・黒田長政はいなかったわけだから、人間つくづく運の巡りあわせだよ。荒木村重は翌天正八年(1580)七月まで花隈城で抗戦したが、織田の重鎮・池田恒興軍に囲まれると、毛利水軍に救助されて安芸尾道に亡命した」
あんみつ![]() 「摂津と丹波が織田により平定され、孤立したのが播磨三木城の別所長治です。寝返りに激怒していた寄せ手の羽柴秀吉は、兵糧補給を断ち切る <三木の干(ひ)殺し> を敢行しました。一方、毛利にしたら三木城を見捨てたらさらなる豪族の離反を招くから、なんとしても救援したい」
「摂津と丹波が織田により平定され、孤立したのが播磨三木城の別所長治です。寝返りに激怒していた寄せ手の羽柴秀吉は、兵糧補給を断ち切る <三木の干(ひ)殺し> を敢行しました。一方、毛利にしたら三木城を見捨てたらさらなる豪族の離反を招くから、なんとしても救援したい」
ぜんざい![]() 「毛利水軍は播磨魚住から兵糧を海上輸送しようとしたが、秀吉の遮断に遭う。そこから花隈、淡河(おうご)、加古川と補給路を変えるもことごとく封鎖されたので、九月、毛利勢と三木城兵が大村にある秀吉の付城を夜襲し、挟み撃ちにして強引に兵糧搬入を決行、壮絶な <大村合戦> となる。作戦は成功したものの甚大な犠牲を出し、これ以降三木城との連絡は絶たれた」
「毛利水軍は播磨魚住から兵糧を海上輸送しようとしたが、秀吉の遮断に遭う。そこから花隈、淡河(おうご)、加古川と補給路を変えるもことごとく封鎖されたので、九月、毛利勢と三木城兵が大村にある秀吉の付城を夜襲し、挟み撃ちにして強引に兵糧搬入を決行、壮絶な <大村合戦> となる。作戦は成功したものの甚大な犠牲を出し、これ以降三木城との連絡は絶たれた」
三木城への補給路封鎖
あんみつ![]() 「秀吉は仕寄せ(付け城)を三木城の目前まで進め、櫓と篝火で四六時中監視、付近の美嚢川には乱杭と大網を打ちます。もはやアリの這い出る隙間もない徹底包囲に、糧秣の尽きた三木城内は悲惨なことになりました。籠城はまる二年、牛馬はもちろん屍肉まで喰った末に餓死者が続出、弓を引き槍を揮う力など誰もありません」
「秀吉は仕寄せ(付け城)を三木城の目前まで進め、櫓と篝火で四六時中監視、付近の美嚢川には乱杭と大網を打ちます。もはやアリの這い出る隙間もない徹底包囲に、糧秣の尽きた三木城内は悲惨なことになりました。籠城はまる二年、牛馬はもちろん屍肉まで喰った末に餓死者が続出、弓を引き槍を揮う力など誰もありません」
ぜんざい![]() 「天正八年(1580)正月、秀吉は別所長治の自刃で城兵は助けると使者を送り、長治は応諾した。秀吉は返礼に酒樽と肴を送って将兵の最期の宴に供したという。長治27歳、弟の23歳友行ら一族も自刃して、三木城はついに開城した」
「天正八年(1580)正月、秀吉は別所長治の自刃で城兵は助けると使者を送り、長治は応諾した。秀吉は返礼に酒樽と肴を送って将兵の最期の宴に供したという。長治27歳、弟の23歳友行ら一族も自刃して、三木城はついに開城した」
あんみつ![]() 「閏三月、大坂本願寺では法主・顕如(光佐)が停戦を受け入れました。力攻めをあきらめた信長が、正親町(おおぎまち)天皇を介して <勅命講和> のかたちで和平交渉していたからです。大局的に勝利はムリと悟った顕如は、これなら名誉が保たれる、と紀伊雑賀の鷺森(さぎのもり)御坊に退去します。五月には但馬の山名祐豊が有子山城で羽柴秀長に降伏しました」
「閏三月、大坂本願寺では法主・顕如(光佐)が停戦を受け入れました。力攻めをあきらめた信長が、正親町(おおぎまち)天皇を介して <勅命講和> のかたちで和平交渉していたからです。大局的に勝利はムリと悟った顕如は、これなら名誉が保たれる、と紀伊雑賀の鷺森(さぎのもり)御坊に退去します。五月には但馬の山名祐豊が有子山城で羽柴秀長に降伏しました」
ぜんざい![]() 「顕如の子・教如(光寿)は新門跡を名乗って父に逆らい抗戦を続けたが、八月に投降。退去のさい、本願寺は放火され、伽藍は灰燼に帰した。これをもって畿内周辺の親毛利勢力は消滅、毛利は進軍どころか、じわじわ防衛線を引き下げていく」
「顕如の子・教如(光寿)は新門跡を名乗って父に逆らい抗戦を続けたが、八月に投降。退去のさい、本願寺は放火され、伽藍は灰燼に帰した。これをもって畿内周辺の親毛利勢力は消滅、毛利は進軍どころか、じわじわ防衛線を引き下げていく」
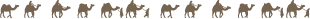
今回はここまでです。
播磨で織田と互角の戦線を張った毛利も、内部の動揺と織田軍の個別撃破により均衡は破れました。
次回、高松の講和 のおはなし。
それではごきげんよう![]()
![]() 。
。
