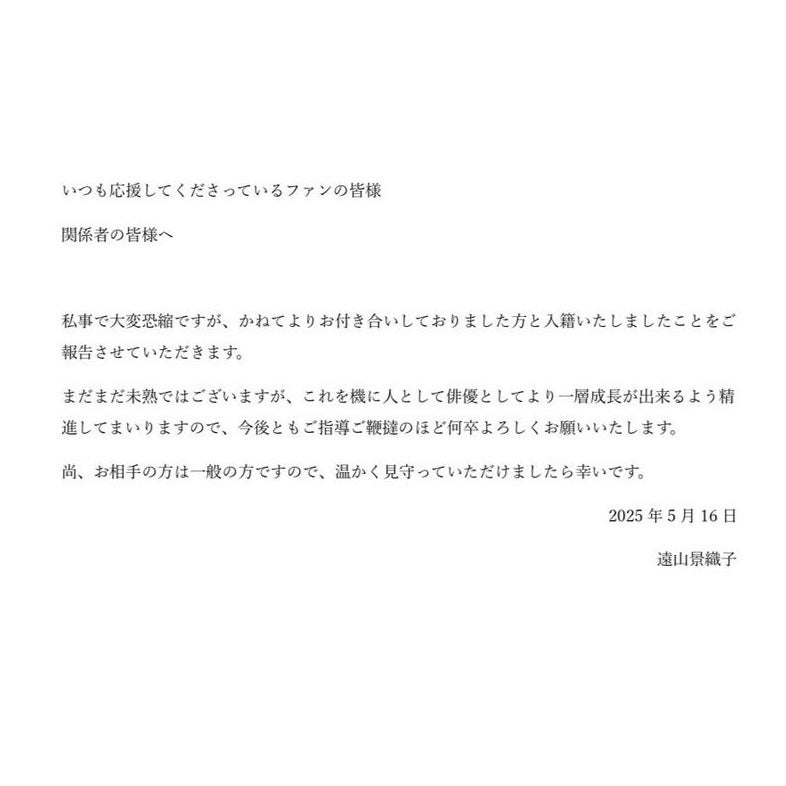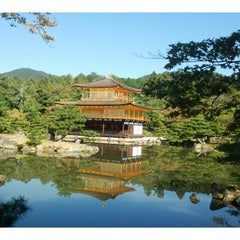鳩森八幡神社から北参道駅まで移動し![]()
代々木八幡駅から歩いて約5分
代々木八幡宮に![]()
代々木八幡宮
【よよぎはちまんぐう】
鎌倉時代、二代将軍・源頼家の側近であった近藤三郎是茂(これもち)の家来で荒井外記(げき)智明(ともあきら)という方が、頼家公暗殺の後、名も宗祐(そうゆう)と改めてこの代々木野に隠遁し、主君の菩提を弔って暮らしていましたが、時に建暦2年(1212年)8月15日夜、霊夢の中で八幡大神の託宣と宝珠の鏡を感得しました。
そこで同年9月23日、元八幡の地に小さな祠を建て、鶴岡八幡宮を勧請したのが創始とされています。

鳥居
草創以来、社僧の手によって管理されてきました
当社の別当寺であった福泉寺の文書によれば、天保元年(1644)伝養律師という方が中興開山として天台宗に改め、次いで二世の僧が社殿、植林などの整備を行い、三世の長秀法師の代に現在の場所へ奉遷したといわれています
これは大和国岩掛城主・山田政秀の第六女、紀州家側室・延寿院殿が甥であった長秀法師のために社地6000坪を始めとする数々の寄進をしたことで実現
明治維新以降、神仏混淆が禁止され当社は村社に列せられました
江戸時代からの稲荷社、天神社の末社に加え、旧代々木村にあった小さな神社が合祀され、天祖社(天照大神)と白山社(白山大神)が八幡さまの配座に祀られることになりました

手水舎
八幡宮と言うだけあって…豪華な感じがしますね

拝殿
御祭神
応神天皇=八幡さま
八幡さまは古くは朝廷や武家からの崇敬をあつめ、国家鎮護、破邪顕正の神と仰がれました
その強いご神徳から「厄除開運」の神さまとして全国で鎮守の神として祀られたんやって
他に家内安全や縁結び、安産・子育てまで幅広いご利益があります

回廊
結婚式も多々行われてるとの事 
皆さんここを歩いてるんですね
有名人では佐々木恭子さんもこちらで結婚式を行われたんやって

狛犬
明治廿六年九月吉祥日
子供の狛犬…顔を上に向いて親を見てるって珍しいよね
ほとんどの神社の狛犬は子を踏みつけるのに…
こちらは子を抱いてます
稲荷社(豊受大神)・天神社(菅原道真公)・榛名社(日本武尊)
稲荷社と天神社については、江戸時代、大和国岩掛城主・山田政秀の第六女、紀州家側室延寿院殿が守護神として祀っていたものが奉祀されたと伝えられているんやって
その後、明治33年、神社合併政策により、山谷301番地(現在の参宮橋駅の西)にあった掘出し稲荷と、新町三番地(現在の文化学園の西)にあった銀杏天神社がそれぞれ合祀
榛名社については、この地域で雨乞い豊作の祈願のために上州の榛名山まで参詣するという習慣があったことから、おそらく各村や家に祀られていた榛名社が、やがて氏神様である八幡宮の境内に移されたものと思われます
また、本殿の八幡宮の相殿として、やはり明治33年、山谷365番地(現在の代々木公園駐車場あたり)にあった天祖社と、同じく山谷139番地(現在の南新宿駅の北)にあった白山社が合祀
このため稲荷・天神・榛名社と両社を合せて祭礼を五社宮祭と称することになったんですね

出世稲荷社
第二次世界大戦の昭和20年(1945)5月25日夜、このあたりは米軍の空襲により大きな被害を受けたとか
幸い神社は焼け残ったが、周辺は一面焼野原となり、その焼跡には家々で祀っていた稲荷社の祠や神使の狐などが無惨な姿をさらしていたとか
それらを放置しておくのはもったいないと、有志の人々らが拾い集め、合祀したのがこの稲荷社の最初で戦災の記憶と平和の大切さを偲ぶよすがともなっているんです
出世や仕事運・商売繁盛などのご利益が強く、大物芸能人が、お参りしたら仕事が増えたという噂が広まり、一躍注目が集まったそうですよ

石燈籠
訣別の碑
現在の代々木公園がある場所(代々木深町)に、かつて陸軍練兵場ができるため移住した住民が別れを惜しんで訣別の言葉を刻み奉納した燈篭なんやって

神楽殿
今でも行事は行われてか…わからん

参集殿
此の宮神輿は、大正12年(1923)8月、渋谷区新町町会(現代々木3,4丁目)の有志により、千葉県行徳の神輿師の許で造られ、祭礼のたびごとに賑々しく町内を巡行していたが、人口の減少にともない、永久保存を願って昭和37年(1962)9月、代々木八幡宮の宮神輿として奉納
関東大震災、東京大空襲の二度の大災害を無事くぐり抜けてきたが、傷みがひどくなったため、平成3年(1991)12月、平成御大典並びに御鎮座780年祭を記念して、氏子崇敬者770名の奉賛(2千万円)により、板橋の東京神輿センターで約70年ぶりに全面的な解体修理が行われ、面目を一新して今日にいたっているんだとか

加曽利E式土器の時代
4畳半程の展示スペースには土器を作る妻のもとに、狩りを終えた夫が「ただいま」と帰ってきた様子が再現されていました
全身が土気色のうつろな目をした人形に目を奪われてしまいがちだが、注目すべきは、その手前に展示されている土器や石器
最も大きな土器は「埋甕炉(うめがめろ)」で、竪穴住居の炉に埋めて使われていたものとか
下半分がないのでこれを灰に埋めると五徳のように使えて便利だったのかもしれないよね
土器様式としては加曽利E式に見えるが、それ以前の勝坂式土器の名残のような眼鏡状の突起がついている
勝坂式土器は、縄文時代中期前半を代表する土器で、おもに中部高地から関東西部にかけて見ることが多いんやって
勝坂式土器は、縄文時代中期前半を代表する土器で、おもに中部高地から関東西部にかけて見ることが多いんやって
顔がついたり、蛇やカエルといった具象的なモチーフが踊ったり、何かがうごめいているような躍動的な印象を残す文様が特徴的とか
しかし、中期後半からの加曽利E式になると、勝坂式に見られた生命感はなりを潜め、口縁部と胴部が明確に分けられ、縄目の地紋に渦巻きやS字などのモチーフを配置したシンプルな土器が多くなったんやって
そこにどんな価値観の転換があったのかはわからないけどね
文様作りに変わる別のムーブメントが興ったのかもしれないし、あるいは土器作りにかけられる時間がなくなったのかもしれないよね

臼田亜浪の碑
『そのむかし 代々木の月の ほととぎす 亜浪』
臼田亜浪(1879〜1951)俳人
長野県出身、法政大学卒
大須賀乙字と俳誌『石楠(シャクナゲ)』を創刊して、高浜虚子らの俳誌『ホトトギス』に対抗
この碑は、その創刊二十周年を記念して昭和9年に建てられたものやって

東京都渋谷区代々木5-1-1

代々木八幡駅前にある
ドリアandグラタンのお店 なつめさんでランチ

メニュー数が多くて悩みまくる
ミート系、シーフード、あとは選べるトッピングもできるんやね
一番人気はシーフードドリアらしい
シンプルなドリアだけだと700円~と良いですね

人気No.1メニューのいろいろシーフードドリア 1485円にしたぁ
鉄板でやってきてグツグツとなっていて…触ると…火傷に…
サーモン、ホタテ、イカ、エビがチーズの海を泳いでましたぁ
すごく具だくさんなんです

口にいれるとチーズが口に広がって最高!
サーモンはチーズとの相性がめちゃ良いんやぁ
ホタテはかんだ瞬間…ブワァ~っとホタテ~が口に広がって爆弾のようでした
イカはとても柔らかく歯切れがよくドリアとの相性もバッチリやしぃ~
エビはもうぷりんぷりんで歯が弾かれますわぁ
しかもたくさん入ってるのでもったいぶらずに食べられます
とにかく具沢山で素材の質も高くとにかく美味しかったです
代々木八幡駅から114m
東京都渋谷区富ヶ谷1-53-2 レオマックビル 1F
代々木八幡駅から114m
東京都渋谷区富ヶ谷1-53-2 レオマックビル 1F