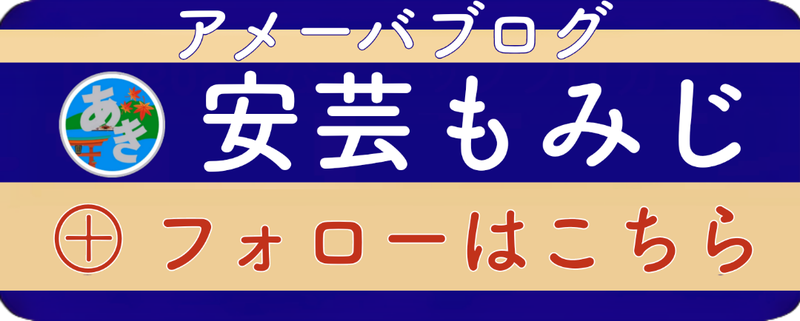JR貨物フェスティバル2023 -⑥
″JR貨物フェスティバル 2023 広島車両所公開″の最終回です。
最終回は広島専用機 = セノハチのシェルパをUPします。
汎用型のオールマイティ EF210形 300番台が量産化され、登坂後押し機関車はもう現れない種別です。
まずはEF67-1号機から。
1位側と2位側で顔立ちが違うのが特徴の機関車ですが、下関向きの顔立ちは非貫通形となっています。
日本最初の新性能機関車 EF60形の原形が色濃く遺るその顔立ちは、若かかりし頃の大スターが、老齢化して再ブレイクしたかのような装いに、いつも見えてしまいます(笑)
非貫通側には今年3月に迎えた、広島車両所80周年記念のヘットマークが掲げられていました。
そして貫通側の顔立ちには、新性能機関車の中で唯一のデッキを備える形状となっています。
EF65形やEF64形のように、通常は貫通扉があっても乗務員の乗降目的ではないため、横側には乗務員扉があります。
が、旧型電気機関車を見ると判るのですが、デッキのある機関車は貫通扉で乗降するので、車体側部には乗務員用乗降扉はありません。
またEF65形1000番台以降の顔立ちに似てはいますが、EF63形のHゴム化した顔立ち、もしくはEF62形に近いデザインです。
国鉄型機関車F級60番シリーズの中で、とても変わり種な最終形式の機関車です。
EF67-1号機の奥隣へチラホラ見え隠れしていた機関車は、こちらEF59形です。
広島車両所で保管されているのはEF59-21号機で、元々は戦前の希少種だったEF56形だった機関車なのですが、実はEF56形としては唯一の現存車でもあります。
山陽本線が電化されるにあたり、西の箱根とか西の碓氷峠などと呼ばれた鉄道の難所のために、登坂後押し専用機として誕生した、日本初の機関車がEF59形でした。
EF59形は戦前の直流機関車の名機だったEF53形全機と、EF56形5機から改造されて誕生した形式で、全24機が1963(昭和38)年から1972(昭和47)にかけて改造されました。
EF59形の本拠地である広島には、EF53形を種車とする機体は現存しませんが、群馬県の碓氷鉄道文化村にはEF53形種車のEF59-1号機と、EF59形から復元工事が施されたEF53-2号機が収蔵展示されています。
EF59形は下関側にはゼブラ塗装が施されていますが、これは後押し専用機と言うことで、岡山側には貨物列車の編成が連結されるための処置でした。
EF67形にはゼブラ塗装が行われていませんが、走りながら連結器を切り離すため、1~3号機には貫通扉とデッキが備えてありました。
尚、今年の展示では岡山側には車掌車のヨ8000形が連結されていましたが、この車掌車を1両単位で個室貸切できる、観光列車とかあったら是非!乗りたいですよね(笑)
こちらはEF67-105号機ですが、昨年3月のラストランで装着されたヘッドマークを着けての展示でした。
EF67形の100番台はEF65形のほぼ原型を保っていて、塗装デザイン以外にはあまり独自性は無い特徴を持っています。
これは走行中の貨車解放を行わず、必ず停車して切り離しをするために、貫通扉もデッキも装備されていません。
因みに現存していないのですが、EF59形とEF67形の間にはEF61形の200番台の形式がいたのですけれど、それが「ありがとう 後押専用機関車」のヘッドマークには描かれています。
EF61形200番台はヘッドライト1灯で貫通扉とデッキを装備した顔立ちで、国鉄標準色を纏っていました。
今となっては、1機も現存していないことが残念でならない機種ですが、セノハチ専用機3機種5タイプの内、唯一現存していない機関車です。
と言うことで、今年は鉄道貨物輸送150周年でしたが、広島車両所には全く居なかったため、京都鉄道博物館のEF65と蒸気機関車を貼りました。
EF67形0番台はEF60形後期型からの改造車で、EF67形100番台はEF65形からの改造です。
こうして見るとほぼほぼ原形なままなのがよく分かりますが、ブルトレ機と比べると地味さは拭えないものの、やはりEF65-1号機がここに居ることは素晴らしいと感じます。
蒸気機関車の9600形もD51形も貨物機としては永遠の名機で、特にD51形のニックネーム「デゴイチ」は、日本最大最速のC62形を抑えて、蒸気機関車の代名詞にもなっています。
さて、館内ではコンテナ特急たからのテールマークが普段は装着されているヨ5000形ですけど、こちらも鉄道貨物輸送150周年の記念マークが掲げられていました。
残念だったのは、EF65-1号機の記念マークが正規のヘッドマークではなく、シールによるマークだったところだけでしょうか(笑)
と言うことで、4年ぶりの開催となったJR貨物フェスティバル2023 広島車両所公開の記事を終わります。