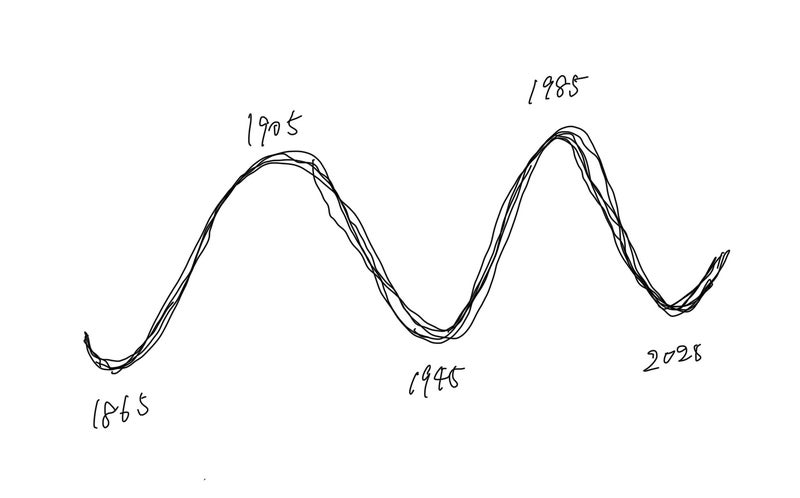太田茂氏が書かれた『新考・近衛文麿論』を読んだので感想を書いてみたいと思います。著者は元検察官で現在は弁護士をされている人で歴史研究の専門家ではないようですが、この本はかなり説得力のある力作になっていると思います。
この本は近衛の2回に及ぶ総理大臣の期間とその後の活動をこれまであまり知られてこなかった中国やアメリカに対する働きかけまでも網羅して近衛の政治活動を総合的に評価しており、著者は近衛について「悲劇の宰相」であり「最後の公家」だったと結論しています。
著者の太田氏が最初に近衛を批判しているのは、第一次内閣で日中戦争が勃発し、陸軍の状況からそれが拡大してしまったのはある意味止むを得なかったが、ドイツのトラウトマン工作により中国との戦争が解決できる可能性があったのに、この時は彼の性格の優柔不断さがもろに出てしまいその結果たいへんな好機を逃してしまったことだった。
「近衛が、一度政府が示した和平条件を釣り上げるようなことをすべきではないと腹を括り、蛮勇を奮って多田次長の参謀本部意見を支持することはできたはずだ。」
おそらくはこれが成功していれば果たして近衛がもう一度総理に返り咲くことがあったかは不明で後から振り返ってもこの時以上に中国との戦争を終わらせる機会があったかは疑問だった。
2回目に総理になった近衛はどうにか日中戦争を解決してアメリカと安定した関係を築こうとしたのだが、その努力は実らなかった。
ルーズベルトとの直接会談で中国からの撤兵などの懸案事項を解決しようとしたが相手が乗り気ではなく、それが実現しなくなった後でも近衛は東條に対して執拗に中国からの撤兵を説いた。それに関して太田氏は「近衛の東條への説得の努力は鬼気迫るものがあったと言って良い」と評価されています。
しかしながら当時の憲法上の制約もあって東條への説得が閣内の不一致を招き内閣が瓦解することになったが、この時の彼の必死の活躍は日本の歴史にとって軍国主義一本ではなかったことの十分な証明になると私は思っています。
真珠湾攻撃が起こった日である12月8日、他の人々が勝利に湧いている中で近衛だけが「えらいことになった。僕は悲惨な敗北を実感する」と正確に将来を見通していた。また彼はいち早く戦争を終わらせようと努力し天皇に対して上奏することによって危機感を伝えるようなことも行った。
また日本の敗北が近づくにつれ日本政府や陸海軍の幹部は甘い見通しでソ連に助けを求めるようなことをしていたが、近衛はこれについても反対だった。
このようにアメリカとの戦争になってからの彼の判断と行動力は今から見ても賞賛に値する。ところが彼は日本が敗れた後で憲法改正の事業に取り組むことになるのだが、著者の太田氏はこの行動について違和感があるという。
日中戦争から対米戦まで近衛に全ての責任があるとは言わないが、やはりそれなりの責任はあるわけでどんなに政界復帰の要望があったとしてもそれを断るべきだったとする太田氏の主張に私も同感だ。結局そのことが近衛を自死に追いやることにもなったのです。
先の大戦を考える上で、この本は近衛の存在の重要性を再確認させてくれるものでした。