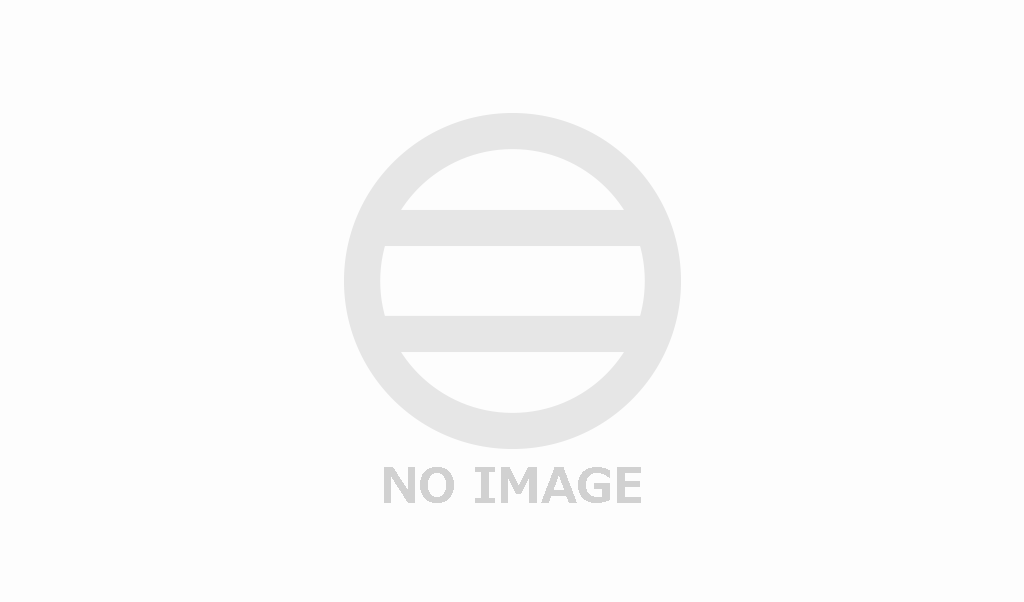2025年1月末、やっと家族で初詣に出かけることが出来ました。
もう何度も書いたのですが、今年は元日から夫と2人でコロナになってしまい、初詣でどころではありませんでした。
毎年家族で川越に初詣に行くのが年中行事でしたが、いろいろな条件が揃ったのが1月末でした。
初詣はいつまでに行くものなのか心配になりましたが、病気だもの仕方ない。
ネットで調べたけれど、関東は松の内に行くのが良いと言われているそうです。
それがだめなら小正月、それでもだめなら節分まで…。
松の内はだいぶ過ぎてしまいましたが、家族3人が元気になったところで同行者(夫)と母と3人そろって、川越を訪ねることにしました。
喜多院(川越大師)
お正月はとんでもなく混んでいるのですが、さすがにガラガラでした。
これならお願い事が、お大師様の耳によーく届くのではないかなどと勝手な事を思ってしまいました。
気づくと、たくさんのバンや軽トラなどが境内に入っていました。
そうか、三が日に隙間なく並んでいる出店も撤収なんですね。
ちょっと不思議な気持ちになりました。
本堂の脇にあったお巡りさんが立っている台なども撤去されていました。
慈眼堂の石畳があみだくじっぽい。
仙波東照宮
この日は残念ながらお休みでした。
駿府城で亡くなり、久能山に葬られた徳川家康を、日光山に改葬する途中、4日間喜多院に留めて法要をしたそうです。
それで「仙波東照宮」が造られたのですね。
当時の建物は1638年(寛永15年)の川越大火で焼失したため、徳川家光公の命により再建されました。
現在の社殿は、1640年(寛永17年)に完成したものです。
いつも人がすごすぎて、あまり周りは見ていないのですが、気になる場所がありました。
「葵庭園」と看板がありました。
赤い橋があるのはなんとなく知っていましたが、木道の様なものがあって、池まで入れるとは知りませんでした。
カモがたくさんいました。
何十年もここに来ているけど、ここから見上げたのは初めてでした。
ほとんど撤収されたお店の中で、派手派手なこのお店は元気に営業中でした。
あ、母は足が痛むので、暖かい場所で休憩中。
私たち二人で散策しています。
この中は、川越市指定史跡「五百羅漢」。
1782年(天明2年)から1825年(文政8年)の約50年間かけて建立されました。
全部で538体の羅漢様が鎮座しているとのことです。
1月3日は、川越大師のだるま市。
その時は、この境内に数えきれないくらいのだるま屋さんが立ち並ぶのですが、この日は数軒が出店しているだけでした。
こちら埼玉県指定有形文化財の「多宝塔」です。
お参りを済ませると、すぐ近くにある「成田山川越別院」へ。
こちらも、静かでびっくりです。
あ!花手水発見。
和風で綺麗です。
カメさん達が、日影で固まっていました。
がんばれー!
川越銘菓といえばの「くらづくり本舗」にやってきました。

どらやきを買うつもりが、試食で出してくれた「あわ大福」がおいしかったので両方購入。
三が日だとものすごく混んでいて、試食どころではないのですが、今日はゆったり。
良いお土産も買えてよかったです。
さて、これから蔵造りの町並みを歩き、一番の課題、「お昼ごはん」です。
果たして母が気に入る食事をとることが出来るのか。
ドキドキですね(笑)
長くなりましたので、そのあたりはまた次回。
またご覧いただけたらうれしいです。
ランキングに参加しています。
下の「東京情報」のボタンを押して頂けると、明日からまたがんばれます!