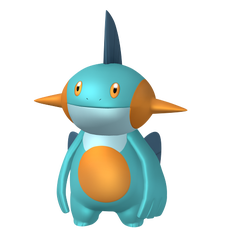娘のテストの待ち時間に『博物館の少女 騒がしい幽霊』を読みました。
一冊目はこちら。
娘は塾の勉強で明治時代を終えたので、前号よりは時代背景が分かるようになりました。(舞台は明治16、7年くらいです。)
主人公は変わらず、博物館の仕事を手伝う少女イカル。探偵にあたる歴史学者のトノサマ、密偵役の少年アキラ、絵師の娘トヨなどがレギュラー。
今回のお話は、イカルが陸軍の大物・大山巌と捨松夫妻の娘たちの家庭教師を仰せつかる事から始まります。
山川捨松と言えば、歴史のお勉強的には「津田梅子らと共に女子初の留学生として渡米。帰国後、大山巌と結婚。語学やダンスの腕前を生かして『鹿鳴館の花』と謳われた」ぐらい知っていれば合格です💮
しかし、彼女はかなりドラマティックな人生を歩んだ女性です。
捨松が使節団に参加したのは満11歳。わー、うちの娘より幼いのか![]()
あの時代、10歳前後の娘を海外に10年も留学させるって、どんな親?
北海道開拓使が募った最初の女子留学生に応募したのは、主に「維新で負けた側の士族の娘たち」だったそうです。
捨松は会津藩の家老の家に生まれ、7歳ぐらいで会津戦争の鶴ヶ城籠城を経験しています。作中でも、この戦で死んだ義姉の幽霊が出た、という描写があります。会津藩が青森下北半島の斗南藩に転封させられた後、北海道の宣教師に預けられたそうです。先に留学生となっていた兄に続き、希望者の少なかった女子留学生となりました。母は、元の「さき」を「捨松」に改名させ、彼女を送り出します。名前に「捨てる」を付けるのは、邪気を払う意味もありますが、海外へ捨てる気持ちで送り出し、でも「待っている」という気持ちを込めた改名なんでしょうね。
約10年の留学を経て、英語やフランス語が堪能になって帰国しましたが、日本語の読み書きが不自由なこともあり望むような教育の仕事に付く事が出来ませんでした。「嫁」としても当時の常識では微妙な彼女に、先妻を亡くした大山巌がプロポーズ。大山は西洋文化にリスペクトがあり、彼女とフランス語で会話することができたそうです。
しかし、薩摩藩出身の重鎮と、会津の家老の家の娘の結婚は、どちら側の支援者からも反発を受けます。大山には先妻との間に3人の娘がおり、実際には捨松は彼女たちを可愛がっていたそうですが、長女信子が嫁ぎ先から肺病で出戻った際に「継子いじめ」をしたという風評が立ちます。原因は徳富蘆花の新聞小説『不如帰』。(この長女信子は、『博物館の少女 騒がしい幽霊』で、イカルが家庭教師をする少女として登場します。)家庭を大切にする捨松は、かなり辛い思いをしたはずです。
「海外で学んだ才覚のある女性」というだけでなく、その生い立ち、妻として母としていろいろな葛藤を抱えていたであろう山川捨松の生涯を考えさせられる一冊でした。
ミステリーとしての『博物館の少女』は、1冊目に続き、探偵役が解き明かす謎もあれば、「科学で解明されない」謎もあるという終わり方をします。今回は「御景鏡」という古い鏡が、死者の霊を写す”オカルトアイテム”でした。
イカルちゃんの大阪弁の明るさが光る本シリーズ、まだまだ続きそうです。