明智家の家紋は、よく知られている桔梗紋です。
桔梗紋は、見てのとおり桔梗の花がデザイン化
された家紋です。
桔梗は秋の七草のひとつで、万葉集に山上憶良が
詠んだ「萩の花 尾花葛花 なでしこの花
をみなへし また藤袴 朝貌(あさがお)の花」
という歌の「朝貌」が桔梗のことだそうです。
最古の漢和辞典「新撰字鏡」(901年ごろ)の桔梗の
説明には「阿佐加保(アサカホ)」という字が
あてられています。
桔梗の花が家紋になったのは、平安時代末期から
鎌倉時代初期の武人、土岐光衡(ときみつひら)に
由来します。
美濃源氏嫡流で土岐氏の祖といわれる光衡は
ある戦におもむく際に、野に咲いていた一輪の
桔梗の花を兜の前立に挿して戦ったところ
大勝利を得ました。
戦いが終わった後も桔梗の花は前立から
落ちておらず、生き生きとした姿をたもったまま
綺麗に咲いていたそうです。
このことから縁起が佳い花として、土岐氏の
家紋となりました。
桔梗という名が「更に吉(よし)」という音に通じる
語呂合わせだとも言われています。
また、桔梗は「岡に咲く神草」という意味で
「岡止々支」(オカトトキ)とも呼ばれます。
土岐氏が本拠とした土岐の地名は、このトトキの
咲くところから生まれたという説もあります。
桔梗紋は優雅な花の形が好まれ、土岐氏以外の
家にも使われるようになっていきました。
最初にできたオリジナルの桔梗紋の他に、
江戸期に入ると土岐氏のみが使う「土岐桔梗」
という紋もできました。
土岐氏の桔梗紋は「水色桔梗」という彩色紋として
有名です。
『太平記』の一説に、土岐悪五郎の「水色の
笠符吹流させ」とあるのが水色桔梗に関する最初の
記述だといわれています。
この彩色紋というのはとてもめずらしく、色を付けた
きっかけは源氏の一流である土岐氏が嫡流の
白色をはばかって幕を水色に染め、家紋も水色に
染めたことからはじまったという説があります。
また、水色に染められた生地に家紋が白抜き
されていた、もしくは黒で家紋が描かれていたので
水色桔梗と呼ばれるようになったという説もあり、
どちらが正しいのかわたしには判断できかねます。
最近の研究では「水色」というのは現代の
水色ではなく、土岐氏の家祖である源頼光の官位
「正四位」を表す色「浅紫」であるのではないかと
されています。
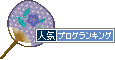
人気ブログランキングへ



