ノーベル賞は個人や組織に与えられるものであって、国に与えるものではありませんが、同じ国で生まれ育った人たちが名誉ある賞を受けたことは素直に喜びたいと思います!
10月6日付の読売新聞で詳しい記事を読んだのですが、医学生理学賞を受賞した大村智先生のインタビューにはとても和むものがありました。
先生は微生物のおかげでノーベル賞を受賞できたのだから、「私より微生物に賞を」あげたいというのです。
「日本では微生物を世の中のために使う伝統があり、そういう環境に生まれて良かった」という言葉もなるほどと思いました。
すぐ思い浮かぶだけでも、酒、みそ、しょうゆ、納豆、いろいろな伝統食材に微生物の恩恵が及んでいますね。そして、思い出したマンガがあったのです。
それが、今回紹介する「もやしもん」(作:石川雅之 講談社)。
この作品は、種麹屋の次男坊である沢木惣右衛門 保(さわき そうえもん ただやす)が主人公で、菌とウイルスにまつわる様々な騒動が展開していくのです。
直保は生まれつき、菌やウィルスを視認し会話ができるという不思議な能力を持っています。幼馴染の結城蛍(ゆうき けい)とともに、祖父の友人が教授を務める「某農業大学」へと入学し、個性的なメンバーと出会いながら、菌とウイルスに関わる話が広がっていきます。
蛍は男性ですが、なぜかゴシックロリータの服装でいつも過ごしています。また、菌やウイルスもキャラクター化されて登場しますが、蛍のゴスロリファッションと相俟って、作品を引き立てています。
マンガ「もやしもん」は2004年に『イブニング』(講談社)で連載が開始され、のちに『月刊モーニングtwo』(同)に移籍し昨年最終回を迎えました。
僕は「もやしもん」を読むようになって、日本の醸造文化の奥行きの広さを改めて感じました。特に地域色豊かなみその多様性に打たれました。全国各地に実にいろいろなみそがあるんですね!
みそ一つとっても、まさに先述の「微生物を世の中のために使う伝統」に満ち溢れています。
あなたも今回の大村先生のノーベル賞受賞を機会に「もやしもん」をひも解いてはいかが(^-^)
下の画像に菌やウイルスのキャラクターが表示されていますよ
もやしもん(1)+ (講談社プラチナコミックス)/講談社
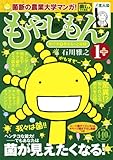
¥440
Amazon.co.jp