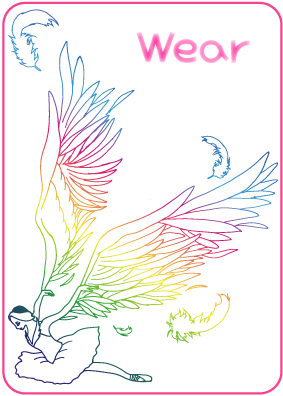【Leg Spring Series on the Trapeze Table レッグ スプリング シリーズ オン ザ トラピーズ テーブル】
脚から足———爪先まで伸びる強い下肢を作り、体幹安定性が向上するエクササイズです。
腕力も必要なので、腕も鍛えられちゃいます♪
クライアントさんにこのエクササイズをやっていただくにあたり、よくある現象は下記のようなものです。
1. 「腕でタワーが押せない」
2. 「足首から爪先まで伸ばすことができない(足首がフレックスのまま、ストラップから足が抜けそうになってしまう)」
対処法を考えてみましょう。
1. 「腕でタワーが押せない」
なぜ押せないのでしょうか?
私達の身体は、日頃やっていることしかできません。
「やっていないのにできる」ということはないのです。
ということは、「押せない」ということは…、普段「何かを押す」という行為をしていないのです。
「何かを押す動作」は普遍的・日常的な行為のように思えます。
しかし「最近力を込めて何かを押した行為を思い出してみて」と言われると、案外出てこないものです。
肉体労働などに縁がない生活をしていれば、別に何かを押すことなく日々は過ぎていきます。
そうやっていつのまにか、我々の全身の筋力は衰えていきます![]()
そしてこのようなエクササイズをやってみて、自分の身体が何かを押すための筋力が発揮できない状態であることを、初めて知るのです![]()
筋力がなくても生きていける高度な社会で生活をしてはいますが、ロコモティブシンドローム(運動器障害・機能低下)によるQOL(生活の質)低下は辛いです。
Leg Spring Seriesができるくらいには、押すための筋力が欲しいものです。
ピラティスマシンがなくても、お家でできることはたくさんあります。
仰向けで壁を押す、立位でも壁を押すなど。
相撲のテッポウを家でされる方は、ほぼいらっしゃらないですよね![]()
そう考えると、日常生活のみでは「押す」という行為に意外と縁遠いことが分かってきます。
手で何かを押す力の源は、背筋にあります![]()
腕で強く何かを押せるようになると、背筋が発達し綺麗な背中になります✨
さて、改めて「腕でタワーが押せない」という現象を考えてみましょう。
なぜ押せないのか?
筋力がないから?
答えは…「押していないから」です![]()
それほど「押す」という行為、あらゆる「筋力を発揮する」という行為は難しいのです。
幼い頃から身体操作を磨いてきたような少数の方を除いて、身体を鍛えたことがない、ただ状況に流されながら今現在に至っている方は多いです。
そのような方々にとって、「押す」という能動的/Activeな行為は難しいのです。
受動的/Passiveでいる経験しか過去にないからです。
「動作とは己の身体を攻略して行うもの、切磋琢磨して身につけるもの」という、一般的にもごく当たり前と思われるような前提にさえ、実際には辿り着けないのです。
「先生は力を入れているように見えないのに、なんでできないんでしょうか?」とよく言われます。
できない動きがあると「筋力がないから」などと考えがちですが、それ以前に「やっていない/やろうとしていないから」というのが最も根本的な原因になります。
受動的/Passiveでいる経験しかない方は、身体操作というのは勝手に無意識に行っているもので、それ以上の世界を知りません。
できない何かをできるようになるためには、その動作に対して、意識的/能動的になる必要があるのです。
まずそれを知ってください![]()
動作というのは勝手に/無意識でできる領域だけではなく、その先に進むためには、自分が意識的/能動的/Activeにならなければいけない、ということを![]()
己の意思を持たなければならないのです![]()
「押せない」時、「押していない」ことがほとんどです。
押せるようになるためには、意思を持って「押し」ましょう![]()
「押す」という行為を意識的に、自覚的に、能動的に行うのです。
「押す」とはどういうことなのか、考えてみましょう。やってみましょう。
そうすると実際に家の壁を押してみたくなったりするかもしれません。
そうやって筋力をつける第一歩を踏み出してください。
「先生は力を入れているように見えないのに、なんでできないんでしょうか?」
↑これは「動作とは、受動的/Passive/勝手に/力を入れずに/無意識でできるもの」という前提に立っている発言です。
筋力トレーニングに来ているのに、依拠している立ち位置・根本的な考え方が誤っているのです。
まずそこから正さなくてはなりません。
私がこの動作をできるのは、押しているからです。
あなたがこの動作をできないのは、押していないからです。
私はこの動作を、能動的/Active/力を入れて/意識的に行っているから、できるのです。
力は入れなければいけません。
無意識ではできません。
どうしたらできるようになるのか他人に訊ねるだけでなく、自分の頭でよく考えてみましょう。
まずは押しましょう![]()
2. 「足首から爪先まで伸ばすことができない(足首がフレックスのまま、ストラップから足が抜けそうになってしまう)」
こちらもよくある現象です。
日常生活のみでは、足首を最終可動域まで底屈(伸ばす・ポイント)させる機会がないので、足首を伸ばすことができなくなっている方は多いです。
関節可動性が低下すると、足部は特に転倒の原因になりやすいです。
固まった関節では、バランスを失った時にそれを取り戻せません。
爪先まで伸びるしなやかな下腿、力強い足の裏の筋力を身に付けたいものです。
これもお家でできることはたくさんあります。
立位で壁などに軽く手をつきながら、ゆっくりゆっくり踵を上下させましょう。
床に対して足の甲が垂直になるまで踵を上げます。
【Standing Heel Raises スタンディング ヒール レイズ/Releve ルルヴェ】
慣れてきたら、片足ずつでもできるように![]()
お年寄りになっても、片足立ちバランスキープを目指しましょう![]()
今できないことが、お年寄りになってできるようになる可能性は低いです。
今できないことは、お年寄りになるとますますできなくなります。
筋トレは1日でも早く、1日でも若いうちに始めましょう。
長座で足首のポイント・フレックスを繰り返すなども、足首の可動域を大きくする練習になります。
爪先までしっかり伸ばしましょう![]()
足の裏が攣りそうになれば効いている証拠です。
攣るほどがんばれている時はよろこび、足を褒めましょう![]()
【Variations ヴァリエーション】
Scissors シザーズ:鋏
Circles サークルズ:円
Frogs フロッグス:カエル足
Frog Kick フロッグ・キック:カエル足キック
Walking ウォーキング:歩行
Bicycle バイシクル:自転車
腹筋群・背筋群の強化
上肢・下肢(特にハムストリングス〜足裏)の筋力強化
肩甲帯の安定性 Shoulder Girdle Organization↑
体幹安定性の向上 Trunk Stability↑
爪先までの足の意識↑
【楽曲】
Ballet Class Music
5. Rond De Jambe A Terre
13. Adagio
8. Developpe
by Iraida Minkus
いつも素敵な曲をありがとうございます![]()