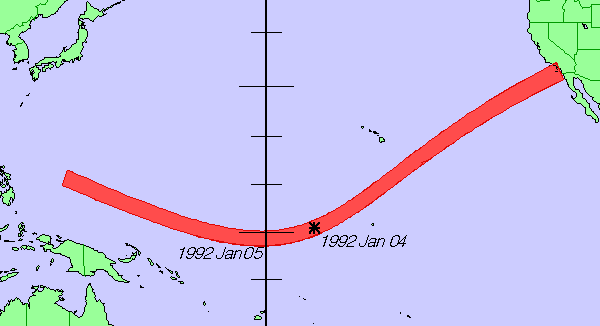
これは、1991年12月28日~1992年1月12日にかけて日食情報センターのW氏が撮影した記録です。
最初は羽田空港からグアムまで飛ぶ予定だったらしいのですが、航空券が年末年始のため予約出来ず、急遽韓国のソウル経由でグアム入りをしました。グァムからキリバスの首都タラワに着き、YS機で真円の金環日食が見られるダビデウェア北島(North Tabiteuea)に行きました。各島を巡るのに1日1便なので、1日掛かりでフライトしたそうです
。YS機の故障や荷物が多すぎて、空港内に預からざるを得ない欧州組もいたらしい。真円の金環日食が見られるキリバスのダビデウェア北島には、1月4日の昼頃に到着したそうです。

この金環日食帯は日付変更線をまたぐので、私が観測しに行ったL.A沖のサンタカタリーナ島では1月4日に金環日食現象が起こるのですが、日本では1月5日早朝に部分日食として日の出部分日食を待ち構えるカメラマンが多数いたそうです。キリバスのダビデウェア北島では、日付変更線の西側に位置していたので1月5日に金環日食が見られることになります。1988年から日食の中心帯を目指して行ったのですが、その当時は日食情報センターとの接点がありませんでした。まだネットが普及する前の時代なので、情報量が限られてツアー会社のツアーに参加せざるを得なかったのです。L.A沖のサンタカタリーナ島では部分日食から曇られてしまい、全ての経過を見ることが出来ませんでした。同じ頃、サンジエゴの海岸沿いでは日没金環日食が見られたので以下に参考映像を掲載します。
この金環日食は、11分41秒も継続したsaros №141系列に属します。
長い継続時間の金環日食は1月3日を中心に分布しています。これは1月3日が平均の近日点日で、太陽の視直径が最も大さくなる日です。これは、月の見かけの直径が小さい時におきます。皆既の場合とは正反対の条件です。長い金環日食は、環の幅が広くなって周囲もそれほど暗くならず、ベイリービーズを見ることも難しくなります。以下の画像は、日食情報センターのW氏が撮影した記録です。
結果的に雨中の雲間から撮影となったのですが、金環継続時間が長かったので見られました。これが短い継続時間だったら、今年の巴里坤皆既日食のような悲劇となったでしょう。前述の欧州隊は飛行機の故障や雨天などで観測地まで辿りつけず、キリバスの首都タラワで部分日食の観測となったそうです。
また日食情報センター会員の帰途ですが、金環日食の翌々日はキリバスの首都タラワに着いたそうです。
その後、台風接近によりグァムまで飛行機が飛ばず4日ほど足止めを食らったそうです。キリバスではYS機に乗らざるを得ないので、少人数の5名で参加。自費ツアーで行かれたそうで、一般には帰国後に詳細が1992年発行の“星の手帖”春号などで報告されました。この天文誌は1978年夏号で創刊、1993年春号に休刊するまで、15年間60号発行された季刊誌です。
ちなみに、以下のツアー会社が来年1月26日にスマトラ島で見られる金環日食観測ツアーを予定しています。
1/24出発-1/28帰国 ツアー代 109,800+燃油サーチャージ 42,600+成田空港使用料 2040=154,440円
他にインドネシア空港税 150000ルピア(日本円で1215円)+インドネシアビザ 10$
1/24出発-1/28帰国 ツアー代 199,000+燃油サーチャージ 42,600+成田空港使用料 2040=243,640円
他にインドネシア空港税 150000ルピア(日本円で1215円)+インドネシアビザ 10$
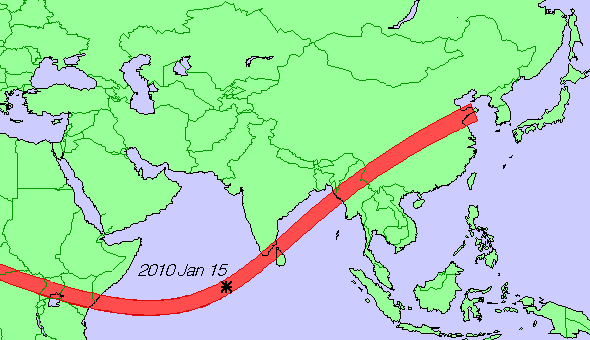
最後に1992年1月4日に見られたキリバス極太金環日食の1サロス後は、再来年の1月15日に起こります。モルジブやスリランカ北部で見られます。モルジブの首都マレでは真円の金環日食は見られないものの、10分46秒も継続する金環日食が見られます。
この極太金環日食は、AC2001年からAC3000年の間で最も長く見られるものです。正午中心食の海上では、11分 8秒も継続時間があります。但し最大接触でも95%しか欠けないので、減光フィルターを付けて観測します。
私は、中国山東半島の青島沖で日没金環日食に再挑戦する予定です。日没近いと金星などの内惑星が見やすくなる上に、金環と金星の位置がとても近くなります。太陽は西南西方向に沈むので、南が海で開けている青島近郊の海岸は絶景の撮影ポイントだと思っています。
下図のシュミレーション画像は、ステラナビゲーター6から作成したものです。5度の範囲内に太陽と月と金星が納まっているので、500mmの望遠レンズでも一緒に撮影が出来ます。青島での金環継続時間は7分14秒ほど。日没でも太陽はかなり明るいのですが、早いシャッタースピードなら減光フィルター無しでも撮影が可能です。デジカメで撮られる方は、液晶ファインダー越しに見ると観測しやすいです。1/8000秒程度のシャッタースピードが必要となります。
