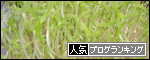昨日、埼玉県北部の市、行田市の工藤市長と面会してきました。
ことの始まりは12日、月曜日にかかってきた一本の電話です。行田市農政課のM様からでした。
「市長が行田在来から育てたもやしの新聞記事 を読んで興味をもたれた。そして私ども(農政課)にもやしでの行田在来の普及を示唆された。まずは一度、飯塚さんにお会いしたいし、もやしを見てみたい」
といった内容でした。そして昨日、収穫したばかりの行田在来もやしを持って私は行田市役所 へ伺ったのでした。
・・・・・・・・・・・
午後1時半、まずは環境経済部農政課で主幹であるM様と対面、課長のK様、環境経済部長のM様をご紹介され、その場で私が持参したもやしの試食が始まります。レンジで軽く加熱したものをそのままみなさま試食なさいました。
「おお。豆がいけますね・・」
「うん。うまい。」
「まるでもやしと別物だ・・」
「ビール飲みたくなるなぁ(笑)」
といった声が上がります。しばしもやしについての話をした後に、皆で市長室へ向かいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ようこそお出でくださいました。どうぞこちらへ」
と工藤市長が気さくに迎えてくれました。早速先ほどと同じ、レンジで調理された行田在来もやしが運ばれ、市長が試食されます。
「ああ・・・うん・・・へえ・・これは美味いね」
と、その行田在来大豆の力、味わいに驚かれました。そして市長室で今後の行田市の取り組む方向性について語られます。工藤市長は国産大豆の低い自給率にも触れつつ、
「私は農政に力をいれたいのです。そして先日、飯塚さんが行田在来の大豆でもやしを栽培した記事を読んで嬉しかった。是非とも行田在来もやしのブランド化にご協力願いたい」
とおっしゃりました。私は、
「わかりました」
と応えました。そして私の経験から、現在食べる人は野菜に何を求めているのか、いかに行田在来もやしがその中で訴求できるか、といったことを新メニューも含めた上で市長に話しました。
この県産在来大豆もやしには「正しい食の広がり」という大きな可能性が感じられます。「正しさの広がり」のためには、とことんその正しさ従って行動していきたいと思います。
市長は今後の普及のための方向性をある程度まとめて、環境経済部農政課のお三方に号令をかけました。
・・・・・・・・・・・・・・
「これからこのもやしを持って営業に行ってきます」
帰り際、実質的なパイプ役となる農政課主幹のM様がそう話しました。M様の手には私が渡した「行田在来大豆もやし」があります。その言葉の強さから何か熱いうねりが感じられました。
・・・・・・・・・・・・
会社に戻り、もやし栽培室「ムロ」に入ります。そこには今やさまざまな種類の豆がもやしにならんとしています。
従来の
「ブラックマッペ」
「緑豆」
を筆頭に、
「借金なし」
「行田在来」
「箕田在来」
「鳩山在来」
「こさまめ(地元の豆)」
「茶豆」
「花園在来」
・・・これらの豆の発芽を眺めてふと考えます。
このもやしたちの正しき育ち方のように、町(自治体)、作り手(農)、食べ手(消費者)、売り手(商)が正しく伸びていければ・・・と。
県産大豆もやしにもっとも早く響いた行田市の情熱はその正しき成長のさきがけになるかも知れません。