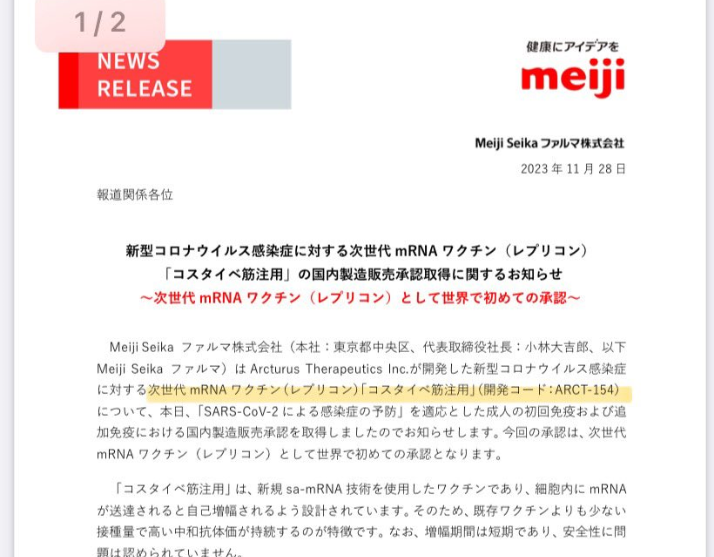去年自然の畑で稲刈りした御米を、干しっぱなしにしていたよ。
脱穀って人力でやれるんだっけ?
今月は予定がパツパツで、全くよゆーが無いんだけど、なんとかして食べたいな。
主食の米を作れれば安心できるんだけど、まだまだ無理っぽいので、イネ科の野草をアレコレ試食した。
不味くはない、たぶん栄養はある。
でも腹いっぱいにはならんな。
ちゅーことで、
岡本よりたかさんのFacebookより転載させていただきます。
いつもありがとうございます。
⇩⇩⇩
「陸稲(おかぼ)」
縄文時代の後期には稲作はあったらしい。しかも水田稲作の技術である。
しかし縄文時代には水田稲作を行なっていない。
理由は様々だろうが、主な理由は、温暖な気候で、わざわざ灌漑工事をしてまで、主食でもない稲作をやる必要がなかったという事だろう。
稲作を全くやっていなかったわけではなく、畑では稲作はしていた。それを陸稲(おかぼ)という。
水の恩恵を受けていた縄文人。今よりも海水面は高く、平野部は少なかった。目の前が海、後ろは山、それを繋ぐ川。
海で海藻を採り、川で魚と貝を採り、山で山菜と木の実を採る。冬は獣を捕らえて保存食にする。
そんな生き方をしていれば、大変な水田稲作などやらなくてもいいわけだ。
その上、水の恩恵を受けている以上、水の神様を怒らせる事はしたくない。川の流れを変え、山の水の流れを変える事は、神への冒涜とも言える。
水の流れを変えた影響で、今の恵みが得られなくなることを恐れていたのでなかろうか。
弥生時代に入り、気候が変わって、今までのような恵みを得られなくなって初めて、水田稲作を始めるのだが、案の定問題が起きる。
水争い。
水をたくさん得た者が豊作となる。土地をたくさん得た者が豊作となる。豊作となれば食料を保管し、"溜め込む"ことが貧富の差を生み出す。
そして、当たり前のように殺し合いが始まるわけだ。
結局、人は食料を得て、その食料を溜め込むことで安心を得る。今に置き換えるならお金だ。
お金をたくさん得て、それを溜め込むという行為は、たくさんの食料を抱え込むことと同意である。
なぜだろう。人は溜め込むと、他人にそれを分け与えることを拒み始める。溜め込んだ物が自分の身体のように思い、与える事は身を切ることと同意となる。
なんとも淺ましい話ではないだろうか。
僕は、水の引けない田んぼで陸稲を作ってみている。水を引こうと思えばできない事はない。しかし、今まで何十年も田んぼをやっていなかった場所で、いきなり大量の水を引き込むと、下流の人たちの反感を買うだろう。
権利はあるのだから、気にする事はないのだが、なぜか納得できない。弥生時代のように争いの種を蒔きたくないのだ。
だからこそ、縄文時代に想いを馳せて、縄文式で稲作をやってみる。
陸稲。おかぼ。りくとう。
水を使わずに稲作ができるなら、それこそ食料の自給に最も近くなる。
所詮、水田稲作は、食料危機の時にはなんの役にも立たなくなるだろう。誰もが水を欲しがり、奪い合うことになり、争いになるから。
それよりも、まるで草木のように育てる食料。その知恵と知識と技術と経験を身につけておいた方が、きっといつか役に立つ。
僕はそう思って、陸稲をやってみているのである。
先着50名さま⇩無料ですよ!
表紙と挿絵を描かせていただきました↓↓
表紙と挿絵を描かせていただきました↓↓
表紙と挿絵を描かせていただきました↓↓
表紙と挿絵を描かせていただきました↓↓
こちらから予約できます↓
野草を摘んで調理して食べるワークショップです。
簡単手抜き料理しか作らないです。
え?