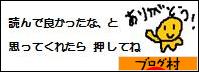日本人ノーベル賞受賞に沸く陰にゆとり教育などで国家の活力奪れ将来の人材出現に危惧が
ノーベル物理学賞、青色LEDの革命
2014年のノーベル賞受賞者が7日に発表され、青色発光ダイオード(LED)を発明し、照明の世界に革..........
≪続きを読む≫
(記事↑をご覧ください)
この記事にも「スウェーデン王立科学アカデミーは、電気のない生活を送る世界中の15億超の人々にLEDが光をもたらすと期待している。」とあります様に、世界的にLED特に青色ダイオードの発明などが物理学上において大きな貢献をされたという事で日本人としても大変誇らしい受賞であるわけです
ただ、三人受賞者のインタビューでも最近大学生が勉強しなくなっている、とか
物理を専攻する学生が極端に減っている等と、将来の日本からのノーベル賞の受賞において暗雲がある事が語られています。
そのお言葉を立証するかのように日本の教育の低下が世界的に見ても著しい状況になってきているわけです
その元凶の具体例として「ゆとり教育」が問題視されています
まずは、国際派日本人養成講座から気になります記事を転載させて頂きます
教育再生 第3部 「ゆとり教育」が奪う「生きる力」
(1) 学力崩壊が階級社会を招く
「結果の平等」思想は、貧しい家庭の子どもたちの自己実現の機会を奪い、愚民として平等化することである。
■ 転送歓迎 ■■
■1.Machine says so.■
教育社会学専攻の藤田英典・東京大学教授が、ペンシルバニア大学の客員教授として、フィラデルフィアに滞在していた1983-4年頃の事である。ある日、インド人の同僚と昼食にハンバーガー・ショップに行った。ベーコン・チーズ・バーガーとスモール・サラダ・バーとコーヒーを注文すると、女の子がレジに注文を打ち込み、1ドル39セントだと言う。
教授はびっくりして、「ベーコン・チーズ・バーガーが1ドル59セントでしょ。それにスモール・サラダ・バーとコーヒーだよ。それで1ドル39セントなの? 税込みで3ドル9セントじゃないの?」と言うと、女の子は、レジをもう一度、打ち直し、再び「1ドル39セント」だと言う。もう一度繰り返して言っても、「機械がそう言っている。 Machine says so.」としか、答えない。
そうこうしている内に、教授の後ろには、5、6人の行列ができてしまった。店のマスターが出てきて、教授から事情を聞き、自分でレジに打ち込むと、やはり同じ答えが返ってくる。マスターはレジに鍵をかけて、女の子には他の機械を使うように言い、カウンターの隅で紙の上に計算を始めた。一の位から順々に計算していくので、もどかしい位に時間がかかったが、ようやく教授の暗算通り3ドル9セントという数字に達した。
一緒に店に入ったインド人の同僚は、もうハンバーガーを半分ほど食べ終えていた。彼は「インドでもこういう事はない。アメリカの学校は、3R's(読み、reading、書き、writing、算数、arithmetic、の基礎学力)の教育をいいかげんにしているからだ」と言った。[1,p60]
■2.教育再建による『強いアメリカ』の復活■
このような光景が、何年かしたら、日本でも広まるかもしれない。アメリカで80年代に問題となった学力崩壊現象が、今や日本でも起きつつあるからだ。その後、アメリカではこの反省から学力重視の教育改革が進められているが、現代の日本では、その失敗を参考にすることもなく「ゆとり」教育が進められている。現代日本の学力崩壊を考える前に、まずアメリカでの前例を概観しておこう。
アメリカでは60年代以降、特に高校で「暴力学園」化が問題となり、押しつけ的で画一的な公立学校のあり方に原因があるとされた。70年代には「学校の人間化」がスローガンとされ、カリキュラムを選択制にして、自動車の整備や、各種ボランティア活動などを単位として認める高校が増えた。
その結果、冒頭のエピソードに見られたように青少年の基礎的学力の低下が顕著となり、1983年、レーガン政権のもとで、レポート「危機に立つ国家、Nationat Risk」が刊行された。その中では、次のような問題提起がなされている。
・ 17歳人口の約13%は、機能的識字能力(社会的自立に必要な読み書き能力)に欠けており、その割合はマイノリティ(黒人その他の少数民族)では40%にも達している。
・ 大学入試委員会の進学適性テスト(SAT)の平均得点は、1963年から1980年まで一貫して低下している。
・ 全国の公立4年生大学における治療コース(十分な基礎学力のない学生に対する補習コース)の割合は、75年から80 年にかけて、72%増加している。
この時に見習うべきモデルとされたのが、日本の教育であった。当時、日本の中高生の学力は世界最高水準にあり、それに基づく高い技術力と労働者の質が、日本の経済的繁栄をもたらしていると見なされた。
報告書は「教育再建による『強いアメリカ』の復活」をスローガンとし、全米各州で高校の卒業水準が引き上げられた。さらに学校選択の幅が広げられ、学校間の競争が促進された。
教育再建による「強いアメリカの復活」は、レーガン政権以降も、ブッシュ政権の「教育サミット」、クリントン政権の「2000年の目標・アメリカ教育法」として、引き継がれている。
■3.算数のできない大学生■
こうして見ると、現在の日本の学級崩壊や不登校の激増は、アメリカの「暴力学園」現象に相当し、「ゆとり」教育が、「教育の人間化」のスローガンと符合していることが分かる。そして「危機に立つ国家」が指摘したのと同様の広範な学力崩壊現象が、近年、日本で急速に進んでいる。
たとえば、早稲田・慶応など全国トップ・レベルの私大の文科系学生に次のような小中学校の問題を解かせた所、15%の学生が計算できなかった。[2]
3x[5+(4-1)x2]-5x(6-4/2)=?
中2で習う連立一次方程式では、正答率77%、中3の2次方程式に至っては、正答率8%という有様であった。[2,p14]
駿台教育研究所などが実施した実態調査では、物理の授業についていけない工学部生や、基本的な数式が分からない経済学部生など、学生の学力低下について学内で問題視している学校が約7割にものぼることが明らかにされた。3割の大学・短大で高校レベルの補習授業を実施している。[3]
学習指導要領では、昭和52年の改訂で教科内容を3割減らし、さらに小中学校では平成14年、高校では15年から始まる新教育課程では、学校完全週五日制および総合学習(生徒の自主的研究)の導入により、従来型の教科の学習時間はさらに3割削減される。合計で、教科内容は半減となる。
この新課程を受けた最初の生徒が大学生となる2006年には、大学の教育・研究水準が大ピンチにおちいると、大学関係者は痛く心配し「2006年問題」なる造語さえ生まれている。
■4.学力も勉強時間も国際水準以下■
かつては世界一だった国際ランキングも急速に落ちている。
小学4年生の国際学力比較では、数学が16位、理科は23位である。シンガポールが両方とも1位で、かつての日本の地位を奪っている。アメリカは数学10位、理科4位と、完全に日本を抜いた。[4]
これも当然で、まず授業時間自体が少ない。中学1年の数学は、日本の99時間対して、アメリカは146時間。さらに、塾も含めた校外学習時間の平均は2.3時間で、世界平均の3時間にも及ばず、調査参加39カ国中、下から9番目であった。
十数年前に、学力世界一だった頃は、
勉強時間も世界一であった。
授業時間も、勉強時間も減ったので、成績も落ちたという、ごく当然の結果となっている。[2,p60、5]
■5.全員100点でないとおかしい■
このような「ゆとり教育」の中心的推進人物である文部省大臣官房政策課長・寺脇研氏の考えを、その発言から探ってみよう。寺脇氏は、大学関係者から問題視されている今回の学習指導要領改訂の狙いを次のように説明する。
__________
2002年からの学習指導要領では、分からないで出る子は一人もいないようにする。中学卒業時点で全員百点でないとおかしいんです。[6]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
また広島県の教育長時代には、高校の定員を希望者総数よりも多くして、次のように自慢している。
__________
高校で学習したいという権利を行使したい人は、たとえ入学試験の点数がゼロ点でも入れます。[6]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
すなわち、中学卒業時点では誰でもが100点をとれるように学習レベルを落とし、高校に入りたい生徒はゼロ点でも入れるようにする、
というのである。
ここには、中学生として、高校生として持つべき学力とは何か、という問いかけはどこにもない。
全員満点卒業、希望者全員進学という「絶対平等」実現のために、学習課程のレベルを落とし、とめどなく「ゆとり」を増やすのみである。
■6.あらゆる差別をなくす■
__________
いじめをなくすには、ひと言で言うと世の中のあらゆる差別をなくしていくことが必要です。差別を根絶するなど簡単にできることではありませんが、限りなくそこに近づいていくことが教育のテーマだと思っています。[6]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
と氏は言う。これは徒競走の順位付けが差別を生み出すとして、足の速い子も遅い子も、全員手をつないで一緒にゴールインさせる
日教組の平等教育とそっくりだ。
氏の見方では、成績表も、入学試験も、そして学力差を生むような教科内容自体が、差別を生み出す源なのである。
実際に寺脇氏は職業教育課長だった平成4年、偏差値教育反対の立場から、中学の業者テスト追放の旗振り役を務め「ミスター偏差値」の異名を持つ。
■7.アルバイターの子はアルバイター■
「学力崩壊による国力低下」は、深刻な問題であるが、ここでは問わないことにする。米国での失敗と反省の歴史を事実に即して調べ、そして近年の日本の大学関係者の悲鳴を聞けば、現在の「ゆとり教育」が誤った方向を向いていることは、議論の余地がないからだ。
ここで問題にしたいのは、寺脇研氏流の平等主義である。冒頭のハンバーガーショップのアルバイターを例に考えよう。舞台を寺脇氏が教育長をしていた広島県に移してみる。この女の子が結婚して、子どもを生む。アルバイターの貧しい収入では、とても私立などにやれないので、この子は公立高校にいくしかない。
昔なら東大に何十人も送り込む公立高があったので、貧しくとも努力して勉強すれば、奨学金を受けて望む大学に行くことができた。
しかし、現在では寺脇教育長時代の
「ゆとり教育」政策などによって、広島の公立高校全体でも、東大進学2名、京大3名という状態である(平成11年度)。
この子がいかに秀才で努力家でも、裕福な家庭に生まれて小学校から塾に行き、私立の中高一貫教育を受けた子どもたちとの間には、超えようのないハンディキャップが存在する。
結局、富める家庭の子どもは、恵まれた私立校から一流大学に行って、ますます高収入の地位に進み、貧しい家庭の子どもは、学力もなく、アルバイターのような単純労働にしかつけずに、ますます貧しくなる。このような階級の固定化、不平等を我々はよしとすべきなのか?
■8.アメリカのような階級差別社会を目指すのか?■
アメリカの教育改革は、学校間の競争を前提としているので、貧富の差が教育格差を生み、それがまた収入格差を拡大するという階級差別が、顕著になってきている。
アメリカの最上位1%の家庭は、平均90億円の資産を持ち、全国民の資産の40.1%を保有している。逆に下位20%の家庭の純資産は、平均マイナス80万円強(すなわち借金)、次の20%はたかだか104万円、合計しても、40%の人口で国民全体の0.5%の資産しか持っていない。
さらに悲惨なのは、83年から95年の間に、上位1%の家庭の資産は17.4%増加しているのに対し、次の4%はかろうじて0.5%の増加、残りの95%はすべて資産が減少していることだ。貧弱な学力しかない一般大衆は、アルバイターなどの単純労働にしかつけず、
貧しいために学力もつけられない、という悪循環にはまっている。[7]
寺脇氏は、「ゆとり教育」では学力が低下して困る、という意見に対して、
__________
そんな身勝手な言い分なんか、放っておきましょう。つめこみ式の勉強をしなければ合格できないような、高偏差値の大学を受けようという生徒など全体の一割にも満たないのです。そのごく一部の生徒のために、他の大多数の子どもを犠牲にしてかまわないと言ってはばからない大人なんて、身勝手としか言いようがありません。[6]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
と言うが、氏の平等思想は、アメリカのように1割の高学力・富裕階級が、9割の低学力・貧困階級を支配する階級差別社会をもたらすのである。
明治以降の日本の公教育のすぐれた点は、どんなに貧しい家庭に生まれても、本人の才覚と努力で、優れた、しかも学費の安い公立校に入ることによって、立身出世の道が開かれていたことだ。
また一方では学歴はなくとも、仕事に励んで腕の良い職人にでもなれば、親方として尊敬され、それなりの収入を得られる道もあった。
このような「機会の平等」こそが、わが国の社会的理想であり、また活力の源泉でもあった。
寺脇氏流の「結果の平等」思想は、貧しい家庭の子どもたちの自己実現の機会を奪い、愚民として平等化することである。それは国家の活力を奪うだけではなく、国民の平等という理想をもねじまげるものだ。我々は本当にそのような階級差別社会を望んでいるのであろか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
転載は以上です
つまり国際間で行なわれている熾烈な競争世界の中で、日本は落ちこぼれましょう、という教育が行われ、それこそが理想だという事を国がやって来ているという事になります
ならば今のノーベル賞日本人受賞者は良き時代の日本の名残になってしまうというのでしょうか
昔から「これ苦は反発の原動力」と言われています
苦が悪いなんて人を馬鹿にした考えですね、人類の持つ問題や困難が無くなったとでも言うのでしょうか、その困難や問題への解決提案などには先の先を行う先達があってこそできる事であって、苦や大きな問題の壁にぶつかって何が何でもやり遂げる、そんな根気と根性があってこそ大きな感動と発展がもたらされて多くの人々の恵みとなるわけです
その英知を得るためには人はこれまでにない勉強や体験・研究に刻苦勉励しないといけないわけで、世界ではそれが24時間行われているわけです
人の脳や能力は不思議なもので、たくさん覚えるともっとたくさん覚えられるわけです。
ですから、世界のトップを作る西欧の教育なんてものすごい詰め込みをやっています。
人間ぼやっとしていたら、どんどん他に抜かされてしまいます、ですから世界や社会を引っ張る人物をどんどん輩出して、恵まれない方々や弱者が救われる社会ができる様に頑張って頂く、この様である事が本当ではないかと申し上げたいわけなのです
世界のトップを作る西欧の教育については↓
リーダーが出ない日本の教育や松下政経塾がダメな理由を世界の実情から指摘
http://ameblo.jp/matsui0816/entry-11249089288.html
ランキングに参加しております。是非1クリックご協力お願いします!
 1クリックお願いします!
1クリックお願いします!
 1クリックお願いします!
1クリックお願いします!
![]() 記事一覧http://ameblo.jp/matsui0816/entrylist.html
記事一覧http://ameblo.jp/matsui0816/entrylist.html
まずは応援クリックをお願い致します。
↓↓↓