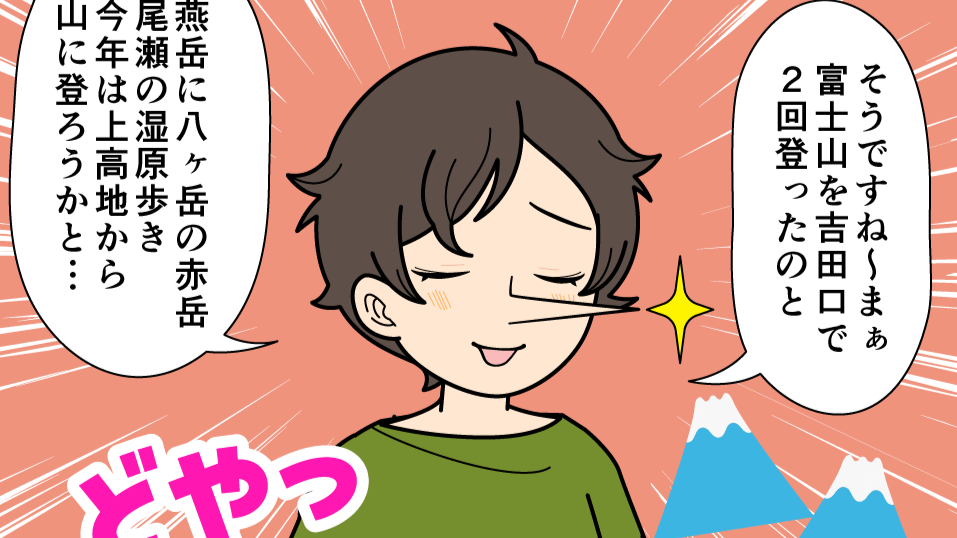「富士登山のレベルと初心者問題(笑)」
娘が実に面白くも考えさせられるサイトを教えて来た。
自分は登山初級者なのに富士登山歴を語ったがためにベテランと会社で思われてしまい、
後悔する日々を送っている人のブログだ。(笑)
これ、思い切り良く理解出来てしまう。
非常に厄介な事に、
富士登山のレベルは日本国ではかなり特殊な位置付けになっているので、
事態を余計にややこしくさせていると思う。
特に北アルプスなどの本格的な登山を好む層の中には、
富士登山を毛嫌いしている人をザラに見る。
ちなみに私の亡き父がその典型だったが。
そのようなベテランの中には未体験なんだけど、
何故か富士登山を蔑視して、
非常に簡単もしくはつまらないと言い切る人もいて、
妙な富士登山像を形成してしまうのに一役買ってしまっている。
そもそも僅か2ヶ月くらいのシーズンしか無い富士登山であるが、
この期間だけで20~30万人が登るのである。
シーズン以外の富士登山は雪と氷に閉ざされてしまい、
登山エリートしか登れない非常に危険な山になるのである。
しかしシーズン中の富士山は大変な人気の山となる。
ところが驚くべき事に、
富士登山に特化した単行本は現在(2024年4月時点)は出版されていない。
山と渓谷社のアルペンガイドに富士山は無い。
しかし一応アルペンガイドだが亜流の、
「関東周辺 週末の山登りベストコース160」
に記載はある。
またJTBパブリッシングから「富士登山パーフェクトガイド」と言うのが出ていたが、
今は改訂中なのか書店には並んでいない。
最も有名なのは山と渓谷社が毎年発行している「富士山ブック」があるも、
新型コロナ禍以降、中止されている。
今年出るのかは分からない。
現時点では「るるぶ」「まっぷる」のムック版の「富士山」があるも、
さすがに旅行系の本なので登山に特化されている訳ではない。
さて、そんな富士登山。
一体どのようなレベルなのかと言うと。
一応前述の「関東周辺 週末の~」では、
富士登山の4つのルートは全て上級として扱われている。
最近盛んに使われるようになっている「コース定数(ルート定数)」と呼ばれる、
体力的な指標で考えるとかなり見えて来る。
コース定数とはおおよそこんな数値だ。
コース定数
10 入門
20 初級(普通の登山のイメージ)
30 中級(健脚向け。日帰り登山の限界の数値)
40以上 上級(健脚向け。1泊2日以上の行程が必要)
これで考えると富士登山は、
吉田ルート(42)、富士宮ルート(40)、須走ルート(50)、御殿場ルート(60)、
となっている。
つまり富士登山は間違いなく体力レベルで考えると全てが上級であり、
さらに1泊2日が要求されるかなり厳しい登山であるのが分かる。
また、富士登山オフィシャルの公式HPでは、
フルマラソンの消費カロリーは2500~3500キロカロリー、
富士登山の消費カロリーは3000~4000キロカロリーと言う記述がある。
この事からも富士登山に要求される体力は、
いわゆる弾丸登山をするのならフルマラソンを走り切るよりも少し多いカロリーとなり、
1泊2日にするならハーフマラソン級の体力が必要なのが判明している。
つまり体力度としては間違いなくマックスだ。
さらに厄介なのは、
富士山は日本で唯一の「高高所」であると言う一点にある。
つまり高山病に罹る可能性が非常に高い場所であると言う現実だ。
高所分類では5段階で表されている。
低地 0~1500m(日本では何ら問題なし)
準高所 1500~2500m(いきなり行ったら高山病になるケースもある)
高所 2500~3500m(高山病に罹る可能性がある)
高高所 3500~5800m(人間が暮らせる限界の層。高山病の危険大)
超高所 5800m以上(高所衰退が起こり人間は暮らせない)
つまり富士登山とは人間が暮らせる限界の層にまで登る事を意味している。
事実、非常に苦しい。
そしてこれまた事実、富士登山においては、
フルマラソンをサブ5くらいで走り抜ける体力と脚力を持った人が、
あっさりと高山病に罹り、全く登る事が出来ない話などザラに聞く。
高山病に強いか弱いかは年齢や体力に関係なく、
若い体力のある人でも罹る人はあっさりと罹る。
イメージとしては、
有名登山アニメ「ヤマノススメ」では、
5人ほどで最初の富士登山に挑戦した主人公達であったが、
その主人公があっさりと高山病に罹ってしまい登れないシーンが生々しく描かれていた。
つまり5人いたら1人は高山病で登れないか、
少なくとも酷い目に遭う人は出て来る、くらいの感覚でいた方がいい。
日本で二番目に高い山は南アルプスの北岳であるが、
標高は3193mとなる。
さすがに高いが高所分類では「高所」なのである。
高所と高高所の差は非常に大きい。
この高度差の感覚は実際に行ってみないと決して分からない。
北岳の頂上は、富士山では八合目くらいであり、
全行程の半分くらいの位置でしかない。
典型的な富士山の登り方は初日に八合目で1泊し、
2日目に登頂、下山と言うパターンになる。
一番人気の吉田ルートでは、
八合目と本八合目には山小屋が多く集結していて、
何と6軒もある。
さてそれはともかくとして、
では富士登山の技術的な難度はどれくらいなのか?と考えた場合、
私的な感覚では、それほど高くないと思っている。
私が登った吉田ルートと富士宮ルートでは、
ちょっとした山だと出て来る「鎖場」は存在していなかった。
かなりな急登が連続するも、鎖を掴んで登るような酷い崖はなかった。
登山をしない素人が見たら崖に見えるような箇所は多数存在しているが。
ちなみに余談だが、一昨年初めて富士山を吉田ルートから登頂した時、
七合目まではまるで余裕で行けて、
七合を抜けた途端に始まる超絶急登を見た時、
本気で回れ右をして帰ろうかと思った。(笑)
真面目に崖に見えた。
(よく見るとちゃんと登れるようになっている)
それほど酷い急登が七合目から八合目までは連続する。
だが、登山技術的に恐い箇所は無い。
ただし高山病の影響が絶対に出て来る場所でもあるため、
また溶岩のゴツゴツした場所でもあるため、
超絶疲労と高山病をダブルパンチで食らってしまい、
万が一急登で倒れたら大ケガが間違いないどころか、
死ぬ可能性すらあると思う。
その意味では非常に恐い場所だと思う。
実際、シーズン中の富士山では毎年毎年数人~6人くらいが亡くなっている。
遭難に関しては僅か2ヶ月間で60~80件くらい発生しているため、
ほぼ毎日富士山のどこかで救助要請がされていると思っていていい。
また通常の山岳遭難と違って、
道迷い遭難は少なく、
大抵は疲労や高山病により身動きが出来なくなって救助要請と言うパターンが多い。
あるいは悪天候と軽装備による低体温症とか。
まとめると、
富士登山とは体力的・高山病的に非常に厳しい場所となるが、
登山技術的にはそれほど高いものは要求されない、となるかと。
富士山の登山経験は山のベテランにも登山をしない人にも大きなインパクトをもたらす。
リンクを貼った記事のように、
自分を初級者だと思っていても上級者扱いをされてしまうもどかしさ。(笑)
どう考えるべきなのか。
富士山に登頂出来た場合、
間違いなく体力的には上級者だと言っていい。
しかし例えば、
鎖場や細尾根がある丹沢表尾根縦走級の中級技術が要求される登山に行った場合、
かなりな恐怖を感じる場面があるはずだ。
それは富士登山の体力的ヤバさとは全く違うレベルの恐怖となる。
登山技術的な恐怖。
以前読んだネットだったか本だったかの古い記事では、
5段階評価で富士登山を表していて、
体力度4、技術度2としていたが、
かなり当たっていると思う。
ちなみに体力度5は1~2泊以上のアルプス縦走登山となり、
コース定数は60を超えて来るものとなる。
技術度3だと鎖場と細尾根などがあり、
50cmくらいの道で両サイドが100mくらい落ちている崖などとなる。
技術度4だと相当ヤバいと思った方がいい。(笑)
物凄く疲れて高山病になるし、
非常にヤバい山なんだけど、
登山技術的には大した事ない、と言う実態。
これが富士登山を非常に分かり難くしている要素だと思う次第だ。
終わり