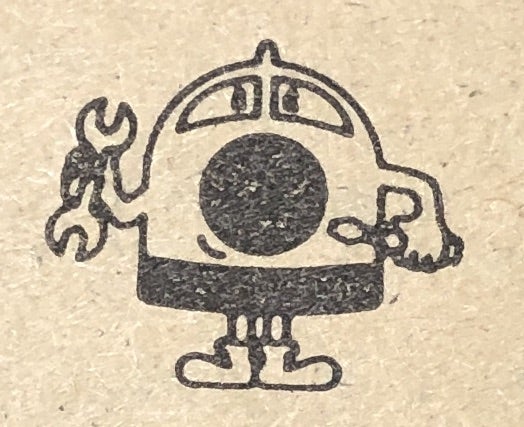今回は、山陽新幹線博多開業後に、大阪〜大分間に設定された夜行急行くにさき号にフォーカスします。先達の皆様はご存知でしょうが、寝台急行ではなく「オール座席車」の急行なのです。
過去のシリーズをまとめたページがあります。よろしかったらバックナンバーもご覧ください。
かつては旧型客車の急行列車
今回取り上げる急行くにさき号の簡単なご紹介です。
1975年 3月 大阪〜大分間に新設
1976年 10月 発着駅が大阪から新大阪に変更
1978年 10月 新大阪(大阪)〜門司間は急行阿蘇号と併結する運行に変更。同時に編成も従来10両編成から5両編成に短縮
1980年 10月 廃止
実は1959年9月から1960年6月まで旧型客車の夜行急行として京都〜大分・都城間で運転されていた時期もあり、こちらは1年3ヶ月とより短命です。このときの消滅理由は急行日向号に愛称変更でした。
そして1975年の「再登板」後は5年余り活躍するわけですが、新幹線開業後に設定された座席急行列車となると、「???」がつく、とても気になる列車なのです。
山陽本線では昼行特急、急行がほぼ全廃される中、夜行列車、それもオール座席車編成の急行がひょっこりと登場します。
くにさき号の名前の由来ですが、大分県にある国東(くにさき)半島から。私は九州出身なので当たり前に読んでいましたが、漢字だと何気に難読地名ですね。
山陽新幹線博多開業時の「九州夜行」の動き
下記は交通公社の時刻表1975年3月号のお知らせページから。
全国ダイヤ改正のあらましとして、国鉄の「成果」を強調しているわけです。
今回ブログテーマ「急行くにさき号」に関連する項目ですと、「京都・新大阪・大阪・岡山発着列車」をピックアップします。
新幹線の博多開業にともない、山陽本線の昼行特急、急行列車は全廃です。申し訳ない程度に「快速・普通列車の列車網を整備」との記事がw。
山陽本線経由の九州行き優等列車はすべて夜行列車となるわけですが、新大阪発着の特急では17往復から13往復に減便。博多行、熊本行の「明星号」、長崎・佐世保行の「あかつき号」、大分行きの「彗星号」がいづれも減便となります。
なお、昼行優等列車の減便によってなくなって九州島内の各都市と接続は、新幹線と九州L特急の組み合わせによる「リレー」でカバーしたのはご存知の通り。
そのなかで、九州行き夜行急行列車として生き残ったのは
・熊本行 阿蘇号
・長崎 雲仙号
・西海号 佐世保行
であり、この削減の流れで新規に1往復設定されたのが、くにさき号 大分行だったわけです。
特急用客車を投入した夜行急行列車
このくにさき号、急行にも関わらず新造の14系特急客車が運用についた、当時としてはハイグレード急行列車でした。14系客車はもともと寝台車用が1970年から製造を開始し、遅れて波動用として1972年以降に製造されています。座席車のクオリティーは183系特急電車に準じて簡易リクライニングシート。従来の12系座席車と比べれば、ハイグレードだったわけです。
運行開始直後のくにさき号の編成ですが、全区間11両で運転された立派な編成でした。全席指定ながらモノクラス編成でしたので、地味さは拭えません。
交通公社の時刻表 1975年3月号から
くにさき号が廃止直前の1980年8月号時刻表での編成は、5両編成となっています。これは急行阿蘇号との併結という制約条件もありながら、利用客がなかったことが最大の理由だったんでしょう。
交通公社の時刻表 1980年8月号より
これ以上の特徴を見つけることができないモノクラス急行でした。
(ブログ筆者の力量とも言えますがw)
度重なる運賃値上げによる客離れに拍車がかかり
この頃の国鉄を語る際に避けては通れないのが、運賃・料金値上げです。
1975年〜1980年あたりに実施された運賃・料金改定ですが、
なかでも有名なのは1976年(昭和51年)11月6日実施分。旅客運賃が基本賃率で55%、各種料金が約43%、初乗り運賃が3キロまで30円から60円に値上げされています。この大幅値上げ以降で、1976年11月から半年間感の旅客輸送人員は前年比17%減ということですから、負債を返すどころが、更に増え続ける状況。
ちなみに、一連の値上げで国鉄離れが止まらないところをみて、1977年(昭和52年)9月20日に特急・急行のグリーン車・A寝台料金のみだが、約30%値下げしています。グリーンだけ値下げしても意味ないでしょ、とツッコミを入れたくなるお上の対応ですw。今の政治家とおんなじ、やったように見せかけた芸当だったわけです。
この値上げにサービスが追いついていたのかの評価は、のちの国鉄民営化が物語るとおり。くにさき号にもこの値上げが影を落としたことは想像に難くなく。減便の一環として、1978年10月の白紙ダイヤ改正では、単独から急行阿蘇号との併結運行となっていました。なお、この改正で発着駅に関して、下りは新大阪発、上りは大阪着と、若干変則的な対応に代わっています。
交通公社の時刻表 1980年 8月号より
そして、1980年10月に実施された白紙ダイヤ改正を迎えます。この改正の目的は、聖域なき列車キロ数の減量。明らかに過剰供給状態だった列車本数を是正するため旅客で3万キロ分、貨物で7万キロ分の列車キロを削減、新幹線もこだま号を中心に大幅に減便されています(代わりにひかり号増便でカバーしている側面もありました)。
この改正では夜行列車、昼行の急行列車も削減され、その中の一列車として、急行くにさき号も廃止となりました。
趣味的な話なら、EF65に引かれて運転されていた14系客車の夜行列車。とても画になるし、何よりも国鉄を感じさせる編成ですよね。。。しかし、乗りたいか?と言われると、興味だけはある、と回答しておくことにしておきますw。
今回は以上となります。
参考サイト:http://www6.plala.or.jp/orchidplace/fare_tokyo_osaka.html
参考資料:交通公社の時刻表 1980年8月号、10月号、1984年10月号、所澤秀樹 国鉄の基礎知識 創元社、日本鉄道旅行歴史地図帳 9号 大阪、JTBの交通ムック 昭和の鉄道<50年代>新幹線網の充実 JTBパブリッシング