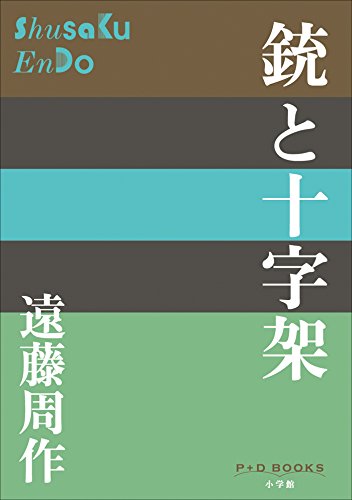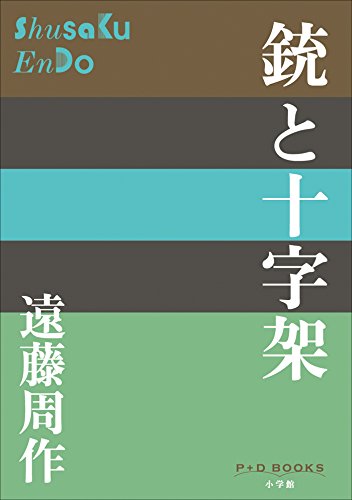
『銃と十字架』 遠藤周作著 1979年
『王国への道』に続き、ローマまで歩いたペドロ岐部に関する2冊目の本。
『王国への道』ではペドロ岐部の出番が非常に少なかったので、本作ではまるまる一冊、岐部さんについて書かれているのだろうと思って読んでみたのですが、そうでもなかったです。
もちろん追いかけているのはペドロ岐部の一生なのですけど、一個人を主人公にした小説ではなく、当時のキリシタン全般の置かれていた状況を描いた作品だと思ったほうが良いでしょう。
まずは1580年に開校した有馬神学校が語られ、信長が突然訪れて生徒の演奏する西洋楽器を聴いたりだとか、4人の生徒が遣欧使節になったなどのエピソードが楽しいです。
しかし秀吉、家康、秀忠、家光と支配者が交代するたびにキリスト教の弾圧が苛烈になっていく後半では、キリシタンがいかに絶望的な布教活動をしていたのかとどれほど過酷な拷問が加えられたかという描写になっていきます。
少年使節団の一人、千々石ミゲルはヨーロッパへ赴く途中で西洋のアジアを植民地にする政策と、教会がそれを黙認している現実を目にして帰国後は棄教しています。
インドのゴアからエルサレムを経てローマに辿り着き、正式に神父となったペドロ岐部もまたその現実を目の当たりにしたことでしょうけれど、それでも遅かれ早かれ拷問か処刑かという未来の待っている日本で布教するため帰国します。
その心情を遠藤周作はさまざま推測するのですが、私には仏教徒がブッダが開いたとされる悟りを追い求めるように、イエス・キリストの受けた受難に憧れているようにさえ感じました。
『王国への道』ではペドロ岐部の描写が妙に少なかったのを奇異に感じましたが、彼を主人公としたこの作品でも同じような描写しか出てこなかったので、どうやら岐部に関する資料が極端に少ないのであろうことが偲ばれました。
そういえば『王国への道』で神父となった岐部がアユタヤで山田長政と再開するシーンがあって、それは小説としての創作だろうと思っていたのですが、実際に帰国する前にアユタヤに立ち寄っていたとのこと。
長政と岐部とが知己であった証拠は何もないのですが、この地で二人の人生がほんの一瞬交差したのには何か運命的なものを感じました。
小説としては『王国への道』のほうが面白いですけど、実際の歴史を知りたい方にはこちらがオススメ。