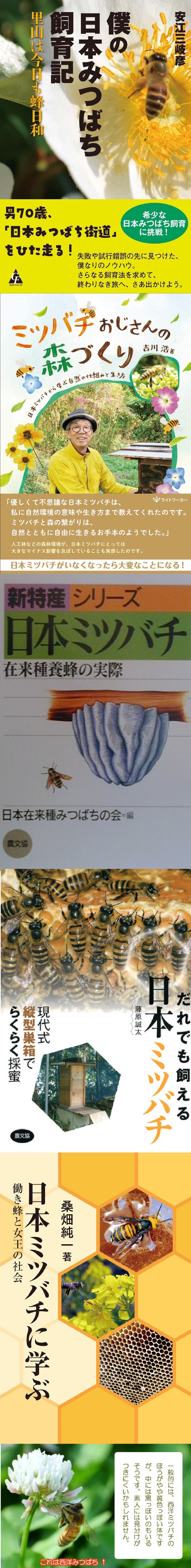・・・とても参考になる★重要な情報がありましたので、紹介します。
《NEWS》2020.5.17琉球新報より
日本のミツバチ、沖縄が支える/クマ被害なく飼育1位に、花粉交配で果樹農園に出荷
農林水産省の2019年の調べで、ミツバチの飼育数で沖縄県が日本一になった。県内ではハチミツ用ではなく、ビニールハウス内で果物を育てる際に使う★花粉交配(ポリネーション)用のミツバチの生産が盛んになっている。冬でも温暖な沖縄の気候がミツバチの繁殖に適し、花粉交配用に県外へと出荷されている。関係者は「日本の農業は沖縄のハチが支えている」と胸を張る。昨年1月時点の都道府県別の飼育状況調査で、沖縄の蜂群(ほうぐん)数が約1万4700群となり、長野の約1万3300群を抜いて初めて1位になった。蜂群は女王バチ1匹が引き連れる集団の単位で、1群はミツバチ約5千~1万匹に相当する。県外では冬場にミツバチの繁殖が止まるが、温暖な沖縄では年間を通して繁殖する。ミツバチは屋外に設置した巣箱で育てるために県外ではクマによる獣害も無視できないが、沖縄はその心配もない。県内では生産者も増加傾向にある。県のまとめでは2010年の県内生産者は71人だったが、19年は196人と10年で約2.7倍になっている。県農林水産部の担当者は「初期投資が比較的少なく、冬期でも収入源になると始める人が多い」と説明する。県外向けのミツバチ出荷は、養蜂業大手★アピ(本社・岐阜県)などが手掛けている。
※アピ株式会社
名護市に拠点を置く、同社ミツバチ沖縄生産管理センターの野口正男センター長は「沖縄産のハチは他県産より長期にわたってよく働くのが特徴だ」と語る。
※アピ(株)養蜂部ミツバチ課スタッフのブログ
http://api-beeblog.blogspot.com/
同社は18年9月から19年5月の間に、約1万4千群を沖縄から県外に出荷した。同社は1群を8千~1万匹としている。アピを通じてミツバチを出荷している農家は、本島北部を中心に約50軒を数える。大宜味村で約600群を飼育する山口進さんは、果樹栽培の傍ら、数年前から花粉交配用のハチ生産に取り組むようになった。農業生産法人を設立し、4人でハチの管理を続ける。
※山口フルーツファーム
905-1303沖縄県国頭郡大宜味村字喜如嘉992-2/0980-44-3210
http://yamaguchi-fruitfarm.com/
農園内の巣箱からハチが飛び立ち、野山からシークヮーサーやセンダンの花粉を集めてくる。それに加えて、各巣箱に週1回程度砂糖水などの餌も与えてミツバチを育てている。山口さんは「ミツバチは沖縄の新たな産業になるかもしれない。若い人を(養蜂に)定着させたい」と目標を語った。
《参考》「蜜蜂飼育届」
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/chikusan/chikusei/documents/siikutodoke.html
沖縄県内で蜜蜂を飼育されている方は、養蜂振興法に基づき、蜜蜂飼育届の提出が必要ですので、居住地の市町村に提出してください。(趣味で飼育されている方も対象となります。)居住地と異なる市町村へ蜂群を設置する場合は、居住地および設置する市町村の両方に、蜜蜂飼育届を提出してください。提出された蜜蜂飼育届は、市町村から沖縄県畜産課に送付されます。また、蜂群配置の適正化を図るため、緯度・経度記入票の提出にご協力ください。
●「沖縄かりゆし養蜂」
https://okinawakariyushi-beekeeping.webnode.jp/
●「新垣養蜂園」
http://www.aaa888.org/index.html
●「蜜蜂ファームときわ」(ショップしゃしくまーる)
http://www.kushibb.jp/~bee-tokiwa/beefarm.html
《西洋蜜蜂と日本蜜蜂》
西洋蜜蜂は、ヨーロッパやアフリカ・中央アジアなどを原産地とする蜜蜂。19世紀半ばに飼育管理方法が広まって以来、家畜として改良され、人間とともに歩んできました。日本では明治時代にアメリカから輸入されたと言われています。現在、スーパーなどの店頭に並んでいる商品や、加工食品の原材料に使用されているハチミツのほとんどが、西洋蜜蜂のハチミツです。
それに対して、日本蜜蜂はもともと日本列島に住んでいた在来種。西洋蜜蜂に比べて飼育が難しく採蜜量も少ないため、商業的に不向きと言われています。
《参考》セイヨウミツバチと生態系への悪影響/アルカエの日々のこと(★名嘉猛留)より2014
https://archae88.exblog.jp/19950930/
・特に、養蜂業が及ぼす沖縄の在来生態系への悪影響については、生物多様性保護派の僕にとって★自分の首をしめるような話題ではありますが、なにやら益虫のイメージばかりが先行しているように思えるセイヨウミツバチ(以下ミツバチ)のことを話すうえで、是非とも触れておきたいミツバチの「個性」でした。
・外来種であるミツバチは、沖縄の他の在来の蜂に比べて1巣あたりの個体数が圧倒的に多く(大体5000~30000匹)、野生化したミツバチの巣は異様な迫力を放っています。他の生き物を寄せ付けない、ひとつの国のような印象を受けます(実際にはいろんな生き物が紛れ込むことがあって、ちょっと面白いのだが!)。子どもの頃からフィールドで馴染みのあるアシナガバチ類やハキリバチ類の巣からすると、★やっぱり不自然な感じです。でも、そういった超大家族から成る社会性のある生活様式こそミツバチたちの長所で、長い進化の歴史の中で獲得した「個性」です。ミツバチたちは、故郷とははるか遠い土地で、精一杯生きているだけ。養蜂を始めてみて実感したことは、養蜂・ミツバチは、人の管理の次第では、よく知られているような人にとっての良い事だけではなくて、自然にとってひいては人にとって★「悪い影響」もあるということです。このことについて、実際に養蜂をしている側だからこそできる、改善に向けての活動があると思っています。まずは、一般の方にも知ってもらいたい、と思いどうしてもお話したかった次第です。
※「グクルの森」
・それと、沖縄にはミツバチの野生化を抑制しうる、★目立った天敵がいないことも危険な要素の一つです。本土で、ミツバチ(在来種ニホンミツバチ除く)が野生化できない大きな理由の一つに、天敵オオスズメバチの存在があげられます。オオスズメバチは、集団でミツバチの巣を襲い、巣を全滅させることが知られています。沖縄にはオオスズメバチがいません。コガタスズメバチという種はいますが、僕の蜂場で観察しているかぎり、ミツバチを襲いはするものの、巣を全滅させるほどの襲撃はできない様子です。むしろ何匹かは返り討ちにあって死んでいます(近年セイヨウミツバチも蜂球を作ってスズメバチを殺すことが分かっています。ただしこちらは熱殺ではなく窒息殺)。
・ミツバチのように★「飼育ケース(巣箱)と野外を自由に行き来する」「集団で花に訪れる」「よく逃げ出す」「野外では主に樹洞に営巣する」というとても個性的な習性をもつ昆虫を飼育している場合、地域の環境や生物相をもっと意識しないと危ないのでは?と強く思いました。つまり、養蜂をしている(またはしようとしている)その地域の自然環境の特色はなんなのか?、そこで暮らしている野生生物の特徴はなにか?、それらはお互いにどんな結びつきをしているのか?、そこでミツバチを放った場合どんな影響が予想されるのか?、飼ってて大丈夫なのか、飼うならどう飼うべきか。ミツバチという昆虫を飼うということ。柵で囲って飼う家畜とは意味が違うこと。★責任と、ある程度危機感を持って臨んだ方がいい思いました。特に、やんばるに生息する固有種たちは樹洞を利用するものも少なくありません。小笠原諸島とは違った危険性をはらんでいる可能性があります(ちなみに、沖縄にもグリーンアノールは侵入しています。那覇空港の付近など、一部地域で野生化しています)。自分を含めてのことなんですが、養蜂家は分蜂(巣別れのこと。そのまま逃げられることが多い)させてしまうことについて、緊張感が足りないように思います。分蜂させてしまって「やっちゃった~」と思ったとしても、それは蜂に逃げられてしまって財産損失もったいないの「やっちゃった~」のほうが多かったのではないでしょうか。
・現在、沖縄を周辺の島々とともに★世界遺産に登録しようという動きがあります。
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/land/bunka/sekaiisan/index.html
固有の動植物が多く生息し豊かな自然環境が残されている、と認識されているからです。登録されるされないにかかわらず、地球の長い歴史の生き証人たちが目立って残されている沖縄は、自分と他の生き物の関係を考えるうえでも価値の高いかけがえのないものだと思います。周りの人に、「これはすごい、大事だ」と言われる前に、住んでいる現地人がその価値に気づけたら素敵です。また、内地と比較して一年中あたたかい沖縄では、ミツバチを増やすうえで好都合な場所です。増やしたミツバチを、イチゴなどのハウス栽培の作物の授粉に役立てるため、★巣箱ごと内地に出荷する事業が沖縄では盛んです。沖縄県もこれを推進すべく動いています。事業の拡大に伴ってミツバチが今後増えていくことを考えると、ますます養蜂家の責任は重いものです。商売のためだけにみつばちを飼う養蜂は、今日の時代になじまないと思います。セイヨウミツバチが増えすぎた結果こうなってしまった、というモデル島にならないために。僕たち県内養蜂家の意識改革は必要不可欠だと思います。
・・・引用が長くなりましたが、現在、新型コロナについてガタガタしているだけに、とても参考になる(納得、説得)素晴らしい内容です。
《NEWS》2018.7.25沖縄タイムスより
日本初の「洞窟性アリ」発見/沖縄。世界でも2例目「ガマアシナガアリ」と命名
沖縄市在住の昆虫研究家の★名嘉猛留(たける)さん(40)ら研究チームは23日、本島中部の洞窟でアリの新種が見つかったと発表した。体の色や形、付近の森林で発見されていないことから、洞窟の中のみで生息する「洞窟性アリ」とみられ、日本初、世界でも2例目となる。研究チームは「ガマアシナガアリ」と名付け、今後は保護活動をしていくという。
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/263
研究に携わった九州大総合研究博物館の丸山宗利准教授は「これまで1カ所でしか発見されていない貴重な洞窟性アリで、沖縄で見つかったのはすごいことだ。ヤンバルクイナなど希少動物が多く存在する沖縄の自然の大事さを認識してほしい」と強調した。アリは、名嘉さんが昨年8月、洞窟内の生き物を調べた時に発見。体長8ミリ、薄い黄色の体色で目が小さく、脚と触角が長いことなどから、真洞窟性の可能性が極めて高いと丸山准教授らが判断した。研究チームによると、これまでも世界各地の洞窟で数種のアリ類が発見されたが、多くはその後、洞窟以外からも採集された。確実に洞窟性と考えられるのは、2003年にラオスで発見された「ハシリハリアリ」のみという。研究論文は同日、ニュージーランドの動物分類学の学術誌「Zootaxa」(電子版)に掲載された。
《参考》2016.3.15沖縄タイムスより
ハチにしか見えないのにガと見破れたワケ/23歳大学院生に聞いた
2015年5月30日、沖縄北部にある国頭村で、まるでハチのようなガを発見した九州大学大学院1年の屋宜禎央(やぎ・さだひさ)さん(23)。
http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/entomology/member.html
そのガは日本で初めて確認されたテイノタルシナ属の新種で、「Teinotarsina aurantiaca(テイノタルシナ アウランティアカ)」と命名した。発見当時は「モグリチリガ科」のガの調査のため、28日に沖縄入りし、林道沿いの植物を観察していた。30日午後3時ごろ、約70センチの高さでアシナガバチのような虫が飛んでいるのを見つけた。通り過ぎようとしたが、「何か違う、スカシバガではないか」と感じて引き返し、捕虫網で採集した。屋宜さんは「後ろ足を下げてゆらゆらしと飛ぶアシナガバチとは違い、後ろ脚を後ろに伸ばしてゆっくりまっすぐ飛んでいた。虫好きじゃないと気付きにくかったのかもしれない。網の中のスカシバガは図鑑で見た覚えもなく、新種ではないかと心躍った」と振り返る。福岡に戻り、九大大学院の広渡俊哉教授、名城大学の有田豊名誉教授と共同研究を開始。新種のガと突き止めた。一般的にスカシバガがハチに擬態するのは、毒針のあるハチに似せることで鳥などの天敵から身を守るためだと考えられている。ハチに擬態化するスカシバガ科テイノタルシナ属のガは、台湾や中国などに分布している。今回の新種と台湾の近縁種と比較すると、交尾器は非常に似ていたが、外見は全く違った。台湾の近縁種は黒や薄いオレンジ色が目立つ一方、発見されたガはオレンジ色が目立った。沖縄本島に生息するハチの多くに見られる暗色化する傾向と一致。屋宜さんたちは論文で地理的な影響を受けている可能性があると結論づけた。琉球列島と中国大陸のガの関係や、そこに分布する昆虫の多様性は十分に調査されていない。屋宜さんたちは今後も調査を続け、日本に生息する昆虫の起源を明らかにしたいと考えている。もともとチョウが好きだった屋宜さんは、ガの専門家の広渡教授と出会い、大学3年から本格的に研究を始めた。ガの魅力について「研究があまり進んでいない分類のガも多く、新種が発見されれば名前を付けられるし、害虫の研究にもつながる」と話す。今後もモグリチビガ科と平行してスカシバガの研究を進める予定だが、懸念していることもある。それは、沖縄本島北部一帯の「ヤンバル」の国立公園化だ。「日本には、研究機関に所属していないガの研究家も多くいる。そのおかげで研究は大きく進歩してきた経緯がある。国立公園になって全面的に虫の採集が禁止になると、今後、なかなか発見されない恐れもある。継続的な調査研究ができるような環境であってほしい」国立公園化されれば、観光客の増加が見込まれ、生態系が乱される恐れもある。しかし、貴重な動植物を保護するだけが目的になってはならないと思う。研究に携わる人たちと★緩やかなすみ分けをすることが、きっと奥深い生態の進化の解明につながるだろうし、生命の神秘ほど心引かれる話題はないのだから。
・・・世界遺産、とりわけ古墳(陵墓)研究とも共通する難しい課題ですね。