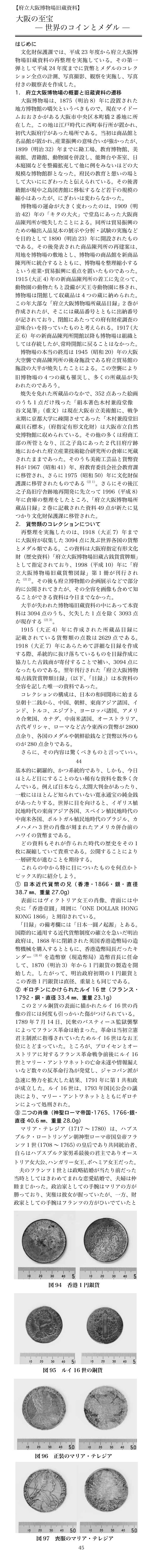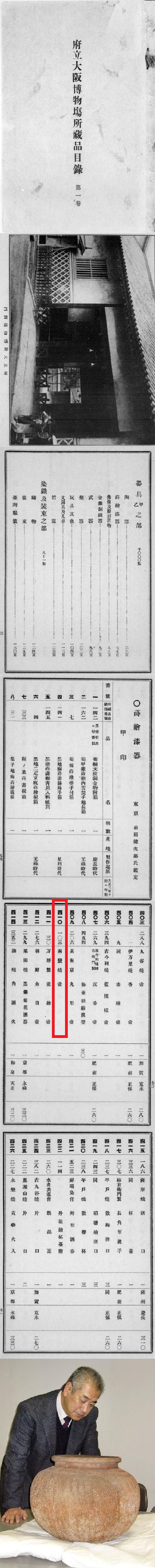・・・「ゴーランド」という言い方もあるようですが、私は「ガウランド」の方がぴったりくるのです。
《参考》マイドームおおさか「敷地の変遷」/大阪産業局より
https://www.mydome.jp/summary/transition/
・・・そもそもガウランドさんのことを知ったのは、探偵アートスクープで★「大阪博物場」を調べていた時です。
《大阪府教育委員会文化財調査事務所年報17》2013年10月大阪府教育委員会
大阪府教育委員会文化財保護課の分室として文化財調査事務所が設置されて17年目を迎えました。本事務所は、総合的な文化財調査機能を持つ拠点施設として開設されるとともに、埋蔵文化財の調査と保護、整理・収蔵を担う埋蔵文化財センターとしての機能を果たしてきました。この間の経済状況の変化は著しく、本調査事務所が開設された平成9年をピークに全国の埋蔵文化財の発掘調査費用も大きく減少に転じています。当調査事務所においても大規模な開発事業は減少傾向にありますが、道路拡幅や歩道設置、既存建物の耐震補強・エレベーター設置などの小規模事業が相対的に増加しています。そのため埋蔵文化財に対する綿密な対応が求められているところです。一方、府民の文化財に対する関心は高まり、世界遺産をはじめとした文化遺産の活用と公開がより一層強く求められる時代となっています。調査事務所では、必要な調査を適切に実施し、調査成果を迅速に公開できるよう、調査実施前の協議調整から、発掘調査の実施、遺物や資料の整理作業、報告書の刊行といった一連の業務を組織的に行っています。また、博物館などの公開施設をはじめ、多様な府民のニーズに応えられるよう、整理した資料を活用できる状態で保管し、そのデータを整理しています。今年度末には、新しく和泉池上収蔵庫が完成する予定で、公開活用を前提にした、より効率的な資料収蔵を実施する計画です。今後とも文化財が国民の財産であるという原点に基づき、文化財保護行政の遂行に努めたいと思いますので、皆様のご支援とご協力を切にお願いするものです。平成25年10月大阪府教育委員会事務局文化財保護課長・荒井大作
・・・目次の中に、
【府立大阪博物場旧蔵資料】 44
大阪の至宝 ― 世界のコインとメダル ― 44
★ガウランドの壺 ― 大阪を愛したお傭い外国人 ― 47
《NEWS》2013.11.21日本経済新聞より
大阪府が所蔵する16世紀のタイの壺(府指定文化財)が、明治時代のお雇い外国人の冶金技師で、日本考古学の父といわれる英国人★ウィリアム・ゴーランド(1842~1922年)の寄贈品だったことが府教育委員会の調査で21日、分かった。お雇い外国人の契約期間は通常3年だが、ゴーランドは16年間、大阪の造幣局などで指導し、1888年(明治21年)に帰国。調査した府立狭山池博物館の広瀬雅信専門員は「帰国の際、愛着のあった大阪に寄贈したのではないか」と話す。壺は高さ35センチ、最大径45センチ。タイのアユタヤで16世紀ごろ作られたもので、1915年の★「府立大阪博物場所蔵品目録」に「南蛮焼」として記されていた。2011年度からの所蔵品再調査で、壺が入っていた箱に「明治二十一年十二月第一〇三南蛮壺造幣局傭ガウランド献納」と5行にわたり記されており、今回残り2行が判読できた。ゴーランドが古墳研究で堺を訪れた際に古物商などで購入した可能性があるという。ゴーランドは滞在中、日本各地の古墳などを調査したほか「日本アルプス」の命名者としても知られる。
・・・「大阪博物場」調査研究も行き詰っていた時に発見した資料だけに、特に印象に残っていました。続いて、
★造幣博物館「明治150年記念特別展~明治期の造幣局~」の開催について(2017年12月1日)
造幣局では、平成30年1月から年間4期に分けて、造幣博物館において「明治150年記念特別展~明治期の造幣局~」を開催いたします。平成30(2018)年は明治元(1868)年から起算して満150年に当たります。「明治150年」関連施策を推進する政府の取組の一つとして、造幣博物館では平成30年1月から4期に分けて、「明治期の造幣局」をシリーズ・テーマとして記念特別展を開催いたします。明治維新政府により設立され、明治4(1871)年に創業した造幣局の明治時代の貨幣や古文書、写真などの展示を通して、当時の技術や文化などを肌で感じていただく機会になることを期待しております。
展示の概要
●Ⅰ期:平成30年1月~3月「造幣局の誕生~創業の功労者たち~」
造幣局の設置計画から創業までの経緯が詳しくわかるような展示を行います。また、造幣局の設置に深く関わった日本人についても紹介します。
主な展示品
・造幣局設置場所の条件について記した古文書・造幣局の設置から創業に深く関係した日本人を詳しく紹介する パネルと写真
●Ⅱ期:平成30年4月~6月「明治天皇の造幣局行幸」
明治5年と10年に明治天皇が造幣局に行幸された時の様子を紹介します。また、造幣寮の応接所として建設された泉布観のことについても紹介します。
主な展示品
・明治5年に明治天皇が造幣局や泉布観に行幸された時の様子が分かる古文書・明治10年に明治天皇が造幣局に行幸された時の様子が分かる古文書・泉布観の図面や写真
●Ⅲ期:平成30年7月〜9月「造幣局で働く人たち」
明治時代に働いていた人たちのことがよくわかるような創業時の写真や、給与、職員の出身地、就業時間などが分かる史料を展示します。また、お雇い外国人についても触れ、明治時代の造幣局では日本人だけでなく、外国人も働いていた点も紹介します。
主な展示品
・明治期の仕事風景が分かる写真・職員規則や職員の募集要項・お雇い外国人一覧と、担当していた仕事内容をまとめたパネル・造幣局が定めた外国人に対する規則を定めた古文書
★Ⅳ期:平成30年10月~12月「旅する外国人ウィリアム・ガウランド」
造幣局のお雇い外国人で、日本各地の古墳を訪ね、また「日本アルプス」の命名者であるウィリアム・ガウランドが国内旅行をする様子を紹介します。
主な展示品
・ガウランドの経歴と日本での仕事について紹介するパネル・ガウランドの行先や旅の目的が分かる古文書
各期共通:主な展示品
・明治期に製造した貨幣、記章・明治期の造幣局の写真、錦絵など
その他
開催期間、展示内容等は予定であり、都合により変更する場合があります。なお、各期の開催期間、展示内容及びイベント等の詳細は、改めてはお知らせいたします。
《明治150年記念特別展~明治期の造幣局~》
【シリーズⅣ期】旅する外国人ウィリアム・ガウランド
平成30年9月22日(土)~12月28日(金)/於:造幣博物館
530-0043大阪市北区天満1-1-79/06-6351-8509(直通)
https://www.mint.go.jp/wide/20180918_s4.html
平成30(2018)年は明治元(1868)年から起算して満150年に当たります。「明治150年」関連施策を推進する政府の取組の一つとして、造幣博物館では平成30年1月から年間4期に分けて、「明治期の造幣局」をシリーズ・テーマとして記念特別展を開催しております。今回、シリーズⅣ期として「旅する外国人ウィリアム・ガウランド」をテーマに、造幣局で働いていたお雇い外国人であるガウランドに関する展示を行います。造幣局との間で交わされた契約書や給与に関する記録に加えて、日本各地で古墳の調査を行ったことが分かる史料、明治19年の岡山調査旅行で、盗難被害に遭った時の報告書についても展示する予定です。これらの史料から外国人の国内旅行が珍しかった明治時代に、日本各地を旅して回ったガウランドの姿を知っていただけたら幸いです。
《参考》特別展「ウィリアム・ガウランドと日本の古墳研究」
2018年10月13日~2018年12月2日/於★明治大学博物館
https://www.meiji.ac.jp/museum/news/2018/6t5h7p00000sjcqr.html
日本アルプスの命名者としても知られる、英国人技師・ガウランド(WilliamGowland、1842-1922)は、明治5(1872)年に来日し、大阪★造幣局に勤めながら数百基に及ぶ日本各地の古墳を調査し、精密な測量図や写真などの記録に基づいた研究論文を帰国後に発表しました。彼の研究は、日本の古墳研究の先駆けとして高く評価されていますが、その全体像はベールに包まれたままでした。今回は、ガウランド・コレクションを収蔵する大英博物館の全面的な協力を得て、ガウランドが収集した古墳出土資料や彼が作成した調査図面、アーネスト・サトウをはじめとする当時の研究者との交流を示す手紙、古墳を撮影した写真といった資料に国内の関連資料を交え、最新の研究に基づいたガウランドの古墳研究の実像に迫ります。大英博物館のコレクションは、日本国内では初めての公開となるのはもちろんのこと、大英博物館でも未公開であった貴重な資料が含まれます。この機会にぜひご覧ください。
・・・ガウランドさんの功績は、誠に大きいと言わざるを得ません。何よりも、そのコレクションや写真の数々が「大英博物館」に多数残っていたとは驚きです。