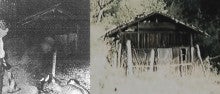(向かって左、遺体が発見された作業小屋付近を捜索する松井田署員〈上毛新聞8月17日付〉。右は、その作業小屋少しクリアな画像)
※※ パソコンからご覧の場合で、画像によってはクリックしても十分な大きさにまで拡大されず、画像中の文字その他の細かい部分が見えにくいという場合があります(画像中に細かい説明書きを入れている画像ほどその傾向が強いです)。その場合は、お手数ですが、ご使用のブラウザで、画面表示の拡大率を「125%」「150%」「175%」等に設定して、ご覧いただければと思います。※※
----------
この事件は、1987年8月に公訴時効を迎えたいわゆる「未解決事件」なので、
その後なされた捜査は、結果としては全て虚しいものに終わった、
ということではあるのですが、
いちおう以下、その後の捜査状況や判明した事実などを、大雑把かつ漫然と並べてみると、
(これまでの記事内容と重複する部分---あるいは省いている部分---があります)
■ 遺体発見の翌日---1972年8月17日---松井田署に、
温井守夫・松井田警察署長を本部長とする「霧積山女性殺人事件捜査本部」を設置。
(温井守夫氏、当時の松井田警察署長であり捜査本部長)
■ 地元の松井田署のみならず、前橋、高崎、伊勢崎、渋川、下仁田の各署、県警機動隊などからも応援を受け、連日200人以上を動員して、凶器や遺留品の捜索、目撃情報の収集(松井田~安中では有線放送でも情報提供を呼び掛けた)、捜査対象者のアリバイ確認などを行った。
■ 捜査の対象となったのは、
当時霧積温泉にあった2軒の旅館の宿泊客(8月12~13日の二日で約260人)、
食事~温泉のみの日帰り客(13日だけで300人近く)や、ハイカー、登山客、
旅館従業員(アルバイトを含めて27人)、
遺体が発見された作業小屋から約2キロ下流の霧積ダム建設工事現場で働いていた作業員(約200人、主に青森や富山から来ていたが、大半が盆休みで帰省中)、
現場一帯の民・国有林で下草刈りに従事していた数組の作業員(30人強)、
Kさんの知人・友人関係(380人近く)等々。
地元松井田町では、その全世帯(約5千世帯)に対して、2度にわたるローラー捜査が実施された。
■ 旅館の宿泊客の中には、偽名を使って泊まっている者もおり、また日帰り客の中には、関わり合いになるのを恐れてか名乗り出る者も少なく、捜査は難渋した。
捜査員は簡単なアリバイを調べるためだけのために、遠く九州や青森にも足を運んだ。
■ 「犯人は遺体発見現場(作業小屋)横のえん堤を伝って対岸に逃走したかもしれず、その際に、凶器や血の付いた衣服を霧積川に捨てたかもしれない」
との意見が捜査会議で示され、それに基づき、地元のダイバーを繰り出してえん堤付近の潜水調査を行ったが、何も発見することができなかった。
(ダイバーによる捜索イメージ。作業小屋横のえん堤付近でも、こうした捜索が行われた)
■ 県内の変質者、素行不良者、前科前歴者の洗い出し、そこからさらに重大な性犯罪歴のある十数人をリストアップし、事件から1ヵ月半後の9月末には、
「犯行時間帯のアリバイがはっきりしない」
「霧積に土地勘がある」
「手口に類似性がある」
などの観点からさらに5人に絞り込み、(この5人については)一時捜査員が昼夜体制でマークをしたが、その後、いずれも捜査対象から外された。
■ 当時の捜査の様子については一般人による証言があり、
「事件から1~2ヵ月は、このあたり一帯警察官だらけで仕事にならなかった。(金湯館の)下にあるきりづみ館から事件のあった小屋よりさらに下流にある霧積ダムの工事現場まで、それこそ何百人という県警の機動隊員がやぶの中を棒でつついたり、刑事たちが河原に降りて、(凶器や遺留品発見のため)水に浸かって川をすくっていた。」(金湯館3代目ご主人談)
「事件前後の日の宿帳どころか、5年も10年も前の宿帳まで警察が(捜査のために)持って行った。」(金湯館3代目女将談)
(向かって左上、きりづみ館から霧積ダム建設工事現場付近までの林道〈現・群馬県道56号〉一帯は、傍を流れる霧積川も含め、徹底した捜索の対象となったという)
■ 遺体発見時のKさんの着衣は、
紺色ノースリーブのブラウス、白のミニスカート、白の運動靴、
スカートがまくれ、下着に乱れあり、
その状態で、8畳間の南側西隅に、頭を南へ向けて仰向けに横たわり、
上からは2枚(あるいは数枚)のトタンの波板がかぶせられていた。
■ 同じ8畳間の北側西隅には、
Kさんのカメラ、手編みの白い帽子、高崎駅のスタンプが押された旅行帳、
針が10時9分を指して止まっていた時計、下着類など、
Kさんの所持品40数点が紺色の布製バッグに入れられ、
これも、上からブリキ板をかぶせられた状態で発見された。
(被せられていた板の種類については、各資料によって、トタン、ブリキ、べニアなどバラつきあり)
(遺留品の時計の針は、10時9分を指したまま止まっていた。カタログに載っている時計がたいていこの時間---10時8~10分---を指して止まっているのと関係があるかどうかは不明)
■ 8月18日(金)付の上毛新聞記事には、
「血痕の付着した床板、腰板すべての場所をトタンで覆い隠している」
とあり、床板の全面が覆い隠されていたかどうかは不明にせよ、少なくとも、血の付いた個所は板で覆われていた様子。
■ 遺体が発見された作業小屋では、入り口のある6畳間から8畳間にかけて、遺体を引きずったとみられる血の跡が見つかった。
この間は血のりがベットリと床にしみ込み、部屋の仕切り部分の腰板には、Kさんをいったん置いたものか、多量の血痕が付着していた。
(引きずった距離については、2メートルとする記事もあり、6~7メートルとする記事もある。殺害された部屋と遺体が置かれていた場所の位置的には、後者が正解ではないかと想像)
■ 殺害現場の状況ということについて、
先に紹介したフジテレビによる番組中で、温井守夫氏(当時の松井田警察署長・捜査本部長)による解説がなされており、
https://www.youtube.com/watch?v=_wPZ5XTXXXM
その部分を書き出してみると、
「被害者は、私なんかが(現場に)来た時は、こちらの部屋(8畳間)にいた」
「(殺された場所は)こちら(と言って6畳間のほうを指さす)」
「こちら(6畳間の入口)から入った、その(6畳間の)奥のほうで殺された」
「床下に、もう、血の塊になってあったわけ。だから、ここ(6畳間)で殺されて、(遺体は)しばらくここにあったんだなと」
(ということは、ここが犯行現場だということですね?)という弁護士の問いかけに対して、温井氏「ということは確かだと思いますね」
(当時警察もそれ---この小屋が殺害現場であるということ---は断定したわけですね?)という弁護士の問いかけに対して、温井氏「ええ、そうですね」
同じく殺害の状況について、温井氏によると、
「胸から腹のほうから、いたるところを刺されていた」
(殺害場所の説明をする当時の松井田警察署長)
■ 遺体にかぶせてあったトタン(ブリキ?)の波板からは
「血の付いた軍手の跡」
が複数採取され、また、室内および小屋の外からは
「地下タビの足跡」
が、これも複数採取されたが、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E8%B6%B3%E8%A2%8B
(地下タビのウィキペディア)
その後の捜査で、地下タビの足跡については、
「かなり古いものとわかり、足跡面からの捜査は振り出しにもどったようで、現在、犯人が現場に残したもので確実なのは、死体や血痕を隠すために使用したブリキに付着している”血のついた手袋の痕跡”だけとなった」(8月19日付、上毛新聞)
「小屋に残されていた地下タビの足跡は、ダム工事現場で作業員たちが使っているもの以外の製品(の足跡)であることから、今までの調べではダム関係者には犯人はいないものと(捜査本部は)みている」(8月18日付、上毛新聞)
とのことで、足跡から犯人に迫る線は、早々に期待薄になってしまった。
(地下タビ一例。現場で採取された地下タビの足跡はかなり古いものだった、とのことだが、それ以外の種類の靴の新しい足跡が発見されたという情報は出ていないのが謎ではある。比較的荒っぽいとみえる遺棄の状況からしても、現場に新しい足跡が残されてなかったとも考えにくいのだが。)
■ 司法解剖の結果について、
遺体発見の翌日(8月17日)午前10時から、群馬大学法医学教室で、
同大医学部の古川研助教授の執刀により約2時間にわたって解剖が行われ、それによると、
死亡推定時刻は「8月13日(日)の昼から夕方にかけて」、
直接の死因は、深さ8センチ、幅5センチにおよぶ左胸の刺し傷による失血死で、
心臓にまで達していたその傷は「アバラ骨三本を切るすさまじいもの」であり(上毛新聞)、
その致命傷に加えて、長さ7センチに及ぶ右頸部の切創、
左手首を貫通した刺し傷、
同じく左手に刃物を握ったとみられる防御創、
その他、背中、臀部、下腹部など、全身にわたり24ヵ所の刺し傷や切り傷が認められ、
下腹部の傷の一部には生活反応のないもの---死後付けられた傷---もあったとのこと。
■ 遺体の傷跡から、凶器は
「幅2.5センチ、長さ10センチ以上で先端鋭利な刃物」
と推定できたが、該当するものとしては、柳葉包丁、登山ナイフ、牛刀、料理用ナイフなど種類が多く、特定は困難だった。
この点、上毛新聞(8月19日付)の見解によると、
「胸の傷跡のように一度刺して骨を切り、引っ張るときに引き裂かれたような状況から、厚みのある相当丈夫なものでなければならないし、持ち運びの容易な長さ、大きさという制限がある。この点から肉厚が2.5~3ミリもあり、肉切り用として作られた牛刀、これに類似するチャッパーナイフなどが考えられる」
とのこと。
(ナイフ一例: 向かって左が渓流ナイフ、右チャッパーナイフ。さすがに右のタイプではないような気がするが・・・)
■ 小屋からは、犯人のものとみられる遺留品は発見されなかった。
また、小屋の周辺からルミノール反応が出なかった(という情報がある。しかし、小屋の床を文字通り血だらけにして逃走している犯人が、小屋周辺の地面に血液の痕跡が残らないよう工夫をする理由がわからず、また仮に遺体発見者ら---被害女性の父親を含む8名---の足裏に微量の血液が付着し、それが小屋周辺の地面に付着すればルミノールは普通反応するのではないか、と思うのだが、とにかく、小屋周辺からはルミノール反応が出なかったという情報があるにはある)
■ 軍手、刃物といった犯人の携行品、霧積川のえん堤横という条件などから、犯人像の一つとして、「釣り人」が有力視された。
しかし、群馬県内だけでも渓流釣りの愛好者は推定1万5千人、この他、許可なく川に入る、いわゆる無鑑札者も多く、釣り人の特定とアリバイ調べは難航した。
■ 現場が山のかなり奥まった場所にある作業小屋であることから、犯人が車で現場に来たであろうことが推測され、犯人像としては、「釣り人」と並んで「車での行楽客」も有力視された。
この点、複数の目撃証言から、犯行のあったとみられる13日午後には、きりづみ館から問題の作業小屋をはさんで霧積ダム工事現場までの約6キロの間に、30台前後の車が駐車していたのが確認されており、なかでも捜査本部が注目したのが、スバルの「R-2」という車種。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BBR-2
(スバル R-2のウィキペディア)
https://www.youtube.com/watch?v=tbwqWfwXZJw
(スバル R-2のYoutube動画)
これと同車種が、事件当日、作業小屋近くの林道に、計7台(うちグリーン系の色が4台)駐車しているのが目撃されていた。
捜査本部は、車両検問を実施するなどしてドライバーからの聴き込みを行ったが、有力な情報は得られなかった。
(スバルR-2、上下ともに1970年モデル。排気量356cc、空冷2気筒・2ストロークの30馬力、リアエンジン、トランクはフロント〈ボンネット下〉)
■ 不審車両という点についても、先のフジの番組で触れられており、
その部分のナレーションを書き出してみると、
「協力を願った当時の地元の警察署長(温井守夫氏・当時の捜査本部長)によると、犯行現場の小屋の前に、乗用車が止められているのが目撃されており、車を利用した犯罪説も有力」
■ 事件から8ヵ月目に入った1973年(昭和48)4月、捜査本部は縮小された。
縮小後の陣容は、捜査本部が松井田署の捜査員6名、これに応援部隊として県警本部の捜査一課・強行班から4名が交代で捜査に当たった。
■ 事件発生から1年間で、のべ8000人の捜査員を投入、その間、調べた捜査対象者が約6000人、同じく捜査対象車両が約1400台におよんだが、その後めぼしい進展もないまま、1987年8月に公訴時効が成立した。