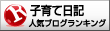こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。
いつもコメント・いいね・リブログ等いただきましてありがとうございます。
★初めましての方へ★
自己紹介ページはこちら
ブログに関するお願い事はこちら
人気の長編シリーズまとめページはこちら
お時間のある時にぜひご覧ください。
****************************************
前回で説明した通り、今回の相続法改正では、相続人や相続分など基礎部分について大きな改正はありません。
では、どのようなところが配偶者にとって優遇なのか、下記マンガのご夫婦のケースで学んでいきましょう!
相続法改正で新たに創設された法律が、配偶者居住権です。
配偶者居住権には、短期居住権と長期居住権があります。
短期居住権は、遺産分割協議成立までの間または6ヶ月間、亡くなった方の持家に住み続けることができる権利です。
例えば、遺産分割協議が相続発生後3ヵ月で配偶者以外が相続するとして成立した場合や、遺言で配偶者以外に遺贈されてしまった場合でも、6ヶ月間の猶予をもらうことができます。
権利は配偶者が亡くなったと同時に当然に発生しますが相続発生時点で配偶者の持家に居住していることが条件です。
ただし亡くなった配偶者が入院や施設入居などで同居していない場合でも大丈夫です。
長期居住権は、原則として終身の間、亡くなった配偶者の持家に住み続けることができる権利です。
こちらも短期居住権と同じく相続発生時点で配偶者の持家に居住していなければ取得できません。
権利を取得するためには、遺産分割協議で配偶者居住権を取得するか、遺言書で遺贈してもらうか、どちらかが必要です。
今回ケースでは、自宅の居住権と預金をバランスよく奥様に取得させることができるため、とてもメリットがありますね。
その他にも、例えば子どもがいないご夫婦の場合は奥様側の親族に自宅の権利が行くことを避けたいという場合もありますよね。
そういったときにも、居住権を遺贈して、夫側の親族に所有権を移転させることができます。
長期居住権と負担付所有権は、土地と建物をそれぞれ分けて評価する必要がありますが、マンガの例のように単純に2分の1の価格という訳ではありません。
居住権を相続する配偶者の年齢や物件の耐用年数など、土地建物それぞれ算定の基準がありますので詳しくは税理士にご相談ください。
長期居住権を取得したとしても、勝手に売却されたりしないのかと不安に思われる方もいるかもしれませんが、所有権だけではなく居住権についても登記されるため安心してください。
ちなみに、遺言で奧さんに居住権を相続させたい場合についての文言ですが、『遺贈する』と記載します。
通常の遺言では、相続人に対して取得させる場合『相続させる』と記載しますが、長期居住権の成立要件に『遺産分割』もしくは『遺贈』によって取得するかどちらかであるとされているためです。
例えば配偶者居住権が奥様にとって必要なかった場合、『相続させる』という文言だと相続放棄するしかありませんが、『遺贈する』の場合は遺贈の放棄だけ行い、他の権利を失うことがないように配慮した法律になっているそうです。
なるほど~。
ただし、2020年4月に施行される法律ですので、配偶者居住権について記載した遺言書を今作っても無効ですのでご注意くださいね。
次回は、配偶者の自宅不動産の贈与についてのお話です。
*************************************
インスタとツイッターやっています
楽天ルームも始めました
楽天room @まえあい
Instagram @maeai_madoka
twitter @maeai_madoka
フォローよろしくお願いいたします♡
外部ランキングサイト2つに登録しています。クリックして応援いただけたら嬉しいです!