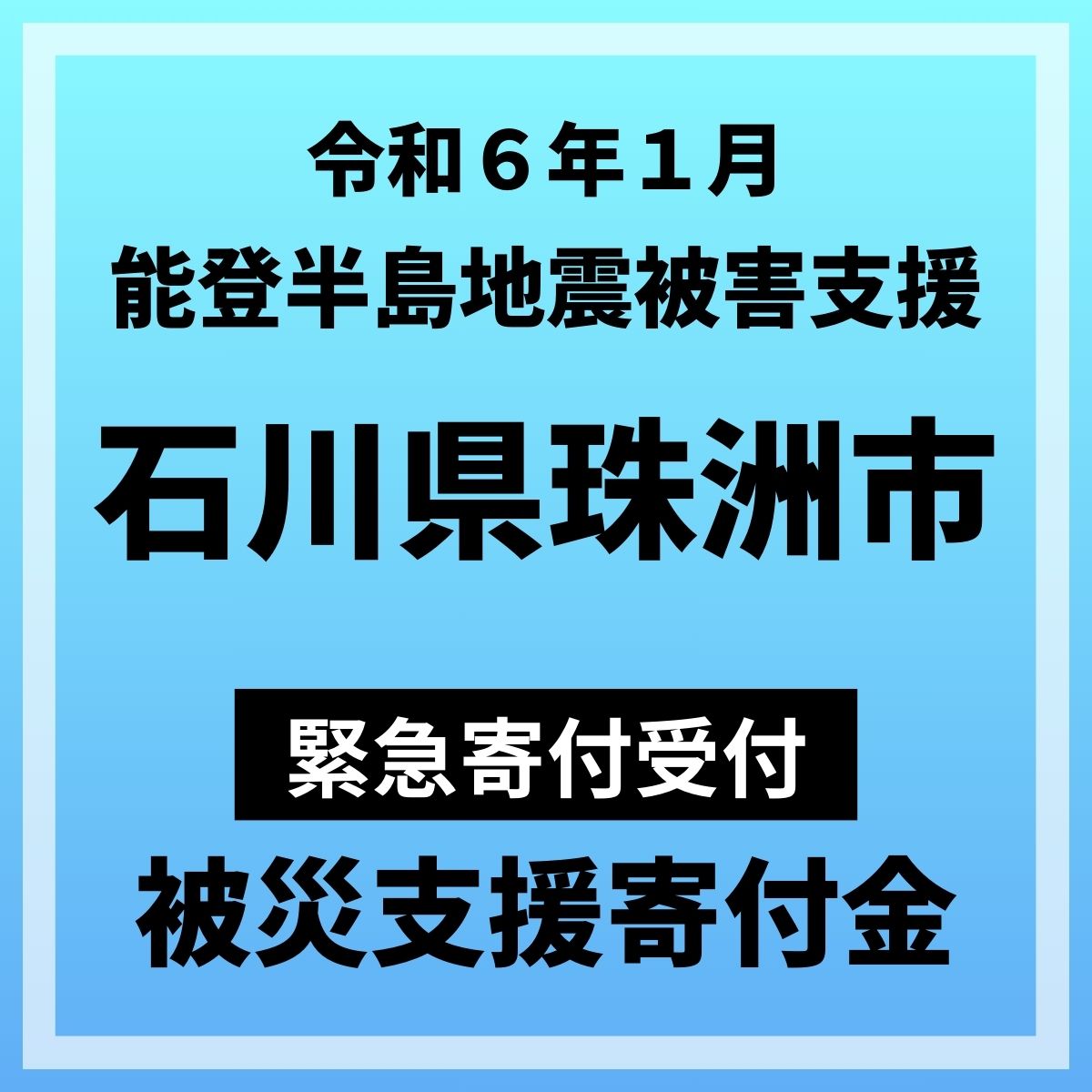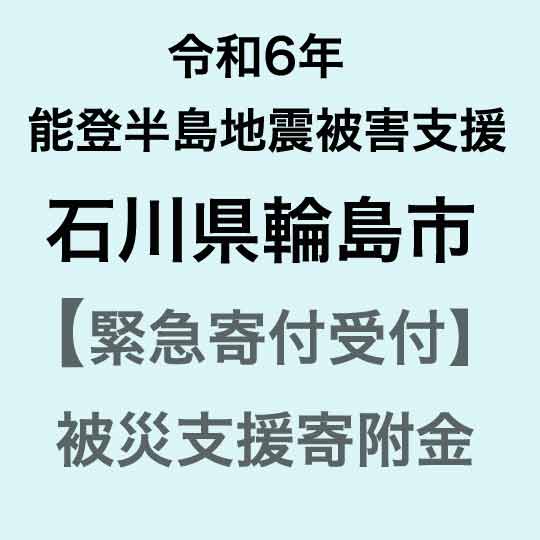今日も、
私のブログを見に来てくださり、
ありがとうございます。
48時間の間で
主人の両親を亡くしました。
(1/31朝義母、2/1夜義父)
無事に
義両親の葬儀を終えることができました。
私の介護に応援してくださった皆様、ありがとうございます。
そして、
これからもよろしくお願いします。
涙が出るというよりかまだやらなきゃいけないことがいっぱいあるので、それをこなすことへの不安やかんがえごとで時間ばかりが流れています。
介護に対する気持ちは達成感と安堵。
「これでよかったんだ」と思っています。
でもね、「もう少し義両親とは一緒にいられるのかな」と思っていました。
来年のお正月は無いかもと思っていたけど、まだ1か月前に年賀状で新年の抱負を語りあったばかりなのに。悲しすぎます。
いつ終わるかわからない介護にイライラしたり、不安になったりでしたが、急にストップしてしまうと、どうしていいかわからなくなるものです。
ましてや、まだまだ一緒にいれると思ったから、1月に入って、義父用の介護食をたんまり買ったばかりで。途方に暮れています。
さて、今日あったことを記録していきますと。
★式の1時間前集合
★導師様との打ち合わせ
義両親の戒名が決まりました。お布施は2人で30万円くらいです。
(義父)教え・誉・〇名前・識・信士
(義母)明るい・誉・〇名前・淳い・信女
二人とも、人柄があらわれた素敵な戒名をつけていただきました。
★葬儀
葬儀が始まる前に、導師様が焼香の仕方を教えてくれました。お話が上手でとても声の良いお坊さんでした。耳が悪い私でもちゃんと聞こえる。
葬儀には葬儀社の方が担当で1名つくのですが、その方の声は小さくて、マスクをしているとほとんど聞き取れませんでした。
私は難聴者だから聞こえなくても仕方ないのかなと思ったけど、みんなに後で聞いたら、みんなも同じこと考えてたって。葬儀はつつましやかに、大声を出すような方はいないのかなと思いました。でも、みんながみんな聞こえる人ばかりじゃないと思うし、ある程度発音をしっかりしていただかないと、指示が伝わらないこともあること、わかってほしいなと思いました。
お経は、私の実家の日蓮宗とは違い、聴きなれないお経だったので、突然大きな声が聞こえてきたり、物を散らしたり、たいまつを投げたり、楽器(銅鑼:どら)を用いたり。ビックリすることだらけでした。
*たいまつを用いるタイミングは、逝去した方を極楽浄土へと送り出す「引導下炬」という儀式を行うときです。この際、2本のたいまつを利用し、1本は穢れているこの世から離れることを願うために利用され、もう1本は浄土を欲する気持ちを表すために利用されるのだそうです。
★最期のお別れ
導師様が退席されると、家族はいったん式場から出されます。いよいよ出棺の準備が行われます。祭壇から棺に入れる花を引き抜いたり、焼香台や導師様が使っていた品物を外に運び出したり、呼び出されて、もう一度中に入ると、そこには義両親が並んでいました。この時にはさすがに私も涙が止まらなくなってしまって。それまでは笑顔で送り出せる状態でしたが、やっぱりさびしい。終わってしまったんだと思うと、何ともやりきれない気持ちになりました。もっとあーしてあげたかった、こうすればよかったと。決して後悔してるわけじゃないと思いたいけど、突然の終わりにどうしていいのやら、涙があふれて止まりませんでした。でも、そんな心の中に、「早く二人を家に連れて帰りたい」気持ちが強くて、それは荼毘にふされて肉体は消えてしまうのに、「早く・・・」って気持ちが強くて。やりきれない気持ちでした。
★出棺
ホールから出ると、2台の霊柩車が停まっていました。
事前の打ち合わせでは、義父の霊柩車には義父の弟(叔父さん)に乗っていただき、義母の霊柩車には喪主である義兄が位牌を持って乗るはずでした。その後ろを遺影を乗せた長男家族の自家用車・次男家族の自家用車と続き、孫や親戚を乗せたタクシー2台が続く形でした。
しかし、義兄が気が動転してたのか、義母の位牌を持ちながら、義父の霊柩車に乗ってしまいました。
棺の色が二人とも同じ色だったので、義父は白・義母は紫にすればよかったと今更ながら後悔。二人一緒ということは、こういうことが起きるのです。
こうして、2台の霊柩車が火葬場までの街の中心部を通る姿は、すごすぎました。でも、そんなの気にとめる人なんて、いないんだろうな。交差点で停まらない限りは。
★火葬場にて
霊柩車から棺をおろすと、お別れのホールになり、再び棺の窓が開けられて、焼香をしながら、お顔を拝むことができました。炉は7基くらいありましたが、1つ飛ばしで2台(3番と5番)使われていて、義両親は4番と6番の炉に入っていきました。
待っている間は、「おしのぎ」と言うらしいのですが、13時の火葬でしたので、軽食を準備なのですが、こちらの火葬場は売店がないので、私が用意したものを口にしながら、火葬が終わるのを待ちました。
前日のうちに、飲み物(ペットボトル350ml)・お菓子・紙皿・紙コップ・おしぼりを買いました。待合室に運ぶタイミングは、炉に棺が納められた時と聞いていたので、三男と駐車場のうちの車まで取りに行きました。ごみは、葬儀社の人が受け取ってくれました。
★収骨
火葬が終わると、喪主ともう1人炉のところに呼ばれるのですが、うちの場合は2人の葬儀となったので、4人で確認に行きました。主人と義兄だけでいいと思ったのですが、私まで呼ばれました。
94歳・92歳にしては立派な骨太な遺骨でした。でも、量としては少なかったのかな。実父(78歳)の時は骨壺に入りきらなくて、ゴリゴリ入れていました。その音にビックリした次男はその場で座り込んでしまいました。そのことがあるから、今日は次男に「ダメだと思ったら、後ろの椅子のところに行っていいからね」と言いましたが、7年経って大人になりましたね。ちゃんと見届けることができました。
義父は耳が遠かったけど、耳の穴と思える部分の骨がしっかり残っていました。歯は総入れ歯でしたので、何もなかったです。眼鏡は棺には入れられなかったので、骨壺の中に入れてもらいました。
義母は、歯がしっかり残っていました。おしゃべりだった母らしいと主人が言っていました。義母はペースメーカーを入れていたのですが、それがぺちゃんこになって、骨の中にありました。係の方が「どうしますか?こちらで処分することもできますが」と
言ってくださいましたが、このペースメーカーがあったおかげで92歳まで生きることができたので、身体の一部として骨壺の中に納めてもらうことにしました。それから、むくみではずされてしまった結婚指輪や思い出の指輪も骨壺の中に納めてもらいました。
骨壺の袋は、義父がゴールド・義母がピンクなので、今度は間違いなく持っていけそうです。
義父は長男家族の車・義母は私たちの車に位牌と遺影とともに乗りました。
★葬祭場に戻り、食事
献杯。親族の代表者が献杯の発声を行います。義両親の元にもお酒がそそがれました。陰膳はありませんでした。故人を偲び、食事を進めます。時間や食事の進み具合を見て、喪主(義兄)よりお礼の挨拶を頂き、散会となりました。
★解散・・・自宅へ
位牌・遺骨・遺影を抱き自宅へ戻りました。後飾壇は昨日のうちに葬儀社の方が作ってくださっていたので、そこに納めました。2人が並ぶっていうのは、幅も取るし、何より2倍ですからね。そして、果物かごと花かごを2つ持ってきましたので、かなりのボリュームです。しかしながら、1つの果物かごは義兄家族が持って帰ってしまいました。それって、故人にお供えするものではないの?
こうして無事に葬儀は終わりました。
うちの車には義母を乗せたので、義母の遺骨を抱きましたが、まだ温かかったなあ。
明日から、毎朝、義両親宅に行き、お水をあげたりしなきゃいけないのよね。まだまだ、ルナさんのお通いはつづく・・・。
▼本日限定!ブログスタンプ
進化・進歩を感じることは?
新型コロナウイルスの影響で、葬儀事情はずいぶん変わったと聞いています。もし、コロナ禍だったら、精進落としの食事はできなかっただろうし、火葬場に行ける人数も限られたのかもしれません。
義母は、2019年の12月にグループホームに入りました。その後すぐにコロナが流行し、面会ができなくなりました。コロナの時期にどっぷりはまっていた我が家の介護。でも、2人は強かった。施設と在宅と生活していく中で、コロナにかかることもなく、この4年間、大きな病気にもならず過ごすことができました。