【体験談】③不登校克服だけじゃない!治療薬からも卒業!
こんにちは、東ちひろです。
いつもありがとうございます。
さて、今回は、発達特性の子にもココロ貯金が効くという体験談の最終回です
①はこちら
②はこちら
宮治ゆみさんの長男さんはADHDの処方された薬を自然と減薬し、止めることができています。
薬をやめてから、今の小6の姿をお伝えしますね。
ASD/ADHDの男の子が不登校を克服し、薬をオフできた話③
◆ASDとADHDと診断され、薬を服用
2年生の夏、息子に大きな転機が訪れました。
発達検査を受けた結果、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)という診断がついたのです。
この診断により、放課後デイサービスの利用が認められ、徐々に人との交流や行動範囲が広がっていくことになります。
また、ADHD の衝動性や多動性を抑えるためのお薬を処方されました。
ところが、どうもうまくいきません。
服用すると昼間に強い眠気が出てしまい、起きられずに学校を休む日が続きました。
情緒を落ち着ける薬を飲むと、学校に行けない――本末転倒な状況に、親としても戸惑いました。

何度か主治医の先生とすり合わせした結果、2種類処方されていたうちの一方は、体質に合わないという結論に。
もう一方の薬だけに絞り、「どのタイミングで、どの量を飲むか」を少しずつ調整していきました。
そして、夜寝る前に服用すると翌日の血中濃度が安定することがわかり、ようやく息子に合ったスタイルが整っていったのです。
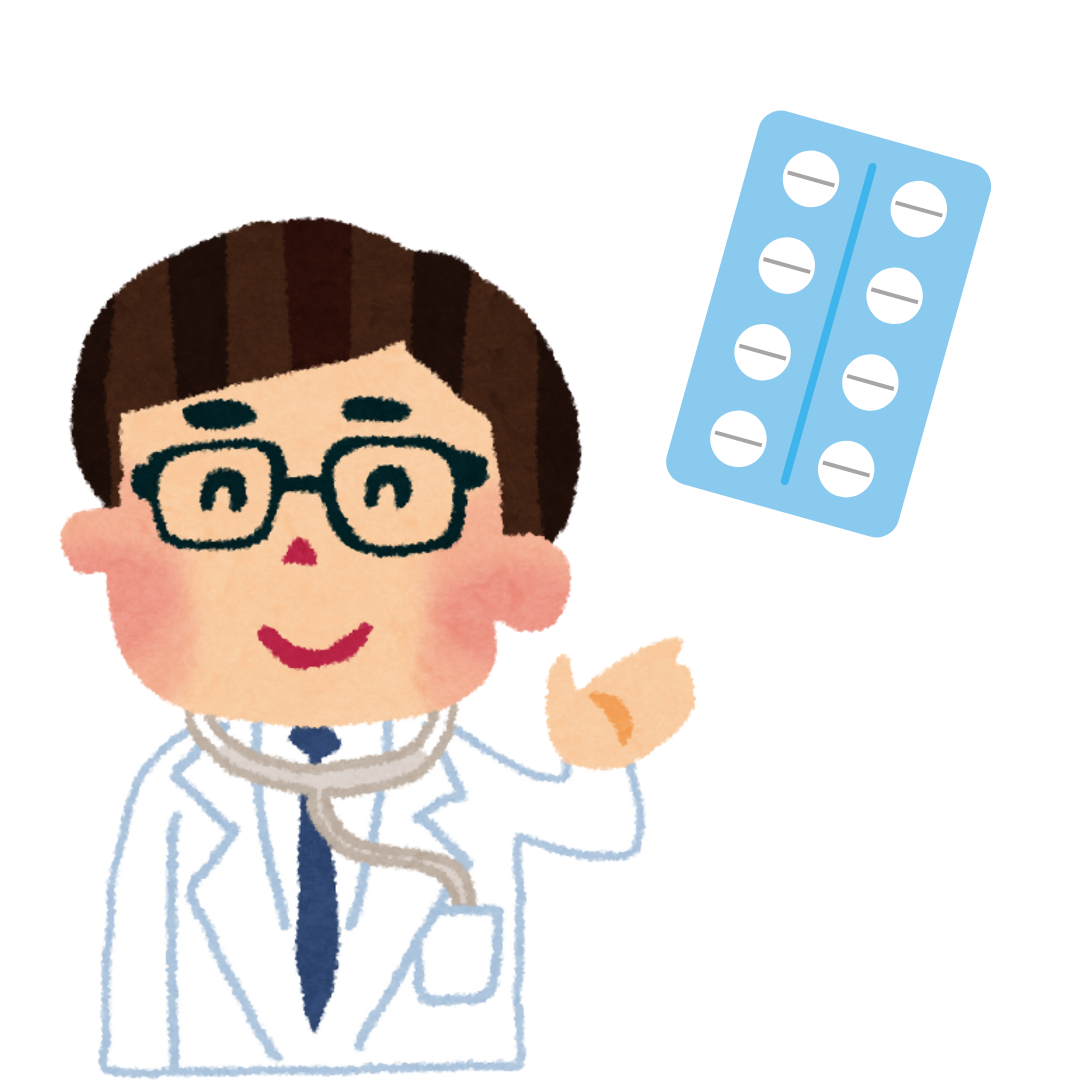
◆ココロ貯金で自然に減薬
ココロ貯金と薬の服用を続けていった結果、少しずつ教室で過ごせる日が増えていきました。
3年生になると、おばあちゃん、おじいちゃん、夫……とわたし以外のつきそいも可能になり、わたしの負担感はぐっと軽くなっていきました。
「薬は最低限の1ミリでいいよ。飲まなくてもよいけれど、どうする?」
主治医の先生にそう言われたのもこの頃のことです。
いきなり止めてしまうのは少し不安。
息子自身も飲んでいた方が安心する感じだったので、お守り代わりに少量だけ服用を続けることにしました。
つきそいが必要な時間は徐々に短くなり、送っていけば帰りは自分で帰ってくる日も増えていきました。
ただ「ランドセルはいやだ」という不思議なこだわりだけは、なかなか手放せずにいました。
ところが、4年生のお正月。
「ぼく、ランドセルしょっていく」
突然宣言した息子は、冬休み明けから、ホコリをかぶっていた“ピカピカのランドセル”で登校するようになりました。
以来ずっと、ランドセルで学校に通っています。

また、朝から下校時刻まで学校にいられるようになったのも4年生でした。
滞在時間が増えたぶん負荷も大きくなったようで、一時的に「ママきいて!」と不安を吐き出す場面が増えました。
でも、「そっかそっか」と寄り添いながら聴いていると、息子の気持ちはだんだんと落ち着いていくようでした。
3年生、4年生と進むにつれて、学校での負荷は確実に増えていったので、薬を止めるタイミングについてはなかなか踏み切れずにいました。
それでも、ランドセル登校を半年続け、息子も自信がついたのかもしれません。
小学5年生の夏。
主治医の先生が「もう薬を止めていいんじゃない?」とたずねたとき、息子はまっすぐに答えたのです。
「ぼく、もう薬はいらない」
こうしてついに──
薬を卒業したのです!
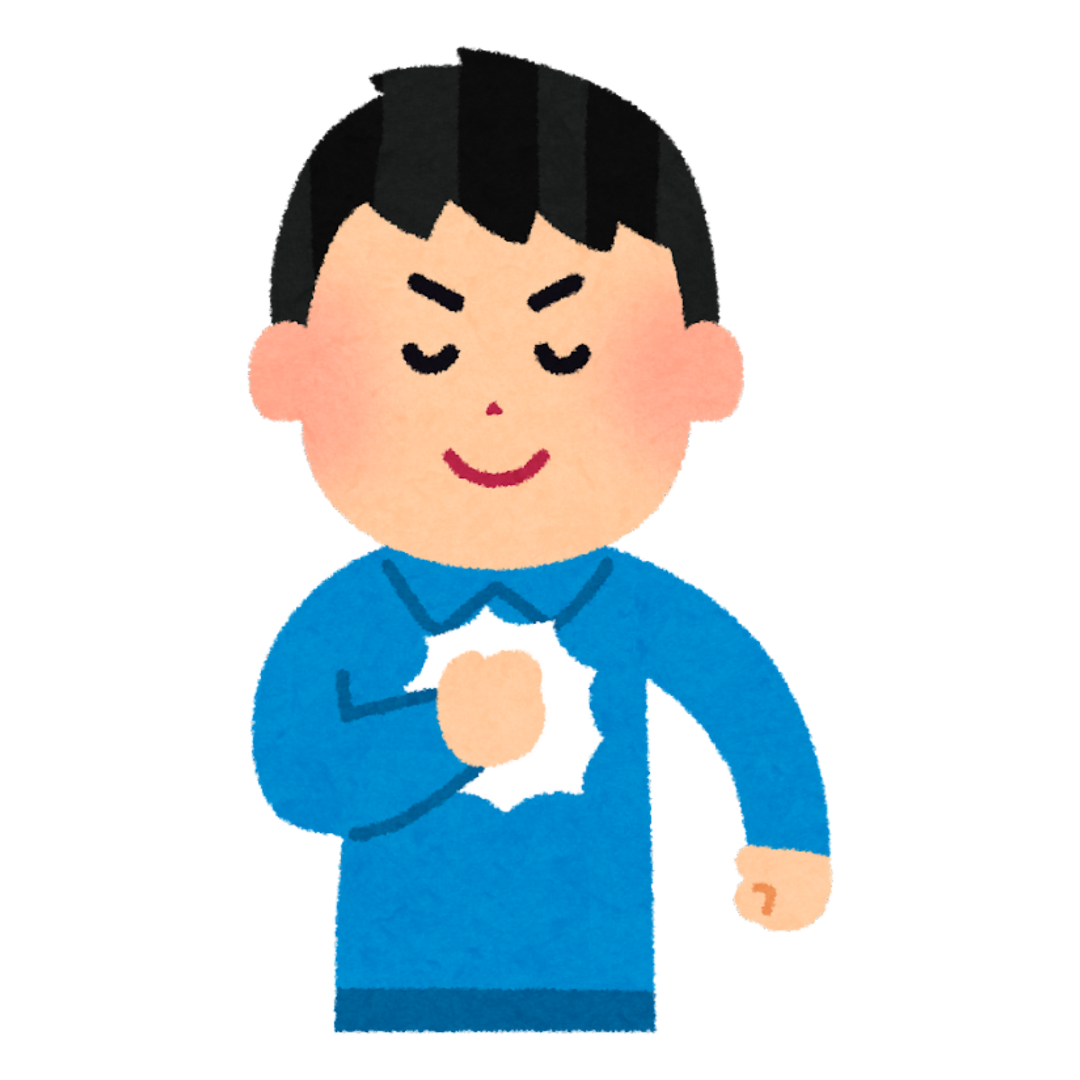
◆息子の今
息子は現在6年生。授業には毎日参加。
例えば、6時間授業のうち1コマだけしんどいときには、その時間だけ保健室に避難して、うまく調整しています。
「今日の社会、あまり好きじゃないから保健室に行きます」といった調子で、朝、先生に宣言するらしいのです。
発達特性のある子らしいな、と思うのですが。
6年生にもなると、まわりの子たちも「なんで保健室行くの?」などとは言わなくなりました。
息子の事情を理解して「そういう子なんだ」と受け入れてくれているのを感じます。
息子が「ありがとう」をよく口にするからか、クラスでもあまり浮いていないようです。

「移動教室は苦手」
「こういうときは不安」
しっかりと言葉で伝えてくれるので、学校へフィードバックしやすく、わたしも無理なく調整役を担えるようになりました。
先生に送っていただいた1週間の予定をもとに、息子は予定を組んでいきます。
「火曜日はしんどそうだから、ここまでにしよう」
「この日は早退して、放課後デイサービスに行こう」
自分で考え、事前に伝えてくれるので、仕事も調整できるようになりました。
どうすれば心地よく過ごせるのか、息子自身が自分のトリセツをわかってきたように感じます。
サポートが欲しいときにはSOSを出せるようになった息子の姿が、とても頼もしく映ります。
小学校に入学したばかりのあの頃、あんなに苦しんでいた日々が嘘のように、息子は今、自分らしく学校に通っています。
お友だちとの関係も親子関係も、穏やかであたたかいものになりました。
──ああ、心を育てるって大事なのだな。
ゆっくり、でも着実に歩んできた息子から、たくさんのことを教わった気がします。

宮治ゆみさんが実践したココロ貯金
・細やかで丁寧なスモールステップ
・息子さんの意思を尊重した自然な減薬
===================
東ちひろ
公認心理師
スクールカウンセラー
毎朝8時にココロ貯金のコツが届きます
■ココロ貯金講座 【事前案内フォーム】
ミニ講座、ココロ貯金講座、カウンセラー養成講座、など東ちひろの講座開催情報を優先的にご連絡差し上げます。
■Facebookグループ
「ママほめ」から「ココロ貯金」へ変わりました
*直接グループに申請された場合は、事務局スタッフよりお知らせがメッセンジャーに届きますので、一読ください。
*子育て世代の安心安全な場を作りたいと思っていますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
![]() 子育て心理学協会から、ココロ貯金を貯める子育てのコツ、ママのメンタル安定法、LINE限定イベント情報などをお送りします。
子育て心理学協会から、ココロ貯金を貯める子育てのコツ、ママのメンタル安定法、LINE限定イベント情報などをお送りします。
▼お友達登録してくださいねヽ(^o^)丿
LINE ID @chihiro.h











