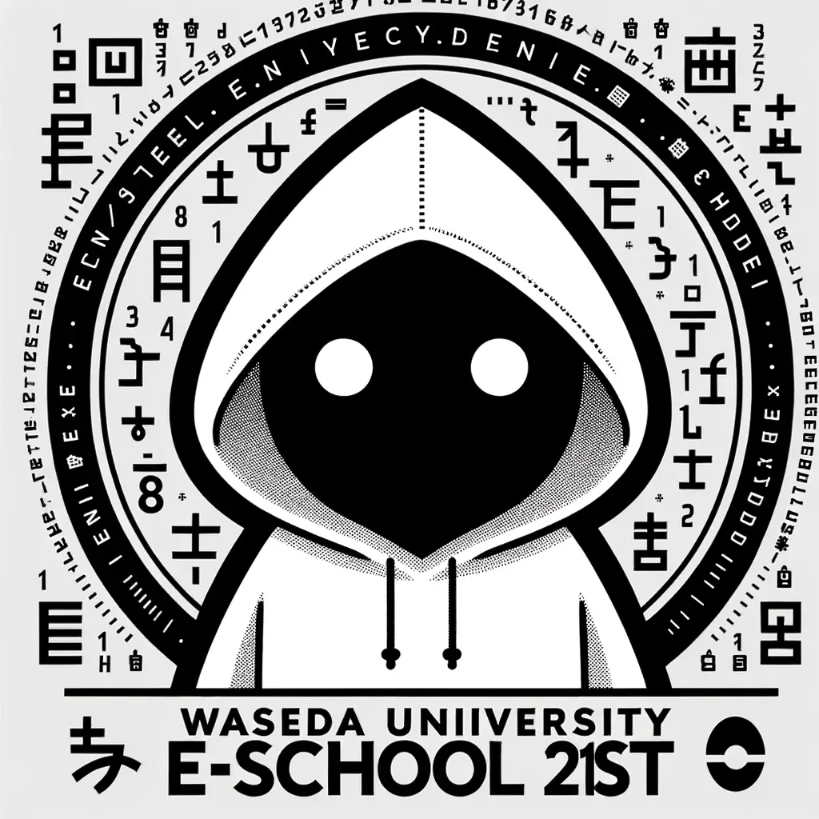社会人として働きながら通信制大学で学ぶことは、果たして現実的なのか。この問いに対する結論は明確である。勉強時間を確保できるのであれば、両立は十分に可能である。
通信制大学の最大の特徴は、自分のペースで学習を進められる柔軟性にある。講義はオンデマンドで配信されており、いつ視聴するかは自分で決められる。レポートの提出期限さえ守れば、平日の夜や休日など、自分の生活スタイルに合わせて学べるのが魅力だ。さらに、多くの大学では1年間に履修する科目数も選べるため、忙しい時期には履修数を減らして負担を調整することも可能である。
実際、通信制大学には多くの社会人学生が在籍している。30代から50代までの幅広い年齢層が学んでおり、その多くがフルタイムで働いている。共通しているのは、「何のために学ぶのか」という目的意識と、限られた時間をうまく活用する工夫である。たとえば通勤時間に講義を視聴したり、毎日30分でも学習時間を確保する習慣をつくったりすることで、学びを継続している。
もちろん、仕事、家事、育児などとの両立は、時間的にも精神的にも負担になることがある。しかし、計画的に時間を使い周囲の理解を得ることで乗り越えられる壁である。
したがって、仕事と通信制大学の両立は、勉強時間の確保ができれば十分に実現可能である。自分の未来に投資するつもりで、計画的に学びの時間をつくっていけば、仕事と学業の両立は決して夢ではない。