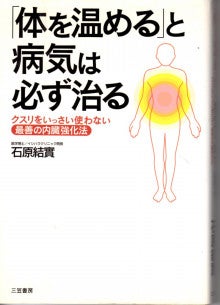連絡先 090-2647-1556
E・メール info@kousenchiryouin.com
飲み水のPFAS基準決定 米、世界的にも厳しく
共同通信社 2024年4月11日 (木)
【ワシントン共同】発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)を巡り、米環境保護局(EPA)は10日、飲み水の濃度基準を最終決定した。強制力を伴った全国基準は初。PFASは数千種類ある物質の総称で、代表的なPFOSとPFOAは各1リットル当たり4ナノグラム(ナノは10億分の1)と、世界的にも厳しい水準に設定した。米国が大きく踏み込んだことで、日本での今後の見直し議論に影響する可能性もある。
この2物質については安全な摂取量は存在しないとして、強制力のない目標値はゼロと決定。その上で、現実的に検査や削減が可能な規制値として1リットル当たり4ナノグラムを採用した。日本は水道水や河川など環境中の水についてPFOSとPFOAの合計で1リットル当たり50ナノグラムを暫定目標値としている。
またEPAは、PFNAやPFHxSなど他の種類についても1リットル当たり10ナノグラムとするなど規制を設けた。
国内6万6千カ所の公共水道は今後3年以内に汚染状況の監視と公表をするよう義務づけられ、規制値を超えた場合は削減措置を実施する。最大10%程度の事業者で対応が必要になるとみている。事業者らの検査・処理体制確立のため各州に資金支援する。
昨年3月に規制案を公表、12万件の意見が寄せられたという。
発がん性の恐れ、化学物質「PFAS」が全国の河川・井戸水から大量検出…国が対策へ
読売新聞 2023年4月28日 (金)
発がん性の恐れが指摘される化学物質「PFAS(ピーファス)」が、国内各地の河川や井戸水から高濃度で検出されている。ただし、健康への影響について不明な点が多く、国の対策は十分に進んでいない。住民から不安の声が上がる中、政府は専門家を交えて、汚染防止の方策について検討を始めた。(山下智寛)
基準の100倍超
「人体への影響を明らかにし、汚染対策の指針を示してほしい」。大阪府摂津市の市民団体のメンバーらが3月8日、PFASの一種、PFOA(ピーフォア)の調査を求める2万3788人分の署名を環境省に提出した。
同市内にある空調機器大手「ダイキン工業」の工場では1960年代から、自動車部品などの製造過程でPFOAを使ってきた。しかし、米環境保護局が米国内に拠点を持つ同社などにPFOAの使用停止を求めたため、2012年に使用を中止した。
その後は周辺の地下水をくみ上げ、活性炭でPFOAを除去していたが、環境省の20年度の調査では、工場近くの大阪市内の地点で、国の暫定目標値(1リットルあたり50ナノ・グラム=ナノは10億分の1)の110倍にあたる5500ナノ・グラムを検出。2年後の府の調査でも、周辺の用水路から6500ナノ・グラムが検出された。
府は地下水を飲まないよう呼びかけ、同社は追加の対策を公表したが、住民の不安は消えない。市民団体の谷口武事務局長は「周辺では農作物を育てているし、子供への影響も心配。国が責任を持って監督してほしい」と訴える。
製造・輸入を禁止
PFASの有害性が注目され始めたのは2000年代。米疾病対策センターが、血中濃度が高まると腎臓がんや精巣がんのリスクが高まる可能性を指摘した。国連のストックホルム条約会議で19年までに、PFASの一種であるPFOAとPFOS(ピーフォス)の製造・使用が原則禁止され、政府も21年までに、国内での製造や輸入を全面禁止とした。
環境省は20年、PFOAとPFOSを含む2リットルの水を毎日飲んでも健康に影響がないレベルとして、含有量の暫定目標値を設定。21年度の調査では全国1133地点のうち、13都府県の81地点で暫定目標値を超過した。
だが自治体の対応は、井戸水の利用停止や河川からの取水停止を呼び掛ける程度にとどまる。環境省が作成した手引には、「排出源の特定のための調査を実施し、濃度低減のために必要な措置を検討する」とあるだけで、具体策を示していないからだ。
神奈川県は超過地点で独自に検査を続けているが、付近に排出源となるような工場はない。県大気水質課の関猛彦課長は「住民の不安を払拭(ふっしょく)したいが、何をどれだけやれば十分なのか……」とこぼす。
不十分な知見
東京・多摩地区や沖縄県宜野湾市など高濃度のPFASが検出された地域では、住民らが独自に血液検査を行う動きが広がっている。
こうした状況を受け、環境省は今年1月、化学物質や公衆衛生などの専門家を集めた会議を設置し、手引の改訂や対策について議論を進めている。海外の最近の研究成果や各国の規制状況を参考に、事業者による排水を規制できるような法整備も視野に入れる。しかし、PFASが健康に与える影響について科学的な知見は海外でも不十分といい、「根本的な解決策を見つけるのは容易ではない」(環境省幹部)のが現状だ。
原田浩二・京都大准教授(環境衛生学)の話「規制強化が進む欧米に比べ、政府の動きは遅い。水質調査だけでなく、住民の血液検査や土壌調査を積極的に行い、汚染の全体像を明らかにすべきだ」
基準厳しい欧米
世界各国は、飲料水に含まれるPFASの基準値を相次いで厳格化している。世界保健機関(WHO)は昨年9月、PFOSとPFOAの基準値を1リットルあたり各100ナノ・グラムとする暫定案を公表したが、「できる限り低い濃度を達成できるように尽力すべきだ」と呼び掛けている。
欧州連合(EU)は、加盟国にWHOより厳しい基準を求めており、ドイツは2028年にPFASのうち4種類の合計で基準値を20ナノ・グラムとする方針。米環境保護局は今年3月、PFOSとPFOAの基準値を各4ナノ・グラムへと厳しくする案を公表。年内に最終決定する。
◆PFAS =有機フッ素化合物の総称。水や油をはじき、熱に強い性質から、フライパンのコーティングやはっ水スプレー、泡消火剤などに広く使用されてきた。自然界で分解されず、人体に長く残留するため、「永遠の化学物質」とも呼ばれる。
妊娠中の殺虫剤・防虫剤の使用と、児の新生児高ビリルビン血症との関連を明らかに
信州大ほか、研究成果は、小児科学系雑誌「Pediatric Research」に掲載
QLifePro 医療ニュース2020年9月4日 (金)
アジア人は他の人種に比べ、核黄疸の頻度が2~3倍高い
信州大学は9月1日、エコチル調査で収集した妊婦のデータを解析した「母親の妊娠中の殺虫剤・防虫剤の使用と児の高ビリルビン血症との関連」についての調査結果を発表した。この研究は、同大医学部衛生学公衆衛生学教室(エコチル調査甲信ユニットセンター)の野見山哲生教授、小児環境保健疫学研究センターの元木倫子講師(特定雇用)、小児医学教室の柴崎拓実氏、国立環境研究所エコチル調査コアセンターの山崎新センター長、同中山祥嗣次長らの研究グループによるもの。研究成果は、小児科学系雑誌「Pediatric Research」に掲載されている。
血清ビリルビンが高値になると黄疸となる。黄疸は新生児期によく見られる症状の一つで、一般的におよそ60%の児が顕性黄疸を呈する。新生児期に黄疸を呈する頻度には人種による差があり、アジア人(黄色人種)は白色人種に比べて2倍、黒色人種の3倍の頻度とされる。高ビリルビン血症は、核黄疸、脳性まひのリスク因子であり、アジア人は核黄疸のリスクが他の人種よりも高いと考えられている。
世界中で広く使用されている農薬や殺虫剤、虫よけ剤には、有機リン、ピレスロイド、カーバメート、ネオニコチノイド系、DEETなどがある。これらの薬剤は体内で抗酸化作用を有する酵素であるSOD(superoxide dismutase)、カタラーゼ、グルタチオンリダクターゼなどの活性低下をきたし、酸化ストレスを誘導するとされている。過剰な酸化ストレスは、赤血球の脂質過酸化から溶血を引き起こす。妊娠中の殺虫剤等のばく露により、児の赤血球が溶血をきたすと、新生児期の高ビリルビン血症のリスク因子となる可能性がある。そこで研究グループは、母親の妊娠中の殺虫剤・防虫剤の使用頻度が光線療法を要した新生児高ビリルビン血症の発生に与える影響について、疫学的手法を用いて調べた。
屋内でのスプレー式殺虫剤の使用頻度が多い母親の児は、新生児高ビリルビン血症の発生が1.21倍高い
今回の研究では、2016年4月に確定された妊婦約10万人のデータを使用。解析対象は、妊婦約10万人から、妊娠中の衣類用防虫剤、屋内でのスプレー式殺虫剤、蚊取り線香・電気式蚊取り器、園芸用農薬・殺虫剤、スプレーもしくはローションタイプの虫よけ剤の使用頻度に関するデータがそろった母親のうち、死産、流産、出生体重が2500g未満の児、および関連因子と考えたものに何らかの欠測データがある人を除いた61,751人とした。
新生児高ビリルビン血症のため光線療法を受けていたのは5,985人(9.7%)だった。母体の殺虫剤・防虫剤へのばく露の程度は、妊娠中期/後期に行った自己記入式質問票への回答を使用した。母親が妊娠中に衣類用防虫剤を使用していたのは36,610人(59.2%)、屋内でスプレー式殺虫剤を使用していたのは20,352人(33.0%)、蚊取り線香・電気式蚊取り器を使用していたのは19,518人(31.6%)、園芸用農薬・殺虫剤を使用していたのは5,333人(8.6%)、スプレーもしくはローションタイプの虫よけ剤を使用していたのは15,309人(24.8%)だった。
一般的に新生児高ビリルビン血症の関連因子として考えられているものには、妊婦の年齢、児の性別、在胎週数、出生体重、出生時仮死の有無、妊娠中の母体合併症の有無、産科的合併症の有無、世帯収入、母の教育歴などがある。そのため、これらの影響について考慮した研究デザインを用い、妊娠中の殺虫剤・防虫剤の使用頻度と光線療法を要した新生児高ビリルビン血症の発生との関連についてロジスティック回帰分析により検討した。
その結果、母親が妊娠中に屋内でスプレー式殺虫剤を使用した頻度が週に数回以上と多い群では、全く使用していない母親から出生した児に比べて、光線療法を要する新生児高ビリルビン血症の発生が1.21倍(95%信頼区間1.05-1.38)高かった。それ以外の使用に関しては、その使用頻度が高いことが光線療法を要する新生児高ビリルビン血症の発生の有無とは明らかな関連がなかった。
今後は化学物質以外の因子等との関係の知見も総合して検討
一方、スプレーもしくはローションタイプの虫よけ剤については、全く使用していない群と比べて使用頻度が週に数回以上と多い群の方が、光線療法を要する新生児高ビリルビン血症の発生が0.70倍(95%信頼区間0.61-0.81)低かった。なお、出生体重が2,500g未満の低出生体重児を含めて解析した場合でも同様の傾向となった。スプレーもしくはローションタイプの虫よけ剤の使用頻度が多い群の方が、光線療法を要する新生児高ビリルビン血症の発生の可能性が低くなる結果となった理由を説明し得る機序については不明としている。同研究は、妊娠中の殺虫剤・防虫剤へのばく露が新生児に与える影響の一つとして、治療を要する新生児高ビリルビン血症を引き起こすリスクについて検討した初めての研究となる。
今回の研究では、母親の殺虫剤・防虫剤のばく露に関する情報が血中濃度など客観的なデータとして得られていない。また、調査時期が妊娠中期/後期であり、最も新生児の高ビリルビン血症に影響を与えると考えられる妊娠末期(出産直前)におけるばく露について正確に評価できていない。加えて、各医療機関で光線療法を行う基準となる血清ビリルビンの値が異なっている可能性もあり、これらの課題について考慮する必要がある。
エコチル調査では、化学物質以外の環境因子、遺伝要因、社会要因、生活習慣要因等についても調べている。今後これらの因子と新生児高ビリルビン血症との関係についても知見が出てくることが予想される。そのため、これらの化学物質以外の因子等との関係の知見も総合して殺虫剤・防虫剤ばく露と新生児高ビリルビン血症の発生との関係について検討する必要がある。引き続き、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因が明らかとなることが期待される。
「カネミ油症」救済になお壁
毎日新聞社 2020年8月11日 (火)
<くらしナビ・環境>
ポリ塩化ビフェニール(PCB)や猛毒のダイオキシン類が混入した食用油による国内最大の食品公害「カネミ油症」の発覚から今年10月で52年。2012年に被害者救済法が制定されたが、今なお認定のハードルは高く、患者の多くが取り残されている。
●子や孫も同じ症状に
生後6カ月で表れた全身の湿疹。成長とともに続く頭痛や腹痛、倦怠(けんたい)感……。長崎県諫早市の下田恵さん(31)は、汚染された食用油を直接口にしていないにもかかわらず、小学1年の時に摂取して油症の患者に認定された母親(59)と同様の症状に苦しんできた。
患者認定を求めて06年からほぼ毎年、県が実施している油症検診を受診しているが、ダイオキシン類のポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)の血中濃度が基準値より低いことを理由に却下され続けてきた。「1世代だけでは終わらない。全身の症状を見てほしい」と訴える。
患者の症状は皮膚の黒ずみや爪の変色、手足のしびれ、倦怠感や頭痛、内臓疾患など、「病気のデパート」と称されるほど多岐にわたるが、根本的な治療法は確立されていない。
さらに、油症の原因となったPCBやPCDFは体内に蓄積されやすく、摂取した母親の胎盤や母乳を介し胎児に影響するとの研究報告がある。摂取した人だけでなく、下田さんのような直接口にしていない子どもや孫にも同様の症状を訴える人は少なくない。
被害が発覚した1968年10月から69年7月の間に、西日本一帯で1万4000人以上が保健所に被害を届けた。当時は皮膚症状が重視され、認定は約900人にとどまったが、その後も被害を訴える患者は増え続けた。
12年に被害者救済法が施行され、公的救済制度がようやくできた。発覚当時に認定患者と同居していた家族は検診を受けなくても認定対象となったが、認定患者数の累計は20年3月末で2345人にとどまっている。なぜか。
●厳しい認定基準
油症かどうかは、国の助成を受ける九州大などの全国油症治療研究班が、検診で吹き出物や色素沈着などの皮膚症状やPCDFの血中濃度などの基準を基に総合的に判断し、都道府県が患者認定する。認定されれば、医療費の自己負担分は汚染油を製造したカネミ倉庫(北九州市)から支払われる。
ところが、汚染油を摂取していてもこれまで認定されなかった人や差別を恐れて検診を受けていなかった人、発覚後に被害者から生まれた子や孫は、検診を受けても血中濃度が基準を下回るケースが多い。厚生労働省によると、12年度からの8年間で、油症検診を受けた未認定者1165人のうち認定されたのは52人。認定率は4・46%にとどまる。このため油症の患者団体は認定基準の見直しを求めている。
同研究班班長の古江増隆・九州大大学院教授(皮膚科学)は「PCDFなどダイオキシン類は一般の人からも検出されるため皮膚に特徴的な症状がない場合は、医学的には血中濃度を見るしかない」と説明。子や孫の健康影響との因果関係についても「十分な科学的知見は得られていない」としている。
●「時間経過し濃度低下も」
ただ、油症の認定基準にPCDFの血中濃度が加わったのは、発覚から36年たった04年だ。油症患者を診察してきた菊陽病院(熊本県)の藤野糺医師(精神神経科)は「時間の経過でPCDFが排出されたため血中濃度が下がった可能性があるほか、摂取量や排出機能に個人差がある。血中濃度が低くても否定の根拠にはならない。現行の診断基準は厳しすぎるので、検証されるべきだ」と指摘する。
藤野医師は14年から長崎県五島市や北九州市、名古屋市などで次世代を含む未認定患者の健康調査を続けている。幼少期に汚染油を食べた北九州市の女性患者は8回の妊娠で4回の流産や死産を経験。4人の子どもは皮膚の色素沈着や倦怠感、頭痛など患者に多い症状があった。また、名古屋市の患者の子や孫には、永久歯の欠如や鼻血など出血が止まりにくい血小板無力症や、性器の先天異常があるといい、「PCDFは母体から胎児への移行だけでなく、遺伝子を傷つけて子や孫に受け継がれている可能性がある」とみる。
水俣病の救済にも取り組んできた藤野医師は「水俣病では未認定者が残されているものの、約7万人が医療費などの救済を受けた。油症事件は汚染された地域の広がりを見ても、その比ではない。摂取した全ての人や次世代を調査し救済すべきだ」と強調する。
千葉県の認定患者の男性(58)は「カネミ油症は終わっていない。あらゆる化学物質があふれる今、真剣に向き合わなければ、同様の食中毒公害が起きかねない」と訴えた。【岩崎歩】
顔のない赤ちゃん生まれる、医師に6か月の停職処分 ポルトガル
AFPBB News 2019年10月26日 (土)
母親の指を握る新生児の手(2013年9月17日撮影、資料写真)。(c)PHILIPPE HUGUEN / AFP
【AFP=時事】ポルトガルで今月、顔のない赤ちゃんが生まれた。これを受けて、担当の産科医が職務怠慢の疑いで停職処分となった。この問題は、同国に衝撃をもたらしている。
ロドリゴちゃんと名付けられたこの新生児は今月7日、首都リスボンから南に約40キロ離れたセトゥバル(Setubal)の病院で、鼻と両目、頭蓋骨の一部がない状態で生まれた。顔面の欠損は、出産時に初めて分かったとされる。
ポルトガルの医療協議会は22日、アルトゥール・カルバーリョ(Artur Carvalho)医師を6か月の停職処分にすることを全会一致で決めた。
セトゥバルの私立医院で母親の健診を担当していたカルバーリョ医師は、義務付けられている3回の超音波検査を実施していたが、懸念をもたらす問題には一度も言及していなかった。
妊娠6か月の時、両親は追加の超音波検査を希望。その際同医師は、胎児に異常がある可能性について伝えたものの、問題ないと話して両親を安心させていた。
母親の親族が民放TVI 24に語ったところによると、同医師は超音波検査では「赤ちゃんの顔が母親のお腹に密着していると、顔の一部が見えないことはままあると説明していた」という。
カルバーリョ医師にはロドリゴちゃんの件以外にも、2013年以降6件の苦情が寄せられていた。
同国南部地方医療協議会の代表は公共放送RTPに対し、同医師の職務怠慢を示す「有力な証拠」があり、「懲戒処分につながり得る」と述べた。
ロドリゴちゃんは現在も、生まれた病院の小児病棟に入院している。【翻訳編集】 AFPBB News
メチル水銀:マグロ過食に注意 妊婦から胎児へ影響、低濃度でも 東北大調査
毎日新聞社 2016年11月28日 (月)
マグロやメカジキなどメチル水銀を比較的多く含む魚介類を妊婦が食べ過ぎると、生まれた子の運動機能や知能の発達に悪影響が出るリスクが増すことが、東北大チームの疫学調査で分かった。メチル水銀は水俣病の原因物質だが、一般的な食用に問題のない低濃度の汚染でも胎児の発達に影響する可能性があることが明らかになるのは、日本人対象の調査では初めて。
2002年から、魚をよく食べていると考えられる東北地方沿岸の母子約800組を継続的に調査。母親の出産時の毛髪に含まれるメチル水銀濃度を測定し、子に対しては1歳半と3歳半の時点で国際的によく用いられる検査で運動機能や知能の発達を調べ、両者の関係を分析した。
毛髪のメチル水銀濃度は低い人が1ppm以下だったのに対し、高い人は10ppmを超えていた。世界保健機関などは、水俣病のような神経障害を引き起こす下限値を50ppmとしている。
濃度が最高レベルの人たちの子は最低レベルに比べ、1歳半時点で実施した「ベイリー検査」という運動機能の発達の指標の点数が約5%低かった。乳幼児期の運動機能は将来の知能発達と関連があるとされる。3歳半時点の知能指数検査では男児のみ約10%の差があった。海外の研究で、男児の方が影響を受けやすいことが知られている。
国は05年、海外の研究を基に、妊婦に対しメチル水銀の1週間当たりの摂取許容量を体重1キロ当たり100万分の2グラムと決めた。厚生労働省はこれに基づき、クロマグロの摂取は週80グラム未満とするなどの目安を示している。今回の調査では食生活も尋ねており、約2割がこれを超えていたと考えられるという。
研究チームの仲井邦彦・東北大教授(発達環境医学)は「目安を守れば、影響は心配しなくてよいと考えられる。魚には貴重な栄養も含まれており、妊婦が魚を断つことは好ましくない。食物連鎖の上位にいるマグロなどを避けサンマなどを食べるなど、魚種を選ぶことが大切だ」と話す。【渡辺諒】
……………………………………………………………………
■解説
◇個人差、環境要因で違い
東北大チームの研究で比較的低濃度のメチル水銀でも妊婦が摂取した場合、胎児の発達に影響するリスクがあることが明らかになったが、影響の受けやすさには個人差があり、多く摂取した母親の子が必ずしも大きな影響を受けるとは限らない。今回の研究結果は、個人レベルではなく、集団として将来知的障害と判断される子の割合が増えることを意味する。
例えば1000人の集団の場合、メチル水銀の影響がなくても、知的障害と判断される子が23人程度生まれることが経験的に分かっている。メチル水銀を多く摂取した結果、ベイリー検査の点数が約5%下がることは、これが約2倍の48人程度になるリスクが生じることに相当するという。
子どもの発達には遺伝や教育など、さまざまな環境要因も大きく影響する。また、低濃度のメチル水銀と子の脳の発達の関係は未解明のことが多い。個々の子に知的障害が疑われる場合、メチル水銀が影響したかどうかは判別できないのが現状だ。【渡辺諒】
……………………………………………………………………
◇厚生労働省が定めた妊婦の摂取目安
週80グラム未満
クロマグロ、メバチマグロ、メカジキ、キンメダイ、ツチクジラなど
週160グラム未満
キダイ、ユメカサゴ、ミナミマグロ、クロムツ、マカジキなど
※刺し身なら1人前、切り身なら1切れが約80グラム
……………………………………………………………………
■ことば
◇メチル水銀
水銀は地殻や土壌に含まれ、火山噴火や石炭の燃焼、金の採掘などに伴って排出される。これが水中や土壌中で微生物の働きなどによって化学変化し、メチル水銀が生成される。海水にも含まれ、食物連鎖によって徐々に濃縮し、上位に位置するクロマグロなどで濃度が高くなる。水俣病は、工場排水中の高濃度のメチル水銀が原因となった。
メチル水銀摂取:妊婦へ周知徹底を 健康影響、研究進まず
毎日新聞社 2016年11月28日 (月)
水俣病のような神経障害を引き起こすよりはるかに低い濃度でも、妊婦のメチル水銀摂取が胎児の発達に悪影響があることが仲井邦彦・東北大教授らの研究で明らかになった。日本は水俣病を経験しながら、これまで低濃度のメチル水銀の健康影響について研究が進んでこなかった。国はさらに実態解明を進めるとともに、妊娠中にメチル水銀を多く含む魚種を控えることで防げるリスクだけに、妊婦の食生活の注意点について周知徹底する必要がある。
今回見られたスコアの差は、本来、子が持っているはずの能力がそれだけ下がることを意味し、「社会に与える影響は大きい」(仲井教授)と言える。国立成育医療研究センターの田中恭子医長も「1歳半の結果に加え、3歳半でも同様の傾向が出ていることは注目される」と指摘する。
厚生労働省は2005年、妊婦に対するメチル水銀を含む食品摂取の目安を定めたが、今回の調査地点では、約2割の妊婦がこれを超えていたと推定された。
厚労省の担当者は「目安は周知しており、浸透していると考えている」と話したが、徹底されていないことが明らかになった。
そもそも日本の摂取許容量は、クジラなどをよく食べるデンマーク自治領フェロー諸島などで1980~90年代に行われた調査を基に決められたもので、これまで日本人のデータはなかった。
吉永淳・東洋大教授(環境健康学)は「疫学研究は、一つの研究結果だけで判断するには不十分な面もある。対象者を変えながら、複数の調査結果を突き合わせて慎重に考える必要がある」と指摘する。
現在、北海道や高知県などで環境省による同様の調査が進んでおり、結果が注目される。【渡辺諒】
アクリルアミド、どう減らす? 食品安全委「発がん性、懸念なしと言えず」
朝日新聞 2016年3月4日 (金)
野菜や穀物などを焼く、炒める、揚げるなど高温で調理すると、アクリルアミドという化学物質が発生する。動物実験で発がん性が認められており、内閣府食品安全委員会の作業部会は「できる限り低減に努める必要がある」という評価書案をまとめた。家庭ではどうしたらいいのだろうか。
先月16日に公表された評価書案はアクリルアミドの発がんリスクについて「ヒトにおける健康影響は明確ではないが、懸念がないとは言えない」と指摘した。どういうことなのか。
作業部会はまず、日本人がどれだけアクリルアミドを摂取しているかを調べた。体重1キロあたりで算出した推定量は1日0・24マイクログラム。その約半分は炒めたモヤシやタマネギ、レンコンといった高温調理した野菜からで、残りはコーヒーや緑茶などの飲料、菓子類や糖類、パンなどの穀類からと推定された。
この量は動物実験でがんの増加が確認された量の1千分の1ほどにすぎない。しかし海外のリスク評価機関には、1万分の1より多い場合は低減対策が必要だとする所もある。「懸念がないとはいえない」という表現になったのはこのためだという。
動物実験ではなく、ヒトの摂取量とがんのリスクとの関連を調べた研究成果も多数分析した。すると、こちらは一貫した傾向はみられなかったという。
食安委の佐藤洋委員長は次のように説明する。
「アクリルアミドは動物実験で発がん性が確認されている。ただ、ヒトを対象とした調査の全体をみるとアクリルアミドが原因でがんが増えているとは認められない。そうした意味ではそれほど心配しなくてもいい。とはいえ摂取しない方がよいことには変わりないので、できるだけ減らすよう気にかけてくださいということです」
■保存や下準備も工夫
アクリルアミドは多くの加熱した食品に、わずかながら含まれる。加熱調理は食材をおいしく安全に食べるために必要なことでもある。アクリルアミドをまったくとらないようにするのは難しい。
だが、家庭でのちょっとした工夫で量を減らすことはできる。
まずは準備段階でできることから。農林水産省によると、炒めたり揚げたりするジャガイモは常温で保存するといい。長期間冷蔵すると、加熱時にアクリルアミド生成の原因となる糖が増えるという。
イモ類やレンコンは、切った後に水にさらすとアクリルアミドに変化する成分が表面から洗い流される。
調理する時は加熱しすぎないことが大切だ。
炒めたり揚げたりする場合は焦がしすぎないよう注意する。農研機構食品総合研究所の実験では、食材を炒める時間が長くなり、焦げ色が濃くなればなるほどアクリルアミドの濃度が増した。食パンを焼いた場合も、トースト時間や焼き色とアクリルアミドの濃度には同じ傾向が出た。
炒めるときは火力を弱めにする。さらによくかき混ぜれば、一部分だけが高温になるのを防げる。
■ゆでる・蒸す・煮る、効果的
ゆでる、蒸す、煮るといった水を利用する調理では、食材の温度は120度以上にならず、アクリルアミドはほとんどできない。炒める調理の一部を蒸す、煮るなどに置き換えることも効果的だ。
食品総合研究所などはそのことをきんぴらゴボウ作りで確かめた。15人の協力者に、それぞれの普段の作り方と研究所が指定した作り方の2通りで作ってもらい、アクリルアミド濃度を比較した。
指定の作り方では、炒める時は火加減を弱くして速くかき混ぜる。さらに炒め時間を短くして、代わりに弱火で15分間蒸し煮にしてもらった。
普段の作り方では、アクリルアミドの濃度は人によってばらつきが出た。一方、指定の作り方では全員、濃度が低く、中には普段の100分の1以下になった人もいた。
味の評価もした。指定の作り方をしたきんぴらゴボウを大学生65人に食べてもらったところ、52人が「普段食べているのと同じくらいおいしい」、3人は「よりおいしい」と答えた。
小野裕嗣上席研究員は「アクリルアミドは少しの工夫で減らせる。できる範囲で工夫をすればよいと思います」と話している。
農林水産省は「安全で健やかな食生活を送るために アクリルアミドを減らすために家庭でできること」という冊子をまとめ、ウェブサイト(http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/acryl_amide/index.html)で公開。希望者には配布している。問い合わせは同省食品安全政策課(03・3502・8731)。(沼田千賀子)
◆キーワード
<アクリルアミド> 有機化合物の一種。食品中では炭水化物を多く含む野菜や穀類などを揚げる、焼く、あぶるなどして120度以上の高温で加熱すると特定のアミノ酸と糖が化学反応を起こして生成される。加工食品に含まれるほか、条件がそろえば家庭での調理でもできる。
ハムやソーセージ「発がん性ある」…WHO外部組織が認定
読売新聞 2015年10月28日 (水)
【ジュネーブ=石黒穣】世界保健機関(WHO)の外部組織、国際がん研究機関(IARC)は26日、ハムやソーセージなど加工肉について新たに「発がん性がある」と認定したと発表した。牛や豚など哺乳動物の赤身の肉についても「恐らく発がん性がある」とした。IARCは、各国政府がリスクと栄養のバランスを考えた肉の摂取指針を示すべきだとしている。
5段階の発がん性評価で、加工肉はリスクが一番大きい「グループ1」、赤身の肉は2番目の「グループ2A」に分類された。
加工肉に関しては、毎日食べる量が50グラム増すごとに大腸がんになる確率が18%上昇するという。赤身の肉は大腸がんのほか、膵臓すいぞうや前立腺のがんを引き起こす危険が認められるという。
専門家グループが、各国で出された800以上の研究報告を分析して結論づけた。
「加工肉に発がん性」 WHO、赤身肉にも恐れ
共同通信社 2015年10月27日 (火)
【ジュネーブ共同】世界保健機関(WHO)の専門組織、国際がん研究機関(IARC、本部フランス・リヨン)は26日、ソーセージやベーコンなどの加工肉について「発がん性が十分認められ、大腸がんになるリスクがある」との調査結果を発表した。赤身肉についても発がん性の恐れがあると指摘した。
欧米メディアによると、発がん性につながる物質が加工段階で生成されるという。欧米に比べると日本人の肉類の消費量は少なく、「日本人の一般的な消費レベルなら大腸がんリスクにはならない」との研究結果もある。
IARCによる発がん性の評価は5段階で、加工肉は喫煙やアスベストなどと同じく最も高いレベル。毎日50グラムの加工肉を消費すれば、大腸がんのリスクが18%増加すると結論付けた。
IARCの専門家は声明で「消費量によってがんが発生するリスクが高まる」と指摘、消費者に食べ過ぎないよう警告した。
赤身肉については、主に大腸がんとの関連があるとしつつ、膵臓(すいぞう)がんや前立腺がんとの関連もみられるとした。
-------------------------------------------------------------------------------
全身の60兆の細胞のために![]()
生活の質(QOL)を下げないために自宅治療が一番![]()
ご自宅で”光線”
医聖ヒポクラテス
「人間は誰でも体の中に百人の名医を持っている」
”光線”で身体を温めれば”自らの内に百人の名医が存分に働いてくれる”のでは![]()
<当方の光線治療器の原理>
1893年、デンマーク人のニールス・フィンゼン博士によって世界で初めて太陽光線と同じ連続スペクトル光線を放射するカーボンアーク灯(人工太陽灯)が開発され、当時不治の病と言われていた皮膚病(尋常性狼瘡(じんじょうせいろうそう))を治して、1903(明治36)年 ノーベル医学生理学賞を受賞しています。
<この原理を進化させているのです>![]()
もっと自分自身を信じて![]()
健康のために
ご注文下さい、当方へ
~・*・~・*・[PR]~・*・~・*・~・*・~・*・~・*・~・*・~・*・~・*
『免疫革命!はじめてがんの原因が分かった!』
先生の方言がきつく中々聞き取れないのですが、ご興味のある方へ文字越しをしたものがありますので当方へご連絡ください。メールでお送りいたします![]()
”がん”でお悩みの方、ご自宅での”光線治療”をお勧めします !!
http://ameblo.jp/kousenchiryou/entry-12023089160.html
光線の”がん”体験!!
http://ameblo.jp/kousenchiryou/entry-11959763004.html
”がん”の温熱療法!!
http://ameblo.jp/kousenchiryou/entry-11991553295.html
”がん”を患い”抗がん剤”を選択されている方々へ
http://ameblo.jp/kousenchiryou/entry-12000475191.html
医者に殺されない47の心得 近藤 誠 著 ㈱アスコム
ご相談は下記E・メールまで![]()
だから
各ご家庭に”光線室”が必要です!!
我が家の場合指を切っても、孫の肺炎、急激な嘔吐などでも光線です。
サンフォートピア療法
光 線 治 療 院
松本 忠
TEL 090-2647-1556
E・メール info@kousenchiryouin.com
URL http://www.kousenchiryouin.com/
光線治療体験 ブログ http://kousenchiryouin.blog.shinobi.jp/
ランキングに挑戦中デス!! ポチッとよろしくお願いします。
山本太郎代表「博打を進める政治なんて終わってる!」2022年9月30日カジノは日本のどこにもいらない!東京大行動 スピーチフル動画【れいわ新選組】2022/10/6
何だっけ?誰だっけ?作戦