では15年たったこの『超「超」整理法』 はどうか? というと、ファイリングが検索に代わりに、その代表がG-mailを使うこと。ということで、他にもいいことは書かれているのですが、自分の中にはあまり入らず・・・。あらためて15年前の俺と変わってないじゃん。と思ってしまいました。(でも全部読み切ったから、その分は進歩しているかなぁ・・・)
すでに雑誌等で野口先生の記事が出ている ので、それを読んでいれば十分かな。と思ってしまった1冊でした。
------------------------------------------------------------------------
目次
序論 『「超」整理法』を書き直す時がきた
第Ⅰ部 デジタル・オフィスの作り方
第1章 Gメール革命
①Gメールのどこが革命的なのか?
②人名をキーとしてメールを読む
③メールのストックを活用する
④合理的な仕事のシステムを作ろう
第2章 デジタル・オフィスはオンライン
①なぜオンラインがよいのか?
②個人データをオンライン格納
③近づくクラウド・コンピューティング
④グーグル・フォビアを克服できるのか?
第3章 紙との共存
①現実的になったデジタル・オフィス
②ワーキングファイルの扱い
③「神様ファイル」の扱い
④「みんなの協力」が不可欠
第Ⅱ部 IT時代の知の技法
第4章 検索を制するものは知を制す
①なぜ検索の方法論が必要なのか
②検索で難しいのは何か?
③具体的にはどうすればよいか
④有用なデータはどこにあるか
⑤自分のデータの検索
第5章 検索は知のスタイルを変える
①検索を使えば目的は直接到達できる
②百科事典とミシュランの思想
③プッシュの受け手から積極的なプルへ
④新しい知の時代における勉強法と教育法
⑤新しい時代が求める専門家はどのような人か?
第6章 新しい時代における知的作業の本質は何か?
①知的作業の核心である三つの作業
②具体的にはどうすればよいのか
第7章 新しい知的生産技術
①みんなで作る知の体系
②コンピュータは知的作業を代行できるのか?
第Ⅲ部 知の産業革命
第8章 日本で知の産業革命が起きるか?
①知的奴隷が使えれば、知の産業革命は起こらない
②搾取されている若い知的労働者
③知の産業革命を起こす主体は知的労働者
------------------------------------------------------------------------
●相当量のデータが、送信メール、受信メール、あるいは添付PDFという形で、メールのログにすでに蓄積 れていた。つまり、「デジタル・オフィス」は、私が気づかないうちに、いつの間にかできあがっていた。
●分類するな。ひたすら検索せよ
●オフィスのデジタル化
→紙と電子の得意分野を見極め、使い分けること。
↓
紙が強いのは、「入力の容易さ」と「一覧の容易さ」だ。つまり最初と最後の段階。
それに対して、途中の段階は、電子情報の方が扱いやすい
●ワーキングファイルの扱い方
①紙ベースの資料
重要な資料であとで使うことが予想される物は、可能な限りPDF化する
②手書きの図
PDF化する。なおスキャンすることを前提とすれば鉛筆で描くのがよい。簡単に消して修正できるから
③使用した手帳の記録やメモ
使用した手帳は、世界に一つしかない貴重な個人データだから、捨てないで保存
PDFでコピー残しておくと、あとで参照するのに便利
紙に書いたメモは、できるだけ早くPCに入力すること
●「神様ファイル」=実際には使わないが、捨てることが出来ない資料(写真、手紙、絵など)
コピーを検索可能な形で保存した方がよい。そして実物は捨てる。必要なのは情報なのだから、実物は必要ないはずだ。実物にこだわるのは、単なる惰性である。
●検索の方法論
・ 「どこにあるにしても、それを探し出す能力」=「検索サービスをうまく使えるかどうか」が重要
・検索の最重要課題は「雑音の排除」。基本的な方法は、複数の検索語を用いたand検索によって絞り込む
・情報力の差は、仮説構築力に大きく依存する
●プッシュメディアとプルメディア
・情報の電子化が進展して、情報をプル(引き出したい)出来る可能性が飛躍的に向上した。検索はこれを行うための強力な道具。
・プル=インターネット
プッシュ=テレビや新聞
・「下流に落ち込みたくない」と考えている30代は多い
→そのための手段は、書店に並んでいるビジネス書からプッシュを受けることではない。
プルが出来る人間になること。
●新しい時代が求める専門家
・自分自身の問題意識を明確に持ち、これを用いて、情報のフィルタリングを行う。その範囲外にあることについては、積極的な情報収集はしない。情報洪水時代に必要なことは、情報の集め方ではなく、情報の選別の仕方や捨て方である。
・必要なのは、情報の意味を正しく理解し、新しい理論を構築出来る人々だ。日本でも、こうした能力を持たなければ研究者として生き残れない時代が到来した。
●知的作業の核心である3つの作業
①「問題の設定」
→「明確な問題意識を持つ」または「テーマを設定する」
②「仮説の構築」
→問題に対する暫定的な答えをもつ
③「モデルの活用」
→「現実の複雑な世界を理解するため、現実を単純化し、本質的な要素を抜き出し、それらの関係がどうなているのかを記述したもの。例えば「需要と供給」などを活用する
●社会人になってから勉強したいという人が多い
→「学校にいる時は問題意識もなく漫然と講義を聞いていたが、社会人になって仕事をしてから講義を聞くと、非常におもしろい」ということがある。これは、実際に仕事をして、問題意識を持つためである。
- 超「超」整理法 知的能力を飛躍的に拡大させるセオリー/野口 悠紀雄
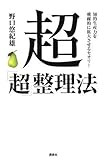
- ¥1,470
- Amazon.co.jp