[絵金の住宅所有者の素顔]
菊水楼跡の向かいには四国銀行赤岡支店が建っているが、ここには以前紹介した寺尾酒造の寺尾梅太郎が設立にかかわった赤岡銀行があった。明治21年に設立された赤岡共立蓄積会がその前身で、29年に組織は赤岡貸金 (株)となり、更に33年、赤岡銀行へと発展する。が、大正8年、土佐銀行に戦略的吸収合併され、12年、旧高知銀行と合併して今の四国銀行となった。
(株)となり、更に33年、赤岡銀行へと発展する。が、大正8年、土佐銀行に戦略的吸収合併され、12年、旧高知銀行と合併して今の四国銀行となった。
菊水楼跡の東隣の商家・野島家はかつて「いさみ屋」という屋号でオレンジ・ジュースやミルクコーヒー等を製造・販売していたが、家のルーツが藩政期に遡るのか否かは不明。
野島邸の東隣は寺尾一族、梅太郎の大叔父・弁吾が初代当主として創業した寺尾木材店跡の商家。赤岡の商家を代表する建築。
現在の住人は姓が違うので、子孫ではないだろう。
寺尾木材店跡の斜向かいには、以前少し触れた、伊能忠敬の測量地点・北緯33度33分の記念碑があるが、その際説明した ように、そこは実際の測量地点ではない。実際の場所にあった記念遺構は戦後、車の通行の妨げになるという理由で撤去されてしまった。
ように、そこは実際の測量地点ではない。実際の場所にあった記念遺構は戦後、車の通行の妨げになるという理由で撤去されてしまった。
元々の測量点はその東の十字路から東に2メートルばかりの赤煉瓦塀沿いにあった。正確に言うなら、十字路角から4枚目の側溝の蓋沿いである。
測量基準点の記念として青石が設置されていたが、明治末、陸軍陸地測量部によって改めて測量し直され、青石の代わりに御影石が設置され、周囲を石で囲まれた。写真がないので分からないが、三角点のような形状を思い浮かべる。
 その赤煉瓦塀の家は、これまで何度か触れた、絵金や徳弘梅左の家屋の所有者だった赤岡村初代村長・小松与右衛門の屋敷。
その赤煉瓦塀の家は、これまで何度か触れた、絵金や徳弘梅左の家屋の所有者だった赤岡村初代村長・小松与右衛門の屋敷。
与右衛門は弘化2年(1845)に生まれた。家は酒の販売を営んでいたが、両親が病気がちだったせいで極貧生活を強いられた。そこでその生活から抜け出そうと、与右衛門は以前解説した琴月堂に通い、読み書きを習った。その勤勉さを見定めた寺尾酒造の当時の当主・太四郎は彼を預かり、一人前の造り酒屋に なれるよう、修行させた。こうして与右衛門は赤岡屈指の酒造家へと成長する。
なれるよう、修行させた。こうして与右衛門は赤岡屈指の酒造家へと成長する。
明治5年、学制発布で琴月堂が廃止されると、有志に小学校建設の必要性を説いて回り、基金や寄付金を募って翌年、廃仏毀釈で廃寺になった須藤楠吉が住職だった正福寺跡に赤岡小学校を建設する。
その後の改築費用についても与右衛門の尽力により、賄われた。
そういう功績もあり、明治22年、初代村長に推薦されたのである。当時の村長職は無報酬だったが、在任中、自費で 湿地帯を美田に造り変えたり、日露戦争戦没者の共同墓地を整備する等、彼が私財をなげうって行った事業は数えきれない。
湿地帯を美田に造り変えたり、日露戦争戦没者の共同墓地を整備する等、彼が私財をなげうって行った事業は数えきれない。
明治44年10月、与右衛門は村人に惜しまれつつ、67年の生涯を閉じた。
昭和のいつごろか分からないが、小松邸は人手に渡り、「宗石煙草靴店」となった。その店も廃業し、空き家になって久しいが、近年、大学生たちが古民家再生に取り組んでいる。高知大学が近年、地域協働学部を創設し、各地域 で活動をしているが、もしかするとその学生たちかも知れない。
で活動をしているが、もしかするとその学生たちかも知れない。
店舗部は近代、改装されているが、裏手に回ると藩政期からの家屋が見られる。
次回、いよいよ龍馬や土佐勤王党も訪れた正福寺跡の遺構を巡る。
が、最近、当ブログの更新をあまり行っていないので、次回は来年になるかも知れない。
尚、当ブログを5日以上更新していない時は、フォートラベルかヤマケイサイトへ投稿していることが多い。
他サイトよりも自身のブログを重視してほしい、という方は下のバナーを
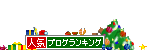 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ